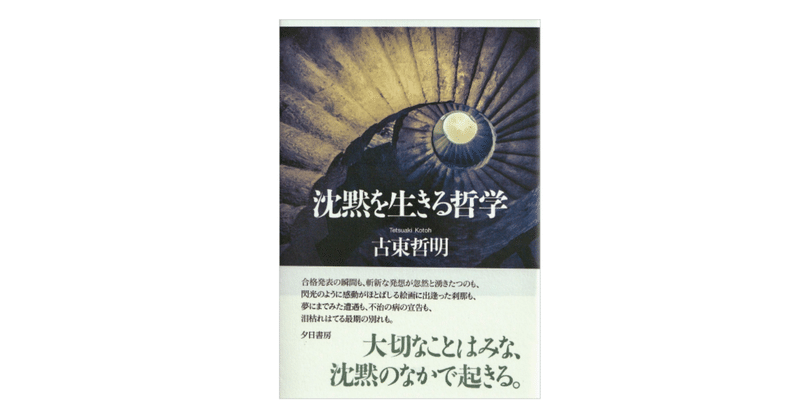- 運営しているクリエイター
2022年12月の記事一覧

第718回「「ほとけ」とは?」
とあるセミナーで、高楠順次郎先生の言葉を紹介しました。 何年か前に、武蔵野大学に講演に行った折に、大学の入り口のところに高楠順次郎先生の言葉が掲げられていたのでした。 それは 「人間の尊さは可能性の広大無辺なることである。その尊さを発揮した完全位が仏である」という言葉でした。 感動してその場で書き写してきたのでした。 仏とは「無限の可能性」であるというのであります。 大乗仏教ではみんな本来仏であると説きます。 みんな誰しも「無限の可能性」を本来持っているのです。 そんな話をしたところ、参加者の方から、 「『仏とは広大無辺な可能性を完全に発揮した人』という説明がありましたが、従来、亡くなった人のことを「仏さん」と言います。この違いをご教授ください。」 という質問をいただきました。 なるほど、たしかに一般の方にとってみれば「ほとけ」というと亡くなった人のことを思います。 刑事ドラマでも殺人現場に刑事が到着すると、「ほとけの身元は?」などと聞いているものです。 「ほとけ」の本来の意味とは何か、そしてなぜ亡くなった人のことを「ほとけ」というようになったのか、いろいろ調べてみました。 すると知らなかったこともたくさんあって、勉強になりました。 まず「ほとけ」を『広辞苑』で調べてみると、 ①〔仏〕 ㋐悟りを得た者。仏陀。 ㋑釈迦牟尼仏。 ②仏像。また、仏の名号。 ③仏法。 ④死者またはその霊。 ⑤仏事を営むこと。 ⑥ほとけのように慈悲心の厚い人。転じて、お人よし。 ⑦大切に思う人。 という七つの意味が出てきます。 やはり一番には悟りを開いた人、仏陀であり、お釈迦さまであります。 死者という意味は四番目に出ています。 更に岩波書店の『仏教辞典』で「ほとけ」を調べてみますと、 「<仏(ぶつ)>の訓読語」とあります。 「仏(ぶつ」を調べてみると 「<ブッダ>すなわち<目覚めた人><真理を悟った人(覚者)>の意をあらわすサンスクリット語に対応する音写。 古くは<浮図(ふと)><浮屠>とも音写され、後には<仏陀>などと音写された。 ほとけ。もとはインド一般に、真理をさとった聖者を意味していた。 仏教の歴史においては仏教の開祖シャーキヤムニ(釈迦牟尼、釈尊)をさすが、教理上は、悟りの普遍性の故に、広く修行者によって達成可能な目標とされる(とくに大乗仏教)。」 と解説されています。 「ほとけ」とは真理を悟った人なのであります。 この「ぶつ」がどうして「ほとけ」となったのか、これには諸説あるようなのです。 まず岩波の『仏教辞典』には、 「その語源については、中国で古く仏(buddha)が<浮屠(ふと)><浮図>と音写され(『後漢書』楚王伝、桓帝紀)、それに<その道の人>を意味する<家(け)>、または性質・気配を意味する接尾語<け>がついて成ったという説」が紹介されています。 「ぶつ」は「ふと」に、そしてそれに「け」がついて、「ふとけ」「ほとけ」となったという説であります。 次に『仏教辞典』には、 「<ほとほりけ>(熱気)からきたもので、仏教が日本に伝来したときたまたま熱病が流行したためにこのように呼ばれたとする説」 が書かれています。 この説は全く存じ上げませんでした。 それから更に 「<ほどけ>(解)からきたもので、仏とは煩悩を解き放った存在であるというところからこう呼んだとする説がある」というのです。 「ほとけとは、ほどけることだ」というのはよく聞かれる話であります。 解脱とは、ほどけることでもあるので意味も通じているのです。 『仏教辞典』には、「いずれも推測の域を脱しない」と書かれていますので、たしかなことは分からないようです。 『広辞苑』にも「ほとけ」の語源については、 「ブツ(仏)の転「ほと」に「け」を付した形、また、「浮屠ふと家」「熱気ほとおりけ」「缶ほとぎ」など、語源に諸説がある」と記されています。 それから「仏の意味で<ほとけ>という和語を使った最初の例としては、753年(天平勝宝5)の薬師寺仏足石歌「釈迦(さか)の御足跡(みあと)石(いは)に写し置き敬(うやま)ひて後(のち)の保止気(ほとけ)に譲りまつらむ捧げまうさむ」が挙げられる」のだそうです。 ずいぶんと古い時代から「ほとけ」という言葉が使われていたことが分かります。 それから、問題となるのが死者をほとけと呼ぶようになったことについてですが、『仏教辞典』には、 「一方、<ほとけ>が死者の意味に使われるようになったことについては、中世以降死者を祭る器として<(ほとき)>が用いられ、それが死者を呼ぶ名ともなったという説がある。」のだそうです。 こういう説も存じ上げませんでした。 死者を祭る器「ほとき」から転じたというのです。 更に『仏教辞典』には、 「しかし、日本では人間そのまま神であり(人神(ひとがみ))、仏教が伝来した当初は仏も神の一種とみなされた(蕃神(となりぐにのかみ))ことから推して、人間そのまま仏とされ、ひいては先祖ないし死者を仏(ぶつ)の意味で<ほとけ>と呼んだとも考えられる」と解説されています。 人はみな仏であるから、先祖も死者もほとけだというのです。 これは死者に限定されたことではありません。 それから更に興味深いことには、『仏教辞典』に、 「なおキリスト教伝来時には、創造主のデウス(Deus、天主)とその下生または子とされたイエス‐キリストを仏といい、その教えを仏法と称した。また仏キ習合的理解から、信者が死んでパライゾ(paraso、天国)に行くことを「仏になる」とも言った。」とかかれているのです。 イエスさまのことを「ほとけ」と呼んでいた時期もあったというのです。 ほとけになるという「成仏」はどういう意味かというと、『広辞苑』には、 ①〔仏〕煩悩を断じて悟りを開くこと。仏になること。 ②(死ぬと直ちに仏になると考えられたことから)死ぬこと という二つの意味が記されています。 『仏教辞典』には、 「仏・ブッダとなること、悟りをひらくこと。 仏教でいうところの真理(伝統的に<法)>と呼ばれる)に目覚めること」という解説があります。 「初期仏典・部派文献では、成仏は実際上、釈尊一人に限定されるのに対し、大乗仏典では、広く衆生一般にも成仏の可能性を認めるという相違がある」と書かれています。 大乗仏教では、みんな仏になれると説いたのです。 そこから、仏になれるということは、仏になる種がこころに宿っていると説くようになりました。 それは、みんな仏の心を持っているのだということです。 そして更に、お互いの心が仏であると説くようになったのが禅の教えなのであります。 「ほとけ」という言葉、実にいろんな変遷があって今日使われているのです。 亡くなった人のことを「ほとけ」というのも中世以来のことですから、かなりの伝統のある使い方なのであります。 しかし本来の「真理に目覚めた人」という意味を忘れてはなりません。 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺

第702回「降魔」
苦行を捨ててヒッパラ樹のもとに坐ったお釈迦さまには、魔の軍勢が襲ってきました。 <魔>とは、死あるいは殺を意味するサンスクリット語マーラに相当する音写であります。 岩波書店の『仏教辞典』によれば、もともと「魔」という漢字はなかったらしいのですが、この「マーラ」という梵語を当てるために作られたというのであります。 「魔」というのは「人の生命を奪い、仏道修行などもろもろの善事に妨害をなすというのがおそらくはその根本性格」としています。 お釈迦さまを襲った魔は、まず美しい女性でありました。 三人の魔女を遣わしてお釈迦さまの心を乱そうとしました。 薄い衣で、瓔珞の花で美しく着飾った妖艶な魔女等を近づかせて、あらゆる媚の限りを尽くして、優しく舞い麗しく歌ったのでした。 大法輪閣の『仏教聖典』には、 「春は来ぬ、春は来ぬ、日のひかり暖かに、若芽ぞ萌え出でぬ。 好き君よ、いかなれば、若き楽を捨てて、遠きさとりを求め給う。 美しの、われらを見ずや、浮世をはなれし、仙者さえも、愛染の心、起こせしものを。」 といって誘惑したと書かれています。 しかしお釈迦さまはそのような誘惑に心動かされることなく、 「あなた方は今善き果報によって、よい身を得ているけれども、やがて無常なるがゆえに老いと死に襲われてしまうだろう。 姿形は妖(あでや)かであるけれども心はただしくない。 それは美しい画を描いた瓶に、臭い毒を盛ったようなものだ。 欲は身を亡す本、死して悪道に堕つる因(たね)である」と告げたのでした。 すると、忽ち三人の美しさは失われ、浅ましい老婆の姿と化(かわ)ったというのです。 更に悪魔はお釈迦さまに告げました。 こちらも『仏教聖典』には、 「痩せ細るおんみの、顔の色の悪しさよ。げに死は近し。 おんみには、死せるぞ多く、生けるや少なし。 生きよ、 生くるこそ善けれ。 生きて、善きことをなせ。 清き行なして、火に事うれば功徳多きに、いかなればかく、徒らに励むや。道行き難く、はた成し難し。」 と書かれています。 それに対してお釈迦さまは毅然として、悪魔を叱りつけました。 「悪魔よ、放逸の奴隷よ、どうして私のところにやって来たのか。 私に要はない。 信仰と精進と、智慧をもって、道に励んでいる私にどうして生きよと薦めるのか。 流れる河も、熱風に吹かれれば乾くだろうけれども、勤め励む私の血がどうして枯れることがあろうか。 血は枯れ、体からあぶらは失せ、肉は落ちて、そうして心静かにおさまっているのだ。 正念と智慧と明らかに、禅定いよいよ固くなっている。 私はかつて、五欲の楽の極みをつくし、 今や、 その欲に望みはない、この清浄の人をみよ。」 といったのでした。 そして悪魔の軍勢を次のように言っています。 「汝の第一軍は楽欲ぞ、第二軍は不快なり、第三軍は飢渇ぞ、第四軍は渇愛、第五軍はこれ懶惰、第六軍は怖畏ぞかし。 第七軍は疑なれや、第八軍は虚栄と剛情、第九の軍は名利にて、第十軍は自讃毀他なり。 悪魔よ、これは、 汝の軍、汝の武器なり。勇者は勝ちて折伏し、安きにこそは、至り得め。」 というのであります。 悪魔の軍勢というのは、第一には、楽しみにふけろうとする欲であります。 第二は、身心に感じる不快であります。 どれも心をかき乱すものです。 第三の飢えと渇きもまた心をかき乱すものです。 第五の懶惰というのは、ものぐさでだらけて怠ける心であります。 第六の怖畏というのは恐れであります。 第七の疑いというのは、この道でいいのだろうかと疑心暗鬼になることです。 第八の虚栄と強情とは、見栄を張ったり、かたくなな心であります。 第九は名利を求める心です。 第十の自讃毀他というのは、自分のことを誇り他人をさげすむことであります。 これら皆が魔となって修行を妨げるのであります。 皆自分の心が引き起こすものにほかなりません。 のちにお釈迦さまが『法句経』に 「戦場において百万人に勝つよりも、唯だ一つの自己に克つ者こそ、じつに最上の勝利者である。」(ダンマパダ103) と仰せになっているように、自己に打つ勝つしかないのであります。 お釈迦さまは、どこまでも毅然として 「大いなる象に乗り、全軍を率いて来たりし悪魔よ、いざ戦え、われ勝たん。汝は我をみだすことなし。」と言っては戦い、そして魔に打ち勝ったのでした。 とうとう悪魔はこの戦いに勝ち目のないのを見て、悄然として悲しんだのでした。 「七年もの間世尊を追いかけてきたけれども、正しい念いに住しているので、このさとりを求める人には隙を見出すことができなかった。 それは、あたかも柔らかい肉に似た石があって、鳥が集って、それを啄んで甘い味を得ようとしても、その味を得ることはできずに鳥が去ってゆくようなものだ。自分たちもその石を啄もうとした鳥のようなものだ」といってすごすごと消えたのでした。 こうして悪魔に打ち勝ってお釈迦さまは、心の平安を得て、深い坐禅に入ってゆかれたのでした。 そして煩悩を滅ぼし尽くす智慧につとめて、世の中は苦であること、そして苦の原因は何であるか、これは苦の滅することによって安らぎのあること、そして苦の滅に達する道をそれぞれ明らかにされました。 これが後に四諦の説法となります。 こうしてこの明らかな智慧によって心は愛欲と無明から脱れて既に解脱したのでした。 そこで「生は尽きた、清らかな行は成し遂げた、なすべきことは成し終わった、之が最後の生で、この後再び迷の生を受けることがない」という智慧を得られたのでした。 毎年臘八摂心の終わり頃になると、このお釈迦さまの降魔の話をしています。 そうして自分自身もお釈迦さまをお慕いしてこの道を変わることなく歩むのだと心に誓うのであります。 臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺