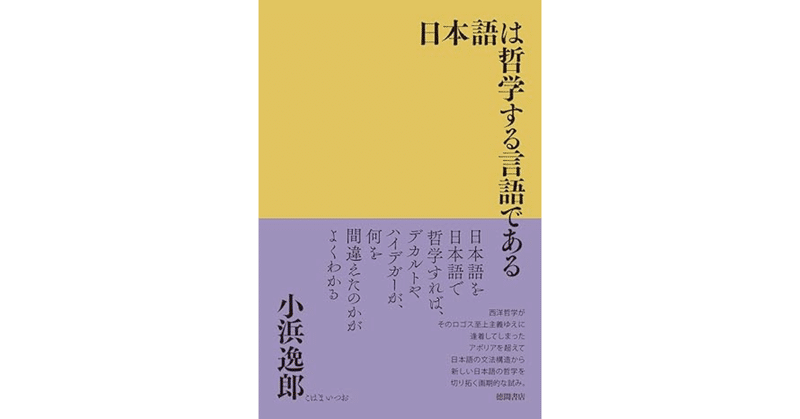
哲学を否定しながら哲学するって?
『日本語は哲学する言語である』小浜逸郎
デカルトやハイデガーはどこで間違えたのか? 西洋哲学が逢着したアポリアを日本語を哲学することで乗り越える画期的論考!日本語は、曖昧で情緒的な言語とみられてきた。一方でデカルトに代表される西洋哲学は、言語をロゴスとして捉え、人間を理性的存在とみなして、情緒的なあり方をパッションに閉じ込めてきた。それゆえ人間の身体性やいまここに立ち現れている現実が歪められてきたのも事実である。本書は、日本語の「曖昧さや情緒」を文法構造に分け入って分析することで、これまで普遍的とされてきた思考とは異なる世界理解を切り拓く日本語による哲学の試みである。
目次
第1章 西洋哲学と格闘した日本人(デカルトの「疑い得ないわれ」を疑う;大森荘蔵の「立ち現れ一元論」 ほか)
第2章 日本語は世界をこのようにとらえる(「いる‐ある」問題;「こと‐もの」問題 ほか)
第3章 言葉の本質(言葉の本源は音声である;言葉は世界を虚構する ほか)
第4章 日本語文法から見えてくる哲学的問題(品詞分類批判;統辞論 ほか)
第5章 語りだけが真実である(真理・真実とは何か;現象が「事実」や「真理」になるための条件 ほか)
西欧哲学の二元論はユダヤ・キリスト教が思考がその奥底にあり、日本人らがもっている自然と心という概念とは違っているというのを言語(言葉)の世界から明らかにしようとする哲学。すごいややこしいのは哲学(論理学)なんだけど、それを西欧の哲学(論理)以外から論じているので、そこが非常にわかりにくく、情(こころ)というのは何を言っているのか?はっきりしなかった。それは神に頼ることない人との関係性だというのだった。
ここからは卵が先か鶏が先かみたいな話になってしまうのだと思う。つまり最初に卵(言葉)を置いたほうがいいのか、鶏との関係(交合)をもってくるべきなのかということなのかな。西欧論理学が二元論なのに外部(他者)を必要としないというのはそこに神がいるということなのか。そこに自然=心を持ってきた一元論の思考なのか?
わかったような、わからないような。
西欧哲学(論理学)批判であるのだが、ユダヤ・キリスト教が哲学の元にあり一神教的問いかけが自己と神になるので堂々巡りしていく。日本語は他者との関係性で成り立っているから哲学的には適した言語だと哲学(論理)しているのは膠着矛盾しているようであまり良く分からなかった。論理だけでなく感情(こころ)も大切だと構造主義的なことなんだと思うがあまり日本語ばかり褒めてもなとも思うのだった。外部の影響があって発展してきたのだから。哲学ならなおさら。論理が複雑に錯綜しているような感じを受けた。ベルグソンとか褒めているのだし。
日本語については哲学ではなく文芸批評とかの方がいいのかもしれない。哲学的に論理でやろうとするとさっぱり何が言いたいのかわからない。まあ日本の伝統云々なんだろうけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
