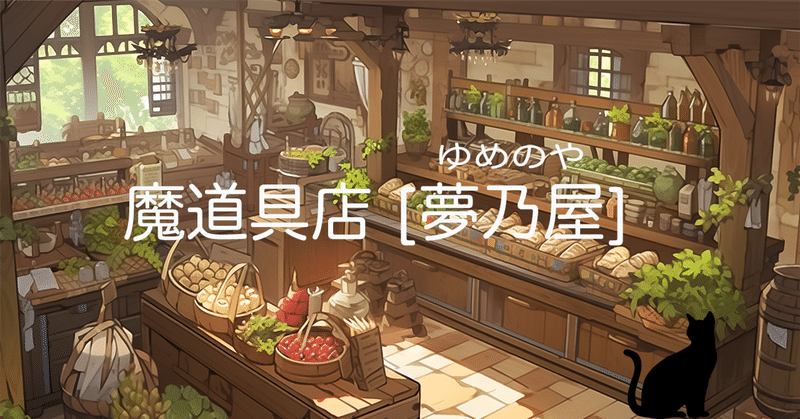
【連載小説】No,1「黒猫を飼い始めた」
黒猫を飼い始めた。
もちろん最初は自分で飼うつもりなんてなかったけど、アパートの階段の陰でずぶ濡れになって鳴いている姿に気づいてしまったら、見ないふりをすることはできなかったのだ。せめて濡れている体を拭いてやって、引き取ってくれそうな人を探す間くらいはなんとか世話をしてみようと決めて、そっと手を伸ばした。
野良のわりに人懐こいようで、逃げる素振りはない。
「よしよし、おいで」
痩せた体はまだ小さい。きっと若い猫だ。抱き上げても軽かった。
まずは部屋に連れ帰って体を拭き、やわらかい毛布にそっと包んで帆布バッグに入れ、抱えるようにしてアパートを出た。バス停の近くに動物病院があることを知っていたので駆け込んで診察してもらった。お財布には痛手だったけど、病気は持っていないと分かってほっとした。
去勢手術の説明も受けた。もう半年は過ぎているだろうから手術するなら早い方がいいと勧められたけど、ひとまず体調を整えるのが先決ということで、落ち着いたらまた改めて検査を受けてくださいと言われた。本当に物入りだ。このまま飼い続けると、じきにこちらが干上がりそうだ。
帰りにスーパーで餌と猫砂を買ったら腕が死んだ。
「早くおまえを引き取ってくれる人が見つかるといいんだけど」
「ニャア……」
ひとり言に可愛い鳴き声が返ってくる。
そんな甘えた声を出しても無駄だよ。こっちはペットを飼う余裕なんて全然ないんだから。譲渡会をやっているところに相談してみるとか、SNSで呼びかけるとか、とにかく早いところ何か手を打たなくては。
「ニャアァ~」
「私は飼ってあげられないの。ここ賃貸だし、失業したばっかりだし。世の中は人手不足のはずなのにねぇ、生え抜き以外は要らないんだってさ。真面目に働くのが馬鹿らしくなるよね」
「ニャァ」
毛並みと同じで、見上げてくるつぶらな瞳も真っ黒だ。
くるんとした丸い眼がつやつやキラキラ輝いている。
「…………可愛いなぁ」
「ニャニャァ?」
「だめだめ、絶対だめ。無理」
病院や餌代でたくさんお金かかるし、そんな場合じゃないでしょと頭の隅で誰かがつぶやいている。分かっている。簡単に決めていいことじゃない。しかもここはペット不可の賃貸アパートだ。見つかったら追い出されるかもしれない。
それなのに安物の毛布に包まってスヤスヤと眠ってしまった小さな生き物の頭をそっと撫でているうちに、名前は何にしようかなんて考えてしまっていた。
要するに、抗えなかったのだ。可愛さと運命に。
だって、出会ってしまったのだから。
その日から小さなオスの黒猫は我が家の住人となった。
名前はクロにした。
「さすがにシンプルすぎるか?」
あれこれ考え、迷ったものの、シャレた名前がどうにもピンとこなかったので結局直球でいくことにした。
まだ発情期に入っていないのか、オスのわりにクロはとても聞き分けのいい、おとなしい猫だった。トイレはすぐ覚えたし、私が出かけている間にいたずらすることもなかった。いままで猫を飼ったことがなかったので比較できないが、ネットで見かける数々の面白エピソードからしてみると、我が家のクロはかなり手間いらずの賢い子のようだ。
代わりに時折、フイと姿を消すことがあった。しっかり戸締りしているはずなのに、いつの間にか居なくなっているのだ。どこかの隙間に入り込んでしまったのかと思って懸命に探しても見つからない。
最初はかなり焦った。交番に届けたりネットで呼びかけたりするべきだろうかと迷った。ところが数時間して玄関の戸をカリカリと爪で引っ掻く音がして、開けてみるとクロが何食わぬ顔で立っていた。
ただいまの代わりに短く「ニャア」と鳴いて、さっさと家に入ってくる。それからはいつも通り。静かに水を飲み、餌のカリカリを半分ほど腹に収めてから、窓際に置いたお気に入りのクッションでくつろぎ始めた。こっちはホッとするやら拍子抜けするやら。
「いったいどこに行ってたのよ?」
「……ニャアァ」
まだ、教えられないね。そう聞こえたような気がした。
クロを飼い始めておよそ半月。
窓際でよく眠り、しっかり餌を食べ、きちんとトイレもできているので、だんだん健康になってきたのだろう。少し毛艶がよくなってきたようだ。
私はというと、その間、転職サイトで見つけた会社へ面接に赴くこと三回。残念ながら、今のところすべて空振りだ。一社目はキャリア不足だと告げられた。
「うちは管理職経験者が欲しいんですよね。UX戦略に関わった経験がある方とか」
「はぁ……そうですか」
募集要項にはそんなこと書いてなかったぞ。ハイクラス転職募集って書いといてくれ。
二社目は社員の表情がどんよりしていてブラックな職場環境が窺い知れた。残業は十時間以内と言われたが、もしかすると残業と認めてもらえるのが十時間までなのかもしれない。三社目は面接前に公共料金の取り立てに来ている場面を目撃してしまい、そのまま帰宅した。
「どうしたもんかしらね」
クサクサするので部屋の大掃除でもしようと窓を開けて掃除機をかけ始めたら、クロがぴょんと窓枠に上り、外へと飛び降りた。
「ちょっ……!!」
しまった!
猫は掃除機の音が嫌いだと聞いたことがある。びっくりさせてしまったかもしれない。慌てて階下を覗き込むと、駐車スペースになっている隣の空き地にちょこんと座っているのが見えた。どうやらケガはしていないようだ。
「…………びっ……くりしたぁ」
ここが二階でよかったと、ひとまず胸を撫で下す。
とはいえ脱走はこれで四度目だ。放っておくわけにはいかない。急いで部屋の鍵をつかむと自分も表に飛び出した。
「クロ! ……クロ?」
こんなときのために小さな鈴を取り付けたリボンを首に巻いておいたのだ。脱走犯を確保するべく周囲をぐるりと見渡し、耳を澄ます。
背後でちりんと音が鳴った。
「いた!」
敷地から出て道路を渡っていく姿を視界の端に捉えて、ますます血の気が引いた。家の前は細い路地だけど車がまったく通らないわけじゃない。
「こらこら! 待ちなさい!」
必死に走って追いかけているのに、あと少しというところでするりと逃げられ、また距離が開く。二度、三度と追いかけっこをくり返し、気づけばよく知らない道に入り込んでいた。駅とは反対方向だから普段まったく足を踏み入れたことのないエリアだ。
「どこに行くのよ」
「ニャアァ!」
クロはまるで私を導くように幾度も立ち止まり、ひと声鳴いて、また走り出す。
じわじわと嫌な予感がし始めたころ、逃避行は突然終わりを告げた。
住宅街の真ん中にぽつんと建つ二階建ての小売店。かなり古そうな建物だけれど外観は洒落た洋風の店舗。ヨーロッパの街中にありそうな佇まいだ。木の看板には『道具店夢乃屋』と書いてある。出入り口も重たそうな木製のドアで、ちょうどその扉が開いてお客さんが一人出てきた拍子に、クロがスッと店内に入ってしまった。
(あっ……ああ~~~~~)
怒られるだろうかとビクビクしながら、後を追って自分も店内に滑り込む。
軽やかなドアベルの音に心臓が縮む。
(これはマズイよ。早く出てきて、クロ)
昼間なのにやや薄暗くて、ひんやりとした空気の店内にはさまざまな品物が並んでいた。
表の看板は道具屋となっていたのに、きれいな装飾が施された絵皿やアクセサリー、鏡、楽器や人形まで置いてある。オルゴールやジュエリーボックスと思しき箱もあれば、一見、何に使うのかよく分からない物も多い。ただなんとなく、どれも値段が張りそうな気がして冷や汗が滲んでくる。
「クロ……どこ?」
そろそろと店内を歩きながら小声で呼んでいると、いらっしゃい、と明るい女性の声が鼓膜を震わせた。床に這わせていた視線を上げると、カウンターの奥にゆったりと腰かけて微笑んでいる年配の女性と目が合った。
白髪交じりの髪はきれいにまとめて結い上げられ、ふんわりとしたブラウスに淡い色合いのショールを羽織っている。上品なマダムという感じだ。この店の店主か、店主の奥様なのだろう。
「あっ……ど、どうも……」
ふと見ると、彼女の手がカウンター上に鎮座している黒猫の背をやさしく撫でている。
「クロ!」
すみません、その猫、ウチのです!
叫びそうになったとき。
「あら、あなたいま、クロって呼ばれているの?」
「うん。見たまんまだけど、わりと気に入ってる」
「そう」
…………あのう、マダム、今うちのクロに話しかけました? 完全に視線が猫に向けられていましたよね。しかもどこからか若い男の子の声で返事が聞こえた気がするんですけど、幻聴ですか? 私ヤバいですか? 相当ヤバいですよね。それともこれは夢なのかな。実は寝ているとか?
面食らってぐるぐる考えていたら、カウンターの女性がふふっと目を細めた。
「そんな顔しなくても大丈夫よ。この店は特別だから、この子の声もちゃんと聞こえるの」
「はぁ……」
いやいや、あなたも大丈夫じゃないです。何言ってんの?
「それにしてもこんなに早く見つけてくるとは思わなかったわ」
「ボクは勘がいいんだ。褒めてくれる?」
「ええ、上出来よ」
だから猫と会話しないで。変な夢。早く目が覚めてくれないかな。
「というわけで、あなた」
この『あなた』は私のことだ。彼女の視線がパッとこちらを向いた。
「ようこそ、魔道具店夢乃屋へ」
「まどうぐ……」
「ええ、そう。魔道具。うちのは全部一級品よ。お客さまも良い方ばっかり。だから安心してね」
「あんしん……?」
会話についていけなくてオウム返ししかできない。
「それにしてもこんなに早く後継者が見つかるなんて。ほっとしたわ。これでようやく旅立てる」
「あのぉ」
「あ、二階が住居になっているから自由に使ってくれていいわよ。お店のことはこの子、クロに聞いてちょうだい。だいたい知ってるから」
「いや、あのですね」
もう何がなんだか。
混乱する私にクロが言った。
「ごめんよ。この店の主が旅に出たいと言うから大急ぎで後継ぎを探していたんだ。キミがボクを拾ってくれてよかった。こんなにピッタリの人材がすぐ近くにいたなんてラッキーだよ」
「ピッタリの人材? 私が?」
「そう。この店ではさまざまな魔道具を扱うからね。よほど強い魔力の持ち主か、あるいはどんな魔法にもまったく影響を受けない魔力ゼロのまっさらな人間か。そのどちらかしかできないんだ」
「いや、大抵の人は魔力なんてないと思うけど」
「そんなことないよ。魔力という表現を使わないだけで、ものすごく直感力の鋭い人とか夢見ができる人、知らずに呪詛を行ったり、それに強く影響されてしまう人もいるでしょ。そういう人はダメなんだ」
……要するに、ものすごく鈍いと言われてるのかな。
「そんな顔しないの。一応、褒めてるんだから」
「さいですか」
結局、私も猫と会話しちゃってるし。
もうなんなの、この夢。
「言っとくけど、夢じゃないからね。よろしく、琴音」
「いやでも」
「仕事探してたんでしょ。ボクと一緒に住める家もあるよ」
「まぁ、そうだけど」
「きっと運命なんだよ。出会っちゃったんだから」
「…………はぁ」
雫川琴音。二十六歳。無職。
訳あって黒猫を飼い始めたら、魔道具店の店主になりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

