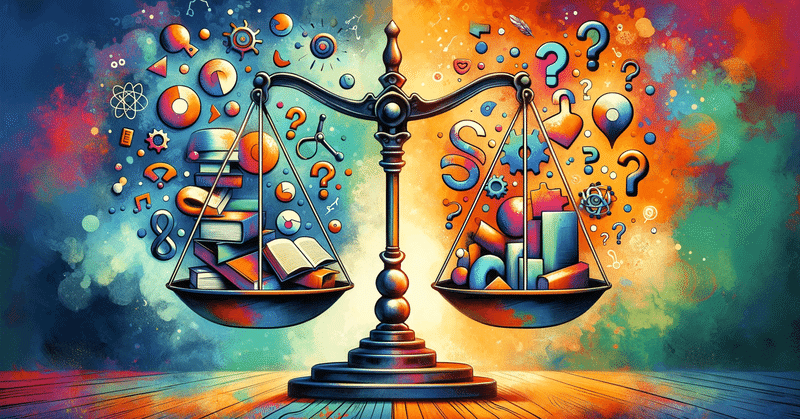
両論併記問題【憂世で生きる智慧】
日本のメディアはしばしば、「両論併記」の原則に従い、オピニオン欄などで異なる意見を掲載することを好む傾向がある。これは、公平さを追求しようとする合理的な行動のように見えるが、その結果、予想外の悪影響をもたらすこともある。政治社会学者の堀内進之介氏は、著書『善意という暴力』でこの問題をとりあげ解説している。
両論併記の問題点
1.均衡の錯覚
両論併記は、対立する意見を公平に紹介することを意図している。しかし、この方法は、科学的事実や広く認められた真実と根拠のない主張を同等に扱うことで、読者に誤った均衡の錯覚を与える可能性がある。
例えば、地球の気温が上がっていることに関する科学者たちの広く認められた意見と、それに反対する少数派の意見を同じように扱うと、読者は両者の信ぴょう性が同じであると誤解するかもしれない。このような均衡の錯覚は、正確な情報を提供するという報道の基本的な使命を損なう。
2.専門知識の軽視
両論併記は、しばしば専門家の意見を軽視し、無知や偏見に基づいた意見を同等に扱うことになる。専門家はその分野で長年の研究や経験を積んでいるが、両論併記では専門家の意見が単なる一つの意見として扱われることがある。例えば、医療分野での専門家の見解と根拠のない代替療法の主張が同等に扱われると、読者はどちらを信じてよいか分からなくなり、混乱を招く可能性が高い。
3.誤情報の拡散
両論併記は、誤情報の拡散を助長することがある。特に、デマや陰謀論が科学的事実と並べて紹介される場合、それが一部の読者によって真実と認識される危険性がある。誤情報が広まると、その修正には多大な労力と時間が必要となり、社会的な混乱や不安を引き起こす可能性がある。
4.時間とリソースの無駄
両論併記を徹底することは、時間とリソースの無駄になることが多い。例えば、地球が平らであるという主張を取り上げて反論するためには、膨大な証拠を提示しなければならないが、科学的にはその必要性が全くない。こうした無駄な論争にリソースを割くことで、重要な問題や有益な議論が後回しにされる恐れがある。
5.真実の相対化
両論併記は、真実が相対的なものであるという誤った認識を助長することがある。真実は客観的なものであり、全ての意見が同等に価値を持つわけではない。しかし、両論併記によって全ての意見が平等に扱われると、読者は真実が一つの意見に過ぎないと誤解する可能性がある。これにより、事実に基づく議論や政策決定が妨げられる。
両論併記と非決定
日本人が大好きな「両論併記」によって致命的な戦争が決定された――日米開戦80年目の真実
会議の慎重な検討がもたらす後悔
何度も会議を重ねて慎重に検討したにもかかわらず、後で「どうしてこんな決断をしてしまったのか」と後悔する経験は、多くの人が持っているのではないだろうか。80年前の日米開戦は、その典型例と言えるだろう。
歴史学者の森山優(もりやまあつし)氏は、著書『日本はなぜ開戦に踏み切ったか 「両論併記」と「非決定」』で、日本の組織の意思決定システムの致命的な欠陥を指摘している。
支離滅裂な「国策」の文面
第二次近衛内閣の時期から開戦までに、10件以上の「国策」が決定された。しかし、その中身を見ると、一つの「国策」の中に矛盾する内容が併記されていたり、解釈が曖昧な表現が多用されていたりと、実際の行動に具体性が欠けていることが多かった。
例えば、1941年1月30日に決定された「対仏印、泰施策要綱」は、仏印(フランス領インドシナ)やタイとの関係強化を図るための強硬な内容であったが、実施時期は「成るべく速に」とだけ記され、具体的な期日は「三、四月頃を目標とし外交上最善を尽くすべし」と曖昧だった。
「両論併記」による非決定
このような支離滅裂な文書は、当時の政策担当者の知性と能力に疑念を抱かせるものである。戦後に広まった「視野の狭い馬鹿な軍人が日本を戦争に引きずり込んだ」というイメージも理解できる。しかし、森山氏は、問題の本質は個人の能力ではなく、組織の行動原理にあったと指摘している。軍部は一枚岩ではなく、コンセンサスを得るために曖昧な文書で問題を先送りするしかなかったのである。
日本型の意思決定システムの欠陥
森山氏は、日本型の意思決定システムの欠陥を次のように整理している。
「両論併記」:一つの「国策」に複数の選択肢を併記すること。多様な指向性が盛り込まれすぎて、同床異夢的な性格を露呈することもある。
「非(避)決定」:対立を避けるために「国策」の決定自体を取り止めたり、文言を削除して先送りにすること。
他の文書を同時に採択して、決定された「国策」を相対化ないしは、その機能を相殺すること。
日米開戦が最もましな選択肢だった理由
日本の意思決定システムは「船頭多くして船山に登る」状態であった。政治学者の丸山眞男は、日本の政治を神輿に喩え、多くの担ぎ手が押し合いへし合いしているうちに物事が予期せぬ方向へ流れていく様子を描写している。
森山氏は、日米開戦に至る国策決定の過程を検証し、「これでよく開戦の意思決定ができたものだ」と述懐している。
日米開戦という選択は、他の選択肢に比べて目先のストレスが少ない道であったため、組織内部のリスク回避を追求した結果、最もましな選択肢となったのである。
非(避)決定の枠内に収まった日米開戦
一見、日米開戦という決断は非(避)決定から踏み出したように見えるが、実際には非(避)決定の構造の枠内に収まっていた。このような日本型組織の意思決定のあり方が、完全に過去のものとなったとは言えない。
[憂世で生きる智慧]記事一覧
#憂世で生きる智慧 #学び #最近の学び #気づき #日々の気づき #今日の気づき #人生
今後ともご贔屓のほど宜しくお願い申し上げます。
