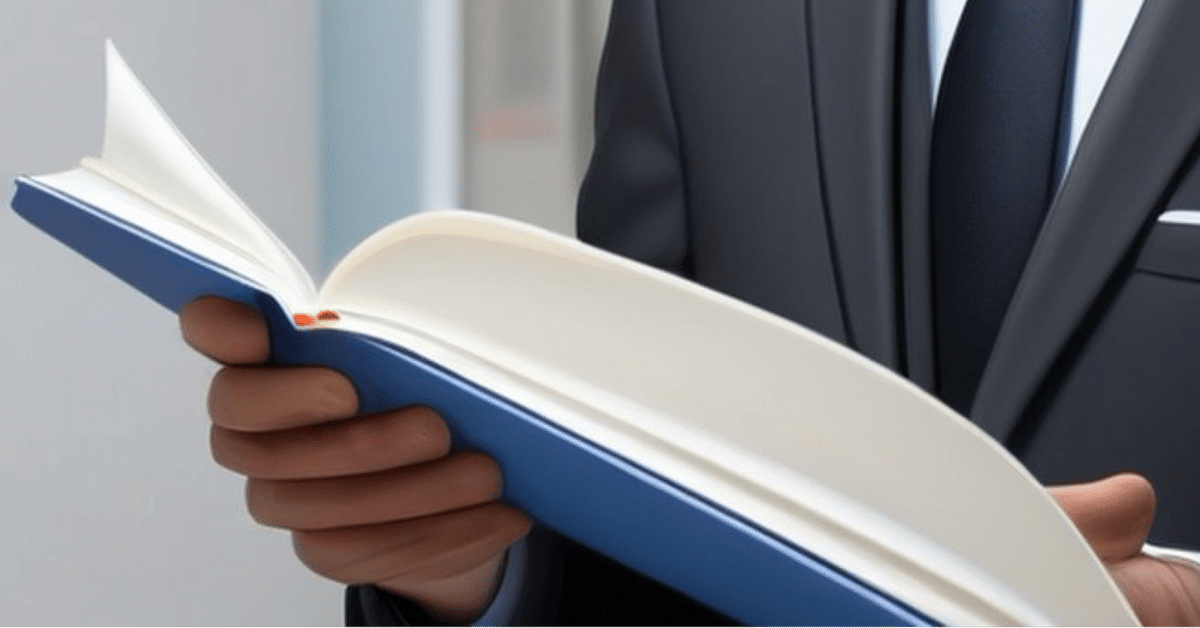
【創作大賞2024応募作・恋愛小説部門】砂の城 第14話 忍sideー 転職
警備のバイトを増やした事で俺の生活は何とか持ち直した。しかし長年建築関連で世話になっていた勝己さんの訃報を聞いたのはつい昨日の事だ。
死因は心筋梗塞。ヘビースモーカーだった勝己さんは相当肺もやられていたらしい。
心臓の手術もしているが、医者と嫁に止められてもタバコは死ぬまで止められないと言い張っていた。俺も他人事とは言えない。
麻衣にもタバコはやめろと言われていたが、口寂しくてどうしても止められない。
俺は警備のバイトを早退きさせてもらい、勝己さんと付き合いが長いという理由で近親者のみの葬儀に参加させてもらった。棺に入っている勝己さんは穏やかな表情で眠っているように見えた。
勝己さんを失った俺はいよいよ日雇い労働の仕事から完全に切られてしまい仕事を失った。東京は家賃も高いので、このまま警備のバイトだけではとても生活出来ない。土地の安いところに引越しして、新たな人生をやり直してもいいかも知れない。そんな矢先──。
俺は珍しく弘樹からの電話で呼び出しを受けていた。俺が麻衣との連絡を絶った事でこいつが律儀に2人の間で伝書鳩めいた事をしてくれている。
また麻衣の近況報告かと思い会いに行くと、弘樹から渡されたの1枚の文書だった。
「はぁ? 俺に病院のヘルパーなんてできる訳ねえだろ」
「絶対そう言うと思った。でも田畑、よく考えてみろよ。麻衣ちゃんが心配だからまだ東京に残っているんだろう? だったら、きちんとボーナスも社会保険もついた仕事の方がいいって」
珍しく弘樹は折れなかった。こいつ、ホント人がいいと言うか、そこまで俺の事心配してくれるのは有難いんだけど、人には向き不向きの仕事がある。
「んな事は分かってるけどよ……だからって、俺に怪我人や年寄りの面倒なんて見れるわけねえだろ、お前だって知ってるだろ? 俺の雑さ」
「田畑は言い方ぶっきらぼうだけど根は優しいし、向いてると思うよ」
「いやあ、看護師のお局様とガチ喧嘩する未来しか見えねえ……」
レトロな喫茶店の木張の天井をぼんやり見つめながら、俺は弘樹のくれた紙を握りしめた。
「考えておいて。いつでも院長先生に斡旋出来るから」
「……これよ、俺がN大学附属病院で働いたらお前にもきちんとメリットあるんだろ? ならやるけど」
「ははっ、よく気づいたな。今新入職者募集キャンペーンやってて、看護助手が1人入社してくれるだけで紹介者にもボーナス手当がつくんだよ」
「ちゃっかりしてんなおい。まあいいや、丁度俺もメインの仕事無くしちまったし。就職できたとしても、何ヶ月働けるかわかんねえけど」
弘樹には記憶喪失になった時も合わせてでかい借りがある。麻衣の事も影で色々サポートしてくれてたみたいだし。
ホント、俺ら兄妹揃ってこいつに散々迷惑かけちまって情けない。
────
金色にしていた髪の毛を久しぶりに黒へ戻し、いざ気合いを入れて面接に挑んだが、なんと弘樹の紹介というだけであっさり採用になった。
しかも、面接に同席していた看護師の偉い人は弘樹のことをベタ褒めしていた。あいつ、もしかしなくてもすげえのか?
弘樹の仕事をリアルタイムで見た事なんて無いし、あいつがすげえ人間だなんて考えた事も無かった。
俺は内科の混合病棟に配属された。病院案内は少し若めの人に引き継ぎされる。
看護助手と呼ばれる仕事は覚える事もかなり多かったが、慣れてしまえば時間で動く単調作業に近い気がした。
ここは女性が9割の職場で、若い子も多く、俺が危惧していたお局様はいなかった。看護師長って人も俺の想像よりも全然若かった。
病棟を案内されている間も、男のヘルパーが珍しいのかパッと見た感じ元気そうな女性の患者が俺に手を振っていた。俺もそれに笑って手を振って返す。それを見ていた看護師長が驚き目を丸めていた。
「田畑さんは人当たり良さそうですね、最初金髪だったって聞いたので、どんな人が来るか心配してたんですよ」
「あ、あぁ、ちょい前まで警備と土方やってたんで。酔っ払いとかに絡まれたりするんで、牽制の意味も込めて染めてました」
「ここの患者さんは手術後と癌の治療を受けている方が多いので、出来れば自然に、穏やかに関わっていただけると嬉しいです」
穏やか……ね。
俺には全く似合わない言葉だ。すぐにカッとなるし、喧嘩っ早い俺が果たしてこの職場で穏やかに仕事出来るのだろうか。
とは言え相手は病人。あっちから突っかかって来なければ俺は一切何もしないけど。
「しかし驚きましたよ、田畑さんは薬剤科の雨宮さんのお知り合いだとか?」
やっぱりあいつ、天然の年上キラーじゃねえか。俺は無言で頷いた。
「普通の仕事だけでも忙しいのに、毎日治療されている方の所に来てくれるんです。患者さんの副作用の相談にも親身になって乗ってくれて、治療について先生にも掛け合ってくれる。本当に若いのによく出来た薬剤師さんですよ」
そっか、てっきりまた年上キラーの話かと思ったらあいつは昔っからブレないままなんとか教授を追いかけて、今も癌治療の勉強してんだな。早とちりした自分が恥ずかしい。
「また分からない事ありましたらいつでも聞いてくださいね。男性は力があるので助かります」
「俺は頭悪いから、力だけがホント取り柄なんで。何でも使ってください」
「若いのに謙虚! いいわよそういう子はこれから伸びるわね。じゃあよろしくね田畑さん」
意外と力のある看護師長さんに背中をバシバシ叩かれ、俺は引き攣った笑いを浮かべた。看護師って細っこい見た目に反してパワフルなんだな。
まだ見習いの俺はベテランの助手さんにくっついて歩いていたんだが、病棟には俺ともう1人しか男性スタッフが居ないせいか、何故かハーレムのように可愛がられる。気がつくと休憩時間は質問攻めにあっていた。
「田畑さんかっこいいですよね、筋肉も凄いし……何かスポーツされているんですか?」
「あ、えーっと、小中学でバドミントンをちらっと。高校でセンコーが気に入らなくてやめた。これでも昔は全国大会で優勝した事あるんだけど、もう過去の栄光だなぁ」
「バドミントン、超カッコいい〜! あのスマッシュ打つ時飛ぶじゃないですかっ、あの姿かっこいいですよね! 私大好きなんです」
「じゃあ、田畑さんに教える先生が良かったら競技続けていたんですか?」
「そうだなあ、確かにセンコーがよかったらやってたかな」
焼きそばパンを頬張りながら俺はふと同じ事を麻衣に言われたのを思い出した。
『……兄貴、もうバドミントンやらないの?』
『ああ。高校のセンコーがクッソ気に入らねえやつでさ。あいつの下でなんか絶対練習したくねぇ』
『勿体無い……スマッシュ打つ時、かっこいいのに……』
ぼそりと呟いた麻衣の言葉を俺は聞き逃さなかった。
『おっ、麻衣ちゃん〜、やっとお兄様のかっこいい所に気づいてくれたなあ。ん? ん?』
『バ、バカ兄貴。別に、辞めたきゃ勝手に辞めりゃいいじゃん。知らないっ……!』
知らないってそっぽ向いた癖に、俺の試合には必ず来るし、応援だって全力でしてくれていた。
うちは貧乏だったからお小遣いなんて無かったのに、麻衣はコツコツ母さんの仕事を手伝って貯めたお金で俺にこっそりタオルを買ってくれた。
記憶が戻るつい最近までずっと使っていたからあちこちもうボロボロになってるけど捨てる気は無かった。
いつもツンツンしてる麻衣が初めて俺の為に、必死に選んでプレゼントしてくれた思い出の品だから。
「田畑さん?」
同僚の声で俺ははっと我に返った。パン食ったままぼーっとしてるなんて変な奴に思われちまう。
「ま、まあ身体は覚えていると思うから、機会があればみんなで運動しようぜ。簡単なことくらいなら教えられると思う」
「やったー! 立ち仕事だから足が浮腫むんですよね、今度田畑さんおやすみの時にやりましょ」
俺より3歳年下の看護師2人組は嬉しそうにキャアキャア言い、お互いの休みを確認して手帳を開いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
