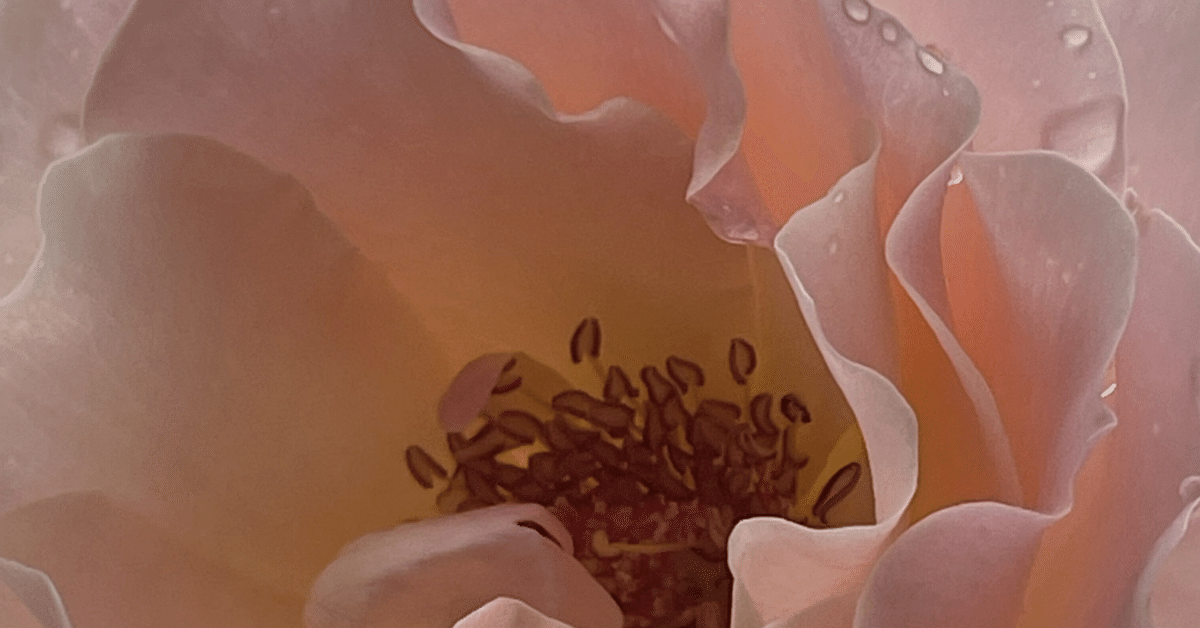
あたしの恋人とあたしをめぐる男たち
どういうわけか、異性の知り合いの数は多い。あたしが長らく在籍した大学院という場所は、今なお男性ばかりの世界だから、こればかりは仕方がない。
恋人は、研究をきっかけにして知り合ったが、研究者ではない。このことにあたしは、毎回心底安堵する。研究者たちはみんな一癖も二癖もある人ばかりで、とにかく油断ならない。恋人は頭がいいけれど、実利的な考え方を好む。研究者にはならないタイプの人間だから、信頼できるのだ。
恋人に出会って数年経つ。あたしは、1センチの疑いの余地もなく幸福だ。
あたしは恋人を愛しているし、恋人はあたしを愛している。それはとても単純なことで、春の次に夏が来るようにきわめて自然な営みだ。
「はやく彼と一緒になりたい?」
友人は、試すような口調であたしにそう尋ねた。
恋人不在の午後、あたしは久しく会っていなかった友人に呼び出されて、一緒にコーヒーを飲んでいた。恋人以外の男の横顔も、ミルクコーヒーのカップも、あたしにとっては何だか非日常の光景だ。
「そりゃあ、そうよ」
友人の問いに、あたしはきっぱりと頷く。それを見て、彼は少し残念そうにコーヒーカップに視線を落とした。この友人は、一時期あたしがフリーに戻ることを望んでいたのだ。
「あたし一人で生きていくなんてとてもできないわ」
あたしは、言い訳するように言葉を続けた。都内で勤務することになったあたしに合わせて、恋人も上京することになっている。問題は、恋人の転職が一筋縄ではいかないことだった。
「僕がそばにいるのに?」
一方の友人は、時期を同じくして都内に異動になった。あたしたちは、関東に親族のいない独身者同士、助け合うことで合意している。それはもちろん恋愛的な意味ではなく、お互いの身の安全を保障し合うという意味だ。
「……ありがとう、いつも助けられてる」
あたしは答えに窮したが、ようやくそう返した。恋人がいる手前、それ以上のことは言えない。それを知っている友人は、仕方がなさそうに笑った。
この友人のことを、異性として全く見ていないと言えば嘘になる。
もしも、恋人に出会っていなければ、あたしはこの男と間違いなく恋に落ちていたと、そう確信をもって言える。しかし、現実にはそうならなかった。友人に出会ったのは、あたしと恋人が愛を誓い合ったそのあとだった。
春のあとに秋が来ることはない。出会いの順番は、ほとんど神秘的な自然の摂理だ。それに反することを、あたしは好まない。それだけなのだ。
背の高い友人の肩越しに、陽光に照らされたオフィス街が見える。季節はもうじき3月になる頃だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
