
介護施設の人事考課は本当に必要なのか?【職員評価の重要性について】
こんにちはアルゴです。
皆さんの職場では人事考課って取り入れられていますか?私の今まで働いた職場では取り入れている職場とそうでない職場がありましたね。
人事考課でなくても、介護事業所が何らかの評価制度を導入していることが多いようです。次の図を観てください。

↑上図は私の住んでいる市の調査によるデータです。
内部評価にしろ外部評価にしろ、半数以上は何らかの評価制度を導入しているようですね。
外部評価制度は2割にも満たないですが、取り入れている施設もあります。私もそうした施設で働いた経験があります。
今回の記事では介護施設の人事考課について、良い点、問題点、改善点などについてお話します。
介護業界に人事考課が取り入れられた背景
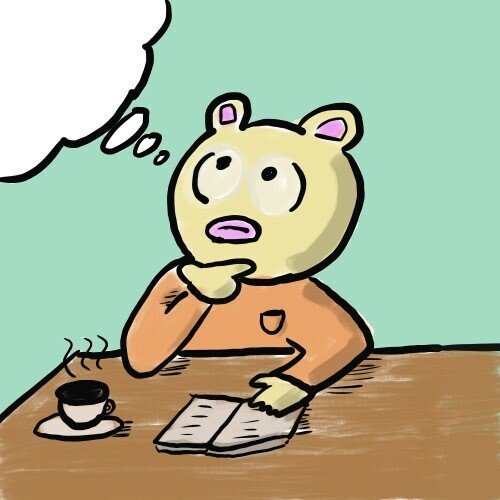
老人ホームなどの介護事業所が人事考課を取り入れはじめたのは、ここ十数年のことです。
その背景には、『人事考課制度のコンサル』『人事考課制度の管理職向け研修』などを経営コンサルタントが売りたいがために、介護業界の諸団体を通じて普及させたことにあります。
介護現場で汗水たらして働く職員が、「人事考課を取り入れよう!」といったわけじゃ決して無いのですね。そもそも施設長ですら制度についてよくわからないうちに、コンサルの言いなりで導入してしまうことだってあります。
そう、コンサルティング会社ってのはコンサルティングを受けてくれる職場がいなければ食っていけないのですから、『人事考課制度』を取り入れるよう、あの手この手を使って説得してきます。
導入の必要がなくても、「導入するべきです」をすすめてくるのは当然です。商売ですから。
そんなこんなで、私の勤めていた特養も、ちょうど私が管理職になる1,2年前に『人事考課制度』が取り入れられたのでした。
人事考課制度の良い点

のっけから人事考課やコンサルの悪口を書いてしまいましたが、私自身は人事考課制度じたいには良いイメージを持ってます。
先程お話しましたが、私は管理職になる前から施設に人事考課制度が取り入れられました。
当時、ピチピチの20代でいち現場の介護職だった私は、
「もっと評価されたい!」
「もっとオレを見てくれ!」
というように、仕事に対する情熱が、自分で言うほど高かったのです。まぁ、今ももちろん介護に対して情熱がありますが、その時は職場のために人生を尽くすような仕事バカだったのです。
そんな若かりし自分は、
「🔥なんでこの職員が自分より先に上にあがるんだ!」
「🔥オレはこんなにがんばっているのに!」
というように、常にいきり立っていました。
今思えば、かなりイタイ奴です(笑
しかしまぁ、上司からの評価というものを理論立ててくれたのが人事考課制度であります。
人事考課には、細かい評価項目がありますから、どれに対してどれだけできているかということが、自己評価と上司からの評価で多面的に記入されます。
人事考課制度が導入する前は、
「👆オレについてこい!上にいけるようにしてやる!」
「👆もっと評価されるように動け!」
・・・と、上司から抽象的な注意や精神論ばかりたたきつけられていました。まぁ、それ自体もキライではなかったのですが、私の性格上、きちっと理屈・・・論理的に何が良くて悪いのかを評価してほしかったのですよね。
人事考課制度が導入されてからは、
「施設がこういうところを評価しているんだな。じゃあ、この項目に対して頑張ればいいし、頑張っている部分を自己評価に記入すればいいんだ😁」
というように、仕事に対するモチベーションも上がりました。
そして、実際に良い評価をつけられた時はとても嬉しかったですね!
しかしながらこの人事評価・・・今思えば、問題もたくさんありました。次の項目ではその点についてお話します。
人事考課制度の問題点

最初にお話したとおり、日本の介護施設が人事考課を取り入れたのは、外部からの圧力によるものが大きいです。
もし施設のトップが理論的に職員の評価を行いたいと思うのならば、人事考課制度が流行る前に、とっくに独自の評価システムを作っていると思うのです。現に私が今でも最もリスペクトする東京都町田市のとある施設は、独自の評価制度を取り入れています。
つまり、人事考課を取り入れる前に、トップ層の方や中間管理職が
「職員を適切に評価してあげたい」
「適切に評価することで、給料やボーナスに反映させたい!」
という気持ちがなければ、よくわかっていない人事考課制度を取り入れてもあまり意味がないと思います。
介護に限った話ではありませんけど。
そんなわけで、ここからは人事考課の問題点をあげていきますね。
問題点①<コストがかかる>
人事考課制度には様々なコストがかかります。
まず導入にあたってコンサル料。コンサル業の人はこれをウリにしているんだから良いんですが、ただでさえお金のない介護保険施設にとって、年間ウン百万というコンサル料はけっこう痛い出費な気がします。
それだったら少しでも職員の給料上げてほしいって思ったこともあります。その理由はこれまた後述します。
コンサル料だけじゃなく、管理者向けの研修は定期的に行う必要があり、講師はコンサルの人です。さらに、管理職は定期的に行う人事考課の評価で残業がしいられます。
もともと中間管理職というのは現場の介護もしながら、他の事務もしなければならないのですが、この人事評価も、評価の記入〜面接までいろいろ大変です。もちろん、ここにも残業代というコストが発生します。
問題点②<途中で人事考課制度をカンタンにやめられない>
2つ目の問題点は人事考課制度を途中で、
「やっぱコストかかりすぎるから辞めるわ🐸」
というように、放り出すことが非常に難しいということです。
職員を適正な評価をするために始めたのに、それを辞めるということは、評価をする取り組みを辞めるということになります。
問題点③<訪問ヘルパーなど、単独行動をしている人の評価がしづらい>
3つ目の問題点は、訪問ヘルパーなどの単独で業務を行う職員の評価を、管理職がしづらいという点です。
人事考課の評価項目には、様々な項目がありますが、例えばその中に
●お客様に対しての声掛けなどの接遇
という項目があったとします。
でも、単独で業務を行う訪問ヘルパーが一人でどれだけの接遇をしているか、基本管理職が確認することはできないのです。
私が管理職になったとき、人事考課研修を受けたわけですが、訪問介護・看護の部署から実際にこのような問題点を指摘する声があがりました。
しかしその時、トップ層から信じられない返答が!
「そこは想像で評価してください。実際に確認できないなら、その職員と面接した時にその職員に確認するとかでも良いかもです」
私は
(・o・;)「え? そんなんでいいの?」
(ポカーン…)
と思ってしまいました(唖然・・・
たしかに直接見ていないものを評価できないんです。でも、想像じゃダメだと思いますし、人事考課の導入やコンサル料にウン百マンもかけているのに、こんなテキトーで良いのだろうかと思いましたね。
せめて、お年寄りやご家族にアンケートをとるとか、間接的に確認する方法もあったのではとは思いますが。
問題点④<結局、評価が給料や賞与に反映されにくい>
人事考課制度導入の目的のひとつ・・・というか最大の目的かもしれませんが、評価をきちんと給料や賞与に反映させることです。
そうすることで職員のモチベーションアップになり、さらに仕事に情熱を燃やしてくれると期待すると思います。
しかし残念ながら、介護保険によって経営される施設では評価が給料に反映されることは難しいです。
まったく反映されないわけではないでしょう。たしかに私が給与明細を見ると、評価制度による項目がしっかり設けられており、数字が書かれています。
しかしそこに書かれている額は雀の涙。管理職の私がAが多い評価で数千円。
(´;ω;`)「これだけがんばって、上司からもしっかり良い評価をされているのに、これだけの額?」
・・・というように、かえって、人事考課がモチベーションダウンをまねくこともあります。
コンサルにかけるコストを、職員の給料にまわしてほしいな…と思いましたね。
問題点⑤<管理職によって全然違う評価>
まぁ、これはちょっと仕方ない面もあります。
たとえば平社員の介護職員が50人いれば、何人かの中間管理職(現場の副主任とか)で担当を振り分けて評価をしていくことになるだろうと思います。
人間ですから、好き嫌いもあります。これはどうにもならないこと。
しかし好き嫌いにとらわれず、管理職全員が適正な評価を心がけてつけたとしても、やはり評価は偏ってしまうのです。
私自身も管理職として部下の評価をしていたときに、お叱りを受けたことがあります。
「アルゴさんがつける評価は全体的に甘すぎる。アルゴさんの担当職員はA項目が他の管理職の担当者に比べて多すぎるんだよ」
と言われました。
まぁ、厳しすぎると言われるよりもイヤな気分はしませんでしたが、やはり偏りがあるというのは問題なんですよね。
でも、もっと問題なのは、多数派の評価基準が正しいということになってしまうこと。
私自身はきちんと部下を評価したつもりでいたのです。厳しい部分は厳しくつけましたからね…。
人事考課制度の改善点(職員の適正な評価制度として)

繰り返しになりますが、私は人事考課制度が導入されて、職員が論理的に評価されるようになったというのは良いことだと考えます。
昭和のような、体育会系の上司が「オレについてこい!」という時代は終わったのです。若い職員にそんな態度で接ししていたら、ウザがられますね。
論理的な評価というのは、最近ご利用者のLIFE加算が導入されたことからも必要なことだと考えます。
しかしお金のない介護施設からすれば、あえて人事考課制度を導入しなくても良いというのが私の考えです。
それでは、どのような評価制度が望ましいのか?ここからは私の成功談・失敗談なや知識に基づく提案になりますが、いくつかお話したいと思います。
①<人事考課制度を辞めるのではなく、より適正な評価システムに切り替えると説明する>
先程お話したように、一度取り入れた人事考課は
「✋やっぱお金かかるので、や〜めます♪」
・・・というように、カンタンにやめることができません。
ですので、コンサル料や研修費、残業などのコストがかからず、そのぶんみんなの給料や賞与に反映されられるシステムに移行するといえば、皆も納得するでしょう。
そうすれば、職員の評価制度というカタチはしっかり残すことができます。
②<施設や部署独自の評価項目を作る>
人事考課制度が最初に私の施設に導入された時、その評価項目に全て納得できたわけではありませんでした。
まず、企画力・・・発想力・・・というような、一般企業なら必要であるかもしれないものを、そのまま介護の人事考課に導入されていたことにびっくり。
まぁ、デイサービスであればレクリエーションなどをしたり、お祭りの計画などもこうした評価項目に入るのかもしれないですが、すべての職員に当てはまるわけではないのです。
項目じたいは悪いものというわけではないですが、問題は
●すべての部署
●管理職・正社員・パート
すべての職員にこれが課せられていたのです。
うーん、企画力があまり関係ない職員もいたんじゃないかなと思います。
他にも『接遇力』という項目。一日中厨房に入りっきりで食事を作っている調理スタッフに、接遇力なんてなかなか評価しづらいでしょう。
ただし、『人事考課制度』のうえで、部署ごとにバラバラの評価項目を作ることは、これまた部署により評価項目が偏ってしまうので難しいのです。
しかしながら、先程の訪問ヘルパーの例もしかり、他の部署と同じ評価項目ではぜったいに評価できないようなこともあるのです。
なので、人事考課制度ではなく、施設独自の評価システムを取り入れて、部署ごと、職員ごとに評価をできるカタチが必要なのだと思います。
③<面接の必要性>
紙面の評価も必要なのですが、やはり上司と部下の直接的なコミュニケーションにまさるものはありません。
上司・部下・同僚はふだん、イヤというほど顔をあわせているとは思いますが、『面接』というかたちで一対一で話すのはまた違うものです。
人事考課制度の良い点は、面接が位置づけられているところ。シフト制の介護の世界では日程調整は大変ですが、コレは本当に大切なものだと私は確信します。
そして、定期的な面接が位置づけられている施設と、そうでない施設では離職率が全然違うように思えました。
ふだん言えないようなことも面接では言うことができたりします。私はそれを管理職の立場からも、いち平社員の立場からも感じることができました。
たとえ人事考課制度を別の評価制度に変えても、面接の機会は必ず設けるべきであると思います。
現場から発信しよう
コンサルというと聴こえは良いですが、けっきょく第三者ビジネスなのです。
成果を上げているコンサルはあるかもしれませんが、導入しても全く何も変化もない場合はただただコストや時間が無駄になってしまいます。
そして現場の職員は、自分たちの関わりのないところで、新しい制度を導入され、困惑することも多いです。
新しいコトの導入は、介護保険制度上、仕方のないものもありますが、『人事考課制度』などべつに義務化されていないものを導入することは、本当に多大なコストをかけてまで必要なものなのか・・・?ということを考えることは大切です。
やはり現場の職員は、しつこいほど意見をトップにあげていくしかありません。愚痴を言っているだけでは何も変わらないので、たくさん提案をしていきましょう。
こういったことは、現場職員目線で書いた著書の中で、びっちり書いていますので、良かったらそちらも見てくださいね。
↓↓↓
介護リーダーの『裏』教科書
https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B091XPN678
サポートですか・・・。人にお願いするまえに、自分が常に努力しなくては。
