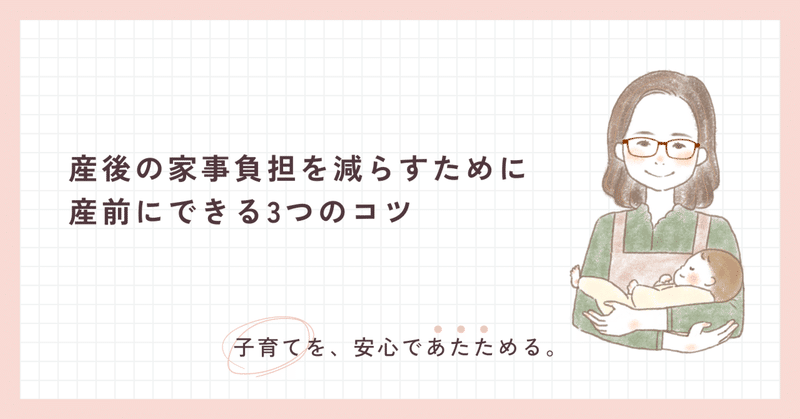
産後の家事負担を減らすために、産前にできる3つのコツ
産後は、自分の心身のケアと、赤ちゃんのお世話が同時に始まる。
日本には、昔から「床上げ」という風習がある。
産後21日間は、布団を敷きっぱなしにして、赤ちゃんのお世話以外は横になって休みましょうという習慣だ。
助産師として、この「床上げ」を強くお勧めしたい。
とはいえ、里帰りをしなかったり、実家に頼れない、サポートしてくれる人が周りにいない中で、産後を過ごす人が増えている今、「床上げ」の産後21日目まで、家事を全くしないで過ごすことが難しい状況の人が多い。
そこで、産後に家事をパートナーに頼む場合に、お互いに家事負担を減らすために産前にできる3つのコツについて紹介しよう。
①産後の生活を計画するときには、産後ママとパパのタイムスケジュールを書き出してみる。
「頼りにできる人が、パートナーしかいない」状況だと、必然的に、パパに家事や育児を頼むことが増える。そうすると、パパへの負担がぐっと重くなる。
産休や育休をとる男性が増えてきているとはいえ、仕事をしながら産後のママをサポートするパパは多い。
パパへの負担が大きすぎると予測されるときには、有料サービスや便利家電などの活用を、もっと導入できないか検討する必要があるだろう。
②誰もが家事をしやすいように、物の配置や環境を整備する。
いつも使う調味料や調理器具が、手に取りやすいところに置いてあれば、ぐっと料理がしやすくなる。
また、洗剤などの消耗品や日用品のストックは、「いつも同じ場所に」置き場所が固定されていると、とても便利だ。
家事ヘルパーさんや、シッターさんが入るときにも、スムーズにサービスが受けられるし、何よりも自分自身が、家事をしやすくなるメリットがある。
産後の生活のために、「誰もが家事をしやすい環境作り」はとても大切だ。
③自分にも、自分以外の人にも、「家事の質をどこまで期待するのか」を線引きしておく。
家事や育児をどの程度までしあげれば「ちゃんと家事をした」ことになるのか。
それは人によって様々だ。
家事や育児の技術力も、人それぞれだろう。
自分が安静にしなければならなくて、家事を人に依頼すると、「自分だったら、こうするのにな」ともどかしく感じることもあるだろう。
でも、自分にも、人にも、「完璧」を求めてしまっては、産後はとても窮屈なものになってしまいます。
その時々の「今のベスト」が尽くせたならば、「それでOK」と気にしないことも、時に必要だろう。
・・・・・・・・・・・
「人に迷惑をかけちゃいけない」「自分のことは、自分でやりなさい」と幼少期から言われてきた私たち。
産後は人に頼ることが必要だけれど、人に頼ることが後ろめたかったり、何となく苦手な人が多いように感じる。
産後は、心身の調子を整える、大切な時期です。
ぜひ、上手に人を頼って、しっかり休息をとって、過ごしていただきたいと願っています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
助産師hana【子育てを、安心であたためる】
妊娠出産・子育てが、人生を彩るしあわせになって、たくさん花咲きますように。
親子の暮らしの中で見つけた、しあわせの種やその温めかたをnoteでお伝えしています。
ぜひフォローして下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
