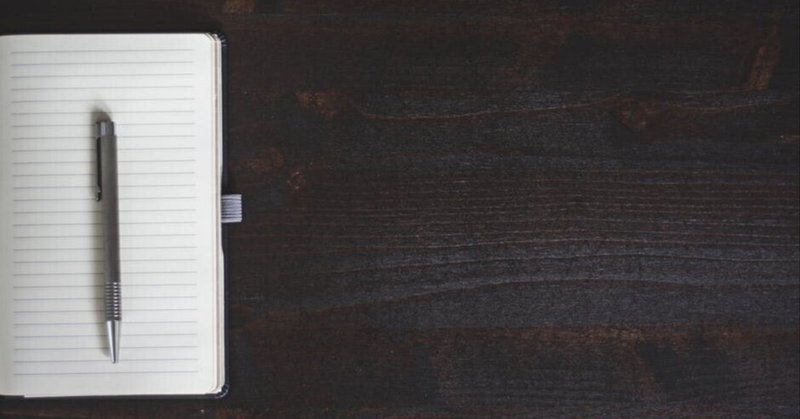
祖母のジャーナリング
珍しく、今期は朝ドラを観て楽しんでいる。
「虎に翼」は、日本史上初めて法曹界に飛び込んだ実在の女性のストーリーに基づくオリジナルの物語だそうで、連日話題になっているほど人気が高いようだ。
このドラマの素晴らしいところは多くあるのだが、手帳好きのわたしとしてはぜひ話題にしてほしいのが、寅子の母はるの手帳習慣のことだ。
はるはいつも、日常的な記録から思いまで手帳に綴っている。
記録を取り、文字にすることでマインドを整理するタイプなのだろう。
ドラマの時代設定は昭和初期。その時代に手帳習慣を持っていた女性がどれくらいいたのか興味深い。
そこで思い出すのが母方の祖母のことだ。
昭和元年生まれなので、ドラマに登場する女性たちの世代設定よりひとまわりほど年若いが、ちょうどこの時代を生きたひとりでもある祖母は、いつも記録をつけていた。
わたしも子どものころから、祖母がノートにしょっちゅう何かを書いているのを目にしていた。
ひとつは日記である。
A4サイズの大学ノートだったと思うが、それを横向きにして縦書きの日記を書いていた。その日の出来事をあっさりとメモするだけのとても短いもので、せいぜい三行程度だったのではないかと思う。
毎日日付と日記を書き、終わると定規を使って縦の線をびっと引いてその日を締めくくる。
実にシンプルなものだが、おそらく何十年と続けてきたのだろう。
もうひとつは、家計簿である。
昔から、買い物をしたらすべてノートに書きつけ、一円単位でお財布の残金を照合するのを日課としてきた。これは、本当に何十年も前からやっていた習慣らしい。
日記と家計簿だけでも、気が遠くなるような年月毎日のようにつけていれば、その情報量は半端ない。そして、個人的な記憶だけでなく、社会情勢や経済情勢を知るためにも貴重な資料となる。
わたし自身は、日記的な記録を一日一ページの手帳に書き込んでいる。今は、ジブン手帳Days miniという手帳を使っている。
当日の予定だけでなく、実際にどこへ行き、何を食べ、誰に会ったなどメモ書きのように記録し、ついでに思ったことを短く付け加える形式だ。
あとは、自宅に置いてある5年日記にまとめている。
思いを綴ったり、ブレインストーミングをしたり、マインドの余白を作るためのジャーナリングは、すべていつもバッグに入れている普通のノートを使用する。この習慣は学生時代から続いていて、現在使用中のノートはモレスキンだ。
旅に出るときは、荷物を軽くするため軽量ノートを使って旅ジャーナリングをしている。
ジャーナリングの良さは色々あるが、やはり記録という面でも非常に重要な役割を担ってくれるものだとつくづく思う。少し前のことでも、一年前のことでも、気づかぬうちにすっかり忘れてしまっているのだ。
その時に何をしたのか。何を思ったのか。
今月、ちょうど一年前にボツワナを旅したときの旅エッセイ本を出版するため、一気に原稿を書いていたのだが、その時に何があったのかなんてすっかり忘れていることが多いのにあらためて気がついた。でも、記録していたことで、気持ちが蘇ってきて、結果としてきちんとした文章に落とし込むことができた。文章に書きまとめるという点でも、わたしにとってジャーナリングは欠かせないのだ。
大正時代の終わったころに生まれた祖母は、ちゃきちゃきのタイピストだった。
長女として兄弟を支え、スポーツウーマンでもあった。美人で新聞にコラム記事が載ったくらいだ。
そんな祖母は、あるとき何十年分にも及ぶ家計簿と日記帳をすべて処分してしまったらしい。
祖母の個人史だけでなく、社会や経済についても知ることができる大切な資料のはずだとは思うが、本人にはきっとそんな意識はないのだろう。
現在、90代も後半になった祖母は、昔のような快活さはなく、お茶の間で昔話を延々と語ることもなくなった。記憶は祖母の心の抽斗の中にしまわれたまま、鍵がかかって取り出せなくなっている。
そんなとき、あのたくさんのノートがあればと思うこともあるが、失われることもまた人生なのかもしれないな、と思うこともあるのだ。
===
雨雲ラジオでもお話しました。standfm、spotify、apple podcastで聴けます
エッセイ100本プロジェクト(2023年9月start)
【20/100本】
言葉と文章が心に響いたら、サポートいただけるとうれしいです。

