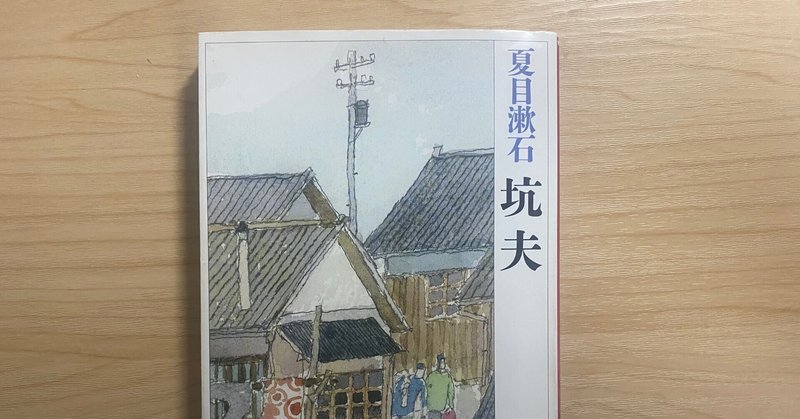
夏目漱石 「坑夫」 書評
夏目漱石の「坑夫」を読みました。
いつもの通り、あらすじと感想を書きました。
「坑夫」は明治41年(1908年)の作品です。
漱石が朝日新聞に入社してから「虞美人草」に次ぐ、2作目となりますので、初期の作品と言えるでしょう。この次に「三四郎」から始まる、いわゆる初期三部作が執筆されます。
漱石は島崎藤村の原稿遅れの穴埋めをすべく、未知の青年(荒井某)から提供された話をもとに「坑夫」を書いたそうです(新潮文庫 「坑夫」巻末解説より)。
ですので、本人の体験があまり素材となっていないところが、他の長編作品と比べて少し特異な点だと思います。
同じ頃に書かれた「三四郎」「夢十夜」「それから」などと比べると、埋もれがちな作品かもしれませんが、ところどころに漱石の哲学が垣間見えて、面白かったです。
※ネタバレ注意
あらすじ
東京の良家のお坊ちゃんである主人公は、恋愛のもつれから、着の身着のまま実家を飛び出してしまう。
自暴自棄になった主人公は、あてどもなく町外れを歩き続けていると、掛茶屋にいたどてらを着たオヤジ(長蔵)に突然声をかけられる。
「御前さん、働く料簡はないかね。どうせ働かなくっちゃならないんだろう」(長蔵)
「働いてもいいですが」(主人公)
長蔵は、俺のいう通りにすれば坑夫にしてやると言う。
明らかに怪しい誘いだが、主人公は放浪の身で半分ヤケになっていることもあり、これを了承し、長蔵に連れられて鉱山に向かう。
長蔵は、道中で赤毛布(あかけっと)を着たみすぼらしい男や、ひもじそうにしている小僧にも、坑夫にして儲けさせてやると声をかけ、連れていく。
長蔵は、身寄りのない男を坑夫に誘い出すポン引きである。
やがて、鉱山に到着すると、主人公は長蔵たちと別れ、崖下に数多く並んでいる飯場(はんば)と呼ばれる長屋に入れられる。
そこで、主人公は坑夫に白い目で見られ、嘲笑の的にされる。
やがて、主人公の身を案じた飯場頭からこう言い放たれる。
「……まあどうして、こんな所へ御出おいでなすったんだか、
(中略)
第一坑夫と一口に云いますがね。なかなかただの人に出来る仕事じゃない、ことにあなたのように学校へ行って教育なんか受けたものは、どうしたって勤まりっこありませんよ。……」
しかし、主人公は帰る当てもないから、自分を坑夫にしてくれと譲らず、飯場頭は仕方なく了承する。
その日は長屋で夜を過ごしたのだが、出された南京米の不味さや、布団の中で南京虫に噛まれたりして、坑夫生活の劣悪さを垣間見る。
明くる日、主人公は先輩坑夫(初さん)に連れられて坑内へ見学にいくと、暗く、狭く、あまりにも危険で劣悪な労働環境を目の当たりにする。
初さんは坑内をどんどん進んでいってしまい、極度に疲労していた主人公はついに置いてけぼりを喰らってしまう。
坑内で完全に迷ってしまった主人公は、安さんという若く、たくましい坑夫に出会う。
安さんにこれまでの顛末を話すと、お互いに身の上を明かし始める。
安さんは高等学校を出たあと、止むを得ない理由で、事件を起こしたため、社会から追放され、しかたなく坑夫に成り下がった身であった。
安さんは高等学校を出たばかりの主人公に大きく共感した上で、坑夫にはなるなと諭す。
「日本人なら、日本のためになるような職業についたらよかろう。学問のあるものが坑夫になるのは日本の損だ。だから早く帰るがよかろう。東京なら東京へ帰るさ。そうして正当な――君に適当な――日本の損にならないような事をやるさ。何と云ってもここはいけない。旅費がなければ、おれが出してやる。だから帰れ。・・・・・」
坑夫の非人情さを肌で感じてきた主人公は、安さんの優しい言葉を聞いて、感動する。
そして、主人公は安さんの提案を断り、帰る旅費が貯まるまでどうしてもここで働くと、改めて伝え、無事に坑の外へ連れ出してもらった。
その後、主人公は、診療所で気管支炎と診断され、坑夫になることはできないと医者から告げられる。
帰る気はない主人公は、飯場頭の提案で、飯場の帳付けの役目をもらい、5ヶ月後、鉱山から去ったのであった。
ーーーーーあらすじ終わりーーーーー
感想
ストーリー自体には特別、面白い点は見られないが、主人公の矛盾した言動や心情に乗せた、人間の「不確かさ」や「頼りなさ」に関する漱石の考えが面白かった。
後にいろいろ経験をして見たが、こんな矛盾は到る所に転がっている。けっして自分ばかりじゃあるまいと思う。近頃ではてんで性格なんてものはないものだと考えている。(中略)
本当の人間は妙に纏めにくいものだ。神さまでも手古ずるくらい纏まらない物体だ。
(略)…人間ほど的あてにならないものはない。約束とか契とか云うものは自分の魂を自覚した人にはとても出来ない話だ。またその約束を楯にとって相手をぎゅぎゅ押しつけるなんて蛮行は野暮の至りである。大抵の約束を実行する場合を、よく注意して調べて見ると、どこかに無理があるにもかかわらず、その無理を強しいて圧しかくして、知らぬ顔でやって退けるまでである。決して魂の自由行動じゃない。
このような記述が多く見られる。
「お前の作品は矛盾だらけだ!」のようなケチを付けられたことに対する漱石の反発ではないかと勝手に予想したがどうなのだろう?
でも言ってることは、的を得ていると思う。
過去の言動をほじくり返して、今との矛盾を揶揄するのは、誰しもやりうることだろうが、実際には、人間自体にそこまで一貫性があるわけではないだろう。
人間は、その時の気分で、思想や信条も変わってしまうくらい当てにできないものである。特に自分は、昨日と今日で言ってることが真反対であることなんてしょっちゅうである。
でも、人間はその性質に逆らって、他人と自分に完璧なる一貫性を求め、一貫性がある人間は「責任感がある」とみなされるのである。
それ自体は間違っていないと思うが、自分みたいな無責任な人間には、どうにも息苦しい。
言ってしまった以上、途中で事情がどう変わったとしても、それを守り抜かないといけないと考えて苦しんでいる人は多いであろう。
もちろん、昨日と今日で言っていることがコロコロ変わる人を信用することはできないし、物事も円滑に進まなくなることは間違いないと思うが、もう少し手綱を緩めておおらかに、生きてもいいのかなと思ってしまう。
言行不一致もそうだが、性格だって年単位で見れば、見た目以上に、いかようにも変わるだろう。なので、判を押したようにその人がどんな人であるのか決めつけるというのも危険だと思う。
引用の漱石の主張を読んで、多少なりとも生きづらさを感じている自分を後押ししてくれたような気分になった。
坑夫生活に関する描写も、迫真に迫るものがあり、実際に漱石が体験したのではないかと思われるくらいであった。
坑夫たちにヘコヘコすることなく、坑夫生活に慣れようとしている主人公をいじらしく感じ、感情移入してしまった。なんども挫けそうにはなり、困難を乗り越えていくという、よくあるパターンであったが、この作品だとあまり臭い感じはない。
また読みたいと思うような良い作品だった。
ーーーーー感想終わりーーーーー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
