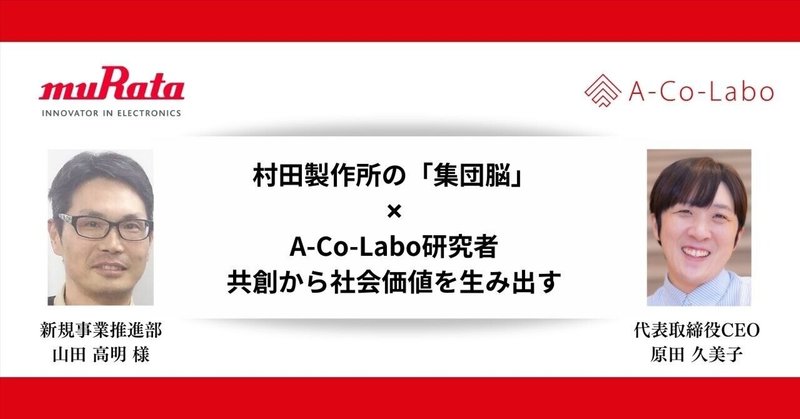
村田製作所の「集団脳」✖A-Co-Labo研究者の共創から社会価値を生み出す【村田製作所様インタビュー】
グローバル化や技術のイノベーション、市場ニーズの急激な変化といった社会環境を背景に、事業創出サイクルの短期化が強いられています。そのため既存事業のみだけでなく、自社の強みを捉えた上での新規事業開発が重要となってきています。
そこで、A-Co-Laboの新規事業創出支援サービスでは、技術に詳しいパートナーが伴走しながら、ユーザーニーズ、社会課題を起点として新規事業創出に向けた研究知の提案を行います。
今回のnoteでは、技術の用途探索において社内でアイディアの行き詰まりを感じていたという、村田製作所 新規事業推進部の山田高明様にインタビューさせていただきました。
株式会社 村田製作所
村田製作所は、革新的な技術やソリューションの創出により、エレクトロニクス社会の進展に貢献しています。
材料から製品までの一貫生産体制を構築し、小型、高機能、薄型化などエレクトロニクス業界のトレンドをリードしています。
製品の90%以上が海外で販売されるなど、グローバルであらゆる地域のお客様に技術、製品、サービスを提供しています。

技術・事業開発本部 技術企画・新規事業推進統括部
新規事業推進部 新規事業推進5課
山田 高明 様
実施内容と結果

~以下は実際のインタビュー内容になります~
新規事業の課題は、
技術と事業視点を持ったスキル育成
A-Co-Labo原田:技術ベースにした新規事業の課題感について教えてください。
弊社は名前の通り「製作所」なので、やっぱり技術ベースでビジネスを回していく文化や歴史があって、今後もそれは変わりないです。ただ技術開発だけではビジネスにならないので、事業開発も同時並行的にすり合わせしながらやっていかないと事業としては成立しない。一言でいうと事業と技術のバランスが難しいです。
A-Co-Labo原田:どちらかが先に出ても難しいですよね。
そうですよね、どちらが先行しても上手くいかないんですよね。そういうタイムリーに両立させて進めていく仕組みが重要になります。
A-Co-Labo原田:どのように仕組み化をされていらっしゃるのですか?
技術担当者のスキルを今育てており、少しずつ成果を上げていっているところです。やはり製作所として事業を継続させるためには、コア技術の開発というところが基盤技術になるので、技術担当者の育成は外せないと思っています。
A-Co-Labo原田:プロジェクトをご一緒させていただいた技術者の皆様も事業開発の知識をお持ちの方が多いと感じました。これもスキル育成の成果なのでしょうか?

前段申したように、事業開発と技術をセットでやらないといけない。それを組織で分割するのも一つですけど、1人の担当が両方見ることができれば、それはそれで良しと、教育も含めて仕組み化を進めているところです。
A-Co-Labo原田:このような人材の仕組み化に関しては、社内風土や文化なども関係し、かなりハードルが高い感じがしますが、村田製作所ならではのコツがあるのでしょうか?
弊社ではスキルを持った者がリーディング的伴走を行っています。ただ寄り添うだけではなくて、最初の部分をきちんとリーディングしていき、担当者が慣れてない部分をケアしています。最初をきちんとケアすることで、割と心理的な安全性が担保されるんですよね。
事業開発に慣れている技術者が、慣れていない技術者をサポートしながら、風土醸成のプラスのスパイラルを回すと、割と裾野が広がるというか、ボトムアップできる感じは、感触として掴んできたところです。
A-Co-Labo原田:心理的に安全が確保された中でリード伴走する形はお互いにとってプラスのスパイラルだし、知識の循環ができる仕組みですね。村田製作所が掲げる集団脳のコアな部分に繋がる感じがします。初回を誰がリードするかもすごく重要ですね。
そうですね。A-Co-Laboのサービスのような共創支援サービスはあるけども、最初の一歩が出ずに「使ってみたいな」で終わってしまうんですよね。僕がリーディングするから一緒にやりましょうって言ったら、安心してついてきてもらえる。これが重要だと思っています。

A-Co-Laboサービスの導入、
その後の成果
A-Co-Labo原田:サービスを立ち上げてまもない段階で導入していただきましたが、A-Co-Laboのどのようなところに可能性を感じたか教えていただけますか?
担当の感度や決断の視点はそれぞれ違いますが、私の場合は、原田さんと話すとき意気投合したのが一番大きなポイントでした。
私の場合は誰と出会うか、その人とどう意気投合するか、この人と一緒に仕事したいと思うかなんですよね。
A-Co-Labo原田:初回に「知と知の融合」の話とか、コア技術の開発機能がどんどん薄れていって、日本のもの作りの危機感話で盛り上がりましたね。

そういう内容に共感できたので、ぜひここはアカデミアの知と知の融合をして、イノベーションの底力をまた復活させたいと思いました。実際この課題を解決するサービス実現される方は少ないじゃないですか。そこの行動と覚悟がおありだったので、いやこれは一緒に共創させてもらって、ビジョンの実現に向かっていきたいなって思いました。
A-Co-Labo原田:そう言っていただけると、やって良かったと心から思います。
実際に初回に複数案件いただき、用途探索のアイディアコンペや研究者とのスポットインタビューでご一緒させてもらったのですが、初回案件に関しての成果に関して伺ってもよろしいですか?
初回は2つのテーマでしたが、アカデミアとの実績が出ました。
1つは素材に対しての新機能の探索、もう1つは潜在用途の探索をA-Co-Laboさんと一緒にやらせてもらったのですが、どちらに関しても社内で見えなかった要素をアカデミアの皆さんと一緒に探すことができ、もう一段上のフェーズのアプリケーション開発に進んでいます。いずれも1歩2歩先に進んだ感覚はありますね。
A-Co-Labo原田:ありがとうございます。事業創出のはじめの一歩で成果を感じていただけてとても嬉しいです。この案件をきっかけに追加案件を複数いただくのですが、横展開の決め手はどこだったのでしょうか?
初回案件はとても重要で、どういう目的でどういう成果を出したかが社内の口コミで広がっていかないといけないです。
1つ目の案件で成果を得られたところが、第2第3の社内のユーザーを産んだといったところですね。「こんないいことあるよ」っていう宣伝をしていたら、「自分も使ってみたい!」という手が上がった感じですね。

村田製作所が感じた
A-Co-Laboのメリット
A-Co-Labo原田:A-Co-Laboのサービスにおいて「ここがよかった」という点などあれば、ぜひお聞かせください。
アカデミアの方々と技術的な融合ができること、社内にはない新しい用途や技術的発見ができるというところですね。大学との共同研究を進めるときに、全国行脚しないといけないんですよね。これがすごいコミュニケーションコストがかかる。
A-Co-Labo原田:研究者を探し会いに行く、これらの工程に結構時間がかかると、皆さんおっしゃいますね。
A-Co-Laboさんは、このコミュニケーションの部分をマッチングしてくださってコストカットしてもらえるだけでなく、課題にふさわしいパートナーの方と出会えることで選択肢を広げてくれるところは非常にメリットを感じます。
今後もいくつかのテーマで相談するかなと思いますので、よろしくお願いします。
A-Co-Labo原田:ありがとうございます。パートナー研究者も増えたので、またご提案できたらと思います。

共創は相互補完をしながら
イノベーションを加速する手段
A-Co-Labo原田: 山田さんはセレンディピティ(偶発性)という言葉を用いて共創のお話をされることが多いなと感じています。アカデミアとの共創はまさにセレンディピティかなと感じていますが、山田さんが考える共創に関してお聞かせください。
感性がそもそもエンジニアなので、アカデミアの皆さんと壁打ちすること自体が楽しい気持ちがあります。ただ事業体なので、その楽しさをいかにビジネスとして成り立たせるかという視点も重要です。
A-Co-Labo原田:技術と事業の両輪の視点ですね。
ただ自社開発は限界があって、特に弊社のような分野でビジネス領域を広げて、戦略のもと事業化を進めている会社においては、我々が慣れてない分野の知らない技術をいきなり自社開発しようとすると、非常にコストがかかります。
慣れてない位置に踏み込んでいく時に、まずは慣れている人のナレッジや経験をお借りするといった、そういう意味の共創は必要不可欠だと思っています。特にアカデミアやスタートアップとか、技術の一部分でも共創する形で、我々のコア技術を吹き込めばさらに進化するパターンは今後あり得るのかなと。

A-Co-Labo原田:共創は両者にとってメリットがある形も重要かなと思っています。その点いかがお考えですか?
大企業の総合力を活かし色々なGIVEの仕方があると思います。例えば、クオリティを高めるのか、コスト、大量生産でコストを下げるのかや、メンテナンスサービスでサポートするのかなど。技術だけでWin-Winの関係というよりかは、全社のアセットを見渡して、どれが必要か見極めた上でギブできたらいいなと思います。
A-Co-Labo原田:アカデミアもスタートアップも「ないもの」の方が多いので、大企業の総合力は魅力的です。双方補完し合う形の共創がもっと広がると良いなと感じます。
村田製作所の集団脳✖研究者の可能性
A-Co-Labo原田:集団脳を活かしたものづくりを通した価値創造に関して教えてください。
村田製作所はやはり技術にこだわりのある会社です。新しい技術の機能を持って、社会価値を出すところはこだわりつつ、スピード感を持って社会に貢献したいなと思っているんです。
なので、技術へのこだわりの部分でアカデミアやスタートアップと共創しあえる仕組みが作れないかと常々思っています。
A-Co-Labo原田:研究者側からの提案も可能なのですか?
はい、可能です。その仕組みがKUMIHIMO Tech Camp(※1)という共創プロジェクトになります。我々の持つ色々な電子部品や商材を使って、社会価値が出そうという提案があればぜひお願いします。
A-Co-Labo原田:ワクワクする共創プロジェクトですね!ぜひ社会実装に挑戦したい研究者へ一言お願いします。
弊社は車載事業に力を入れているところがあり、MaaSサービスに関連する技術を、今自社開発していたり、スカウティングしていたりするので、関連する方や詳しい方とまずは情報交換からさせていただきたいなと思っています。
それだけに関わらず、研究者の視点から「この技術は必ず役立つはずだ!」みたいなものがあれば、どんどん提案して欲しいなと。
アカデミアの研究者に期待するのは事業体ではできない「長期的な視点」です。事業を見据えた技術開発となると、どうしても難しい部分が出てきます。実現に向けて一緒に向かっていける形を作っていければ、長期的なビジョンや、研究者視点での知見を共有していただければ、新しいもの・ことづくりに繋げるきっかけになるのではないかと思います。
A-Co-Labo原田:将来を見据えると、研究者の視点も重要であるという言葉は、研究者も社会に挑戦するきっかけになると思います。まさに「集団脳」を活かしたものづくりに向けて、研究者と一緒に価値創造できる場をもっと増やしていこうと思いました。今日はありがとうございました。

※1 KUMIHIMO Tech Camp
https://solution.murata.com/ja-jp/collaboration/kumihimo-tech-camp/
・・・
A-Co-Laboについて
弊社では研究者が持つ、研究経験・知識・スキルを活かして企業の課題を解決することを目的としています。研究者のキャリア問題に課題を感じている研究者3名で立ち上げました。
弊社の事業内容を始め、立ち上げの想いやクライント・パートナー研究者の声などが紹介された動画はこちらからご覧いただけます。
【企業の方】
「誰に相談していいかわからない」という課題に対し、パートナー研究者達を含めたA-Co-Laboチームが解決に向けたサポートを行います。新しい挑戦をしたいと思っている企業様と、社会に挑戦したい研究者の共創の場を作っています。
研究者との接点がない!といったお悩みや、新規事業にまつわる疑問や相談、アイディアレベルのものまで、何でも受け付けております。
初回相談は無料!0からサポートいたします!😊
【研究者の方】
自身の研究経験やスキルを本業だけでなく、副業・兼業といった形で活かしてみませんか?
弊社では短期から中長期まで、研究者に合った様々なプロジェクトへの関わり方をご提案しています。
これまでの研究で培ったナレッジやスキルを、プロジェクト単位で企業の事業開発に提供することができます。またプロジェクト毎に専属のコーディネーターが伴走することで、安心してプロジェクトに参画することができます。
また、A-Co-Laboは企業でのビジネス経験を持つ研究者で運営しています。自身の研究者としての経験を活かしたキャリア形成について、いつでも無料で相談が可能です。
興味が湧いた研究者の方、企業の方がいらっしゃいましたらこちらからお問い合わせ下さい。
ご登録希望の研究者の方はこちらから登録申請していただけます。
[関連記事]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
