
西坂に行ったことと巡礼にまつわる疑問など
西坂で処刑された日本二十六聖人、そしてその地を願望できるかつての外国人居留地に建つ大浦天主堂のことをこの間書いた。そしてそのうちに、とおもっていた西坂のその場所にさっそく行ってきた。
車を停めて、二十六聖人記念館前に公園として整地されている場所に立ってみたけれど、案の定目線を遮る建物が多すぎて、ここから大浦天主堂界隈はとうてい見渡せない。当時はこんなふうに高い建物はなかったろうから、目を凝らせばきっと見えたであろう。
今回は記念館やフィリッポ教会に入ることはしなかったんだけれど、観光客とおもわれる数人が行き来していた。いいことだとおもった。
そんなことをしていたら、ちょうど1年前に東彼杵にある二十六聖人乗船場跡を訪ねたのを思い出した。
26人(前半は24人、途中で2人が加わった)の殉教者たちは京都から各地を通り、1597(慶長2)年の2月4日に東彼杵の浜辺(彼杵港)から、船で時津港へと渡り、そこから浦上街道を歩き、翌日2月5日に西坂の地で処刑された。東彼杵の乗船場には記念碑がある。

*
いま手元に、2013年に発行された『日本二十六聖人 長崎への道 巡礼Map』という本があって、それを開いてみた。1597年1月3日の京都ひきまわしから始まって、2月5日に西坂に到着するまでの足あとを辿って、各日の始点と終点、行程やエピソード、宿泊地、現代の道路状況に沿った推奨ルート、順路に沿った交差点やルート上の風景写真などで構成されている。史実と照らし合わせながら、実際に足をつかって作ったんだろうと想像される1冊だった。そういえばこの本は評判がいいと聞いていた。
昨年からは、長崎県が世界遺産と絡めた『世界遺産巡礼の道』という企画に着手していて、今年3月にルートブックが出来上がっておりそれも手元にある。この企画はルートブックがまとめられる以前、もっと簡易な各エリアの巡礼路がホームページ上で公開されていた。昨年東彼杵やその他いくつかを巡ったのは、その簡易版を参考にし、試しにちょっと辿ってみるという仕事の上でのことだった。
そのときの印象というのが、とても実用とはおもえないというか、机上で設定されたルートなんじゃないか、というものだった。私はこの中からいくつかのエリアを選び、徒歩でなく車で走って各ポイントを巡ったのだったけれど、「ここ、歩くの?」と首をひねる箇所がけっこうあったのだ。
具体的なところでいうと、雲仙市から南島原市あたりなんかは、歩道のない山道の、しかもカーブの多い道が続くところなどがある。車で走りながら、この企画がいったいどんな人向けに設定されようとしているのかとか、目的がなんなのか(観光なのか巡礼なのか)とか、そんな疑問がいくつも浮かんだ。

今年発行されたルートブックを見てみると、やはり行政の企画ということもあって観光寄りといった感じではあるが、各エリアの概要やエピソード、各ポイントや施設の営業時間や問合せ先なども入り、情報としてはずいぶん増えている。ただ先にあげた『日本二十六聖人 長崎への道 巡礼Map』と比較すると地図のおそまつ感が否めない。ちなみに巡礼Mapのほうは昭文社の地図を用い、二十六聖人が辿ったとおもわれる当時の道はほとんど残されていない現状と、さらに史実等を参考にしたうえで安全に歩ける道を選んで設定されていて、発行の2013年からもうじき10年が経とうとしているけれど実用に耐えうる地図だとおもう。
ルートブックの方はというと、おそまつな地図を補うかのように公式サイトにGoogleマイマップが貼りつけられていて、それでよかろうとでも言いたげである。この企画全体にいったいいくらの、どんな性質のお金をかけたんだろう(心の声)。まああまり文句をいうのはやめにしておこう(遅いかな)。
*
巡礼だとか、観光地めぐりでよく企画されるものとして、スタンプラリーやカード配布というのがある。
長崎の各地の教会にも、それぞれの教会が来訪記念的に押せる小教区独自(とおもわれる)スタンプと、他に巡礼に特化した団体が規格を揃えて作ったスタンプという感じで並べて置いてあるところが多い。巡礼スタンプは人気があり、特に世界遺産登録前後には台紙の入手場所や設置箇所に関する問合せがとても多かった。
また、先日知ったものにダムカードがある。つい先日、3つの行政区域にまたがった数箇所分を手に入れたのだけど、サイズの規格が違うダムがあった。カード配布場所をまわって集めるというと、似たようなものとしてマンホールカードなどがある。

それから2年ほど前に小値賀島・野崎島を訪ねたときに、ガイドの方からほいと渡されたカードがあった。なんだろう、コレ、とおもったけど例えば世界遺産と関係があるとか、各教会のものを作っているわけではなさそうだ(だって見たことがないから)。そうおもいつつ持ち帰り、なんとなく保管しておいた。
このたびダムカードというものに触れて、小値賀で貰ったこのカードのことを思い出した。調べてみたら、これはロゲットカードというもので、95枚(2022年4月現在)を全種類として、札幌から沖縄のいくつかの観光スポットで配布しているものらしい。内容からして施設などに統一があるとかいうわけではなさそうだ。サイトを見ると長崎では軍艦島でも配布しているらしいけれど昨年行ったときは貰わなかったな(ひとりごと)。

今年に入ってスタートしたものにこんなものもある。世界文化遺産スタンプラリーといって、19か所に設置されているものらしいけれど、スタンプラリーというか各設置場所で1シートに1つのスタンプを押すことになっている。折りたたみA5サイズのぺら紙を、全国各地で集めてまわるってどうなんだろうか(小声)。
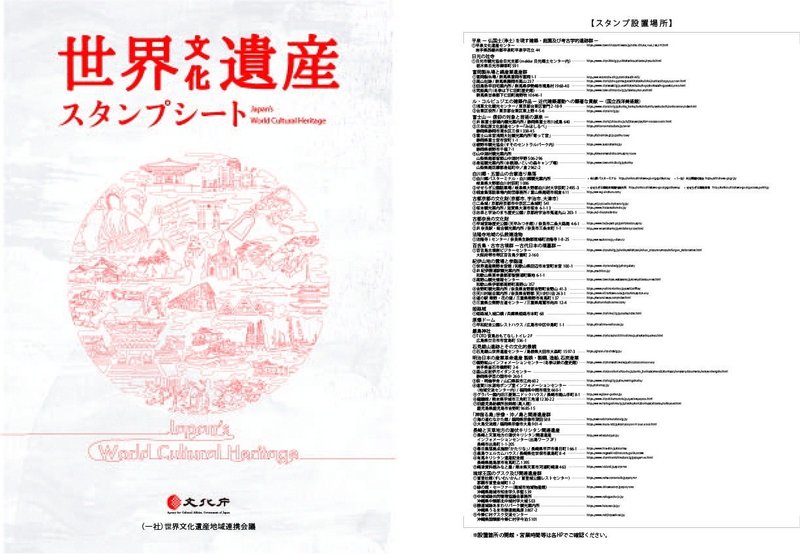
*
あれこれ書いてしまった。最後に昨年東彼杵を訪ねたときのことを少しだけ。
この日は長崎市内からこの場所(乗船場跡)にまず向かい、ここをスタートと設定し、南下する巡礼ルートを通ってみたのだった。東彼杵に着いたのは正午ごろだった。
5月の終りで、晴れていた。浜辺に立つと、風が吹いて波が打ちよせていた。周りには民家もあるけれど、駐車場が設けられたこの乗船場跡にはあまり人もいないし、しばらく歩いたりして沖のほうを眺めたりした。
そんなことをしてみたところで、約ひと月をかけて、京都からここまで引き回しののちに、ひたすら歩かされ西坂で処刑された、殉教者たちの心境というのが理解できるというものでもないのはわかっていたけれど。

ほんとうははじめ、日本二十六聖人について書いてみるつもりだったんだけど、どんどんずれていってしまったので、またいつか。
サポートを頂戴しましたら、チョコレートか機材か旅の資金にさせていただきます。
