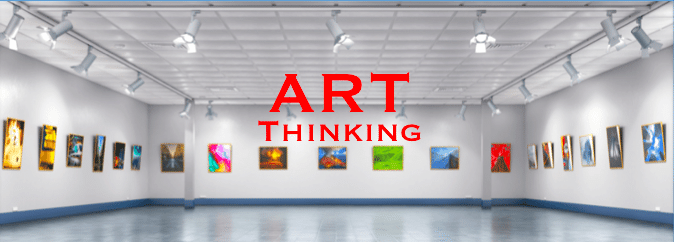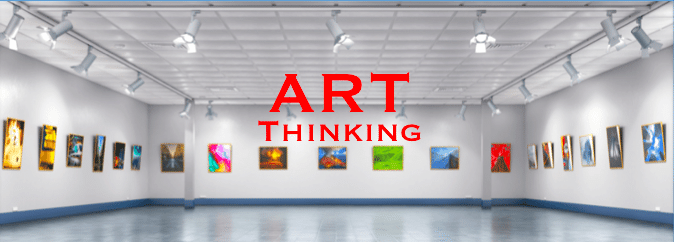【アートファシリテーションと臨床美術】
正解の見えない時代をアート思考でどう乗り切るか?をテーマにしたセミナー&トークセッション。毎回様々な角度毎回様々な角度から多彩なゲスト講師をお招きして開催しています。アート思考とは何か。その様々な入り口を、様々なジャンルのプロフェッショナルと一緒に探求していけたらと思っています。
今、アート思考という概念はビジネスシーンのフレームワークから、個人のマインドシフト(自己啓発)まで、多様な視点から注目されています。閉ざされてしまった、それぞれ人に内在するアートマインドを引き出す臨