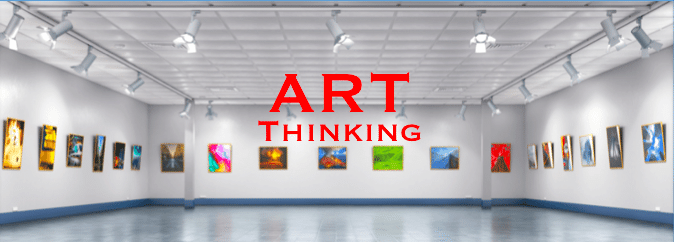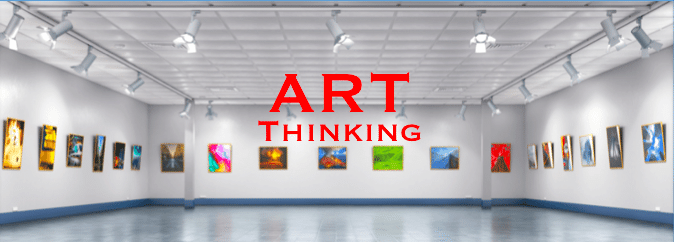【IdeaScaleのイノベーション・エバンジェリストに就任しました】
トヨタ自動車や内閣府の地域経済分析システム(RESAS)、その他、携わってきたイノベーティブな事業は未知の世界を生み出すワクワクと死を覚悟するくらいに過酷な環境から生み出されました。
ジョブズがMacintoshを世に出す時、スタッフは「90HoursAWeekAndLovingIt」と書いたTシャツを着て働いていたそうです。
そりゃ、当然そうなります。
未知のものを生み出す仕事に終電前に帰るなんて有り得ない。
ベゾスはAmazon立ち上げ当初、バス代は払わなかったといいます