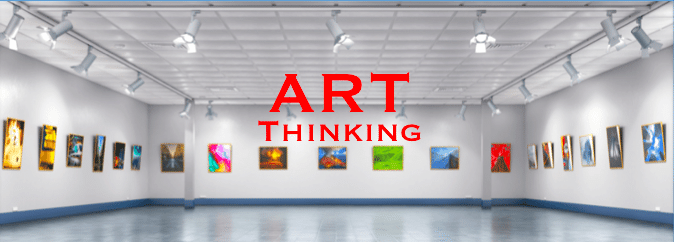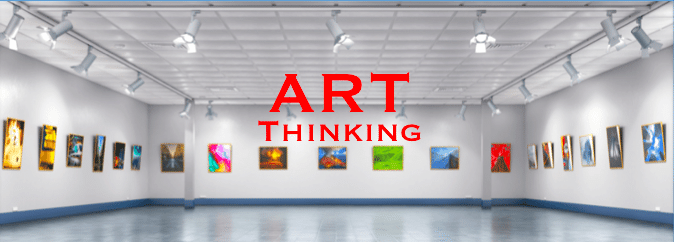自然経営と老子とハイブリッド
「自然経営」の著書であり、たぶん日本で最初にティール型組織を会社に実装したダイヤモンドメディア社の創業者・武井浩三氏も参加したアクティブブックダイアログに参加しました。
「自然経営」(じねんけいえい)の名前の由来は自然農法で、肥料もやらず放ったらかし(管理しない)で収穫をあげる方法だそうです。
武井さんが実践したティール組織の課題や問題解決策などティールの実用書という側面と、ヒエラルキー型の機械的な組織から、生命体のような有機的組織へ向かう実存的変容について解説されてます。武