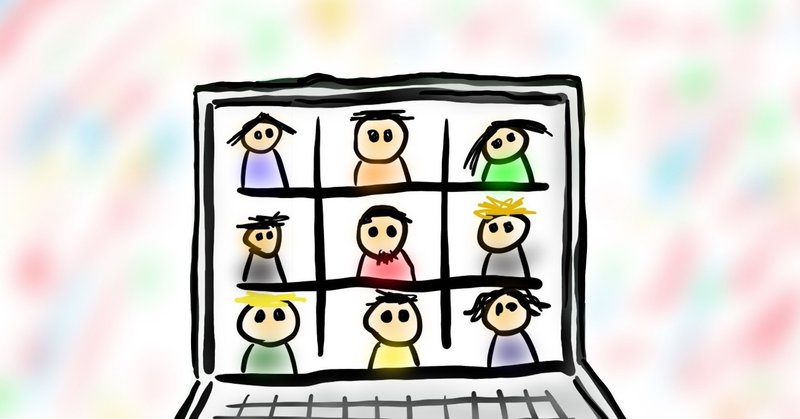
画面上のあなたと僕
念入りに石鹸で手を洗い、タオルで水をふきとってから、実家から送られてきたアルコール消毒ジェルを手のひら全体にすり込んだ。
鮭に塩と胡椒をふりかける。棚から、みりんと酒と味噌をひっぱり出して、テーブルに並べた。レシピには「みりん:大さじ一杯」「酒:大さじ一杯」「味噌:大さじ二杯」と書いてあるが、計るのが面倒なので、てきとうにボウルの中に流し込んでかきまぜた。買い物袋から、舞茸、しめじ、たまねぎ、キャベツを取り出し、ひとつずつそれらしいかたちに切り分けた。バターがぶくぶくと沸騰したフライパンに鮭を放り込むと、煙とともにジューという音が台所に広がった。魚や肉が焼ける音というのは、料理が好きかどうかは関係がなく、原始的な心地よさがあるような気がする。鮭の身が赤から淡白な色に変わっていくのを眺めながら、これがタンパク質か、と自分でもわけのわからないことをつぶやいた。
家にこもりっぱなしのゴールデンウィークは、初めてではなかった。昔から活動的な気質ではなく、人混みも嫌いなので、こうした連休ほど自宅で過ごすことが多かった。家で映画を観たり、本を読んで過ごすだけで、休日というものを十分に満喫することができた。ただこれまでと違うのは、ゴールデンウィークのずっと前から、自宅にこもりっぱなしということだった。
大学の授業はオンラインになり、バイト先は休業となったが、別にそれほど困りはしなかった。もともと通学の時間は好きではなかったし、遅刻する恐れもなくなった。外出することもなく、家で映画を観ているだけなので、出費も減り、親からの仕送りだけで生活するには困らなかった。ただひとつ残念なのは、友人たちと安い居酒屋でする飲み会がなくなったことだった。
ひとりで飲むほどお酒が好きなわけでもなく、飲み会でバカみたいに騒ぐのが好きなわけでもない。友人たちの他愛もない話を聞いたり、芸人の真似事を安い印刷機でコピーしたようなやりとりを眺めたりするのも嫌いではなかったが、何よりも楽しみにしていたのは、ひとつ歳下のYさんとの帰り道だった。
Yさんと初めて会ったのは、去年のサークルの忘年会だった。映画サークルということになってはいるが、映画を撮ったりするひとはおらず、映画について議論するということもなかった。一年生の頃は、四年生のS先輩と最近観た映画の話をしたり、僕が好きそうな映画を教えてもらったりすることができたので、よく部室に顔を出していたが、S先輩が卒業してからは次第に部室に行く頻度が減っていった。それでも、同級生のKに誘われたときだけは、たまに顔を出すことにしていた。
去年の忘年会も、Kに呼ばれて顔を出した。
19時から駅前の居酒屋を予約していると聞いたので、20時半頃に店に向かった。店に入ると、あちらこちらで似たような集団が騒いでいて、すぐに店を出たくなったが、奥からKの声が聞こえてきたので、ひとまず合流することにした。Kはいつものように通路側に座り、周りよりも少し大きな声で話しては皆を笑わせていた。Kは僕と目が合うと、少し横に動き、「やっときたか。ビールでいいよな」と言って、さっきまで自分が座っていた座布団をぽんぽんと叩いた。
三杯目か四杯目かのビールを飲み干した頃だった。「つぎもビールですか?」と女に声をかけられた。口調から後輩のような気がしたが、定かではなかったし、初対面なので「大丈夫です」と答えた。
「大丈夫って、ビールってことですか?」と女が微笑んだ。
「あ、自分で頼むので大丈夫って意味でした」
「先輩なのに敬語なんですね」
「そうですね。初対面なので、どうしても」
女は「面白いですね」と笑っていたが、正直何が面白いのかいまいち分からなかった。僕はハイボールを注文し、女はウーロン茶を注文した。
店員から受け取ったハイボールを僕に差し出し、女は「Yって言います。はじめましてです」とウーロン茶の入ったグラスを僕の方へとつき出した。二人で小さな乾杯をしてハイボールをひとくち飲んだ。「乾杯」の言い方が可愛いと思った。
「Tって言います。Kと同じ三年です」
「あ、やっぱりTさんですよね。Kさんから話を聞いたことあります」
Kが僕がいない時に僕の話をしているとは考えたこともなかったので少し動揺したが、Kのことなので、悪いように話すことはないだろうとも思った。Kは、他人を蔑んで笑いをとるようなことはしない。
「すごく映画に詳しいって聞きました」
「詳しいというか、好きで、たくさん観てるだけですけどね」
謙遜ではなく、本音だった。まるで教養のひとつかのような姿勢で映画を観たり、自分のセンスを誇示するためにマニアックな作品に手を出したりする自称映画通は嫌いだった。誰かに示すためではなく、もっと純粋に、自分の心を動かすものは何なのだろうと探求する感覚に近かった。S先輩とは、そうした映画に対する感覚が近くて、仲良くなれた。
「最近のオススメの作品って何ですか?」
「とても答えづらい質問ですね、それ」
自分自身を知るために映画を観ているようなものなので、初対面のひとに明かすのは、喉の奥に指を入れて吐き出したものを見せながら「昨日食べた美味しいゴーヤチャンプルです」と言うような恥ずかしさがある。そんなことを考えていると、消化液でぐちゃぐちゃになったゴーヤチャンプルを想像してしまい、気分が悪くなった。
「そろそろ二軒目に移動しまーす」とKが言い、皆がそれぞれに動き出した。二軒目は沖縄料理の居酒屋らしく、さっきのゴーヤチャンプルが再び脳裏に浮かんでしまい、また気分が悪くなったが、Kに「たまには二次会も付き合えよ」と言われたので、水を一杯飲んでから二軒目へと向かった。二軒目に向かう道中、後ろからYさんの声が聞こえていた。
どこか懐かしい沖縄民謡が流れる店内には、シーサーの置物や麦わら帽子などが飾られており、過剰なまでの演出が逆に嘘っぽさを感じさせた。僕はKの隣りに座り、少し呂律が悪くなったKの話を聞きながら、さんぴん茶ハイを飲んだ。Yさんは端の方に座り、皆と同じようにKの話に笑っていた。
駅前のコンビニでアメリカンスピリットとミネラルウォーターを買っていると、Kから「また明日、学校でな」とLINEがきた。わざわざ律儀だなと感心し、「また飲みすぎて遅刻すんなよ」と返信した。すぐに「起こしてね」と返信がきたので既読無視した。街灯の少ない一本道を歩きながら、帰って何の映画を観るか考えていた。酔っている自覚があったので、あまり難しい映画は観れないなと思った。
「Tさんもこっちの方向なんですね」
振り返ると、Yさんが自転車を押して歩いていた。
「びっくりした。三次会には行かなかったんですね」
二次会が終わると、Kたちと一緒の方向に歩いて行ったので、Yさんも三次会に向かったのだと思っていた。
「自転車を駐輪場にとりに行ってたんですよ。ひとりでここ歩くのいつも怖かったのでラッキーです」
「街灯少なくて暗いですもんね」と当たり前のことをくちにした。
「まだ敬語なんですね。面白い。そういえばまだ教えてもらってないですよ」
「何を?」
「オススメの映画ですよ」
映画は自分が楽しむためだけに観ているので、他人に何をもってオススメとするかが難しく、どんな映画を薦められるとYさんは嬉しいのだろうかと、しばらく考え込んでしまった。駅から離れていくにつれ、どんどん街灯がなくなっていく。Yさんの自転車の灯りだけが目の前をゆらゆらと照らしていた。
「『ダンサー・イン・ザ・ダーク』かな」
Yさんのように明るいひとに薦めるような作品ではないと思いつつも、辺りが真っ暗なせいか、不意に出た回答だった。
「あ、それ聞いたことあります。結構悲しい話なんですよね?」
「悲しいというか、救われない話ですね」
「救われない話か...。あまり観ないタイプの映画っぽいです」
「そんな気はしました」
「あ、もしかして、いまちょっとバカにしました?」
「いや、バカにはしてないです。ただ、ハッピーエンドな作品ばっかり観てそうだなと思ったんで」
「やっぱりちょっとバカにしてるじゃないですか」
帰ったら『マスク』を観ようと思った。
それからというもの、飲み会に参加する頻度が増えた。相変わらず部室に顔を出すことは滅多になかったが、忘年会で二次会まで行ったこともあってか、Kに誘われることが多くなった。春休みで暇を持て余していたというのもあったのだろう。Yさんは毎回参加していたわけではなかったが、一緒のときは、帰り道に映画の話をして歩いた。僕が映画の話をするのは、Yさんと歩いているときだけだった。
春休みも終盤に差し掛かった頃、世間の話題は一色だった。日に日に深刻さを増していく報道を目にすると、家の中にいても落ち着かなくなった。かといって外に出るわけにも行かず、映画と本を繰り返して過ごした。たまに外出するとしても、コンビニやスーパーに行くだけだった。もともと大学もバイトも休みの日は、似たような生活をしていたので、初めの頃は苦ではなかったが、こうした生活にも限界があることを知った。引きこもりのひとを凄いと思った瞬間もあったが、尊敬の類いではなかった。
春学期の開始が延期になった。報道の様子からそうなることは予想がついていたので、嬉しくも悲しくもなかった。大学のホームページに掲載された「家にいろ」という学部長のメッセージが、ツイッターで話題になっているらしかった。僕はツイッターをしていないので知らなかったが、KからLINEが送られてきた。「かっこいいよな」と送られてきたので「べつに」と返した。すぐに「沢尻かよ」と返信がきたが、よく分からなかったので既読無視した。
Kから何度か「オンライン飲み会」に誘われた。一度だけ参加したことはあったが、四六時中映画を観る生活をしていたせいもあって、誰かと向き合うのが面倒に感じてしまい、それ以来断っていた。それに、いつもの飲み会であれば、次第に存在感を消していくことで、その場に溶け込むことができていたが、オンライン飲み会ではひとりひとりに等しい面積の画面が与えられてしまうことも嫌な理由のひとつであった。
「ゴールデンウィークということで、明日オンライン飲み会をしたいと思います」とサークルのLINEグループに送られてきた。Kからだった。「今回は、それぞれゴハンを作って参加してください。いちばん美味しそうなゴハンを作ったひとにプレゼントがあります。プレゼントは考え中です(笑)」と続いていた。プレゼントが何かで参加する人数も変わりそうなものだと思ったが、自分には関係ないと思い、画面を閉じた。と同時に、またLINEが送られてきた。
「明日の、参加しますか?」
Yさんからだ。
「しないつもりでした」と返信した。「でした」と過去形にしていたことに気づき、どちらにも受け取れる返し方をしていた自分が卑怯に思えた。
「しましょうよ! 料理つくるの得意そうですし!」
絶対に得意そうには見えないだろうと思ったが、悪い気はしなかった。「じゃあ、する」とだけ返すと、上手いのか下手なのか判断が難しいイラストのスタンプが送られてきた。僕は『男はつらいよ』の寅さんが照れ笑いしているスタンプを送った。
昨日決めた料理の材料を買いに、スーパーへ向かった。客も店員も、皆がマスクをしている光景にもすっかり慣れてしまった。僕はマスクが家にないので、できるだけしっかりと口を閉じて歩いた。感染を恐れていたというよりも、マスクをしていないことを申し訳なく思っていますと伝えるためであった。鼻呼吸をしながら、足早に買い物をすませた。
家に着くなり、念入りに石鹸で手を洗い、タオルで水をふきとってから、実家から送られてきたアルコール消毒ジェルを手のひら全体にすり込んだ。ひさしぶりにレシピを見ながら料理をするので、少し緊張している。鮭のちゃんちゃん焼きは、食べたことはなかったが、見つけた写真がとても美味しそうで即決だった。
開始時間から少し遅れて入ると、すでに19人参加していた。僕の参加によって、パソコンの画面が20分割された。このくらいの人数なら、自分の面積もさほど気にならないものだなと思った。「お、Tも登場です」とKが言うので、僕はミュートを解除して「遅れてごめん」と言い、またミュートに戻した。画面の隅っこにいるYさんは、大学では見たことがないスウェット姿で、こんな姿が見れるならオンライン飲み会も悪くないなと思わせてくれた。
ちゃんと料理を作ってきたひとは、ほとんどいなかった。コンビニで買ったり、ウーバーイーツで注文していたようだった。Kは、ドミノピザを頼んでいた。「今回は全員引き分けだな」とKが笑うと、皆もそれにあわせて笑っていた。Yさんも同じように笑っている。僕は、ほぐした鮭の身と舞茸をくちに入れ、ハイボールで流し込むと、我ながら美味しくできたと満足した。
オンライン飲み会の数をこなしたKの仕切りは見事だった。いつもよりも少し抑えめの声量で、外出自粛中のエピソードを語ったり、話を引き出したりする様子を見ていると、なんだかラジオを聴いているような気持ちになってくる。Yさんも、DJ Kのいちリスナーになっているようだった。オンライン飲み会は、いつもの飲み会よりも、酔いが回るのは早いようだ。Kの呂律が悪くなるのが早めだったので、そう思った。
23時を回ったあたりで「そろそろ今夜はおひらきかな」とKが言った。前回参加したときは、終わりどきが難しく、だらだらと続いていたのが苦痛だったが、さすがにKは学んでいたようだった。「次回はちゃんと料理をしてくるように! おれも作ります! それじゃあ、おやすみ」と言って、画面に向かって手を振ると、画面が20分割から19分割になった。皆がそれぞれにおやすみと言っては、画面の分割がひとつずつ少なくなっていく。僕はYさんの画面が消えるまで眺めていたいと思い、誰に見せているわけでもないのに、消し方が分からないふりをしていた。
ひとり、またひとりと消えていくにつれ、スウェット姿をしたYさんの画面の面積が大きくなっていく。僕はまだ、消し方が分からないふりを続けている。
とうとう画面上には、僕とYさんだけになった。
「まだ寝ないんですか?」と、Yさんが言った。
話しかけられたことに動揺して、「切るのが面倒くさくて」とわけのわからない言い訳をしてしまったが、ミュートにしたままだったので聞こえていなかった。余計に恥ずかしかった。
「みんな、いなくなっちゃいましたね」とYさんが続けた。
「ですね。Yさんはまだ寝ないんですか?」
「寝ますよ。でも、もう少しだけ起きてようかなと思いました。そういえば、Tさん、ちゃんと料理作ってきてましたね」
生真面目に料理してきたことがばれていて、へその周りがこそばゆくなったが、ほんの一瞬でも僕のことを見てくれたのだと思い直すと、等しく分割されていた画面にも感謝することができた。
「何を作ったんですか?」
「鮭のちゃんちゃん焼き、というやつです」
くちに出してみると、ちゃんちゃん、という響きがひどく間抜けに思えた。
「ちゃんちゃん焼き? 美味しかったですか?」
「お酒にはぴったりでしたね」
Kだったら、もっと気の利いたことが言えたのだろう。
「Tさんは、まだ寝ないんですか?」
「これから映画でも観ようかなと思って」
「さすがですね。何を観るんですか?」
「今夜は『最強のふたり』を観ようかなと」
「あ、その作品、わたしも好きです! オススメですよ!」
本当は、今夜は映画を観るつもりはなかったし、その作品も先日観たばかりのものだった。Yさんが好きそうだな、というのがそのときの感想で、機会があれば薦めてみようかなと思っていた。
「そういえば、Yさんにオススメの作品ありますよ」
「何ていう作品ですか?」
「『マスク』です」
「知らないです。どんな作品ですか?」
プシュッと缶のふたを開ける音がして、Yさんは、ほろよいをひとくち飲んだ。僕は、ハイボールの入ったグラスに少しだけウイスキーをそそいだ。
「頭を使わなくて楽しいやつです」
「いまちょっとバカにしましたよね?」
パソコンの画面には、僕とYさんだけが等しく並んでいる。
最後まで読んでくださり、ありがとうござました! 映画や落語が好きな方は、ぜひフォローしてください!
