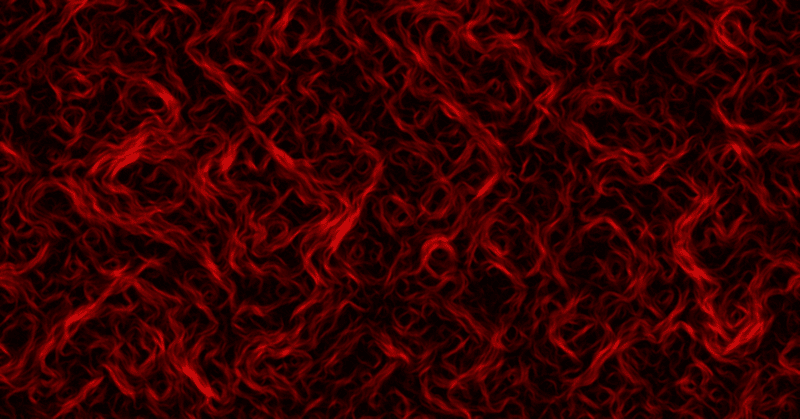
【小説】キープ・オン・チェンジング!!(7)
「やめて!」
ぼくは思わずさけんでいた。
すると、ぼんやりとだけれど、合田くんの姿が見えた。白と青のチェックのシャツにべっとりと赤い血が付着しているのが、暗やみでも分かった。
「どうしてこんなことするの? 福岡くんは関係ないでしょ!」
ぼくの声は小さい粒になって、消えていく。合田くんに届いているという手ごたえがない。
「この子、福岡くんっていうんだ」
低く、くぐもった声がした。また、何人もの声が重なったような声だ。部屋のいたるところからぼくに向けられている気もするし、頭の中に直接ひびいている気もした。
「君は、この男の子と遊ぶようになった。そして、ぼくとは遊んでくれなくなった。この子さえいなくなれば、君はまたぼくと遊んでくれる」
合田くんの口は、そう告げたように見えた。空気はいつの間にか冷たくなっていて、ぼくのふるえは大きくなっていく。
「そうだよ。ぼくのせいだ。ぼくが合田くんと遊ばなくなったから、合田くんは夜な夜な出るようになったんだね。本当にごめんなさい。でも、」
ふるえを抑えて、ぼくは言う。
「でも、だからって福岡くんを殺していいの?ここで本当に福岡くんの命をうばったら、ぼくは合田くんのことを絶対に許さない。公園でまた会っても知らないふりをするし、話しかけられても無視する。絶交するよ。それでもいいの?」
合田くんは手をはなさず、福岡くんは宙に浮いたままだった。足の動きはもう小さくなってしまっていて、あと少しだって持ちそうにない。
ぼくは続けた。福岡くんを助けるために。
「どうしても殺したいんだったら、ぼくを殺してよ。その手でぼくの首をしめて、殺せばいいでしょ。そうすれば、天国でいつでも会える。いつまでも遊べる」
部屋中からにらまれている気がした。ひんやりした空気がぼくをチクチクさす。光のない合田くんの目にも分かるように、ぼくは大きく手を広げた。
「ほら、早くしてよ。ぼくなら大丈夫だから。お願いだから福岡くんから手を放して。そして、ぼくを殺して」
ぼくそう言った次の瞬間、福岡くんはばたりとベッドにたおれこんだ。どうやら合田くんから解放されたらしい。
よかった、と思うのも束の間、ぼくは合田くんに首を掴まれた。目にもとまらぬ速さで合田くんは移動し、ぼくを殺す準備をはじめていた。
体が持ち上がる。床に足がつかない。暗やみの中にとけてしまいそうだった。
しかし、ぼくの首を掴む合田くんの手は、まだそれほど力が入っていない。ためらっているのか、ぼくに少し話す余裕をくれている。
「ねぇ、合田くん。天国って本当にあるのかな。死んだ後には何もない空間が広がっていて、ぼくと合田くんは永遠に会えなかったらどうしよう」
死ぬと覚悟を決めたはずなのに、ぼくはそう口走っていた。合田くんの手は冷たいはずなのに、ぼくは汗をかいていた。足がジタバタともがいている。口は呼吸をしようと、一生けん命開く。
ぼくの体は、死にたくないとうったえていた。生きたいと必死だった。
「合田くん、死ぬときってどんな感じなんだろう。きっとものすごく痛くて、苦しいんだろうな。でも、それは一瞬のことで、あとはただ眠っているみたいに気持ちいいのかもしれないね」
合田くんの手に力がこもっていく。ぼくの息は苦しくなる。足を動かす元気さえない。視界がかすみはじめた。
「合田くん……。ありがとう……。ぼくの前に現れてくれて……。そして、ごめんね……。本当に、ごめんね……」
ぼくはまぶたを閉じた。最後のとりでである意識さえうすれていく。
ぼくはまもなく死ぬ。天国へのとびらはどこにあるんだろう。何も見えないな。でも、なんだかとっても……。
ドサッという音がした。ぼくの口に、のどに、一気に空気が入ってくる。ぼくは首を抑えて何度もせき込んだ。吐きそうなくらい何度も。
そうしたら少し落ち着いて、ぼくは顔を上げた。暗やみの中に合田くんが立っている。血のついたシャツはそのままで、両手が握られていた。
ふるえている。
ぼくは、何もできず、合田くんを見上げるだけだった。
声がひびく。
「どうしたらいいんだよ!」
その声は誰のものでもない合田くんのものだった。まだ声変わり前で、あどけなさの残る合田くんの声。永遠に変わることのない声が、暗やみにこだました。
「ぼくは殺してまで君に会いたくない! 生きている君に会いたいのに!」
「合田くん……」
ぼくが苦し紛れにつぶやくと、合田くんはぼくの方をぐるりと向いた。よくは見えないけれど、くちびるを必死にかみしめていることは分かる。
今にも消え入りそうな小さい声で、合田くんは言う。
「僕だって、もっと生きたかった。あんなところでひかれたくはなかった。もっと学校にも行きたかったし、お父さんやお母さんともいっしょにいたかった。なのに、今のぼくには何にもできない。お父さんとお母さんが、今どこに住んでいるかさえ分からないんだ」
いつの間にか風の音は止んでいた。一階がさわがしくなっている気配もない。部屋には、合田くんの声しかしなかった。
「ねぇ、奥井くん。どうして、人はずっとは生きていられないんだろうね」
合田くんは、ゆっくりと自らを落ち着けるように言った。ぼくは黙ってしまう。どんなにすばらしい言葉でも、合田くんをなぐさめることはできない気がした。生きている人間の文句なんて、死んだ人間からすれば、ただ身勝手なだけだ。糸口さえ見つからない。
それでも、ぼくは口を開いていた。出てきたのはありのままの言葉だった。
「分からない」
ぼくの言葉に、合田くんは肩を落とした。不思議だけれど、落胆しているのがありありと分かった。
自分でも意識しないうちに、ぼくは発していた。
「でも」
ぼくは続ける。
「でも、思ったんだ。ぼくたちはどんどん変わっていく。学年が上がって教室が変わるみたいに、いつまでも同じところになんていられない。変わって、変わって、変わり続けて。たぶん、死ぬってことも変化の一つに過ぎないと、ぼくは思う。卒業して学校が変わるみたいに、生きることから死ぬことへと変わるだけなんだ」
暗やみの中で、ぼくの声も消え入りそうだったけれど、伝えた。伝えようとした。言葉がこんなに重く感じたのははじめてだった。
「だけど、僕はこんなに早く変わりたくなんてなかった。もっと生きたままでいたかったんだよ」
合田くんの言うことは、もっともだ。ぼくだって、まだ死にたくはない。
「でも、合田くんは死んでから、ぼくに出会った。合田くんは死んでなお、変わったんだよ。たった一人から、ぼくと二人に」
「死んでなお、変わった……」
「そう。ぼくだって、いつかは変わる。でも、そこで終わりじゃない。まだまだ変わり続けられるって、ぼくはそう思いたいんだ」
「僕はまだ変われるのかな……」
「変われるよ。変わりたいと願うのなら、きっと。ほら、生まれ変わりっていうでしょ。人はずっと、ずっと変わり続けていくんだよ、たぶん」
合田くんは顔をぐっと近づけた。ぼくは少し後ずさりしてしまう。だけれど、その顔からは苦しみが消え去っていた。口元も穏やかに閉じられて、ぼくにほほえみかけている。
公園で何度も見た合田くんの顔だ。懐かしくて、ぼくも思わずほほえんでしまう。体のふるえはいつの間にか収まっていた。
「分かった。奥井くん、ぼくは変わるよ。絶対に。変わって、変わって。変わった先にあるどこかで、きっとまた会えるよね」
「うん、きっと会えるよ。そのために、ぼくも変わり続ける。変わって、変わって。どこまでも合田くんに会えるように変わってみせるから」
合田くんの口がゆっくりと動いた。声は出ていなかった。
次の瞬間、急に天井の明かりがついて、部屋は一気に明るくなった。寒気も消えて、空気は六月の生ぬるさを取り戻している。
福岡くんが咳とともに、息を吹き返す。ぼくは、福岡くんのもとに駆け寄って、背中をさすった。福岡くんが落ち着いたところで、ぼくは部屋を見わたしてみた。どこにも合田くんの姿はなかった。
合田くんは、変わったのだ。変わり続けることを、選んだのだ。
ぼくは、小さくある言葉をつぶやいた。合田くんが最後に言いたかったであろう言葉を。誰にも聞こえないように、天井に向かって。
その日は朝から雲一つない青空だった。梅雨の晴れ間というらしい。水たまりが日光を反射してかがやいている。
ぼくたちはあの公園で待ち合わせて、学校に向かった。休みの日の通学路は、なんだかこそばゆい。すれ違う子どもたちは誰もランドセルを背負っていなかった。
ぼくの後ろについてくる男の子。彼は、普段はこの道を通らない。
ぼくたちは、広い道路を歩き続けた。やがて、遠くにスーパーマーケットが見えた。坂の上にはぼくたちの学校も見える。自動車が途切れ途切れに行き交っていて、横断歩道をおばあさんが渡っていた。ぼくは、駐車場に近づいていく。
ここに来るのは二週間ぶりだ。やはりスーパーマーケットには人が多く出入りしていて、誰も足を止めようとはしなかった。
駐車場の角。白いフェンス。ぼくたちがそこに行くと、小さな紫色の花束はなくなっていた。代わりに白い菊の花束が置かれている。まだ新しいものなのか、ぬれてはおらず、花びらの一枚一枚までみずみずしく見えた。
「ここが、その事故現場?」
ぼくの隣に立つ福岡くんがたずねてくる。二年前の事故のことは覚えていない。福岡くんはそう言っていた。だけれど、事故のことを伝えたときに、少し間を置いて首をふっていた。
ぼくはそれ以上何も聞かなかった。聞いてもあまり意味はないように感じた。
「うん、ここで二年前に事故があって、八歳の子どもがぎせいになったんだよ。やり切れないよね」
ぼくはお父さんが買ってくれた紫色の花束を、菊の花束の隣に置いた。二つの花束は、お互いを引き立て合うみたいによりそっているように、ぼくには思えた。
変わりゆくぼくたちの、大事な水準点。一年後のぼくは、どんな顔をして、ここを訪れるのだろうか。
ぼくは花束に向かって、手を合わせた。真似して、福岡くんも手を合わせる。
ぼくは目をつぶって、数秒、願いを込めた。
変わることを、恐れない自分になれますように。
怖がらずに、変わり続けていられますように。
変わった先に、想像をこえる未来がありますように。
完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
