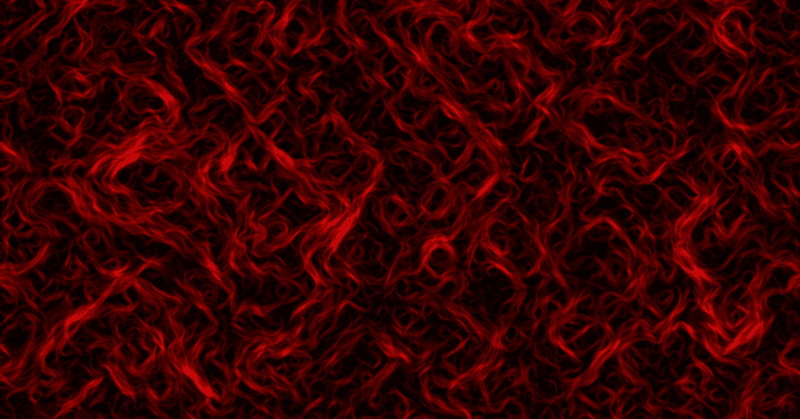
【小説】キープ・オン・チェンジング!!(2)
それからも、福岡くんはほとんど毎日ぼくに話しかけてきた。今日の天気はどうだとか、休みの日は何をしているのだとか、そんな他愛もない話だった。その度に、ぼくは感情のこもっていない言葉を返して、なんとか場をやりすごしていた。
たぶんぼくだったら、こんなヤツのことはとっくにきらいになっていたと思う。
それでも、福岡くんは毎日あきずに、ぼくに話しかけてきていた。ぼくしか気軽に話せる相手がいなかったこともある。
それでも、ぼくは福岡くんに話しかけられるのを、だんだん面倒くさいとは思わなくなってきていた。ひとりぼっちじゃないことの喜びを知りはじめていた。
一方、合田くんとのつきあいも、新学期になってからも続いていた。合田くんは隣の富士田第三小学校に通っていて、クラスメイトの面白い話を、ぼくにしてくれた。成瀬さんという女の子がじゃんけんに強く、いつも給食の余り物をいただいているので、じゃんけん女王と呼ばれているという話が、ぼくのお気に入りだ。
つまり、四年生になってからのぼくは、親以外の話し相手を、二人も手に入れていたことになる。今までのぼくの人生の中でも、類を見ない事態だ。
その日も、いつもの公園でぼくたちはすべり台の近くのベンチに腰掛けて、人の行き来を眺めていた。ぼくは缶ジュースを飲みながら、スマートフォンを見た。もうすぐ六時になろうとしていた。空があい色に変わっていく。
合田くんはスマートフォンを持っていない。家庭がなかなか厳しいらしく、いつも日が暮れる前には帰ってしまう。
自動販売機の前でだって、合田くんはぼくがジュースを彼の分まで買うことを、よしとしなかった。買い食いはいけないことだと教えられているのだろうか。
ぼくは合田くんが、何かを食べているところを見たことがない。
ただ集まって、話をして、帰っていく。それが、ぼくと合田くんの関係のすべてだった。
「でさ、佐々木がさ、そこで『お前のもんは俺のもんだ』っていうわけ。もうジャイアンかよって。まさかリアルで、そんなセリフ聞けるとは思ってなかったから、思わず吹き出しちまったよ」
「それは面白いね」
「だろ? でも、先生が『じゃあ山村くんのそうじ当番も佐々木くんのものだね』って言ったら、佐々木、とたんに黙っちゃって、最後にはごめんなさいってちゃんと謝ってたな」
ほがらかに笑う合田くん。ぼくは、座ったまま足を振った。空を切る心地がした。
「合田くんは学校、楽しそうだね。クラスの人とも仲良いの?」
「まぁ人並みにはな」
「その人並みってどんな感じ? いつもどんな風に過ごしてるの?」
「それより、お前はどうなんだよ。新しいクラスにはもう慣れたのか?」
むりやり話題を変える合田くん。いつもこうだ。合田くんは自分の話を、あまりしたがらない。
いつだって他人や、テレビや、ユーチューブ。自分が登場しない話ばかりしている。たまに聞いても、ありきたりな言葉ではぐらかすだけだ。案外シャイなのだろうか。
「うん、まあまあだよ。福岡くんっていういつも話しかけてくれる人もいるし、三年生のときよりはいい感じかな」
「そっか。そりゃよかったな」
合田くんは、再び公園の外に視線を戻した。親子が手をつないで、マンションに入っていく。合田くんが小さくため息をついてしまったのが、ぼくには分かってしまった。
合田くんが話したくないならそれでいいのだけれど、この日に限っては、合田くんの態度がへんに気になってしまった。
「ねぇ、合田くんの家って、どんな家なの?」
ぼくは、合田くんの家を知らない。
いつも合田くんがぼくの家を訪ねてくるか、何の気なしに公園に行くと、一人でベンチに座っているところを見るだけで、ぼくが合田くんの家に行ったことは、一回もない。マンションか一軒家かも分からないのだ。
「別に、普通の家庭だよ。でも、父ちゃんと母ちゃんはどっちも働いていて、帰りもだいぶ遅いな。そのくせ、自分たちがいないところで、他の人に家に上がられるのがいやらしくて。何されるか分かったもんじゃないって。だから、ごめんな。家に呼べなくて」
「ううん、大丈夫。お父さんとお母さん、忙しいんだね。でも、休みの日ぐらいは合田くんの家に遊びに行きたいな。今度、行ってもいい?」
「ごめんな、平日も休日もない仕事なんだよ。どっちも」
そう言うと、合田くんはそっぽを向いてしまった。ぼくは合田くんの触ってほしくないところに、触れてしまったらしい。
合田くんは、ぼくをきらいになってしまったのだろうか。そうだとしたら、ぼくの平和な時間が一つなくなってしまう。心がえぐり取られて、くぼんでしまう。
ぼくは、合田くんに一言「ごめん」と謝る。合田くんが「別にいいよ」と笑顔で答えてくれたので、ぼくはホッと一息つく。
空は、かなり暗くなってきていた。
「俺そろそろ帰るわ。じゃあまた明日、ここでな」
「うん、また明日」
ベンチから立つ合田くんのお尻に、少しの砂がついていた。合田くんは、それを払うそぶりも見せず、マンションの角を曲がって、ぼくの前から去っていった。ぼくは、ジュースを飲み干した後も、ベンチに座ったまま、人の行き来を眺めていた。
公園の中を、レジ袋を持ったお母さんが横切る。ぼくは、勢いよくベンチからかけ出した。
四月の終わりには、ぼくと福岡くんは途中まで一緒に帰る仲になっていた。背の高い福岡くんの歩幅は大きかったけれど、ぼくに合わせてゆっくりと歩いてくれていた。
遠足の班決めのときも、福岡くんはいの一番にぼくを誘ってくれた。他の子もクラスになじめていない、あまりものの集合みたいな班だったけれど、福岡くんが一緒ならそこまで悪くないと思った。
遠足の行き先は動物園だった。
ゾウがゆっくりと鼻を上げ、サルが山をすばやく登っていく。名前も分からない鳥の鳴き声が、わめいているように聞こえる。平日だというのに人は意外と多く、どこの動物の前にも必ずといっていいほど人がいた。
スマートフォンを向けたり、あごに手を当てたりしている人たち。この人たちはふだん何をしているんだろうとちょっと思ったりもした。
ぼくは、二才のときに、この動物園に来たことがあるらしい。遠足で動物園に行くことをお母さんに言ったら、そう教えてくれたけど、ぼくはいまいち覚えていなかった。
矢城先生に引率されて、園内を一通り見て回る。ゴリラやトラなんかを見て、クラスの中心グループはわいわい盛り上がっていたけれど、ぼくはそこまで楽しいとは思えなかった。おりに閉じ込められた動物はなんだかかわいそうだったし、自分が周りたいように周られないと、心のどこかが落ち着かない。
小さな石をけりながら歩いた。石は道路とおりの間のくぼみに落ちて消えてしまった。このまま楽しくもない遠足が続くのだと、そのくぼみを見ながら思った。
だから、お昼ご飯を食べた後に、班行動になったときは、思わずにやついてしまった。二時間後に再び入り口前に集合さえすれば、どこに行ってもいいのだ。
ぼくたちの班のリーダーは福岡くんだ。だけれど、福岡くんもそんなに引っ張っていく方ではないので、ある程度は自由にできるだろう。
ぼくたちの班は、橋を渡って別のエリアに移動した。サイやキリンなどアフリカの動物たちが、のんびり暮らしている。ゆったりと動くその姿には余裕すら感じられたけれど、班のメンバーは誰も何も言わなかった。そもそも、ここで喋れるようだったらこの班にはいない。
ただ気まずい移動をしているうちに、半円状のカーブをえがく建物が見えた。ぼくは誰にも言わず、建物の中に入ってしまった。館内はあたたかく、ジャングルを思わせる植物が生えていた。ガラス越しのワニは、ごつごつした肌に今にもかみついてきそうな眼をしていて、少しおののく。反対に、陸の上でひたすらに休むカメは、いくらでも見ていられそうだ。
ぼくは、ゆっくりと動物たちを見て周った。ぼんやりと動物を見ていると、何も思い出さなくてすんだ。
しかし、建物から出ると、福岡くんたち班員の姿はどこにもなかった。もう別の場所に移動してしまったのだろうか。ぼくは一人取り残されていた。最初は平気だったが、建物から親子連れが出てくるのを見ると、急に心細くなってしまう。
ぼくは、近くのベンチに座るしかなかった。池に水草がいっぱい張っている。
不安で仕方がなかった。見ないようにしても、目線は落ち着かなかった。
あたりをきょろきょろと見渡し続けて、どれくらい経っただろう。後の話では、ぼくがはぐれたのは一時間ほどだったらしいが、ぼくにはその数倍もの時間が経ったように感じられた。
自分から探しに行った方がいいのかなと立ち上がったとき、遠くに福岡くんの姿が見えた。他の班員は誰もいない。福岡くんもぼくに気づいたようで、早足で近づいてくる。
「奥井くん、無事だったんだね。見つかってよかった」
そう言う福岡くんの顔は、心配と安心がごちゃ混ぜになっていて、なんだか弱々しく見えた。
「ごめん、一人で勝手に行動して。福岡くんたちと一緒にいるべきだった」
謝るぼくの声もまた、弱々しかった。
「ぼくも、奥井くんの行きたいところを聞かなかったのは悪かったよ。ごめんね」
「どうして福岡くんが謝るの。悪いのはぼくなのに」
「いや、奥井くんに気を配れなかったぼくが悪いんだ。ごめんね。でも、本当に見つかってよかったよ。奥井くんは
大事な班員だからね」
福岡くんの言葉は裏表がなくて、心の底まで見通せた。ぼくは、目を背けたくなったけど、じっと福岡くんを見る。心配はどこかに消えていた。
「じゃあ、行こうか。みんな待ってるよ」
動物園のざわめきは午後になってもやむことはない。福岡くんはぼくの手を握って、そのざわめきの中へと歩き出していった。福岡くんの手は大きく、手のひらも厚かった。
ぼくは、連れていかれるというよりも、一緒にみんなの元へ戻るといった思いで、福岡くんの後を歩いた。さっき見たワニやカメのことはもう忘れてしまっていた。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
