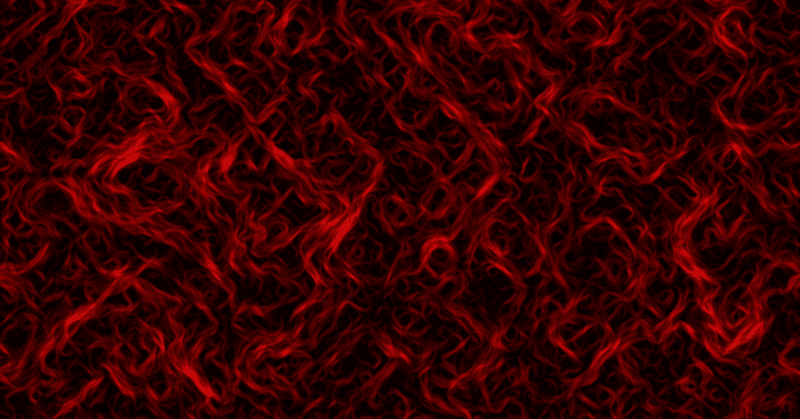
【小説】キープ・オン・チェンジング!!(6)
福岡くんは水色のパジャマのまま階段を下ってくる。近くで見ると、脇がじっとりと湿っていた。
「ちょっと、大翔。大丈夫なの? 具合悪いんじゃ……?」
「なんとか大丈夫。それより奥井くん、来てくれてありがとうね」
福岡くんの顔は、頬が少し細くなっていて、瞼も重そうだった。笑おうとしているみたいだけれど、上手く笑えていない。ぼくの描く下手な絵みたいだった。きっと無理をしてくれているのだろう。
ぼくは福岡くんに感謝と申し訳なさを覚えつつ、聞いた。
「うん、全然大丈夫だよ。それより福岡くん、どうしたの? 何かいやなことでもあったの?」
福岡くんはうなだれて答えない。しかし、その身長差からかぼくは福岡くんの顔をのぞくことができた。口元がぐにゃりとゆがんでいた。
「もし、答えたくなかったら、答えなくていいんだけど、何か怖い思いでもしたの? たとえば、夜中にいるはずのない誰かの姿を見たりとか……?」
ぼくがそう言うと、急に福岡くんが顔を上げた。口は中途半端に開いていて、大きい目がより大きく見開かれている。間違いない。ぼくの言葉に驚いている。
きょろきょろとぼくたちを見る福岡くんのお母さんは、何が起こっているのか分からないといった様子だ。ぼくたちにはあまり関係がない。固まったままでいる福岡くんに、ぼくはさらに聞いた。
「もしかして、その人って子供だった? ぼくたちと同じか、ちょっと小さいくらいの」
福岡くんは首を縦にふった。決まりだ。
福岡くんは昨日の夜、合田くんを見たのだ。合田くんはぼくにしたように、夜中に急に現れて福岡くんをおどかしたに違いない。ベッドの前に知らない人が立っていたのには、さぞ怖かったことだろう。
ぼくはいいけれど、福岡くんは合田くんを知らないのだ。どうせ来るなら、ぼくのところに来てほしい。そうすれば、少しは話しようがある。
「ねぇ、福岡くん。相談なんだけど、来週の水曜日の夜、ぼく、福岡くんの家に泊まっていいかな。迷惑はかけないから」
そうだ。合田くんがぼくのもとに来てくれないのなら、ぼくの方から行けばいいのだ。
せっかくできたぼくの友だちを怖がらせるようなことは、いくら合田くんであっても許せない。ぼくの中で、小さな使命感が芽生えた。
ぼくは、合田くんと話ができる。話して、もう福岡くんの家に来ないようにしてもらおう。
「ごめん、それはちょっとできないよ。奥井くんをいやな目にあわせたくないんだ」
福岡くんがそう断っても、ぼくは自分の主張をおし通しそうとした。何度も何度も頼み込む。やがて、福岡くんとお母さんは観念したようで、ぼくが泊まることを許してくれた。二人のまばたきが多くなっていたので、急なお願いにとまどっているのがありありと見てとれる。
ぼくは、二人に深く頭を下げた。泊まることを許してくれた嬉しさはない。それよりも、その日をどうするかで、ぼくの頭はいっぱいだった。
今朝ご飯を食べているとき、テレビの天気予報でアナウンサーが、梅雨に入ったと言っていた。その言葉通り今日は、傘をさしていいのかどうか判断に迷うくらいの雨が降っている。空はどんよりと雲がおおっていて、かなり機嫌が悪そうだ。
ぼくは傘を持って家を出た。教科書がぬれても別にいいと思った。いつものように通学路を歩く。足どりは少し重い。傘をさした人々がぼくを追い抜いていく。
三丁目の交差点はゆるやかな坂道の入り口になっている。スーパーマーケットの駐車場に、まだ車は見当たらない。そのフェンスの前に、花束が置かれているのが遠くからでも分かった。
近づいてみると、むらさき色の小さい花が集まったささやかな花束だった。いくつかの花びらが地面に落ちている。昨日の夜は土砂降りだった。雨に打ち付けられた花はすっかりしおれてしまっていて、野原に咲いていたころの元気は見る影もない。
この交差点で二年前に、合田くん、いや、合田靖人くんは交通事故にあったのだ。下校時間を過ぎて、友達の家に遊びに行く途中だったのかもしれない。
代わってあげたい。あのとき車にひかれたのが合田くんじゃなくてぼくだったら。そんなことを全く思えない自分がいやになりそうだ。ぼくは生きていてよかったと思っている。合田くんをしのぶむらさきの花束の前で。ぼくと合田くんの違いなんてあのとき、この交差点にいたかどうかの違いでしかない。
合田くんのことをかわいそうとは思わなかった。ぼくの心は、ただ静かな悲しみに満ちていた。
花束に向かって手を合わせる。雨あしが強くなってきたけれど、ぼくは時間が許す限り、ずっと手を合わせていた。
たしかに合田くんからしてみれば、やり切れないと思う。ぼくの前に出てきたい気持ちも、思い上がりだと思うけど分かる。しかし、だからといって福岡くんにまで危害を及ぼしていいわけがない。
ぼくは決意を新たにして、学校に向かって歩きだした。坂の上から流れてくる雨水が花束にたまっていた。
学校での時間は矢のように過ぎ去って、放課後になった。ぼくはお父さんとお母さんをなんとか説得して、福岡くんの家に向かった。福岡くんのお母さんは、ぼくをこころよく歓迎してくれて、夕食にカレーライスをふるまってくれた。とんかつが一人一個ついていて、それがスーパーのおそうざいだとしても、高級感がある。広い窓の外では雨が上がり、雲の間から星がまたたくのが見えた。
福岡くんの部屋には物が多く、本棚にぎっちりとマンガが詰め込まれていた。部屋のすみにジャンプやらマガジンやらが積まれているところを見るに、ぼくが来る前に急いで掃除をしたみたいだ。壁には野球チームのポスターが貼ってある。胸に「Japan」と書かれていた。そのポスターの下に水色の布団が敷かれていた。ぼくの布団なんかよりもずっと厚くて、ふわふわとしていそうだった。
しかし、ぼくは今日は寝ないと決めている。福岡くんもここ数週間の出来事から、すっきり寝れなくなってしまっていたようで、ぼくたちはマンガとかうらないとか他愛もない話をして過ごした。福岡くんは、学校にいる時よりもよくしゃべった。口から言葉がついて出るみたいに、ゆううつな気分をまぎらわすためにしゃべり続けていた。
だけれど、その努力もむなしく、ぼくたちの会話はあまり続かなかった。コミュニケーションが苦手なもの同士であることを、あらためて思い知らされた。スマートフォンで動画を見たりして、時間をつぶしたつもりだったけれど、まだ夜の一一時も過ぎていない。夜はとてつもなく長いのだと感じる。授業中なんかよりよっぽど。
ぼくは、布団に横になってしまった。天井の明かりがついたままだと、まぶたの裏が少しかすむ。そして、そのまま眠りに落ちてしまった。何の夢も見ず、頭の中にはただ暗い空間が広がっているだけだった。
すると、ぼくの意識の外で風が吹き始めた。ひゅうひゅうとつむじ風のように、音は大きくなっていく。耳をふさぎたくなるほどの轟音。
ぼくはおそるおそる目を開けた。いつの間にか天井の明かりは消されている。
風は嵐の中みたいに強さを増していき、窓がガタガタとふるえている。福岡くんも目を覚ましたらしい。歯がガチガチと揺れている。
ぼくたちは暗やみの中に、ぼんやりと起き上がるあやふやな像を見た。夜よりもずっと黒くて、小さい粒が輪かくをかたどっている。福岡くんは「何だよこれ」と言って、あたりを見回す。
ぼくは耳をふさいだ。それでも、風の音は止むことはなく、暗やみをかけぬける。部屋のすみに置かれたマンガ雑誌が、音を立ててくずれる。かべのポスターがビリッという音ともに破ける。福岡くんはうずくまってしまっていたけど、ぼくは立ち続けることに全力を注いだ。
この現象の原因をぼくは知っている。合田くんだ。思えば、家族で過ごした夜に起きた不思議な現象の数々も、合田くんのしわざだったのだ。
ぼくは合田くんの姿が見たかった。来るなら来いとさえ思っていた。それでも、足はふるえてしまっていて、ぼくは自分がおじけづいてしまっていることに気づく。
目をこらすと、黒い粒々が虫みたいにうごめいていた。だから、肩に手を置かれたときは、飛び上がりたくなった。
置かれた手は相変わらず冷たく、生気を感じない。
ふりはらいたい衝動にかられたけど、ぼくはゆっくりと肩の方を向いた。そこに手はなく、ふりかえってみても誰もいなかった。今度は首筋をなでられる。ぼくの息は早く、荒くなる。心臓がかんかんと、くるったようにかねを鳴らしている。
しかし、がんばって動かないでいると、しばらくして手はぼくから離れた。気配がぼくの横を通り過ぎた。そんな感じがした。
よくは見えないけれど、ベッドの上で福岡くんは相変わらずうずくまったままだった。
しかし、とつぜん手をふりはらいだす。まるで、何かをかき消そうとするように。実体をつかもうともがくように。手をふり回し続ける福岡くんの姿は、ほとんどこわれてしまったようにぼくには見えた。
そして、福岡くんは立ち上がり、というよりも無理やり立たされた。あごが上を向いていて、体が少しだけ宙に浮いている。足をばたつかせてぬけ出そうとしているけど、それも叶わない。苦しそうにしている福岡くんを見て、ぼくは彼が首をしめられているのだとさとった。
福岡くんの顔はどんどん赤くなっていく。目から涙がこぼれている。いくら合田くんだからといって、こんなことが許されるはずがない。
「やめて!」
ぼくは思わずさけんでいた。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
