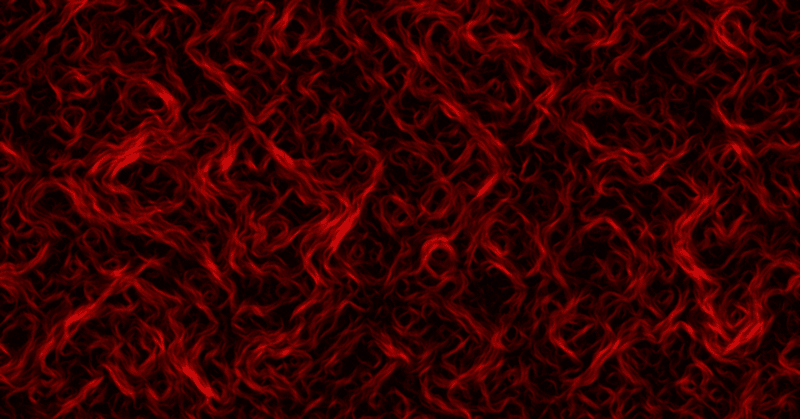
【小説】キープ・オン・チェンジング!!(3)
遠足のことがあってから、ぼくと福岡くんは放課後も二人で遊ぶようになった。
福岡くんの家に行って、最新のゲームをしたり、特撮ものの番組を一緒に見たりした。福岡くんの家は、ぼくの家とは違い一戸建てで、家に行くと福岡くんのお母さんが、必ずお菓子を用意して歓迎してくれた。ぼくが福岡くんの家に行くのを、お父さんとお母さんは止めなかったし、気づけば毎日のように福岡くんの家に通っていた。
そして、合田くんとはあまり会わなくなった。
その日も福岡くんの家に寄ってから、ぼくは家に帰った。
水曜日の午後七時三〇分。家族三人での夕食だ。メニューはエビフライとポテトサラダ。どちらもぼくの好物である。
ぼくたちはテーブルを囲んで、ご飯を食べながらとりとめもない話をくり広げた。
お父さんは科学の話が好きで、よく宇宙の謎について、ぼくに話してくれる。 それが食事の場に適切な話かは分からないが、ぼくは愛想よく語るお父さんがきらいではなかった。
窓際のテレビは、バラエティ番組を放送していて、お笑い芸人が激辛料理にわめきながらも挑んでいる。お母さんが笑ったので、ぼくもほほえんだ。
エビフライを半分までかじったとき、ぼくの耳元に小さな風の音が聞こえた。ささやくように、ひゅうひゅうという音がどこからともなく流れている。音はだんだん大きくなる。自転車で下り坂を降りるときみたいな風。
でも、カレンダーもレースのカーテンも何一つ揺れてはいない。お父さんとお母さんも変わらずお箸を進めている。
やがてぼうぼうと風の音は強さを増し、ぼくが耳を塞ごうとした瞬間、ドアの横にある本棚から、一段丸ごと本が崩れ落ちた。何の前触れもなく、いきなり。何かに押し出されたように。
突然のことにみんなが目を丸くした。
本は一か所に集まることなく、散らばって落ちていた。一冊一冊の表紙まで、ちゃんと見える。
「どうしたんだろうな」と、お父さんが言う。お母さんは不思議そうに首をかしげる。
ぼくは「直してくるよ」と、席を立って本棚に向かった。本棚へはぼくの席が一番近かったこともあるけど、なぜかぼくが行かなければならないと感じたからだ。
近寄ってみると、本の表紙には細かい傷がいくつもついていた。ガラスの破片でつけられたみたいな傷が、いくつも。手に取るとざらついた感触が、ぼくの呼吸を早める。目まいさえしそうだった。
それでも一冊一冊、心配してやってきたお父さんと一緒に本をしまっていると、一瞬にして、ぼくの目の前は真っ暗になった。ぼくが目を閉じたのではない。目を開けたままで、暗い。
つまりは停電だ。
ぼくは自分の姿を確認できず、空中に手をさまよわせた。どこに行くか分からない手は、体とつながってないみたいだった。手が壁に当たると、ぼくは一時的な安心を得た。さらさらとしたさわり心地は、少しだけ冷たかったけれど。
「ブレーカーが落ちたのかな。ちょっと見てくる」
お父さんはズボンのポケットからスマートフォンを出し、懐中電灯代わりにして、リビングから出ていった。取り残されたぼくとお母さんは、不安の海に浮かんでいるしかなかった。ぼくは、壁に手を当てたまま動かない。
すると、いきなりテレビがついた。元のバラエティを流しているけど、音は途切れ途切れで、映像もときどき黒い粒子のようなものが砂ぼこりみたいに混ざる。ぼくの姿は調子の悪いテレビに照らされて、振り向くとお母さんは椅子に座って、頭を抱えて俯いていた。停電はまだ直らず、テレビだけが瞬いているような状況だった。
雑音と風の音。家の中で吹雪が吹いているみたいだ。
やがて、リビングの電気がつくと、テレビは正常に戻り、ノイズのないなめらかな放送を流していた。お父さんが戻ってきて、「やっぱりブレーカー、落ちてただけだった」と、ぼくたちに告げる。お母さんは、さきほどテレビがおかしくなったことについて、自分を落ち着かせるように慎重に説明する。
けれど、お父さんが「そんな非科学的なことあるわけないだろ。疲れてんだよ」となだめるので、一応は冷静さを取り戻したようだった。そんな二人をよそに、ぼくは本棚に本を戻す作業を再開した。
表紙の細かい傷は、いつの間にか消えていた。
それから一週間が経った日の夜。ぼくはなんだか眠ることができずにいた。一二時を回ってもまだまだ眠くない。体育の授業もあったのに。
ずっと起きているとベッドの中にいても、頭の中は暗い洞窟を探検をしているみたいに感じられる。
ぼくはトイレに行こうと寝室を出た。お父さんとお母さんはもう寝てしまっている。今起きているのはぼくしかいないはずだった。
テーブルの上には、お父さんが飲みっぱなしにしたビールの空き缶があった。ぼくはそれをゴミ箱に捨て、トイレに向かう。
ぼくの家のトイレは玄関の近くにある。暗い廊下を歩きたくのが怖くて、ぼくは照明をつけた。ぼくが歩くと照明がちかちか光って、廊下がまばらに照らされる。まるでぼくの行く手を阻むかのようだ。
しかし、ぼくは足を止めず廊下を歩く。背後に何かの気配があった。シャンプーをして目をつぶっているときに感じる人の気配とは全然ちがう。パジャマを通してうすら寒さが伝わってくるのだ。
まるで、五月にはまだ早い冷房を入れたかのように、ぼくの背中だけが冷やされている気がした。ふるえる心をおさえて、トイレの前まで歩いて振り返ってみる。
そこには、だれもいなかった。気のせいだったのかな、とぼくは一つ頭をかいた。
だけれど、トイレのドアノブを掴んだ瞬間、何かがぼくの手に触れた。それは見えなかったけれど、間違いなく人の手だった。つるっとした五本の指がぼくの手を握ったのだ。乾いていて、力が弱くて、何よりその手は冷たかった。氷よりもずっと冷たい手が、ぼくの体温を奪う。
ぼくは、ドアノブから手を振り払った。あたりを見ても人の姿はない。点滅する照明の下でたたずむぼくがいるだけだ。
ぼくは走って部屋まで戻った。布団にくるまって、そのまま朝が来ることを願った。
足音がうるさかったようで、お母さんを起こしてしまったらしい。ぼくのベッドにまでやってきて、「寝れないの?」と声をかけてくれた。一〇才は自分の意思で寝られるよ。そう返そうとしたけど、やめた。お母さんにあったことを話しても信じてもらえるわけがない。
ぼくは、お母さんに背を向け続けた。
それでも、そばにお母さんがいることが、幼稚園児のときみたいに心が落ち着いて、気づいたらぼくは寝てしまっていた。寝ている間は、なんの夢も見なかった。
また、水曜日の夜の出来事だった。
「どうしたの、奥井くん?何かあったの?」
一時間目が終わって、福岡くんが話しかけてくる。次の日、ぼくは寝坊して遅刻をしてしまった。
起きると体の節々が重く、とても学校に行ける状態ではなかったけれど、なんとか登校した。子どもが一人もいない通学路は、別の世界に続いているみたいだった。
矢城先生は怒ることもなく、簡単な注意をして、一時間目の授業をはじめてくれた。めったに注目されないのに、こんなときだけ注目される。クラスメイトの視線が痛かった。
「ちょっと寝れなくてね」
ぼくがそう言うと、福岡くんは口を開けて、分かったように頷いた。
「もしかしたらストレスがたまってるんじゃない? 最近、いやなことあった?」
福岡くんになら話してもいいと一瞬思った。しかし、たぶん信じてもらえないだろうと、かき消した。ぼくだったらこんなばかげた話、信じない。いや、信じたくない。
ぼくはうつむいて、首を横に振ることしかできなかった。
「大丈夫? 気分がすぐれないなら保健室に行った方がいいよ」
「別にそこまで大したことじゃないよ。すごしているうちに楽になると思うから」
保健室は苦手だ。消毒のにおいが気になってしまう。それに、ベッドで寝ていると、自分がいる場所が分からなくなって居心地が悪い。
「あのさ、今日も家で遊びたいなって思ってたんだけど、どう? 来れる?」
「ごめん、今日はちょっと無理そう。また、来週ね」
断りの言葉は失礼かなとも思ったけれど、福岡くんは納得したように「分かった」と言ってくれたので、ぼくはほんの少しだけ心が軽くなった。
二時間目のはじまりを告げるチャイムが鳴る。 さわいでいたクラスメイトもみんな自分の席に戻っていく。矢城先生が黒板に数式を書くのを、ぼくはノートも取らず、ぼうっと眺めていた。
放課後、ぼくはあの公園に行ってみた。いつも合田くんと遊んでいた、マンションの間の公園だ。いつもなら幼稚園や学校を終えた子供たちが遊んでいるのに、この日は誰もいなかった。ちょっとでも話し声がないと、ぼくだけ公園においていかれた気がして、心が上手く回らない。
一人、ブランコに乗ってみた。足を振ってもブランコはやっぱり動かない。こういうとき、合田くんなら笑わずにあたたかく見守ってくれるのに、いつまで経っても合田くんは現れなかった。厳しい合田くんの家のことだ。きっと塾にでも通っているのだろう。
ぼくは合田くんのことを少し気の毒に思った。別に合田くんは同情されたくないだろうけど、合田くんを頭にとどめておくためには、たとえ望まれていなくても、思いやるしかない。
少し待ってみたけど、やっぱり合田くんは来なかった。ぼくは、家に帰ることを決めた。
立ち上がってブランコから離れようとすると、隣のブランコがわずかにゆれた。風は全く吹いていないのに、きぃという音を立ててゆれていた。
ぼくは、しばらくその場を動けなかった。ブランコの影が長くのびていた。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
