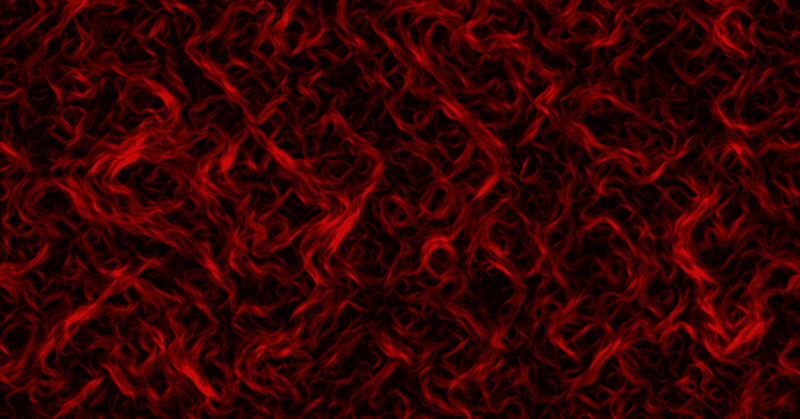
【小説】キープ・オン・チェンジング!!(1)
「どうして、人はずっとは生きていられないんだろうね」
夕暮れ時をすぎた公園は、日差しもなくなり、少しのさびしさに包まれていた。
左右をマンションにはさまれている小さな公園。
ぼくよりも小さい子どもたちが、ジャングルジムに登って、ヒーローごっこをして遊んでいる。飛び降りて骨折しないかが心配だ。
「さあ。ずっと生きていたら、生きることにあきちゃうからじゃないの」
合田くんがブランコをこぎながら、答える。きぃきぃ音を立てるブランコは、ぼくたちが生まれる前からあったものらしい。
「でもさ、今日で春休みも終わりでしょ。このまま一学期も終わって、夏休みも終わって。二学期も冬休みも三学期も気づいたら終わっていて。そうしてすぐ来年になって、来年もまたすぐに終わって。そんなことをくり返しているうちに、あっという間に大人になっちゃうんだろうね」
ブランコに座りながら、僕は、佐藤先生のことを思い出していた。
三年間、ぼくたちのクラスの担任をしてくれた佐藤先生。なのに先月の卒業式で、いきなり市外の小学校に移ることが発表になった。
ショックを受けて泣いているぼくをなぐさめてくれたその顔は、いつもの優しい佐藤先生のままだった。
そのあたたかい顔が、ぼくの胸に彫刻刀で彫ったような傷をつけている。
「何?怖いの?まだ、転勤になった佐藤先生のことを引きずってるんだ?あのね、奥井くん。世の中には大人の事情ってもんがあるんだから、早いとこ受け入れないとダメだよ。しょせん、ぼくたち子どもにはどうしようもないんだから」
合田くんはぼくの方を向いて、ゆっくりと話す。教科書のさし絵みたいに、やわらかな表情だった。
「合田くんは、担任の先生が別の学校に行っちゃったとかないの?」
「ぼくはないかな。三年生になるときにクラスがえがあったけど、先生は二年生のときと同じだったし」
下を向いて、「そっか」とだけ答える。
合田くんは別れのつらさを知らないんだ。少しうらやましいな。
ぼくは不純にもそう考えてしまった。傷を見ないふりは失敗だ。
いたいけな子供たちのむじゃきな笑い声だけが、公園にこだましている。
「そういえば、奥井くんの学校では、四年生になる時にクラスがえをするんだよね。もしかして心配なの?」
「うん、すごく心配。合田くんはどうやってクラスがえを乗り切ったの……?」
「うーん、どうやってって、気合い? とにかく自分から話しかけること。それ以外にないんじゃないかな」
それができたら苦労しない。その言葉を、ぼくはぐっと飲み込んだ。
入学したときに、誰にも話しかけられずに、教室のすみに追いやられたぼくにとっては、耳がいたくなる言葉だ。
ぼくだって本当は話しかけたい。けれど、あいさつだけで終わらないようにする方法が分からないのだ。
「まあ、奥井くんなら、きっと大丈夫だよ。新しいクラスにもなじめると思う。そんなに心配しなくても、声をかけてくれる人だってきっといるだろうし、もっと気楽にかまえていても、いいんじゃないかな」
そう言って、合田くんはブランコからジャンプした。
ぼくの身長ぐらいの距離を飛び、ぴたっと着地して、振り向く。日差しはないのに、金色の折り紙みたいに、光っているみたいに見えた。
ぼくはブランコがこげない。 足を振ってみても、ブランコはびどうだにしない。
もどかしい。
それでも合田くんはバカにすることなく、隣のブランコにそっと座ってくれる。いないものとして見られることが多いぼくにとっては、ほほえみたくなるくらいありがたい。
遠くで、帰宅をうながすチャイムが鳴る。
合田くんが「じゃあ、またな」と言って去っていくのを、ぼくはブランコに座ったまま眺めていた。
今年の春は桜の開花が早く、ぼくが一つ学年を上がるころには、もう散りはじめてさえいた。
通学路は、ゆるやかな坂道になっていて、新品のランドセルを背負った一年生が、ぼくを追い抜いていく。花束が置かれた交差点を通りすぎると、校舎が見えてくる。
新学期の校舎は、何も変わっていないはずなのに、ぼくの目にはちょっとゆがんでいるように映った。
校門をくぐると、校舎の横に人が集まっているのが見える。掲示板に新しいクラス名簿が貼られているからだ。
波のような人混みをかき分けて、ぼくは掲示板を確認する。
四年六組だった。
三年生のときも六組だったから、クラス自体は変わっていない。
いやなことといえば、教室が遠いことと、全校集会が終わった後にずいぶん待たされること。あと、なんか脇役っぽいところも気に入らない。
名簿には知っている名前も、知らない名前もあったけど、ぼくにはあまり関係なかった。
教室のどこにいても、無人島にいるみたいに周りから引きはなされた感覚は、変わらないだろうから。
なんとなく授業を、行事を、休み時間をやりすごして卒業できればいい。変わったことなんて一個もいらない。
ぼくは人混みを押しのけて、玄関へ向かった。すでに下駄箱が新しいクラスに変わっているのが、少しいやだった。
始業式は、特に何事もなく終わった。
ぼくたちの新しい先生は、矢城先生というメガネをかけたおばちゃんの先生だった。少し太っていて、メガネの奥の目が細くやわらかい。ぼくの話でも、ちゃんと聞いてくれそうな雰囲気だった。
四年生になって最初の日は自己紹介と簡単な連絡事項だけで、午後三時には放課後になっていた。
自己紹介は名前と「よろしくお願いします」しか言えなかった。
ぼくの後にも二〇人くらいの人が喋ったから、ぼくのことなんて誰も覚えていないだろう。
それでも、ぼくも他の人の自己紹介を、壁にかけられた時計を見ながら聞き流していたからおあいこだ。耳に残ったのは、矢城先生がしてくれた拍手だけだ。
なんとなく教室を見渡してみる。
三年生のときに同じクラスだったのか、すでにいくつかのグループができあがっていた。窓際で女子たちが明るい声で、同じクラスになれたことを喜んでいる。
ぼくはくちびるをかんだ。ドアに一番近い席に座っていたぼくは、どのグループにも入れず、のけ者でしかなかった。
元三年六組のグループに話しかけようとは思う。しかし、金しばりにあったみたいに、体が動いてくれない。ただ、気づかれないようにときどき目線をやることしかできない。
クラスは変わったけれど、ぼくは何も変わらないのだ。
あきらめを胸にいだきながら、席を立とうとしたそのときだった。
「あの、奥井渡(おくいわたる)くんだよね。ちょっと話してもいい……?」
机の横には、一人の男の子が立っていた。
ぼくよりも背が高いその子は、顔も縦に長くて、両目が少し離れている。薄いくちびるから、くすみかけている歯がのぞく。
クラスのすみっこに追いやられるタイプの子だと、ぼくは直感した。どこのグループにも属していない。つまりは、ぼくと同じ部類の子のようだ。
名前は、当然分からない。
「ぼく、福岡大翔(ふくおかひろと)っていうんだけど、はじめまして、だよね……」
福岡くんの手は、胸の前で組まれて、細かく指を動かしていた。
ぼくは、はじめて自分の名前が、仕方なくという同情をぬきにして、呼ばれたことにかすかにおどろいていた。誰にも覚えられないと思っていたのに。
「うん、はじめまして」と言った声が、自分でもあきれるくらい上ずっていた。
「ねぇ、奥井くんって何色が好き? ぼくは黄色が好きなんだけど……」
どうしていきなり好きな色を聞くんだろう。もっと、元のクラスとかどのあたりに住んでいるとかいろいろ聞くことはあるはずだ。
しかし、ぼくを見る福岡くんのまなざしは、どこまでも澄んでいて、本当に好きな色を知りたがっている様子だった。
「ぼくは、緑色が好きかな」
そう答えると、福岡くんはしばらく考え込んでしまった。言葉がないと、今ぼくたちがどう見られているのかが気になってしまう。だれの視線も向けられてはいないけれど。
「そっか、緑色か。じゃあ穏やかなものが好きなんだね。ぼくも穏やかなものは好きだよ。風に揺れる葉っぱとか。見ていると落ち着くよね」
勝手に決めつけるなよとも思ったが、知り合って間もない福岡くんにきらわれるのはいやなので、ぼくはだまってうなずくことしかできなかった。
福岡くんも次の言葉がなかなか見つからないみたいだった。うつむいてキョロキョロしている。
のしかかる気まずさに耐え切れずに、ぼくはランドセルを持って席を立った。「じゃあね」と言うと、福岡くんもおずおずと手を上げて「じゃあね」と返す。
小学校に上がってはじめて、同じクラスの誰かと「じゃあね」なんて言葉を交わした。
ぼくはそっけなく教室を後にする。下駄箱で急いで靴を履き替えて、早歩きで校門を出た。
息が必要ないほどはずんでいた。
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
