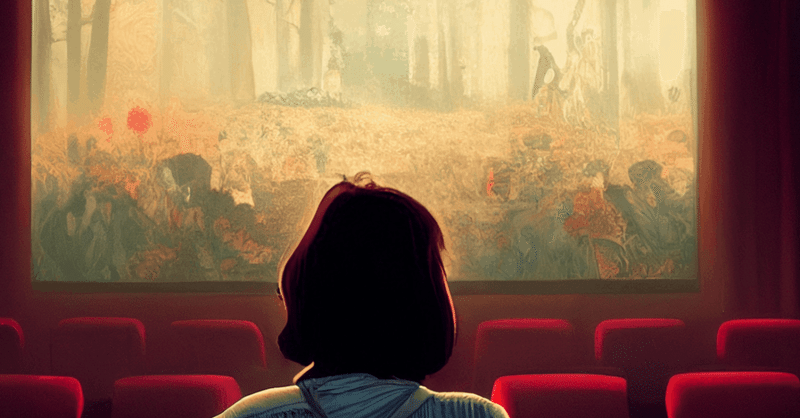
完璧な映画翻訳って何だ~"I am Sam"の"I wouldn’t want any daddy but you."について~
文系学部に所属する大学の四回生というと、往々にして時間ばかりあって金がない。これといった社会的責任もなく、社会において極めて無意味で自堕落な存在だと自覚することもしばしばだが、しかしそうであるからこそ自分のやろうと思ったことを勝手にやれるという強みもある。
当時あまりに暇すぎて、私は大学の図書館で映画を見ることがあった。大学の図書館であるから、レンタル料も視聴料もかからず、財布にも優しい。
その際に”I am Sam”という映画を見た。
幼年期のダコタ・ファニングがクソ可愛いということもさることながら、ストーリーも(若干リアリティはないが)よかった。
簡単に言うと、知的障害のある父親と娘の話で、娘が父親の知能を追い抜いてしまったことから「知的障害のある父親に養育する力はない」として引き離されてしまう。しかしその残酷な環境のもとでこそ、父親と娘との親子愛が光る――と、そんな作品である。
その中でもとりわけ印象的だったのが、娘のルーシーが父親のサムとの会話の中で言う以下のセリフだった。
「私の父親はパパだけよ(I wouldn’t want any daddy but you.)」
見れば明らかなのだが、この訳は文法的には何の意味も持ち合わせていない。考えるまでもなく「父親とは“ほぼ”パパ」なのだから、「私の父親はパパだけ」といわれても、「そりゃそうだ」という話になる。
結局、この文はほぼ「頭痛が痛い」とか、「馬から落馬した」という文章と似たようなトートロジーにすぎない。
しかし、”ほぼ”としたのがミソである。「馬から落馬した」というときの「馬」と、自分が落ちた「馬」というものに、何ら差異はない。ところが、「父親」と「パパ」という言葉が持つ意味は、違う。
父親を指す言葉には「父」「おやじ」「とーちゃん」「オトン」「父上」「父様」「父さん」など、日本語にはいろいろある。
その一つ一つの言葉が持つ、雰囲気、温もり、距離感…のようなものは、言葉で説明するのはなかなか難しく、その差異は非常に微妙なものだ。そして同時に、この差異をわざわざ一つ一つ説明するのも野暮ったい。
それらの言葉の持つ一つ一つのイメージなどの差異が翻訳の小さな一言に出てきていることに気づくだけで、作品に登場していない誰かの姿がふと見えたような気がして、差異がどうであるとかはもはや瑣末な問題なのである。
映画の翻訳は文字数の限りもあり非常に難しいらしい。一秒当たり四文字というのが目安らしいが、例えばある単語が非常に短いながらも冗長な意味を持つ、などという話になれば、適当な言葉をひねり出すのも大変だ。
字幕の短さに気を取られて「話の流れが分からない」ということになれば、翻訳の機能を失う。意味を取らせることだけでも大変なのに、更にそれ以上の機能を翻訳に付与するというのは至難の業である。
あらかじめ紡がれた物語の世界を壊さないように、翻訳は「物語に添える」ものでしかないのだ。
ここから少しややこしい話になるのだが、主張しすぎたために自分の世界の中で映画という物語が消化されてしまって、結果としてオリジナルとは別の新しいものが出来上がってしまうことだってあり得る。
更に抽象的に考えてみれば、物語の中には原作者の世界が内在している。翻訳で訳者の世界を介在させたら、原作者の世界と翻訳者が解釈した世界との二つの世界が衝突することだってあり得る。その衝突が、世界の齟齬を生むことさえある。翻訳を通して「添える」以上のことをするのは、出過ぎた真似であり、とかくかしましい。
もちろん上手く行けば、その翻訳者の言葉でその物語の世界を描き上げることが出来る。
仮に「もしパパじゃなかったら、他のパパなんていらないわ」なんて訳だったら、きっと私は何とも思わず素通りをしていたはずである。
「私の父親はパパだけよ」という、作品を貫く親子愛というものを全く破壊しないままに、話の流れも遮らず、文章がトートロジカルであるという「違和感」に意識を向けさせることによって、その気づきのヒントを与えつつ、そして「父親」と「パパ」という二つの「同じ」意味の言葉の違いを感じさせているこの一文は、秀逸というほかない。そしてこれは、作品の世界観に沿った翻訳だ。
これほど完璧な形で私の前に翻訳が立ち止まることは今後そう多くはないだろう。
立ち止まる言葉と通り過ぎる言葉と――なるべくなら沢山の言葉が自分の目の前に立ち止まってくれればと願いながら、英語を聞きとることができない貧弱な耳に代わって映画の字幕に目を走らせる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
