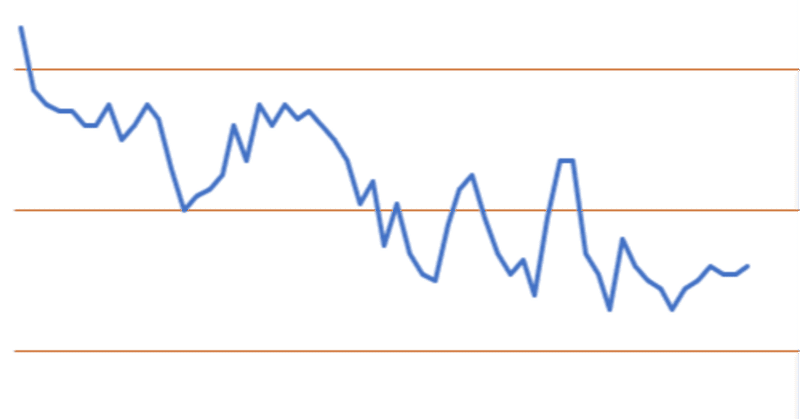
統計嫌いフィルターが外れたきっかけにメモ
★よく出てくる用語
①平均
・全体の傾向をつかむために出す数値。
・Mで表すこともある
・合計÷サンプル数。
・エクセルの関数は下記を使用する
=AVERAGE(範囲を指定する)
②標準偏差
・全体の傾向をつかむために出す数値
・SDで表すこともある
・要はデータのばらつき
・つりがね状に分布した端っこは「協力者のうち、○名は誤答率が20%に達していたため、分析から除外し、○名のデータで分析を実施した。」的な感じで使わないことも。
・ばらつきが大きい場合は仮説が採用されない場合もある。そういう場合はサンプル数を増やすことで、傾向がつかめる場合もある。
・エクセルの関数は下記を使用する
=STDEVP(範囲を指定する)
③t検定
※以下は「~があることを検証する」という仮説の立て方をした場合というのが前提
・ざっくり言えば「実験において偶然が原因で実験結果がブレる可能性(本当は無いのに有るという結果が出る可能性)」のこと
・心理学の場合、検定の結果が5%(0.05)、もっと厳密にいうと1%(0.01)よりも小さければ仮説は「t検定の結果~となり、今回の仮説は統計的に有意であると言える」として「仮説は支持された」とし、大きければ仮説は「~ということは出来ず、今回の仮説は棄却することとする」みたいな感じで書く。尚、5%以上10%未満では「~ということは出来ず、今回の仮説は棄却することとするものの、~であるとの一定の傾向が確認された。」とする。
・実験協力者が同一で、条件を変えて2パターン試行した場合は「一対の標本による平均の検定」(=対応があるt検定)を使う
・実験参加者を2群に分けてそれぞれ条件を変えて合計2パターン試行した場合は「等分散を仮定した2標本による検定」(=対応がないt検定)を使う
・条件(次元)が3つの場合は分散分析と多重比較を併用するかたちとなるので注意する。
※多重分析を併用する理由は、分散分析だけでは条件Aと条件Bの差なのか、条件Bと条件Cの差なのか、条件Aと条件Cの差なのかが分からない為。
★エクセルを使ってt検定を行う方法
分析ツールをアクティブにする
※そのパソコンで初めてt検定をする場合にのみやる必要がある
2度目以降は3以降からでOK
1.エクセルを開く
2.ファイル→オプション→アドイン→分析ツール→OK
3.「データ」のタブの右端「データの分析」
4.「分析ツール」の中から実験協力者が同一か否かを基準に使うものを選ぶ
5.「変数1の入力範囲」に条件1のデータを、「変数2の入力範囲」に条件2のデータ範囲を指定する
※もし表のラベルも含めて範囲指定した場合はラベルにチェックを入れる
★書き方のポイント
・書き方は下記の並びで書く。
具体的な数字はエクセルなどでt検定を行った結果表示された表の数字を
小数点以下の数値を整えたうえでそのまま当てはめる
t(自由度)=t値,有意確率
ちなみに自由度は「サンプル数ー1」
t値は表の「t」に書かれた数字を小数点以下2桁~3桁にしてそのまま書く
有意確率は「p(T<=t)両側」に書かれた数字を2桁~3桁にして以下を参考に数字を書く。ちなみにpは有意確率のこと。片側でも悪くはないけど両側の方がより厳密なのでmore betterというニュアンスらしい。
書き方は下記☆の3パターンを参照
☆0.001未満の場合
※1より小さい場合は小数点の前の0は省く
p=<.001
☆0.01以上1未満の場合
p=.(小数点以下の数字3桁)
例:p=.510
☆1以上の場合
p=(小数点以下3桁)
例:p=1.234
【重要!】tやpはイタリック(斜めのフォント)にすること!
★その他
・論文を書くとき、考察は現在形で他は基本的に過去形で書く。
・グラフのことを「プロフィール」と言う
・実験協力者が同一で、条件を変えて2パターン試行した場合、条件の1をやって、条件2をやる群と条件2をやって条件1をやる群に分けてデータをとるパターンもある。これは慣れによるスピード上昇などの効果を相殺して無かったことにするため。
こういう場合は論文を書くとき、「手続き」の項目で「慣れによるスピード上昇の効果を相殺するため、参加者間でカウンターバランスをとった」などと一文添える。
・論文で表を挿入するときは縦棒を消す。
一番シンプルなやり方はエクセルで縦線を消して横棒だけで構成された表
をつくり、最後に表全体を選択した状態で「塗りつぶし」→「白色」を選択。それをコピーしてワードで論文を開き、図としてペーストする
・論文に挿入するグラフと表ではラベル(「図1:○○〇〇」「表1:○○〇〇」)の位置が異なるので作成時に注意する。
具体的には、グラフのラベルはグラフの下に置き、表のラベルは表の上に配置する。
・論文の「引用文献」のところで著者が3名以上の場合初回は苗字を全員分書くものの2回目以降は「Yamada et al.(2023)」という感じで書くが、このet alは「エトオール」と読み、「山田他」の意味。ちなみに西暦は論文発表の年や本の初刊の年。
・文献リストは著者の姓のアルファベット順。(五十音順ではないので注意)
・ウィキペディアやブログなど電子媒体からの引用は避ける。削除されたり著者が明らかでなかったり、内容が上書きされたりするので。
・7件法の評定尺度の一番スタンダードのものは以下の通り。
左右の端に対をなすA(例えば「悪い」)とB(例えば「良い」)の項目を置いて「非常にA(悪い)」「かなりA(悪い)」「ややA(悪い)」「どちらとも言えない」「ややB(良い)」「かなりB(良い)」「非常にB(良い)」として「非常にA(良い)」から順番に1~7点として数値化する。これをもって「評価」「力量」「活動性」に属する形容詞対を用いると、情緒や感性などの抽象概念を数値化してとらえることができる(※SD法)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
