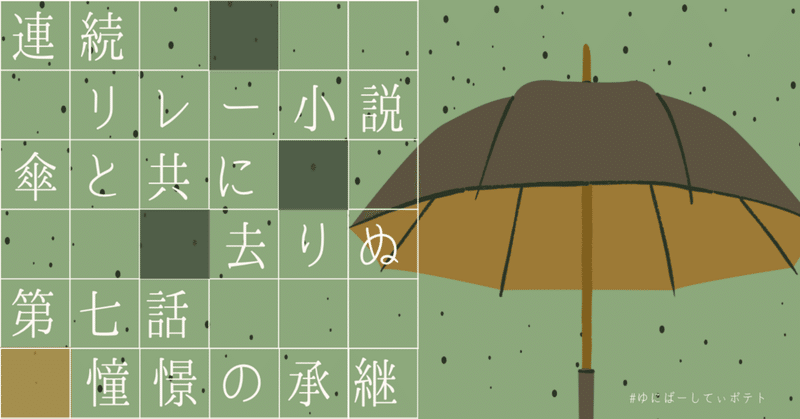
【小説】傘と共に去りぬ 第7話 憧憬の承継【毎月20日更新!】
第6話はこちらから▼
憧れって、いつから自分の足を引っ張るようになるんだろう。どうしてその弱々しい針をもって、ほかの誰でもない自分に先端を向けたりするんだろう。
もう少しだけ、キレイゴトが生きやすい世の中であればよかった。
そうすればきっと、私の同級生も、不登校になったりなんかしなかった。
8月/持田二菜
去年、藤倉蒼と私の間には、いろんな言い訳があった。同じクラスで、同じ美術部で、どっちも上のきょうだいがいる。会話をしても、不自然でないだけの言い訳が、たくさん。
それがいいことであったのかどうか、私には判断が難しい。
夏休み明けから教室にも部活にも姿をあらわさなくなった彼が今、家で何を考えているのかによる。そもそも、私のことなんて思い出していないかもしれない。
それは寂しいな、と思いかけて、息を吐く。
いや、そうでもないな、と思い直した自分のことをどう受け止めたらいいのか。
答えを出す前に、送信ボタンを押した。三十分の力作が、ひゅっと画面の中をのぼった。「どなたですか?」なんて返ってきたら、さすがに寂しいかもしれない。
『映画観に行かない? インディの最後のやつ』
画面上の私がどんな声色で話しているのかは、既読がつくまで誰にもわからない。
ここにいる私がどんな顔をしていても藤倉くんには見えないし、彼が「どなたですか?」と思いつつ、「お久しぶりです。せっかくですが、ご遠慮しますね」と送ってきても、いや、まあ、さすがにわかるか。文面で。そんなに鈍くはない。
「楽しそうだね。何かいいことあった?」
鈍いやつが来たなあ、と思いながら、「さすがお姉様、観察眼がおありだわ」と苦笑いして呟く。「特に何もないよ」
「そういうお姉ちゃんはないの? 何か、いいこと」
「え、あっ、今朝の占い、五位だったよ」
「びみょくない? ほぼ真ん中じゃん」
「真ん中くらいが一番いいと思うんだけどなあ」
ううん、と唸りながら、いやに薄着の姉は棒のアイスに大口でかぶりつき、期待を裏切るサイズで歯形を残した。「あ、お風呂でたよ、次どうぞ」と破顔する彼女に、見ればわかる、などと言ったりはしない。画面の中でさえなければ、自分がどんな声色をしているのかがわかるからだ。
「例の傘と、傘の王子様は?」
今年の二月、姉の一花は「雨の日に傘を忘れて困っていたら、イケメン(推定)が傘を渡して去っていった」という、一周回って新しい少女漫画を実体験したばかりだ。
そして、どこか天然の入った彼女は「返却するために、いついかなるときも傘を持ち歩く」という暴挙をやらかしかけて、うっかり肝心の傘を無くしてしまっている。いろいろあって彼女の同級生が見つけてくれたらしいのだが、受け渡しまでの間に再び紛失してしまったようだ。
傘も、その持ち主の王子様もいまだ探している最中だが、結果はあんまりみたいだ。「なんかテニプリみたいな言い方」とくすくす笑うそれが照れ隠しであることは明白だった。
「一花ゾーンには入ってこないの、傘の王子様は」
「なっ、ないない!」
「ゾーン」に笑うべきか、からかわれたことに反応すべきか、迷った挙句に後者が勝ったらしい。「っていうか、今どき王子様とか、痛くない? 私……」とぶつぶつぼやいている。今頃気づいたのか。
「二菜たちみたいにさ、気兼ねなく一緒にいられる関係、みたいな感じがいいよね」
「たちって、誰のこと?」
「藤木くんだっけ、同じ美術部の子」
「それちびまる子ちゃんでしょ。声低いキャラ」
「あ、唇が紫色の」
「そうそう」
「特技がスケートで」
「そうなの?」
「アメリカンドッグが好物」
「やたら詳しいな藤木くんについて」
スマホの通知画面には、『ごめん』と表示されている。
続いて何かメッセージが来ていたけれど、見る気にはなれない。
ああ、本当に鈍いやつだなあ。今この瞬間、どなたですかと言われたほうがよかった、と思っていることなんて、ちっとも気づいてやしないのだ、この人は。
***
「二つの野菜で、にいなって読むの。外国人みたいでしょ」
最初に声をかけたときの一言のほうが、スマホのメッセージより力作だった。藤倉くんに話しかけるために、私は一ヶ月の時を要した。私を後押ししてくれたのは、背後でニヤニヤしながら囁く部員たちの声が、どんな色をしているかわかったことだった。
藤倉くんの背中は、絵を描くときだけいつも真っ直ぐに伸びていた。実際には、彼の座高は普段とまったく変わらなかったから、これは私の主観でしかない。
でも、それがすべての答えだ。
イーゼルの前から離れた瞬間、彼の背中はふんにゃりと重力に従い、どんな言葉にもちょっと困ったように笑うのだ。甘いものも辛いものも、痛いものも、柔らかくて軽くて、優しいものも。全部おんなじように受け取って、おんなじように笑うのだ。
その手の中にあるものが、あなたに向けられる、どんな剣やペンよりも強いものだとも知らずに。そこから生まれるものが、あなたを王子様にだってしてくれることも知らずに。
薄汚い、行くあてのない、あさましい浮浪者のふりをして、それにすらぺこぺこと頭を下げている。
「ほんとだね」
「顔めっちゃ日本人なんだけどね」
「うん。でも、いいじゃん」
そこで、彼がはっとしたように顔を上げたことを、よく覚えている。
自分が口にした言葉が、まるで何者かから与えられた天啓でもあるかのようだった。
そこから私たち二人はそれなりに親しくなった。
その後、彼の身に何が起こったのか、ありていに言えば、「陰キャのくせに女子と楽しそうにしててムカつく」と思った男子が彼に何をしたのか、私はよく知っている。
あのときも、今も、私は何をどうしたらいいのか、わからないままだ。
だから、ときどきふと頭をよぎる。脳内の私が、「いっそ」と口にする。「いっそ、何?」と、これまた脳内の藤倉くんが、いつもの調子で聞き返してくる。
彼からの返信をちゃんと見ることができたのは、翌日の朝、日曜日らしく大ざっぱな朝に分類される時間だった。
「ごめん」の続きを見る勇気が出たのは、昔の彼のことを思い出したからかもしれない。藤倉くんが、去年から変わっていなかったらいいのになあ、と目を細めてメッセージアプリを立ち上げた。今の私には、今年の彼と会話をする方法がわからない。たぶん、去年の彼による通訳が必要だ。
しかし、「ごめん」のあとに続いた言葉は、私の予想も期待も裏切った。
『その、映画? って、何?』
『えいがって読むの?』
は?
疑問符は音にならなかった。
それをかき消す爆音が外から響いて、そちら用の新しい「は?」を生産したからだ。
自室の窓を開けて、外を見回す。同じようにしている近所の人が何人かいて、私は彼らの視線の先を必死に探った。
程なくして、音の元凶が家の向かい側にあるアパートかららしい、ということがわかった。
いろんな色が耳に届く中で、ふと、違和感のある声が響いた。聞きなれた声であるような、暗闇の中で遭遇した不審者でもあるような、そんな。
「……あれ?」
思わず手元のスマホを見る。
「なんで私、藤倉くんと、」
藤倉くんは、もと同じクラスで、上のきょうだいがいる同士で、名前に似たようなコンプレックスがあって。それから、それから?
──願い、聞き届けたり。
頭の中で、誰でもない声がした。
(つづく)
第六話担当 前条透
次回の更新は9月20日です!
「記事を保存」を押していただくと、より続きが楽しめます!
ぜひよろしくお願いします!
過去のリレー小説
▼2022年「そして誰もいなくならなかった」
▼2021年「すべてはIMOになる」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
