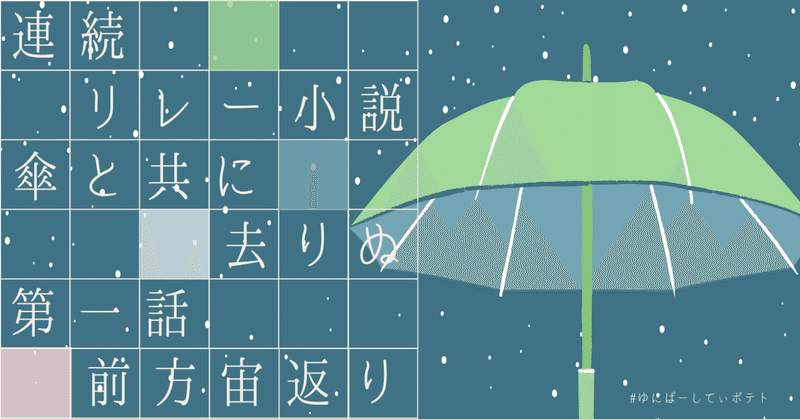
【小説】傘と共に去りぬ 第1話 前方宙返り【毎月20日更新!】
2月/持田一花
「つめたっ」
うなじになにかが当たって、首をすくめる。
顔を上げると、天使が降りてきたみたいに降っていた。白くて、ふわふわしていて、世界がたちまちスローモーションになったみたいだった。
冷たさに驚いたことなんてすっかり忘れて、手でお皿を作る。待っているだけで収まるそれは、わたしの熱ですぐに溶けて、不格好な水になった。今年はじめて見る幻想的な景色に、わたしは人並みに感動していた。
でも、立ち止まっている場合じゃない。
学校の帰り道。部活で温まった身体を、わたしは本屋さんへ持っていく。どうしても手に入れたい本がある。今日はその発売日。
駅前の交差点を抜けて信号が変わるのを待っていると、お姉ちゃんのおさがりでもらった黒いコートに白が積もる。手で払っても、しばらくすると元に戻ってしまうから、わたしは諦めてポケットに手を入れた。目の前を大きなトラックが通り過ぎると、威勢よく空気が渦巻くのがわかる。
目当ての本が手に入った。
お金を払うと、バッグのファスナーを開けて本をしまう。妹とおそろいで付けている、とあるアニメキャラクターのキーホルダーが揺れた。チェーンの部分が絡まると、すぐに背中を向けてしまうから、わたしはときより解いて元に戻してあげる。
店員さんの健気な「ありがとうございましたー」から、外の景色に意識が移る。
さっきまでかわいらしい天気だったはずなのに、いつの間にか牙をむいていた。猫が虎になったみたいだ。
玄関マットの上から身動きが取れなかった。自動ドアが開くと、獰猛な風がスカートの裾を押しつける。朝練に遅刻しないようにと慌てた朝のわたしは、天気予報を見る余裕なんてなかった。ママも、なにも言ってくれなかった。こんなに降るなんて聞いてない。
「は? めっちゃ降ってんじゃん」とわたしを追い越した男の子が言う。男の子は体を丸めながら、横殴りの風を切るようにして勇敢に走る。さすが男の子だなぁ、と彼との間に途方もない距離を感じつつ、しばらく本屋に残ることにした。エアコンの暖かい風が、わたしに居場所をくれる。十分も経てば、止んでくれるよね? そう願いながら、わたしは来週に控えるバレンタインデーに向けて、友チョコの作り方を勉強する。
足がむくんできた気がして、棚に本を戻す。
思っていたよりも長居しちゃったと思いながら窓の外を見ると、景色はなにひとつ変わっていなかった。そろそろ家に帰らないと、ママに心配をかけてしまう。でも、深みを増した空のせいで、出るのが怖い。でも、このまま動かないわけにもいかない。
深刻な寒さを前にすると、決意もろとも飛ばされてしまいそうだった。店先に出るのが精一杯だった。
どうしようもないことはわかってる。たかが吹雪。我慢すればいいだけの話。
わたしはきっと、ほかの男の子たちから言わせれば、悩まなくても良いことでずっと悩んでる、もどかしい女だ。それを笑ってくれる家族も友達もいるから、今まで面倒な扱いをされずに生きてきたけれど、ひとりになると足元がおぼつかなくなるくらい心細い。
周りの人はたくましく傘を構えている。ヒールを履いた大人の女性だって、吹き飛ばされそうになりながらも必死にこらえて、着実に足を動かしている。すごいな。なんでそんなに、強いんだろう。なんでこんなに、わたしは弱いのだろう。
「傘、持ってないの?」
お気に入りのマフラーと首周りを密着させながら、ただじっとたたずんでいるわたしに、声をかけてくれる人がいた。彼の目は前髪で隠れていて、表情がわからない。
あまりにも突然のことに、わたしは返事ができなかった。喉がまだ、話せる状態になっていない。あたふたと、適切な言葉を探していると、彼はわたしの返事を待たずに、「これ使っていいよ。俺、そこのバスに乗るから」と言って、店先から夜へ、勢いよく飛び出ていった。背中の大きな人だった。
「えっ、あ、あのっ」
呼び止めようとしたけど、わたしの声は重たい風にかき消されてしまった。
彼はポケットに手を入れたまま、バス停に向かって走る。バスに乗り込むと、空気の抜ける音とともに扉が閉まった。わたしはそれをただ見ていることしかできなかった。
手元にはビニール傘だけが残った。コンビニとかに売っている、どこにでもあるタイプの傘だ。でもよく見てみると、持ち手の部分に星形のアクリルチャームがついている。丸い青色だった。わたしはそれを、彼の優しさを表す色のような気がして、愛おしく思えた。
渡されたビニール傘を使って良いものなのか、どんな顔して傘を広げていいのか、わたしにはわからなかった。でも使わないのはもっと悪いような気がした。名前も知らないわたしに渡した勇気を想像して、わたしはストッパーを押す。
夜空に透明な幕がかかる。街の明かりがにじんで、わたしを生きやすくさせた。
***
気温がそこまで下がらなかったせいか、積もることはなかった。
新鮮な陽の光に当てられ、世界がいつもよりちょっぴり輝いて見える。わたしは、昨晩の奇跡をまだ引きずっていた。彼に会って、お礼を言いたい。思い返してみれば、彼は制服を着ていた。どこの学校かはわからないけど、遠い存在ではない気がする。
天気予報では降水確率0パーセントって言ってたけど、いつ彼に会えるかわからないから、いつでも返せるように傘を持ち歩こうと決めた。ちょうど、画用紙を入れるための筒が妹の部屋にあったから、わたしはそれを借りることにした。付属のひもをたすきがけして背負うと、星のチャームが揺れた。
「お姉ちゃん。それ恥ずかしいから止めなよ」
家を出るや否や、冷たい視線が背中を刺す。
「だって、いつ会えるかわかんないでしょ」
「夢見すぎじゃない? それに『あの時のわたしです』って言ったとしても、わたしなら引いちゃうかな。鶴の恩返じゃあるまいし、ちょっと怖い」「嘘っ、お姉ちゃん怖い?」
「怖いっていうか、それを普通と思ってる感性ヤバいよ。鏡見てごらん。武士みたいだよ」
「武士!?」
妹のヤバい人認定されるわたしって……。
背中を丸めながら、わたしたちは地下鉄の入口へ向かう。定期券を改札にかざし、いつもの電車を待つ。
指摘されてはじめて、傘を背負っていることが恥ずかしくなってきた。電車のドアが開いた時、すでに乗っている人たちの視線がわたしたちに集まるような気がした。傘は見えていないかもしれないけど、なにか良くないことを思われているんじゃないかって想像して、怖くなる。
周りの邪魔にならないように、傘が入った筒をおろす。確かに、ビニール傘をこうやって持ち歩く人は見たことない。持ってくるんじゃなかった。今日一日、これを持ち歩いて生活することを思うと、確かに恥ずかしくなった。
落ち込んでいるわたしに、妹が声をかける。
「お姉ちゃんって、恋とかしたことないもんね」
「こここっ!?」
動揺するわたしを、妹は冷静にあしらう。そういえば妹は、男友達を家に招いてたことあったっけ。同じ遺伝子を持ってるはずなのに、なんでもこうも違うのだろうか。
「わざわざ持ち歩かなくても、わたしだったらこうやってスマホで写真撮って、待ち受けにでもしとくかな」
そう言いながら、チャームの形がわかる角度を探して写真に収める。慣れた手つきでスマホを触っていたかと思えば、わたしのスマホに写真を送ってくれていた。「貸して」と妹が手を伸ばす。誰にも教えていないはずのパスワードをなぜか打ち込み、待ち受け画面を変えた。そのスピード感たるや、恐ろしくなる。
「わぁ、すごい。これなら毎日持っていかなくても済むね!」
「えっ、今日だけのつもりじゃなかったんだ……」
ぼそっとなにか言われたような気がしたが、電車の揺れる音とアナウンスの声で聞き取れなかった。待ち受け画面に目を落とす。時計部分とチャームの位置が考え尽くされていることにわたしは感動した。
妹からしてみると、わたしが見えている世界より、何十倍も高い解像度で世界が見えているのだろう。
ドア付近の壁にもたれかかる。電車の中って案外暗い。照明の明るさもあるけど、スマホを眺めてる人や本を読んでいる人、肩を縮ませながら目をつむる人とかもいて、それぞれの視野が内面に向いているのがわかる。みんな、現実を見たくないんだ。
「そんなにカッコ良かったの?」
妹が尋ねてくる。嫌味はこもってなくて、とてもシンプルな口調だった。
「いや、顔は全然見れてなくて……。わかってる、おかしいよね。ただ、傘を貸してくれただけの知らない男の子を追いかけて。お姉ちゃんバカみたいだよね」
視線を落とし、壁に立てかけた傘を見る。
たぶん、世の中の女の子たちが感じる、好き、ってものとは違う。
中学高校と、わたしの人生には記憶に残るような出来事がなかった。退屈とはまた違うけど、このままで良いのかなって、漠然とした焦りがあって、変わらない毎日に疑問を抱くようになった。不満ってほどでもない。正直、わたしはわたしの気持ちが、まだわかっていない。
でも、あの時、知らない男の子から傘をもらって、ちょっとだけ、自分が物語の主人公になれたような気がして、楽しかったんだ。このまま傘を持っていれば、さらに楽しいことが待っているような気がしちゃったんだ。この気持ちを大切にしたい。元の高校生活に後戻りなんて嫌だ。うまくいく自信はないけど、もがいてみたい。
「わたしは良いと思うよ」
妹が言う。まるでその声以外の音がすべてなくなったみたいに、わたしの内側で響いた。
「本当に?」
背中を押されても、やっぱり怖かった。どうしても、彼女の言葉を疑ってしまう。
「いつもお家でだらだらとYouTube見てるだけのお姉ちゃんが、なにか夢中になってるの、新鮮だなーって思ってたんだ。女子高生なら、これくらいは健全なんじゃないかな」
「そっか、そうだよね。ありがとう。なんか勇気もらっちゃった」
「出会えると良いね」
わたしは無邪気にうなずいた。
人の波に押されながら、電車を降りる。地元の高校だったら、今この瞬間も近くにいるかもしれない。わたしは記憶と照らし合わせながら、あの人がいないか探した。妹も、「身長何センチくらいなの?」と聞いて、一緒に探してくれた。なにかが動き出す、この瞬間が楽しくて仕方がない。
改札が視界に入って、上着のポケットを叩く。定期券を取り出そうと、指を入れると、不思議な違和感がった。なんだか、手が軽いような——。
「あぁ! 傘、置いてきちゃった!」
「えっ!? もしかして電車の中? えっ、でも、学校遅刻しちゃうよ。ほら行かなきゃ」
せっかく、前向きになれたのに。この場でうずくまって泣き出したかったけど、わたしは 妹に腕を掴まれながら改札をくぐった。
「ほら、写真残ってるし、大丈夫だよ。帰りに忘れ物なかったか聞こうね」
励ましの声は耳を通らなかった。なんで忘れちゃったんだろう。大事にするつもりだったのに。傘を持っていた感覚がまだ体に染みついている。湧き出る後悔が、いつまでもわたしの胸を絞めつけた。
(つづく)
第一話担当 飛由ユウヒ
次回の更新は3月20日です!
「記事を保存」を押していただくと、より続きが楽しめます!
ぜひよろしくお願いします!
第2話はこちら▼
過去のリレー小説
▼2022年「そして誰もいなくならなかった」
▼2021年「すべてがIMOになる」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
