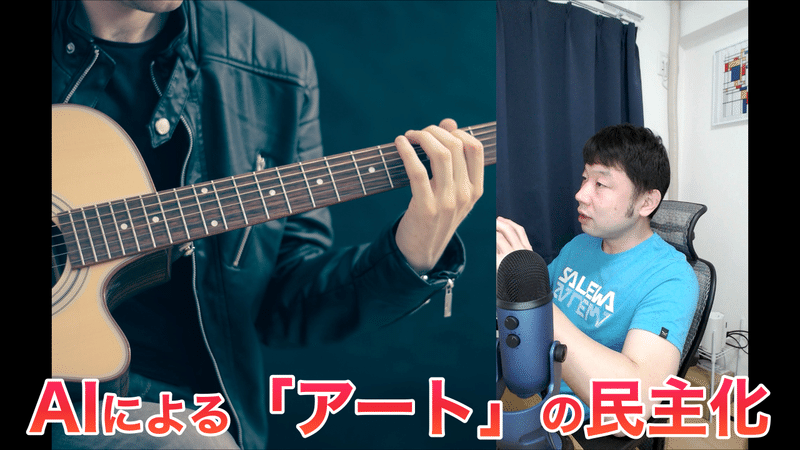【News! AIRS-Lab #027】今週のAIトピック「熟練の職人に代わるAI」、明日3/28のライブ講義など
今回は、明日3/28のライブ講義、今週のAIトピック、Udemyコースの一部無料公開などについてお知らせします。
なお、この配信のバックナンバーは、noteの方で公開しています。
https://note.com/yuky_az/m/m36799465e0f4
【Streamlitの様々な機能】
明日3/28(月)の21時から、ライブ講義「【Streamlit+Colab】人工知能Webアプリを手軽に公開しよう!」 Section2が始まります。
【Streamlit+Colab】人工知能Webアプリを手軽に公開しよう! Section2 【Live! AIRS-Lab #85】 https://youtu.be/jIke-oqXF5Y

「人工知能Webアプリを手軽に公開しよう!」は、人工知能、機械学習Webアプリを手軽に公開する方法を学ぶ講座です。
Google Colaboratory環境で、「Streamlit」を使ったWebアプリを作成します。
Streamlitとは、WebアプリをPythonのみで手軽に公開できるフレームワークです。
Pandas の DataFrame や、 plotlyなどの描画ライブラリで作成したグラフを埋め込むことができて、データ分析結果を簡単に表示することができます。
アプリを公開するコストが大きく抑えられるため、人気が急上昇中です。
本講座では、このようなStreamlitの基本的な扱い方を学んだ上で、様々なWebアプリを公開します。
人工知能、機械学習の成果を、Webアプリとして公開できるようになりましょう。
【コミュニティ「自由研究室 AIRS-Lab」】
「AI」をテーマに交流し、創造するWeb上のコミュニティ「自由研究室 AIRS-Lab」を開設しました。
メンバーにはUdemy新コースの無料提供、毎月のイベントへの参加、動画の先行公開、Slackコミュニティへの参加などの特典があります。
https://www.airs-lab.jp/
活動報告: https://note.com/yuky_az/m/me9b21d94f4e7
【News! AIRS-Lab】
AIの話題、講義動画、Udemyコース割引などの、AIRS-Labの最新コンテンツを配信する無料のメルマガです。
メルマガ登録: https://www.airs-lab.jp/newsletter
バックナンバー: https://note.com/yuky_az/m/m36799465e0f4
【今週のAIトピック: 「熟練の職人に代わるAI」など】
MITのチーターロボット、4足歩行なのに凄いスピードで走ります。
https://youtu.be/-BqNl3AtPVw
このようなロボット、今はまだ高価ですがやがて量産されることで値段は落ち着くのでしょうか。
とりあえず思いつく応用はバイク便の代わりですが、そうなれば街中をこのようなロボットが走り回ることになりますね。
書類などの振動に強い物体の搬送には適してそうですが、食品は振動に弱いのでUber Eatsの代わりにはならなそうです。
AIを使った翻訳機「ポケトーク」がウクライナから日本への避難民に配布されるとのこと。
https://ai-start-lab.com/news/388
ウクライナ語にも対応しているようです。
こういったAIの平和利用はどんどん盛り上げていくべきかと。
日本の宗教「神道」が「オンライン布教」により世界中で少しずつ信者を増やしているとのこと。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1398f336f3c7726c0e7ec740497ffa33ed10f483
仏教は発祥の地インドよりも中国や朝鮮、日本で発展しましたが、同じように神道も日本以外で発展することがあるかもしれません。
寿司も海外でカリフォルニアロールなどの発展形が生まれてますね。
日本の大半の神社ではインターネットを使った宗教活動はタブーとされているが、「アメリカ椿大神社」や「アメリカ出世稲荷神社」など、海外の神社では独自のオンラインコミュニティが形成されている。これらの神社では、神事や祭典をライブ配信し、行事予定を発信し、SNSでも活発に活動している。また、アメリカ出世稲荷神社は、「ペイトリオン」のようなクラウドファンディングサイトで資金調達の方法を模索している。
この辺り、保守的な日本の神社よりも海外の方がテクノロジーの活用に積極的なようです。
八百万の神といいますが、やがてコンピュータのプログラムにも神が宿ると考えるようになるのでしょうか。
そうであれば、高度な判断を行う「神としてのAI」は、意外と神道と相性がいいのかもしれません。
Unityによる技術デモ「Enemies」。
https://news.denfaminicogamer.jp/news/220321m
高度な「血流や髪のシミュレーション」を採用し、「顔の産毛」、「シワ」などが表現された、リアルタイムCGのデモンストレーションとなる。
肌や髪の毛の質感、表情など本物にしか見えません。
自然現象のシミュレーションというディープフェイクとは異なる方向性で、リアルな映像が作れてしまうのですね。
現実世界の人をコピーした場合、本物と見分けがつかなくなるのではないでしょうか。
AIとデザイナーが共同で製作した器の展示会が開催されるとのこと。
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000029.000050375&g=prt
造形には3Dプリンターを使うようです。
新たな「陶芸」の形なのでしょうか。
陶芸をやってみたいけれど土を扱うのが苦手な人は、こういった形で陶芸に関わることも可能になるのかもしれません。
やはり、AIはアートを民主化するようです。
5億5000万年前の、地球最古の左右相称動物かもしれない化石が発掘されたとのこと。
https://gigazine.net/news/20200324-oldest-bilaterian-ikaria-wariootia/
これまでの研究で、エディアカラ紀(約6億2000万年前~約5億4200万年前)には左右相称動物が登場していたと考えられていましたが、説の根拠となる化石は生物の作った穴の痕跡しか見つかっておらず、エディアカラ紀の左右相称動物そのものの化石が見つかったのは今回が初めてだとのこと。
我々の先祖は、このイモムシのようなシンプルな生き物なのでしょうか。
どのような神経系をもち、どのようなメカニズムで学習が行われていたのか気になりますが、おそら化石がそれを教えてくれることはないのでしょう。
神経系の起源について、クラゲなどが持つ散在神経系から考察しています。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikakuseiriseika/33/3/33_116/_article/-char/ja/
最もシンプルな神経系は、どのようなメカニズムで動作するのでしょうか。
その結果,現在,「発達程度は低いとしても,刺胞動物の散在神経系は,神経系の要素の全てを持ち合わせている」と考えている。この点は,中枢神経系に関しても同様ではないかと予想している。
クラゲの段階で、我々の神経系が持っている本質的な要素は全て備えているとのことです。
果たして、この段階で「意識」の原型のようなものは持っているのでしょうか。
最もシンプルな知性は、どのようにして実装されているのかが気になります。
強化学習による化学プラントの制御、35日間の自律制御に成功したとのこと。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/12500/?n_cid=nbpnxt_twbn
強い安全性が求められる分野に強化学習を適用できたのは、かなりの進歩なのではないでしょうか。
これまで熟練の職人技が必要であった分野に、AIが進出した一つの例かと思います。
ちょっと前までAI業界の人から「強化学習は使い物にならない」との話をよく聞きましたが、その潮流が変わりつつあることを感じます。
難病で運動機能を失い、「脳に閉じめこめられた」男性が家族とのコミュニケーションに成功したとのこと。
https://nazology.net/archives/106697
脳に合計128本の電極をインプラントしたようです。
するとジョンは1分間に1文字というペースながらも、文字を選択できるようになりました。
そして最初につづった単語は、研究チームのリーダーであるNiels Birbaumer氏に対しての「ありがとう」でした。
しかしながら、脳の電極を差し込んだ箇所に問題が生じたとのこと。
ジョンの言葉が途絶えた原因として研究者たちは電極が刺さっている脳部位が瘢痕(傷跡)化しており、神経信号が微弱になっていることをあげています。
脳に電極を打ち込む実験にとって瘢痕化は最大の問題の1つであり、現状では避ける手段は限られています。
生体と電極のインターフェイスが、やはり大きな問題として残っているようです。
AIは膨大な電力を消費しますが、近年各国でエネルギー不足が深刻になりつつあります。
https://president.jp/articles/-/55620
そこで、オイルを生産する「藻類」が、新たなエネルギー源として注目を集めているようです。
まだ研究段階ですが、下水処理の下水からオイルの生産が可能になったとのこと。
深さ1.4メートルのタンクでも増殖が可能になったようで、これまでよりもずっと狭い面積での生産ができるようになったようです。
次の課題は、バイオ原油回収のようで、汚水や細胞の器官が混ざった液からどうやって低いコストで精製するかが難しい課題に見えます。
果たして、研究と商用化の間に横たわる「死の谷」を藻類は乗り越えることができるのでしょうか。
【コースの一部無料公開について】
Udemyコース「【Streamlit+Colab】人工知能Webアプリを手軽に公開しよう!」は、4月半ばに公開予定です。
このコースの動画の一部は、YouTube上で無料公開されています。
【Section1: Streamlitの概要】【Streamlit+Colab】人工知能Webアプリを手軽に公開しよう! -Udemyコースを一部無料公開- : https://youtu.be/QGZ-qqHtnQ4
【AIと遊ぼう!AIRS-Lab】
もう一つのYouTubeチャンネル、「AIと遊ぼう!AIRS-Lab」の動画はコミュニティ「自由研究室 AIRS-Lab」内で先行公開しています。
一般公開は2週間後です。
「歌声」を作るAIとアートの民主化【AIと遊ぼう! AIRS-Lab #074】: https://youtu.be/E6y3vRaQ6uQ
【書籍】
Udemyコース「AIパーフェクトマスター講座」が書籍になりました。
新刊「Google Colaboratoryで学ぶ!あたらしい人工知能技術の教科書」(翔泳社)は9/8に書店に並びました。
Google Colaboratoryを使って、CNN、RNN、生成モデル、強化学習、転移学習などの人工知能技術を一通り学ぶ本です。
また、他のUdmeyコースの書籍化の企画が既に始まっています。どうぞご期待ください。
今後も、皆様にとって有益なコンテンツを提供していけたらと思います。
ご意見、ご感想、コースのご要望などがありましたら、ぜひお聞かせください。
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!