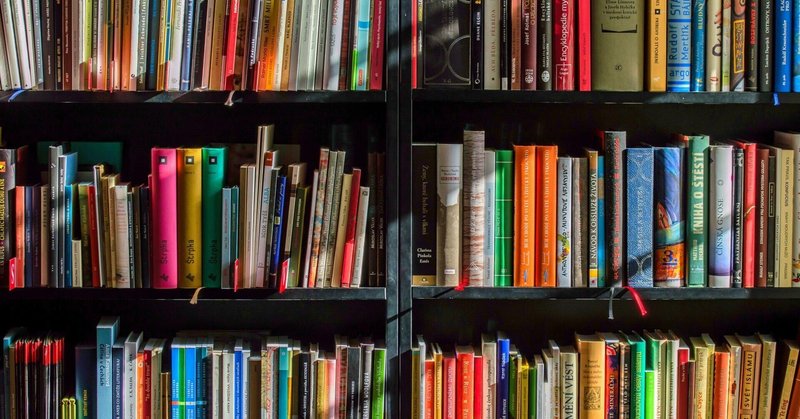
臨床心理士なるみの『ブリーフセラピーびいき』第1回
世話人をしている「認定心理士パワーアップファクトリー(通称PUF)」のHPにて、スタッフブログの連載を始めたので、こちらでもコピペで掲載します。
ブリーフセラピストである私が、なにゆえそこまでブリーフセラピーに惚れ込んでいるのかをしっかり書いて、そのことによってブリーフセラピーの魅力を広く皆様にお届けしていこう。そんな思いから、始めました。どうぞおつきあいください。
希望、失望、疑問
現在自分が臨床心理士として活動しているのは、セカンドキャリアである。最初の大学卒業後は、広告業界で言葉を産出するコピーライターという仕事をしていたのだが、思うところあって、30歳を過ぎて臨床心理学科の3年次に編入した。その大学は基礎を重要視しており、臨床心理学だけでなく基礎心理学の科目をみっちりと履修し、実験計画・実験・レポートを繰り返し行う基礎演習にあけくれた。2年間、とてもハードで濃密な学びだった。その後、東京にあった米国学校法人の社会人大学院に入ったものの、修了まであと1年というところまできて伝統的な心理療法への不信感と疑問に圧倒され、「臨床心理学を学んだことは失敗だったのではないか」と考えるようになってしまった。
当時の環境では、精神分析的な心理療法を軸とした折衷的な個人カウンセリングの訓練を受けていた。ここで教えられることの根本には「今現在の問題の原因には、過去の心的外傷の体験がある。」という前提があり、学びが深まるほどに自分の中で、認知的不協和が鳴り響いた。当時の自分の理解で言うと、カウンセリングの専門家としてやっていくには、あらゆる人間に共通する心的外傷の影響と精神病理を知り尽くした客観者でいなければならない。あらゆる事例で、心的外傷の影響や精神病理をアセスメントできないといけない。そしてその上でクライエントに共感して寄り添えていなければならない。かなりざっくりまとめると、このゲームはこんなルールだった。しかし自分はそんなことは不可能だと思ったし、そもそも「学術的専門知識を持つ合理的な治療者が、専門知識がなく不合理なクライエントを治療する」という土台が、どうしても受け入れられなかった。はたしてそれは本当に対人援助といえるのか?と。

湧き出でる疑問は、とどまるところを知らなかった。学術的専門知識が治療者の客観的立場を保証するものと言えるのだろうか? 専門知識によって一人の人間の心的構造なるものを理解できるものなのだろうか? その心的構造というのも一つの観念に過ぎないのではないか? 本当に専門知識が悩み苦しみの解決に役立つのか? そもそも心理療法は解決を目指しているのか? クライエント自身の経験と認識よりも専門家の観念的な認識の方が常に客観的であると言えるのはなぜなのか? 臨床心理学者は神の位置を目指すのか? こういった疑問が次から次へと浮かんできて、増えることはあっても解消して減ることはなかった。その他、ロジャーズの来談者中心療法、パールズのゲシュタルト療法、ベックの認知療法などの個人療法の概要を聞いても、その時はもう、どれも腑に落ちることがなく、焦りばかりが募った。
家族療法との出会い
そんなもやもやした気分でいたある時、何かのきっかけで家族療法を知った。これまで学んできたものとはまったく異なる論理に、強い関心を持った。すぐに書店に行き、家族療法の歴史や諸学派の概要が俯瞰された一冊の厚い本を買った。とても興味深かったのは、家族療法というものが、精神分析による個人治療の限界を乗り越えようとして生まれたものであったということだった。自分が疑問に思うようなことはすでに先人たちが疑問に答えを与え、家族療法という、その先の新たな心理療法を生んでくれていたのだった。心からありがたいと思った。
当時の自分がもっとも強烈に食いついた点は、家族療法が、クライエントの病理だとか、過去の心的外傷体験だとか、成育環境といったことを理論の中心に据えていないこと。そして家族療法でいう専門家とは、全知全能の客観者ではなく、クライエントと共に治療システムの内側から、クライエントと協働して具体的問題の解決に当たる存在だったこと。家族療法家とは、問題解決の専門家であって、クライエントの心や経験の専門家ではない。どれもが、まさに自分が求めていた臨床活動の土台となるものだった。

希望、失望から、再び希望へ
読書で家族療法を概観したあと、諸学派を学ぼうと何冊かの本を買った。そのうちの1冊が、コミュニケーション学派、あるいはMRIグループといわれるブリーフセラピー(短期療法)についての著書で、日本でブリーフセラピーを実践しつつ研究されている先生方の本だった。この本は未だに読み返して学んでいる。当時はとても難しく感じて、何の話をされているのかもよく分からなかった。それでもクライエントを専門知識で切り刻むことなく、心からエンパワメントし、落語のような展開で事態を改善するセラピーだということははっきりわかった。一読してそれまで抱いていた臨床心理学への疑念、疑問からはスカッとさわやかに解放された。失望と絶望の道のりに、希望の光が差し込んだ瞬間だった。
次回に続く
今週末以下のイベントを開催します。よかったらぜひご参加ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
