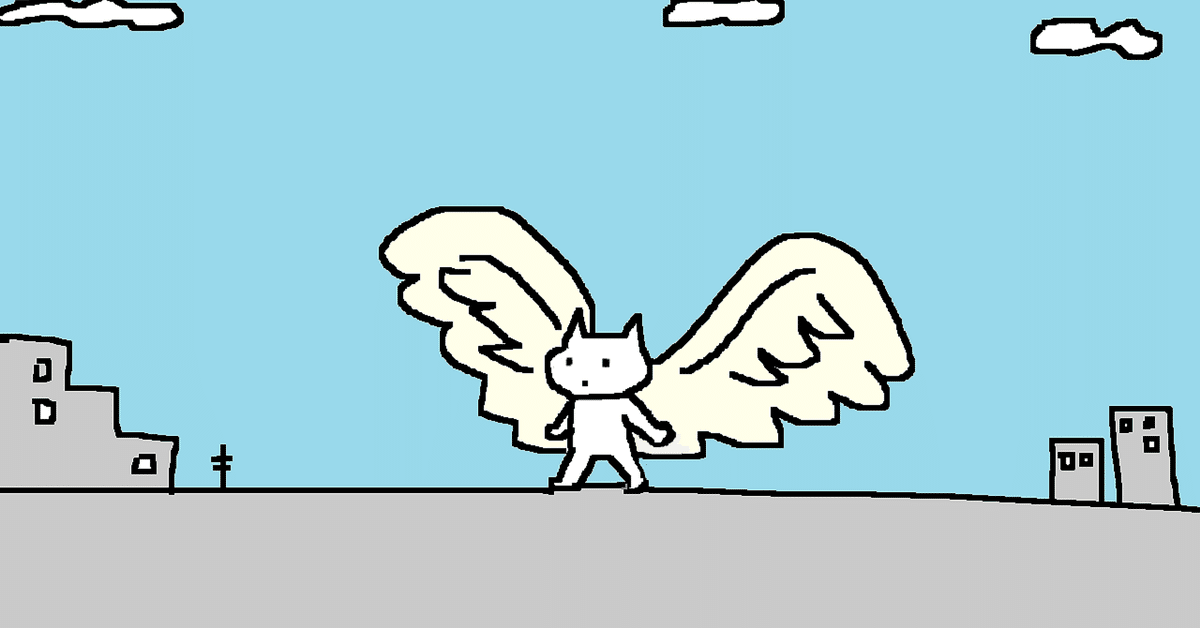
八百万の神 〜環境問題を考える時
八百万の神 (やおよろずのかみ)
環境系の仕事をするようになりセミナーなどでよく聞くようになった言葉。古代からの日本人の思想の土台となるものだ。
世界で多くみられる一神教とは異なり、自然のすべてのものに神が宿っているという考え方、自分もそのような感覚がある。
数多くの神,すべての神のこと。類似の語に八十神(やそがみ),八十万神(やそよろずのかみ),千万神(ちよろずのかみ)がある。森羅万象に神の発現を認める古代日本の神観念を表す言葉。
「私は無宗教なんですよね〜」
小さい頃から僕も当然のようにそんな感じでよく話したりしてきた。
でも、グローバルでこのような発言をすると、場合によっては人間性を疑われ、一目置かれることはないと、京都のお寺のご住職からお話を伺った。
一神教の国と異なり、日本ではきちんと教育を受けていないこともあって宗教観がないひとが多いと感じる。そういう僕もそのひとり。
でも、近所の氏神様や、いろんな願掛けの時に決まって行く神社やお寺、実家にある仏様には、いつも神様が宿っていると信じているところもある。
こういう感覚が、”無宗教”ではなくて”八百万の神”の信仰なんだろう。
一神教とついになる多神教という言葉も少し掘り下げて調べてみる。
やはり日本の八百万の神は、同じ多神教でも少し考え方が異なるようだ。
一神教が砂漠の宗教であるのに対して多神教は農耕社会に多くみられ,配偶神や親子神のように地上的・現世的な性格を多分にもっている。日本の記紀神話にあらわれる八百万神(やおよろずのかみ)の世界も多神教の一種であるが,その神々は古代ギリシアの宗教やインドのヒンドゥー教における多神教とは異なって,肉体的な特徴や個性をもたず,目にみえない存在であった。また日本の神話には世界を創造する造化の神や自然神が登場するが,その多くは祖先神(または氏神)であって,山や森などのある特定の場所に鎮(しず)まり,個性や機能を強くは主張しない存在とされてきた。
日本は昔、「自然」という言葉すらなかったという話も聞いた。
里地里山のような環境には神様が宿っていて、それを敬い感謝して、環境と一体となって共生していた。
「自然」と対立して支配しようとする考え方はなかったんだろう。
切り拓いた自然を、また人間の手で作り直そうとしても、それはハリボテで不完全なものしかできない。
環境問題を考える時、自然と人間が二元論的に捉えられているように感じる。
八百万の神の思想を持つ日本人の、もともと里地里山で自然と一体となり暮らしてきたストーリーを回帰することで、自然に対して優しくなれたり、一体感を取り戻せたりできないだろうか?と考え続けている。
エシカルというカタカナ言葉、これも日本語じゃないから、人間だけが一元論的に倫理的になっただけのように感じる。それだけだと、なにかが足りない気がする。
善行や徳を積むということ。
それを意識せずに無意識に行動できること。
それを自分の欲を満たすためにやっていないこと。
神様は自分のなかにもいて、バチがあたることもあるし、運がまわってくることもあるんだと思う。
所詮人間が考えていることは虚構なもので、自然と一体としてある生命として、循環しているのが原理なんだと感じる。
自然を人間と別のものとして認識している時点で、環境破壊は止まらないのだと思う。
日本人らしいやさしい考え方で、これからも環境問題を考えてゆきたい。
©️2023 Mahalopine
この記事が参加している募集
記事執筆のための、いろいろな本の購入費用として活用させていただきます!
