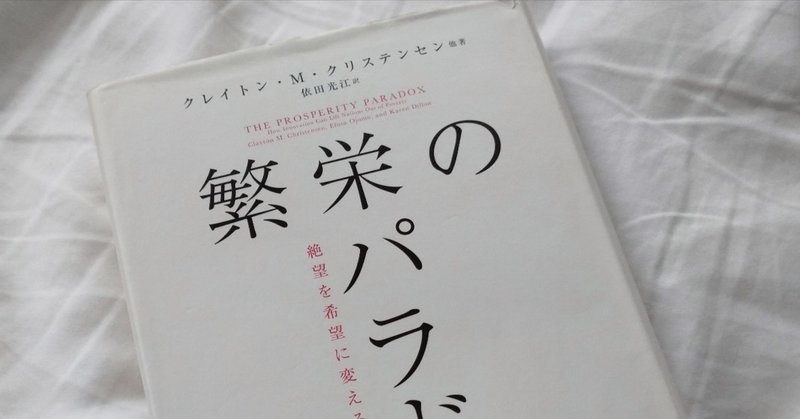
『繁栄のパラドクス』を読んで
おっ!ジョブ理論の人の本がある!
先月読んだビジネス書のレビューです。書店で何かないかなと物色していたら、クレイトン・M・クリステンセン先生の本が!
ジョブ理論は有名なのでご存知な方も多いとおもいますが、これは有名なのかなぁ。
タイトルが難しそうですがストーリーが多かったので、さらっと読みやすい内容でした。
また、ジョブ理論など読んでいない方でも、要所要所でポイントを踏まえて引用されているので、わかりやすいかなと思います。
日本企業のかっこいいイノベーションの話も多く出てきますが、やはり鉄板ネタのソニーやらトヨタやらの話。
こうやって読書している私のような現役リーマンの世代は、まさにパラドクスなのでしょうね。
いつもながら、Evernoteの雑なメモを振り返りながら、レビューしていきたいと思います。
繁栄のパラドクス クレイトン・M・クリステンセン 他著 依田光江訳
絶望を希望に変えるイノベーションの経済学
THE PROSPERITY PARADOX
How Innovation Can Lift Nations Our of Poverty

イベーションの種類、インベンションとサービスの持続型イノベーション
イノベーションの種類
接続型、効率化、市場創造型の3つに分類。
過去に存在していなかったまったく新しいものを生み出す発明 インベンション
サービスの持続型イノベーション/効率化イノベーション
最初の方から、もう核論的な話が出てきますが、この本は一貫して市場創造型で、継続性のあるイノベーションについて、具体的なストーリーを交え、綴っています。
イノベーションとインベンションを混同している!的な書籍やコラムも多いですが、改めて継続的に国力にもつながるような"イノベーション"とは何かを考えさせられます。
自分たちもICT業界でよくイノベーション創出だ、のようなプレゼンをよく聞いたり、場合によっては自分でも言っちゃったりしている訳ですが、何でもかんでもいいんだということではないということですね。
無消費、それの原因となるバリアや成約
無消費というキーワード、さらにジョブ理論をベースに思考を重ねています。
イノベーション系は、参照されてる本などもう少し古い書籍も読んでいかないと理解が深まらないなと思いました。
"バリアを特定する"
スコット・アンソニー『イノベーションの解 実践編』
無消費の原因となりうるバリアや制約。主に、スキル、資産、アクセス、時間がある。
無消費という聞きなれない言葉。でもすごくキーワードだなと思いました。どうしても私たちは既存のマーケットに目が向いてしまい、「マネタイズができない!」とか「競合他社にこれじゃ勝てない!」みたいなトークを普段してしまいます。一般の経済学者や投資家視点になってしまうんでしょうね。それも悪いことではないと思いますが、本当に持続性のあるイノベーションを考えるベースは、無消費を発見し、その原因(ニーズ・シーズはあるのにできていない理由)を深く考察する必要がある、そのことが如何にできていないかを痛感します。
"ジョブ理論"
人は満足のいかない方法でジョブを解決するプロダクト/サービスを「雇用」するよりは、それなしで、つまり無消費者ままでやり過ごしがち。
"無関心と競争する"
「現在の習慣」顧客をきつく縛っている。知った悪魔のほうが、知らない何かよりは耐えられる気がする。
"人には、損失回避という心理性向がある。"
「損をしたくない」気持ちのほうが、「得をしたい」気持ちよりも2倍強い。
1979年、カーネマンとエイモス・トベルスキーが明らかにした。新しい解決策を雇用するときに感じる不安も強力。
無消費者の彼らが本当に片づけたいと思っているジョブのレンズを通して見ることが、何を売るかだけでなく、どうやって売るかについて考え直すきっかけとなった。
「さあ、保険を買おうと思って、朝目覚める人はいない。」
出ました!本家ジョブ理論!!
やはり、原点の考えかたというか、ここでいう"ジョブのレンズ"を通して見ることが本当に大切です。基本中の基本なのですが、人間の特性上、慣れや習慣にほぼ雁字搦めになってしまっていることを、まずは自分が理解した上で、ここに書かれているように"無関心と競争する"ことが大切。
そのためには、自分自身が逆の発想でこれらの重力的な思想から逃れないといけないなと思いました。自分の人生経験も、振り返って見ると「損失回避」ばかり考えているように思います。

プッシュ戦略とプル戦略
大量の資源をプッシュして痛みを取り除こうとするが、改善したかどうかわかりやすい痛みの途去ばかり気を取られ、病気そのものを治しているのではないということ。
様々な世界の事例のストーリーが紹介されています。ワールドカップの例として、南アフリカの2010年の話がありましたが、交通機関や通信やスタジアムの整備に投じた予算 = 31.2億ドルで10%しか回収できずに終わった・・・という話で、FIFAが南アフリカに遺した悪き産物・・・と語り草になったようです。
スタジアムは2010年以降少なくとも3200万ドルの維持費用がかかっていて、市の財政を圧迫。それも、熱烈なサッカーファンの非白人の住居エリアからは遠い・・・。このような"プッシュ戦略"の事例を見れば見るほど、現在、日本のオリンピックも、1年延期となり(開催されるのかどうかも怪しい状況もありますが)その後の持続的なストーリーはどの程度具体的な戦略があるのかを徹底的に考える必要はあるのだと思いました。
プル戦略が、他の戦略に比べて、持続可能な繁栄の起点となる効果が遥かに高い理由。
① 日常の消費者の不便や苦痛に、市場の具体的なニーズに応えようとする現場のイノベーターによって始められることが多い。
② 現場把握や調査を重視したアプローチを採る。イノベーターは現場で学び、持続可能な方法で難題を解決しようとする。
③ まず市場を創造することに、あるいは市場のニーズを見極めることに集中する。そのあとで、市場の存続に必要な資源を引き入れていく。
何かを動かそうとする強い熱意から出現する。
ここで述べられている通り、プル型の戦略にはベースとなる消費者の不便や苦痛のような広く(場合によっては見えていない)ニーズがあり、それらにジョブ理論を持って、解決していく小さな活動の積み上げが、プル戦略の根幹であり、それが連鎖的・持続的になった結果が持続可能な繁栄であり、逆に起点を考えるとプルしかないのではないかと理解できました。
あとはそれを考える強い熱意は大切ですね。そのような閃きが来たら動かないと!ダメですね。まだ来てない・・・うーん(汗)
アメリカを変えたイノベーション物語、日本や韓国も。一方で効率化イノベーションは?
コダック 未来を撮る
現代人は2分ごとに、150年前に存在した写真の合計枚数以上の写真を撮っている。
ソニー 市場創造マシン
無消費をターゲットとして新たな市場を創出。
メキシコ
効率化イノベーション。アウトソーシングなども具体的な例。
既存の資源や新たに獲得した資産をできるだけ効率的に消費しようとする。プロダクト販売は消費経済。限られたパイ。
ロシアも、原油、石油精製商品の輸出に依存。
原油価格の変動がロシア経済に大きく影響を与える。
障壁を乗り越える〜膨大な無消費の存在する経済では、インフラや制度面の欠如が否めない。
問題を解決しない方法
他国で機能しているシステムにどのくらい似せられたかで測ろうとしがち。
制度は文化に追随する。
文化とは、共通の目的に向かって協働する方法であって、人々が他の方法で物事をおこなおうとは考えもしないほど非常に頻繁に、かつ非常に首尾よく踏襲されてきたものである。
ひとたび文化が形成されると、人は成功するために必要なことを自律的に行うようになる。
「共有学習」を通じて生まれる産物。
もとの構想がいかに善意に基づいていても、地域の多くの人に恩恵が届くような市場を創造するか、そうした市場と結びつけることができなければ、構想を持続させることは難しい。
馬のまえに荷車をつないだところで、荷車も馬も動かない。
無消費層に目をつけたイノベーションによるビジネスは、ベースとなる基盤インフラは無いわけで、それを先進国から無理やりコピーしたり、有識者がいくら議論したところで失敗するケースが多いというストーリーです。
インフラや制度。これが「共通学習」によって、それぞれの歴史のようなものを経て、時間をかけて民族の中で醸成されるものだと理解しました。それこそ人間の暗黙知の結晶なんだと思います。
私見ですが、世界の中でも日本人は、ダントツでハイコンテキストな文化があるから、他国から見て特殊な国なんだろうなと思います。でも、私も含め、北米やヨーロッパ諸国のもの(文化)はかっこいいと思っちゃいます。
そういう意味では、文化の輸入については順応性は高いのかもしれません。
ただ、カタカナのようなコトバを作ったことも一つかもしれませんが、グローバルで英語圏の市場は一つになっている中で、失われた20年的にイノベーションの鎖国状態な気はします。日本の経済発展の中でのインフラや制度で、世界にアピールできるような仕組みは多いかと考えます。それらの文化自体をサービスとして展開していきたいものです。
3つの教訓
制度の構築及び維持には、市場を創造するイノベーションが先行する。
制度は地域の状況を踏まえて構築する必要があるということ。
イノベーションは空中分解せずに機能していく接着剤の役割を果たす。

繁栄のパラドクスから繁栄のプロセスへ 〜市場創造型イノベーション
プロセスの力
インドのナラナヤ・ヘルス病院
デビ・プラサド・シェティ医師
「世界の貧しい人を1日1ドル未満で治したい」という夢。
ヘンリーフォード「働いて入れば誰でも買える大衆車をつくりたい」
歴史の偉人から学ぶ、シンプルなプロセスの源流となるストーリー。
うちの会社のような大企業になると、このような創業の起点となるストーリーって薄れてしまいます。
というか、NTTみたいな元公務員的な企業こそ、この手の心を動かされる人のビジョン・ストーリーが必要なんだと思いますが。ある意味、孫さんのソフトバンクや、楽天の三木谷さんはあるのかもですがw
受け売りになってしまいますが、以前、会社のマネージャー研修を外部講師で受講した際に、課題図書で『シンギュラリティ大学が教える飛躍する方法』という本を読んで、MTP(Massive Transformative Purpose)を意識するようになりました。
事業というものは、そのストーリーに共感した人たちの集合体が企業であるべきです。まさに繁栄に繋がることも同じだと思いました。
(参考)サリム・イスマイル氏の著書『シンギュラリティ大学が教える飛躍する方法』
市場創造型イノベーションの5つの原則
市場創造型イノベーションは、私たちの抱える深刻な問題を解決に導き、その過程で、貧困に苦しむ多くの国々の経済に成長の火を熾す(おこす)
雇用を生み、インフラや制度を引き入れ、将来の成長の強力な基盤となり、触媒として作用する力がある。イノベーションとは社会が成長するプロセスそのもの。新しいレンズで見る。
1. どの国にもすばらしい成長の可能性がある。
2. すでに市場に存在するプロダクトのほとんどは、入手しやすくすることで、新しい成長市場を創造する可能性がある。
3. 市場創造型イノベーションはたんなるプロダクト/サービスではない。
4. プッシュではなくプルを重視する。
5. 無消費をターゲットにすれば、規模の拡大に費用がかからない。
未来の可能性に視野を広げ、イノベーションとは、社会が成長するプロセスそのもの、ほんとその通りですね。新しいレンズという表現が、自分にもしっくり来ました。自分はコンタクトレンズですが(笑)たまには違う眼鏡でもかけて視点をと視座を意識して変えていかないといけないと思いました。とにかく小さいことから実行なのですが、その際にレンズを切り替えることを忘れちゃいけないという自戒です。
繁栄のパラドクスへの解決策
ライト兄弟
当時有望とされていた、天文学者・物理学者で発明家であったサミュエル・ピアポント・ラングレーだった。
当時の研究費は5万ドル(現在価値で140万ドル)
ライト兄弟が実験に費やしたのは、およそ1000ドルだけだった。
1903年 ラングレーの二度目で最後の挑戦のわずか9日後、有人動力飛行を成功させた。
ライト兄弟にそんなストーリーがあったとは、知りませんでした。奇跡の成功ではあったのだと思いますが、そのチャレンジの経験が良いレンズと通して継続していたことがポイントなんだと思いました。
最後に注釈こそなかったですが、学生・経営者に重要な資質は、良い質問をできる能力だとの記載が目に止まりました。
よい質問をできる能力。
なぜこの方法を採るのか?
私たちが信じていることをなぜ信じるのか?
物事をちがうふうに考えてみたらどうなるか?
私たちの使命は何か、それはなぜか?
なぜ私たちはこの問題にかかわっているのか?
なぜ私たちはこの方法で開発をおこなうのか?
私自身は、まだまだ未熟で自己主張が激しく、質問も受けないくらい余裕がないのですが、少しでもよい質問ができるように上記の6つは自問していきたいなと思いました。

日本語版解説も共感できました。
最後の最後、日本語版解説ですが、読み応えありました!クリステンセンさんのインタビューも日本について語ってくれており、頑張らないと!と思わされます。
短期的に合理的な意思決定は、長期的な成功に結びつくとは限らない。
「イノベーションのジレンマ」で、優良企業が合理的な判断を行うがゆえに「破壊」されるというパラドキシカルなメカニズムを解明している。
「破壊的」イノベーションは市場を拡大させる。市場全体が拡大し、雇用を生み、経済全体を押し上げる効果。
グローバルな雇用は危険を孕んでいる。
市場がないことはチャンスである。
やりくりをしているところにジョブがある。無消費者。安価で身近な解決策を待っている。
製品であればサービスであれ、解決策を押し付け(プッシュ)ても機能しない。
この本にあるポイントを抑えた上で、私たち日本の現役リーマンも頭をフル回転させて、繁栄のパラドクスに挑み、繁栄のプロセスを掴みたいものです。
ついつい、相手の置かれた環境を理解せずに足りないものを指摘し、良かれと思った解決策を押し付けてしまう傾向にある。自戒の念を込めて、注意したい。「市場創造型のイノベーションに投資することは、取りも直さず国づくりに加担しているー」
私たちが繁栄を続けるための当たり前のプロセスとして定着していく・・・
ポスト・コロナ時代となり、この手の書籍がより一層身にしみる今日この頃。
日頃のビジネスにおいても、雑駁にこなすだけでなく、深く思考をして持続性のあるビジネスを、小さいことから生み出していきたいと思いました。
©️Mahalopine
記事執筆のための、いろいろな本の購入費用として活用させていただきます!
