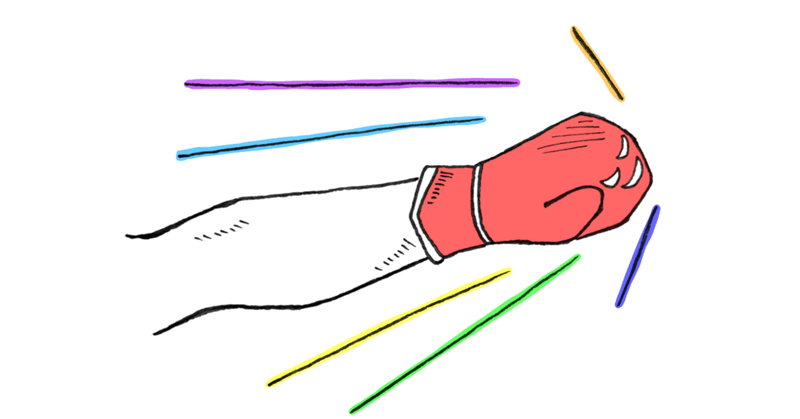
"多様性"という言葉の暴力。
”多様性”という言葉は、非常に便利な言葉だ。
この言葉を使うだけで、「私はどんな人にも理解を示し、差別しません。」と言った心構えを示せる。いわゆる”いい人”に簡単になれる。
しかし、「”多様性”ってそんなに簡単なものではないよな。」、「”多様性”という言葉を安易に使いすぎているのではないか?」そんな思いが私の心にはずっと残っている。
それもそのはず、私自身がこれまでずっと”多様性”という言葉を安易に使ってきた人間だからだ。
私は大学時代、卒業制作のテーマに「多様性」を選んだ。
理由としては、現代のトレンドとマッチしていて、先生方からの評価を得やすかったためだ。
私自身がLGBTQでもなければ、周りにLGBTQであることをカミングアウトしている友達がいるわけでもない。ただただ、自分自身の評価のために私は「多様性」というテーマを使ってしまった。
そして、今日までずっと安易に多様性という言葉を使い続けてきたことを後悔してきた。
話しは少し変わるが、最近『正欲』という小説を読んだ。
去年、映画化もされたこの作品は、まさに「多様性」がテーマである。
しかし、この作品では、LGBTQなどの多様性のど真ん中にあたる人に焦点を当てるのではなく、多様性の時代でさえもすり落ちてしまう更なるマイノリティーが中心となって描かれている。
この小説を読んで私は、やはり一人の人間が全てを理解できるほど”多様性”と言う言葉は、簡単なものではないと感じた。また、多様性という言葉が、誰かを傷つけたり、落胆させたりすることに繋がる場合があることも理解した。
人間の素晴らしいところは、想像力によって相手を思いやることができる点だが、私があなたでない以上、全てを理解することはできない。
”多様性”という言葉はどうも「私はあなたがマイノリティーであれ、あなたの”全て”を受け入れますよ」と言ったニュアンスがあるように思う。
そうではなく、「このラーメン美味しいね」や「そのアニメ私も好きなんだ」など、お互い分かり合える一部を探す方が大切なのではなかろうか?
おしまい。
P.S なんだか難しく重い内容になってしまったため、次のnoteではもっと気楽にくだらないテーマで書きます!(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
