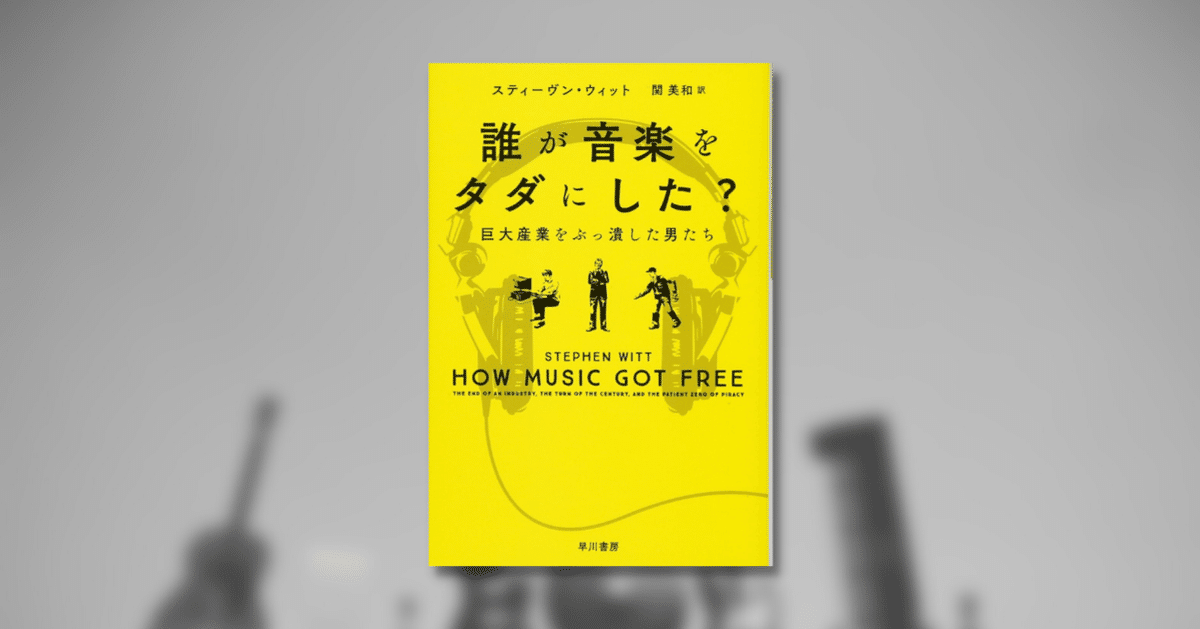
【読書感想】アメリカの音楽業界の激動を描いたノンフィクション
こんにちは、Yukiです。
今回ご紹介する本は、スティーブン・ウィットの『誰が音楽をタダにした?──巨大産業をぶっ潰した男たち』です。
本の内容
ここ20年で音楽を取り巻く環境は、劇的に変化しました。一昔前なら、音楽を聴きたい場合CDを購入して再生する必要がありました。ところが今では、わざわざCDを手に入れなくとも、ネットで購入すればダウンロードしてすぐに聴くことができます。他にも、定額制のストリーミング配信も行われています。
本書の主な舞台は、アメリカの音楽産業でその激動を、緻密な取材を元に迫っていきます。
始まりは1990年のMP3の開発です。MP3とは、「音響データを圧縮する技術の1つであり、それから作られる音声ファイルフォーマット」です。おそらく1度は聞いたことがあるでしょう。この技術を開発したのが、本書の主要人物の1人であるカールハインツ・ブランデンブルグです。
MP3はCDと同じ音質を保ったまま、少ないデータ容量で済ませられるという特徴があります。例えば、従来では3分のCDをデータ化したい場合、30MBの容量が必要でした。しかしMP3を使えば、3MBで済ませることできます。
これはつまり、CDと同じ品質を保ったまま複製できるということです。この技術の登場によって、アメリカの音楽産業は大きな変化を迫られました。端的に言えば、CDが売れなくなりました。本書によると、CDの売り上げはピーク時からずっと下がっていたそうです。それによって音楽業界は収入モデル、つまりビジネスモデルをシフトせざるを得ませんでした。こうしてできたのが、広告収入モデルです。
こうした大きな変化が、MP3開発者、音楽業界のエグゼクティブ、曲の海賊版を作成する人物達、海賊版を取り締まる捜査官という様々な視点から語られていきます。
音楽に関心がある人、1990年代から2000年代にかけて洋楽にはまっていた人、これから音楽業界に進もうと考えている人にオススメです。
読んだ感想
この本もあまりにも面白すぎて、一気読みしてしまいました。著者が長い時間をかけて、忍耐強くたくさんの人に緻密な取材をして、書き上げたということが、良く分かります。
例えば、本書の重要人物の1人にグローバーという人がいます。彼は、音楽の違法アップロード、すなわち海賊版の世界で最強の男です。著者が入手した海賊版ファイルのほとんどは、グローバーが出所だったといいます。ところが、彼は誰にも知られていません。それもそのはずで、彼はノースカロライナ州の西にあるシェルビーという田舎町に住んでおり、CD梱包工場で働く普通の人物だったからです。
世間的には、全くと言って良いほど知られていません。著者は、取材の行き詰まりの末に彼にたどり着きます。そしてそこから3年以上もの歳月をかけてグローバーとの間に信頼関係を築き、話を聞いたとのことです。
MP3の生みの親であるブランデンブルグや、音楽業界の大物なら話は分かります。なぜなら彼らはある程度知名度があり、少し調べたり人に尋ねればたどり着けることが予想できるからです。ところがグローバーの場合は違います。海賊版の世界では絶大な影響力を誇っていても、世間的にはただの一般人です。それも、テクノロジーや音楽とはかけはなれた町に住んでいます。
著者の一般人である彼を見つけ出すという執念、そこから3年もの時間を費やして信頼を勝ち取り、きちんと裏付けを行って取材をするという精確さと緻密さには脱帽です。こうしてできた本書は、話の展開がとてもスリリングで面白かったです。
僕は1999年に生まれたので、当時のことは当然よく知りません。遠く離れた大陸で、こんなにも大きな変化が起きていたとは思いもしませんでした。知らなかったことを知ることができたという意味でも、良書でした。
実は、以前の僕はあまりというかほとんどノンフィクション作品を読みませんでした。なぜなのか僕にも良く分かりません。しかし今回この本を読んだことで、ノンフィクション作品もたくさん読みたくなりました。
終りに
本書ではCDが隆盛を誇っていた時代から、CDが売れなくなる時代を描いています。しかし、当然ながら音楽の変化は現在進行形です。もしかしたら20年後には、全く想像もしなかった形に変化しているかも知れません。
未来を考えるという意味でも、過去を描いた本書からは学べることは多いのではないでしょうか。是非とも手に取って読んでみてください。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
読んでいただきありがとうございます! 他の記事も読んでいただけたり、コメントしてくださると嬉しいです
