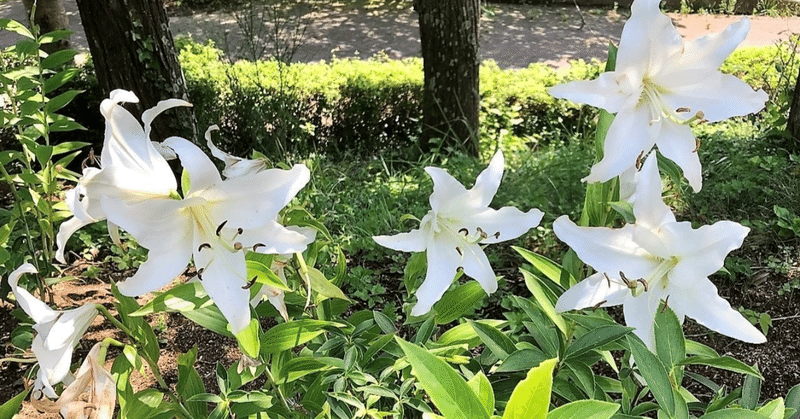
令和源氏物語 宇治の恋華 第百五話
第百五話 迷想(十五)
果たしてあれほど後の世もと誓った殿方の心持ちとは如何なるものか。
六の姫はさすが夕霧の大臣が自慢するだけあり、年若いながらも成熟した柔らかい物腰しの姫君でした。
少し垂れた目尻が愛らしく、笑うと花がこぼれるようです。
これで性格に難があれば、と願うばかりに惹かれ、やはり思うようにいかぬほど魅力的で鷹揚に構えていらっしゃる。
これほどの姫とはまいった。
匂宮は六の姫を前にして中君への愛などはすっかり忘れてしまっているのでした。
女人の愛はひとつであるのを強いられるのに男性はいくつもの愛を持っておられる。
それぞれの女人を前にするとその愛は別々のものだとか。
殿方の言い分はわたくし共女には理解いたしかねますが、匂宮が中君も六の姫も愛しているというのが真実というのならばそうなのでしょう。
平安時代の女人はこのように殿方の愛に縋るのみ。
男性の移ろう心は責められず、女人は生まれつき身分が下るものとして浮気な人は責められたのです。
匂宮は夜も明けぬ前に六条院を去りましたが、六の姫への愛の余韻に浸り、二条院へ戻ってもすぐに中君の元へは行きませんでした。
しばらく休んでから六の姫に後朝の文を差し上げる頃には陽が中天に近づく頃でした。
後朝の文をしたためるにも念入り紙を選び、筆を置いては物想うように目を閉じる姿を目の当たりにして、近くに仕える女房たちは対の上(中君)が不憫に思われてなりません。
「どうやら六の姫がお気に召したようだわね」
「ただでさえ権勢の強い姫君ですからねぇ。中君さまが気圧されなければよろしいのだけれど」
こちらに仕えている限り中君への寵愛が損なわれるのを辛く感じる者たちなのです。
宮は見慣れた二条院にあるとやはり中君が気になるもので、後朝の文の返事をこちらで待ってからあちらに渡ろうとは思うものの、婚礼とわかって空けた夜だけに気になって急いで北の対に渡られました。
ほんの少しばかりの思慮が足りないばかりに女人の心を傷つけることをこの宮はご存知ないのです。
中君は身重な上にふさぎ込んで気力もなく臥していられるのを宮は拗ねているのかと気楽に声をかけられる。しかし悪阻で物も食べられず青い顔をしている中君はそれに応えることもできません。
「いったいどうしたことでお加減が悪いのでしょうかね」
「わたくしはもともとこういう体質で時折加減が悪くなりますの。どうかご心配なさらずに」
そうかと言われてもまさか懐妊とはいまだ気付かぬ宮なのです。
身体が辛くて心も萎えた中君は宮の結婚について知らぬふりでいようと決めておりましたが、この時ばかりは涙がほろほろとこぼれ落ちてしまいました。
ひとたび涙がこぼれるとどうにも止まらなくとめどなく溢れるもので、中君はそれを見苦しいと思いつつも留めることはできないのです。
そんな姿を目の当たりにすると匂宮もこれほど愛しい人はおりはしないのに、と胸が痛むのでした。
「ああ、どうしたらあなたはその涙を留めてくれるのだろうか。私が心変わりをして六の姫を娶ったのではないということはわかってくれているね?」
「もちろんですわ。頭では理解しておりますけれども涙が勝手に出てくるのでございます」
そうして恥ずかしそうに目を伏せる姿がいじらしく、宮は中君を抱き寄せずにはいられません。
「これは口にするべきではないが、もしも皆が言うように私が御座に上るようなことがあるならば、その時には誰にも遠慮せずにあなたを一の妻としよう。こうしてこの二条院の女主人としたように」
口先ばかりの殿方の約束などはあてにはなりませんが、その約束が実現するか否かは置いておくとして、いつでも宮は本気でそれを語っているのです。
中君にはそれがわかるばかりに夫を恨むということができません。
なんとずるい御方か、そう思うにつけても涙は溢れてくるのでした。
「ともかく何か食べなくては身体ももたない。これ、中納言の君。果物などでは甘ったるくて食欲もわかぬ。粥を作り、鮑などをことさらに軟らかく煮て調理させなさい」
「かしこまりました」
そうしてなにくれと囁きかける宮は出会った時と変わらぬ接し方をするもので、昨晩の婚礼は夢ではなかったか、と落ち着きを取り戻す中君でしたが、やはり現実は辛いものです。
六条院から後朝の返事を持った使者がほろ酔い気分でこちらの対に現われたのです。
褒美に賜ったらしい色とりどりの装束を羽織り、肩に担いでの配慮の無い登場に匂宮は不快で鼻白みましたが、ここで下人を咎めたとて覆水は戻りません。持参した文を読まぬのも不自然ですので宮は何食わぬ顔で無造作に開きました。
こなれた手跡はどうやら六の姫の継母、今は一条の宮と呼ばれる方のものでしょうか。
女郎花しをれぞまさる朝露の
いかにおきける名残なるらむ
(女郎花=六の君が萎れておりますのは、あなたがつれなくなさったからでしょうか)
「なんと気の重くなることよ」
宮は深い溜息を吐くようにして開いた手紙を中君に見せました。
「これ以上私にどうしようというのだろうねぇ。今宵はもう行くのはやめようか」
そうしてにやりと悪戯っぽく笑うので中君もついつられて笑みをこぼしました。
やはりこの人は笑顔がもっとも似合っている、と宮はようやくいつもの妻に戻ったのでほっと胸を撫で下ろしました。
しかしながら宮はやはり左大臣への憚りがあるのか、六の姫への好色心が動くのか、日が暮れる頃に早々と六条院へと向かったのでした。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
