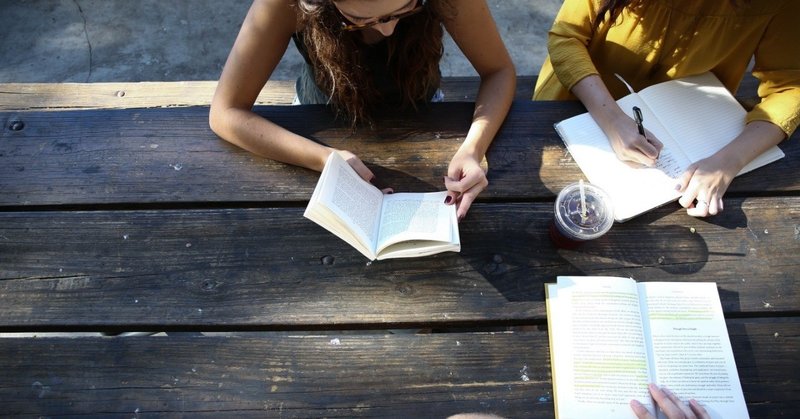
女の子が情報工学部に進むべきか否か
はじめに
先日、IT業界のジェンダーギャップを埋めるためのNPO活動をされているアイヴィーさやかさんにお会いし、私の情報工学出身の女性エンジニアとしての経験、業界で課題に思っていること等について私見を語らせていただきました。
その議論のあと、アイヴィーさんが呟かれたツイートについて、この業界のジェンダーギャップに関心がある方々にとっては一見「なぜ?」と思われるような内容だったかもしれません。
今日少なくとも分かったのは、女子中高生に情報工学部の大学に進路選択してもらうことが、gender gapをうめるKPIではないことだ
— アイヴィー👩💻IT業界のジェンダーギャップなんとかしたい (@ivy_sayaka) March 12, 2019
彼女がこの呟きにいたるまでには私からお話させていた色々な話題があったんですが、第三者がこのツイートだけを見ると疑問に思われるかなと感じたこと、また当日私の時間が十分取れなかったこともあり、彼女に自分の考えに至るエピソードを十分お伝えできなかったことがあるので、改めてどういう考えでもって私がこの話題を話したのかをまとめたいとこの記事を書いた次第です。
正確に問題定義すると
タイトルの文章は実のところ様々に解釈できる要素を含んでいて、そこが疑問の原因になるのかと思っています。
改めて私が当日話した話題を分解すると(下記以外にもあるけれど)
1.「(NPO団体が支援しているようなイベントなどで)アプリ制作を学んだ女の子達が情報工学の学科に行くべきかどうか」
という話と
2.「情報工学含む工学系学科全般のジェンダーギャップをそのままにしていいのか」
の、2点あります。
もちろん後者の2に対する私の答えは迷うことなくNO。放置すれば多種多様な問題が発生する(というか既に多々発生している)ので、是正に向けて取り組むべきだと思っています。
けど前者の1に対する回答として、あえて私は自身の経験を踏まえ「必ずしもアプリ制作を学んだ子どもたちの進路として情報工学学科が最適だとは限らない」と答えさせていただいた背景があるんです。
一つの分野のみ追い求める危険
大学入学以前から自主的にコンピュータを学ぶような子たちは、きっととてもこの分野に関心があるのだと思う。
けれど関心のある分野それ一つを追い求めるとなると、研究テーマを決める際や社会に出るときに苦労したり、パッとした成果を出せない危険もあったりするわけですね。
テクノロジーは結局のところツールです。ツールの使い方ばかり知っていても、その知識だけではツールで課題解決できることを見つけ出すことはできません。
なんとか見つけ出したとしても、今度は課題そのものの背景知識が足りなくて適切なアプローチが考え出せないこともあります。
ようは「技術的な知識ばかりあるが、現場を知らないエンジニア」になる危険性があるわけです。
また単純にツールとしてのコンピュータの知識を学ぶ場合、この業界は情報のトレンドが早く、かつMOOCSなどで豊富な教育コンテンツにアクセスできる場合も多いんですよ。
本当にそれぞれの子どもたちとって必要な知識が大学の情報工学へ進むことでしか効率よく学べないのか?と自身の経験を振り返ると、必ずしもそうとは言えないという気持ちがありまして。
それならば大学ではコンピュータ以外の、大学に行かないと学べないような知識が得られる別の学科に進み、ツールとしてのコンピュータの知識は独学で別途研鑽に努めたほうが、幅が広がるエンジニアになる可能性も高いという考え方もあるんじゃないかと思うわけです。
もちろん純然たるコンピュータのテクノロジーそのものに興味があるという場合は情報工学が最適だろうし、コンピュータ以外に関心ある分野のほうが大学に行かなくても知識を得られる環境にある、だから逆に大学では情報工学を専門で学ぶという戦略もあり、必ずしも情報工学学科不要論を主張したいわけではないです。
ただコンピュータに関心のある子どもたちなればこそ、視野が狭まらないためにも、他で必要な知識を入手できる場面が多いコンピュータの世界に関わりたいならば、あえて情報工学という選択を第一にするのはオススメしない、というお話をした次第です。
(そしてこの話は男女関係なく全ての子どもたちに対して言えることでもある)
一つの分野ばかり攻める危険性については、リクルート出身で小学校校長を勤める藤原和博氏という方が非常に分かりやすく述べられておられるので引用させていただこうと思います。元サイトの全インタビューも必見。
「日本で普通に仕事をするとき、(引用注:時給が)800円から8万円まで差がつくのはなぜなの?」
(略)
仕事というのも実は商品の値段と同じように、需要と供給の関係で決まるということを示してるわけなんです。そういう風に学校では教えないから、なかなかこれが理解されない。でも、実際には皆さんも需要がどんどん膨らむ分野で、かつ供給が少ない仕事に自分を振るということがすごく大事になります。
(略)
だから自分の希少性をいかに高めるか。
(略)
その希少性を100万分の1に高め、皆さんが一世代に自分1人しかいないという状態となるためにはどうしたらいいかという話をしたいと思います。これはすごく簡単な理屈です。3つのキャリアを掛け算して、いわば三角形をつくるような感じ。それで自分の希少性を高めましょう。
もちろん1つのキャリアだけで…、相撲でも体操でも会計でもいいですが、1つの仕事だけで100万分の1の希少性を確保する力がある人は、それでやったらいいと思います。ただ、それで勝負するのはかなり大変。99万999数人を倒さなきゃいけないし、さらに言えば、それで屍みたいな人も出ると思うんです。そのリスクが結構あります。
でも、皆さんは今まで積み上げてきたものを左足の軸としてベースにしつつ、もう1つぐらい何か積み上げてきたものがあればそれを右足の軸としてベースにする。そうして左右両足のベースをしっかり踏みしめながら、次にもう一発勝負をかけて三角形を大きくする。それによって自分の希少性を最大限まで高めることができる筈なんですよ。その三角形の大きさが…、のちほど「クレジット」という言い方をしますが、その面積が希少性の大きさになると理解してもいいです。
なお、私のような情報工学出身者が情報工学進学不要論的な話題を述べるのは、隣の芝生は青い理論になっている部分があるかもしれない。
逆の立場…非情報系・非理系出身のエンジニアの方々が「大学は情報系・理系を選択していればよかった」と仰っている場合もあり、それはそれで非常に根拠のある主張なので、子どもたちの進路選択の参考になるよう両論併記しておきます。
下記の方のツイートも本当にその通りかと思うので・・・。
エンジニアになるのに学歴は要らないという人がいるそうです。
— Yusuke Ando (@yando) February 27, 2019
Fラン私立の文系卒ですが、苦労しました。米国のビザでもヒヤヒヤしました。大学はまぁどこでもいいよしても、情報ないし理数の学部を出て少なくとも修士、出来れば博士まで進むのが良いと思います。
専門性は本当に重要です。
学歴が無くてもエンジニアになる事はできるでしょうが、選べる選択肢が狭められますし、よりより待遇を得るのも難しくなります。
— Yusuke Ando (@yando) February 28, 2019
専門的な学位を得るほうがより速くキャリアが向上できるはずです。学生の方は特に貴重な機会を活用してください。(自分は遠回りして悔やむ気持ちはあります)
アメリカの就業ビザを取る際には、就く予定の職業に相応しいだけの専門性を持っているかを判断する際に、持っている学位が非常に重要視されているそうな。
なので、文系出身だけれどエンジニアとして大活躍されているような人が、シリコンバレーの企業に挑戦しようとして無事に面接には受かったのに、学歴が原因でビザが取れず転職に失敗した…などという辛すぎる話も聞いたことがあります。
転職時の面接自体は、実力さえあれば学歴の壁は吹っ飛ばせるけれど、いかんせんビザの審査は企業側の判断とは別軸の社会的要因(移民政策等)で決まるので、早晩この事情がどうにか変わる可能性は低いです。
こういった事情や進展激しいMOOCSなどによる学習環境の変化、子どもたち自身の考える将来像を踏まえて、アプリ制作を学んだ子どもたちの進路はもっと多角的な選択肢から検討したほうがいい、というのが私の一見解です。
個人的な経験を言うと、私は小さい頃からコンピュータが大好きで大好きで、父の背中を見て勝手に趣味で自作パソコンを始めて弄りまくったり、コンピュータ系の記事を毎日読み漁ったり、高校生の頃には工業系の高校でもないのに基本情報技術者の勉強をみっちりやって資格を取ったりして、けっこうこの分野に関して自主的に勉強してそのまま地方国立の情報工学学科に進んだんですね。
そうすると、正直大学の授業では「このへんもう知ってるしなぁ・・・」と思うような場面も少なくなくてですね。
少なくない同級生がプログラミングの課題で四苦八苦するのを尻目に、自分はさくっと課題を任意回答問題も込みで提出して評価Sもらったりとかしてました。
いや、勿論大学に行ったからこそ学べるものはたくさんありましたよ。
大学レベルの数学とか統計学とか、実験の仕方とか実験レポートの書き方とか、研究の仕方とか論文の書き方とか。
これらの知識を身に着けたことで随分と世の中のモノの見え方が変わりましたし、もし人生をやり直すチャンスがあったとしても、これを学ぶために大学へ行くという選択肢は変えないと断言します。
ただ、それを学ぶためには情報工学である意味があった?と言われると、私の立ち位置的にはかなり微妙だったというか、少なくとも同じ理系で別の学科に行っていたほうが同じ大学に通う期間でも学べる学問の幅も広かったんじゃないか、というのが人生振り返った時に思うところだったりします。
そんなわけで、自分と同じく大学に行くより前からコンピュータやアプリ制作に興味を持つような子どもたちならばこそ、逆にがっつりコンピュータ系専門!みたいな学科に行くのは必ずしもそればかりが選択肢ではないかもしれないよ、というある先輩の話でした。
工学部のジェンダーギャップが危険な理由
一方、そもそもの問題として工学部(と、そのほかにも社会全般)の中に存在するジェンダーギャップを放置していいのかという観点で話すのならば、それはもうNoと断言します。
その理由は世間で多様性の重要さを述べる理屈とほぼ同じですが、あらためて工学部という観点で語るならば次の二つのように言えると思います。
1.競争力の低下
大学というのは学校側が工夫しない限り、非常に人材の多様性が著しく欠けてしまう場なんですね。
年齢は18から22にプラマイ数年する程度の範囲にだいたい収まるし、
教育には金がかかるので大学のレベルと家庭環境には一定の対比関係が発生するし、
実家の位置や帰省のコストを考えると遠くの大学には通い辛いから学生の出身地域は大学の周辺に偏るし、
学科の専門性が高まる以上同じようなことに興味を持ったもの同士になる。
そこに加えて更に性別まで偏っていたら、その集団は恐ろしいほどに似通った家庭環境と経験と嗜好を持つ集団になるんです。
つまりその集団では、皆が皆同じような視点で、同じようなやり方で問題のテーマを探し、同じような解決手法を用いて研究をすることになってしまう。
そういった集団から世の中を変えるような、常識を変えるようなイノベーションという結果は生まれ辛い。
大学がよくポリシーとかで掲げる「創造性を育む」とは真逆の状況ではないでしょうか。
結局のところ、それは大学の研究成果の質が下がり、ひいては大学の競争力低下に繋がります。
だからジェンダーギャップの解消およびそれ以上の多様性確保が大学には必要だ、というわけです。
このへんの話題は、大学を企業に、研究成果を製品の売り上げなどと言い換えたときに世間でよく言われる理屈と同じですね。
2.不適切な行動を行う危険性の増加
そしてもう一つの大きな理由は、多様性の欠如した集団は意思決定プロセスも歪むことです。
自分たちの内輪の中での常識が当たり前に正しいことだと勘違いしてしまう。
それがしばしば集団の中のマイノリティに対して不当な扱いを生み出したり、その集団の行動に世間の目が当てられたとき、その認証ズレからあまりにも不適切な言動をしていると見なされて非難の的に…ようは炎上に繋がったりするわけです。
多様性の低い集団が多様なアイデアは出せないように、多様性の低い集団がほかの集団にとって不適切とみなされない行動をできるかといえば、はっきり言って無理です。
人間の想像力は自身の経験に縛られる。世の中に色々な人々がいる以上、自分だけは他者の考えをなんでも把握できるなんて思い上がりにも等しい話で。
だから多様な人間が意見を交わせる場が必要なのです。
ただ女子を増やすだけでは活躍できない
大学を卒業してエンジニアの世界で働き出してからも、残念ながら多様性の欠如から来る意思決定プロセスが歪んだ行動だな、と思うようなことを目撃することが少なくないんです。
それは女性が職場に飛び込んだとき、マイノリティたる彼女らが理不尽な意思決定を押し付けられ、精神的に追い詰められ、活躍の可能性を狭め、最終的に離職という選択肢にすら繋がってしまう。
海外ではこのことを【パイプライン漏れ】と表現されているようです。
マイノリティたる女性側の人材供給自体を増やすのはもちろん大事なんですが、供給だけを増やしても上記のような、マジョリティが無自覚に生み出しているマイノリティへの障壁を解消しなければ、結局は供給した先から大量に離脱するだけに終わってしまうという危機感があるんですね。
それはつまり、障壁を無自覚に生み出しているマジョリティへ積極的な働きかけをしないと、マイノリティへの施策 - 例えば女の子たちにプログラミングを教えるだけでは効果は頭打ちになるのではないか、という危機感でもあります。
パイプラインへの水の供給を増やしても、パイプライン漏れを無くさなきゃ、水は途中でただ漏れして最後まで届かない - そんな状況なんだと思います。
こういった私自身の経験・考え方などなどをアイヴィーさんにお話し、彼女がこの業界のジェンダーギャップを埋める活動をするにあたり、必ずしも女の子たちに情報工学部を進路選択してもらうことをKPIにするのは適正ではないかもしれない、と私見を語ったのが最終的にあのツイートになったのかと思います。
なので、あのツイートに反応された方々の考えは、決して私の考えと相反するものではありません。
課題山積のジェンダーギャップ
当日お話していて改めて思ったのが、ジェンダーギャップの原因には実に多種多様なものがあって、どれも一筋縄ではいかないなぁ、ということだったりします。
それらはエンジニアの世界独特の理由から日本共通の問題、あるいは世界共通の問題であったり。
ここさえ解消すれば問題解決に効く!といった銀の弾丸は存在しない。
そんなわけだから、ジェンダーギャップを埋めるための活動のKPIをどのように決めるべきか、というのも大変難しい課題かと思います。
正直に言って、男に生まれてエンジニアになっていればこんなに苦労することはなかったのに、こんなにチャンスを逃すことはなかったのにと感じる場面は多々ありました。
けれども私の話がこの問題で苦労した話が、この難しい問題に取り組む際の参考になるのならば、女に生まれてエンジニアをやってて良かったと、ようやくそう考えられるのかな、と思ったのでした。
Photo by Alexis Brown on Unsplash
最後まで読んで頂きありがとうございます! いただいたサポートは記事を書く際の資料となる書籍や、現地調査に使うお金に使わせて頂きますm(_ _)m
