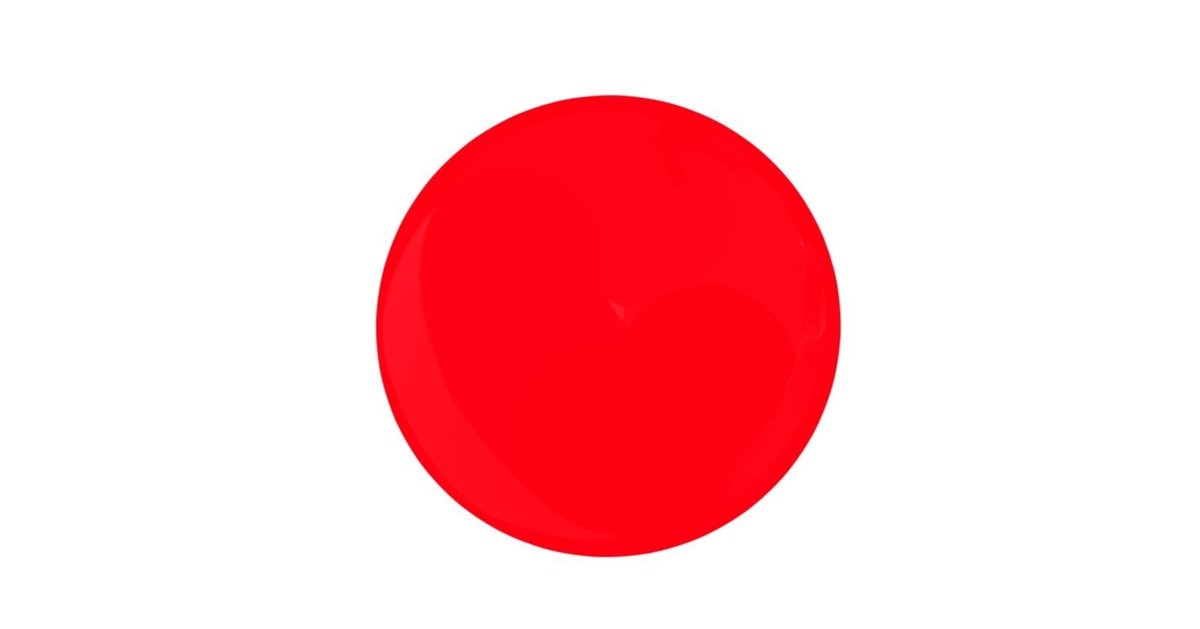
近代理念と宗教道徳 社会契約と親孝行 道徳の東西 中
近代理念と宗教道徳 社会契約と親孝行 道徳の東西
現代の国学
「やまとこころ」と近代理念の一致について
第二章 宗教とは何か? 啓蒙との本質的な違いについて
サッチャーという「女カルヴァン」は、南アフリカのアパルトヘイトに抗議すべきというエリザベス女王の提案を拒否したことがある。カルヴァン派の自己責任論とは、神に選ばれた白人に生まれていないことが自己責任であるという観念論であるのだから、これは当然のことだ。
こうした実績を考えると、ロバート・オーウェンの「空想的社会主義」よりもジョージ・オーウェルの「空想的全体主義」の方が、サッチャーの精神に近いものであった。オーウェンの社会主義は実体として空想的という程ではなかったが、彼の公平さは貴族的なイギリスの精神であった。その実において、「揺り籠から墓場まで」という文句の方が、本来のイギリス的な社会契約を表していると言える。
一方で、サッチャーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義への信仰」は、ルターやカルヴァンのような神官の空想でしかない。権威主義者達は自己が救われることだけを考えていて、他者を救うことを考えていないが、人間は人間を救えないという奴隷意思論と運命予定説が、この自己責任論を創り出したのだ。言論の不自由と福祉の削減を信仰するアメリカ人は、相互扶助よりも奴隷制度と人種差別を好んでいるという事実を、日本人は強く認識しておかなければならない。
ビスマルクの政策こそが現実的社会主義と評するべきものである。一方で、ロマン主義者のヒトラーの政策はユダヤ人に対して極大的な被害妄想を抱いていたことに起因しているのだから、空想的社会主義というよりも妄想的社会主義と呼ぶべきだ。ビスマルクは確かにマキャベリストであったが、ヒトラーのようなエゴイストとは完全に別物であった。
現代日本においては、社会が貧しくなるだけではなくて、助け合いが無くなったが故に、己が儲けることと現実逃避のための妄想しか考えない者が増え続けた。そうして人間関係が営利化したわけだが、実はそれらは全て宗教によって発生した現象であって、勤労カルヴィニズムにも儒教にも公共のためにという思想は一切において存在していない。
神官の自己責任論は、金持ちにならなければならないという脅迫観念であって、人助けをしないことへの信仰でもあり、金儲け以外に何も挑戦しない人間を大量に生み出すことになる。公共判断や法治権力について考えるのではなく、全てを権威主義と個人利益に還元することこそが勤労カルヴィニズムで道徳の正体であって、これは徹底的に民主主義に反している。
飢えた百人の敵を放置しておけばこちらに襲い掛かってくるだろうが、十人分のパンを投げれば彼等は内乱を起こして自滅する。選民思想を用いて分断工作を行ったサッチャーは、これをよく理解していたことは間違いがない。民衆が煽動されてお互いに叩き合いを始める姿を見ることは、彼女にとっては愉快なことかも知れないが、国家にとっては究極の不幸そのものだ。
神の見えざる手という人間による制御の否定は、政治の否定であってそれは問題解決の否定であり野放図への狂信しかない。これは公共の福祉に反し、民主主義に対する侮蔑であって、問題解決を行わないことへの信仰そのものだろう。
実は、この自己責任論においては、経済的な自立が唱えられようとも、精神的な権威への依存はどこまでも強まるという皮肉が存在している。そもそも、こうした自己責任論は法律における自力救済権を認めているわけではないのだから、これは人間の意思によって公平性やら法秩序を達成するという公共責任論の対極であって、つまりは野放図への信仰でしかない。そもそも、運命予定説とは究極の他力本願であるのだから、彼等は実際には責任意識など持っているはずがないのだ。
実体公平性に基づいて自己責任論を唱える資格を持つ者は、アルコール中毒の父親と薬物中毒の母親に虐待して育てられ、遺産もなく他者からの支援もなしに、公共判断を重んじた上で合法的に成功した人間だけであろう。そのような環境で成功できる程に知的な人間は客観性を有しているが故に自己責任論を唱えることがあるはずもないが、困窮した他人の心情と境遇を理解しようとしない者には政治が務まるわけがない。
自己責任とはトランプ前大統領のように他人のことを絶対に認めない人間が持つ観念であって、否定のための否定であり、自分を肯定するために他人を否定しなければ死んでしまう情けない病気である。単純に自己を認められず、実体を捉えられず、比較と権威主義でしか考えられないが故に、彼等は保身にだけ取り憑かれるのだ。
集団に迎合することを共感やら同情やらと呼ぶことがあったとしても、その共感と同情は他者のことを考える能力のことではなくて、「群れ意識」による「我の消滅」であり、単なる思考停止から生まれる集団同化に過ぎない。観察し、判断して、意見を出し、議論し合うことを求めずに、ただ群れるだけのことを望む心性は、民主主義社会を破壊する「自由からの逃走」そのものだ。とはいえ、政治による問題解決を求めさせずに、自己責任という名の他者と公共政治への無関心を妄信させていれば、権威の支配が安泰となることだけは確かである。
サッチャーには、「社会というものはない。あるのは個人としての男と女と家族だけだ」という発言も存在する。家族主義の彼女は、カルヴァン派である以上に儒教徒であったのかも知れないが、イギリス的な精神と無縁であったことは確かだ。
儒教や勤労カルヴィニズムが唱える愛国心という言葉は、「不自由・不平等・偏愛」を意味する民主主義を破壊する民族主義であって、国家権力の行使によってどのように社会契約を守るかを考える精神ではない。国民を貧乏に追い込むことで思考力を減らし、それに合わせて権威主義宗教を流布させれば、支持率を得ることなど簡単なことなのだ。
これらの宗教においては、問題解決は放棄されていて、神が解決するやら、問題がそのままであることが天意であるとされている。個々人が分断された社会は、最終的に全体主義に行き着くとハンナ・アーレントが述べた話であるが、アジア的専制もナチスも上命下服の中央集権の一党独裁であって、国民の個々人の双方向的な連携によって政治権力を創り出す国家主義とは最も遠い。こうした社会をして、「いじめと政治と宗教の三位一体」とでも言うべきだろう。
現代の拝金教は、他者への不信と観念的なヴァーチャリズムによる実体生産力への無関心が、金への絶対的な信用という個人利益主義に具現化されたものだ。人間関係が金で売買されるようになったせいで恐ろしいまでに希薄化したが、これも金という権威に対する奴隷意思論の実現として尊ばれることである。だが、金による結びつきしかない社会は、ただただ無様で哀れだ。
不況とそれを対処しない政府が悪いのではなくて、自らが安定した企業に入れないのが悪い、実体産業力に関わらないマネーゲームで儲けられないことが悪いなどというのであらば、公共権力を否定しているに過ぎない。こうした思考は、公平性と権威の区分を混ぜこぜにして公平性を完全に否定するという保身であるが、「万人の万人に対する闘争」が激化した最後にはそこら中が燃え上がり、水や安全どころか酸素さえも蓄財した金では買えなくなるという状態に帰結する。文明というものは人間の尽力によってはじめて成立するものであって、正義を失えば全てが崩壊し、何もかもを失うだけだ。
とはいえ、自らが救われることだけを考えていて、他者を救うことは何も考えていないゲルマン民族が、この事実に気付いていないのは必然のことでしかないだろう。彼等は、金を蓄積することによって自らが選民であると証明したいだけで、社会的目的とは無縁なのだ。マルクスの階級闘争史観は他の世界では成立するものではないだろうが、人間的探究精神や統治者に必要な資質とは無縁なゲルマン民族からすれば、当然の認識であるのかも知れない。ロマン主義によって己の妄想に浸るだけの連中には公共性などあるはずもなく、公平性を無視した自己満足的な選民思想を好むことも必然のことだ。民族主義というものも、公共性を否定する個人利益主義を民族集団に拡大しただけのものに過ぎない。
少し考えてみれば自明のことでしかないのだが、階級の問題に関わらず、権威主義者が権力を握れば社会は最低の状態に陥ることが必然である。そして、ゲルマン民族は権威主義者だらけである上に政教一致を好むが故に、適切な統治状態がいつまでたっても成立しないわけだ。権威と服従、不公平と信仰、支配と被支配以外の関係性を許さないのがゲルマン的世界観である。野蛮の本質とは愚かさと権威主義であって、餓鬼畜生道は反知性によって下らない諍いによって時間と資源を無駄にすることの繰り返すものなのだ。
他者を失敗させることを信仰し、反知性と偏愛こそを道徳として崇める狂信者達は、差別するための非白人さえ居れば満足であって、公共の破壊による内乱こそが聖書の予言のハルマゲドンであるとして狂喜し、狂信の内に死んでいくことであろう。己のことしか考えられない彼等は、社会的な問題解決を放棄しても、他者を抑圧することが出来ればそれで満足なのだから。
他者と協力し合わないと死ぬということは、宗教的な題目であるというよりも、必要性に基づいた事実である。責任転嫁によって他人を犠牲にし続けて保身することは、美が伴わない以上に社会の破滅に終わって保身すらも出来ず、何よりも危険なことなのだ。蓄財した財産を持ってアメリカに逃げようとも、白人でない貴方は迫害されるだけに終わる。アメリカの白人を妄信し、アメリカの白人であるかのように振舞うことを信仰しているのかも知れないが、貴方はどこまでも白人ではない。日本という国家について関心を持たない限り、最終的に貴方を含む日本の全員が困ることになる。
もっと言ってしまうならば、勤労カルヴィニズムは思考停止した労働を信仰しているのだから、この宗教の偏愛道徳というものは文化的知性に対して徹底的に不寛容であって、それらは徹底的に破壊されることになる。儒教や勤労カルヴィニズムの個人利益主義によって、社会から出世や金儲け以外を考える人間が消滅することは、必然の帰結でしかない。
儒教であっても勤労カルヴィニズムであってもナチズムであっても、徹底した唯心論の偏重と教典原理主義を備えていて、これらは徹底的に現実実体を規格化するイデオロギーなのだ。これらは実体の多様性を否定して、権威主義序列に置き換えるだけのものであって、彼等は自己正当化にだけ興味を持ち、実体世界には徹底的に無関心である。
このような宗教権威は、人間を戒律で束縛することと、教義によって人間の観察する力を破壊することと、道徳によって人間の思考する力を抹殺することにしか興味がない。だが、言うまでもなくこれに反抗する者を殺害することにはそれ以上の関心を抱いている。
彼等は、思考停止して権威に服従して、前後不覚の夢遊病の内に労働する「意識弱い系」の人間以外を社会から消滅させることを望んでいる。公共に何かを残すことではなくて、自らが儲けられればいいといった個人利益主義は、文明を残さずに破壊的収奪を繰り返すこと以外が出来るわけもない。環境を破壊して公共が壊滅したとしても、儲けられるならばそれで良しという信仰は、イースター島のモアイ産業と何ら変わるところがない。
サッチャー首相は収奪的経済によってイギリスの経済を後退させたのが実績であって、実体経済力の強化による国力の向上よりも観念的なイメージ操作による民衆の扇動が彼女の得意分野であった。勤労カルヴィニズムはケインズ理論の対極であって、実体的な需要ではなくて観念的な勤労生産が経済を回すと考えられているのだからこれは当然のことだ。自分の経済的成功以外は全て他人事であるという自閉症的で無関心たる保身意識こそが、勤労カルヴィニズムにおける道徳であるのは、説明不要のことだろう。
実は、ロナルド・レーガン大統領は、軍拡という公共事業で軍事企業へのバラマキを行ったため、単なるサプライサイド経済学ではなく、ポリシーミックス政策を取っていたと言える。狙撃されても動じることが無かったロナルドは、前大統領のドナルドのような弱い男とは異なる「強いアメリカ」であったことは疑いようのない事実だろう。そして、アメリカは双子の赤字を出したが、ソ連を倒すことが出来たし、現時点においても財政赤字が原因で国家が崩壊しているというわけでもないのだ。
なんであれど、アメリカが本気で自国の民主主義を守るつもりならば、世界の民主主義を守る必要があるし、それにはレーガン大統領のような覚悟と強い決断力が必要となる。トランプ前大統領に分かることは個人利益主義が限界であって、彼は政治的理念を提示することが出来ないのだから、大衆迎合と権威主義的専制によって人々を弾圧することしか選択肢が無い。
実際に、彼は世界の民主主義を守るどころか、アメリカの民主主義を破壊することを選んだ。だが、政治とは個人利益ではなく、公共利益を選ぶためのものなのだから、国家の民主主義を守るためには世界の民主主義を守る必要があるし、そのためには個人利益を犠牲にしなければならないこともあるのだ。
この記事が参加している募集
私の記事が面白いと思ったならば、私の食事を豪華にしていただけませんか? 明日からの記事はもっと面白くなります!
