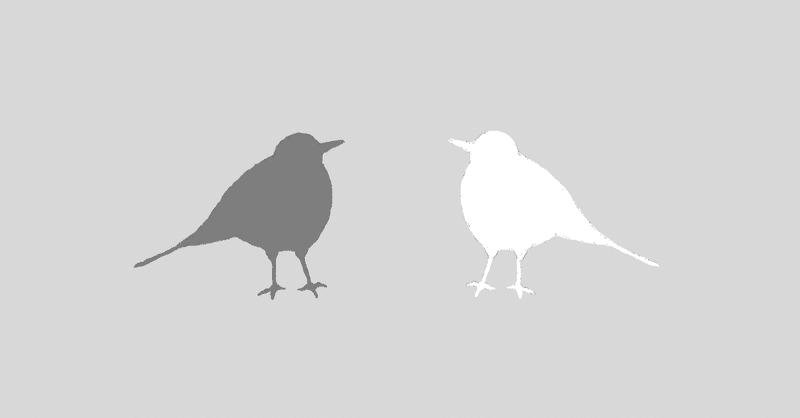
ゆめゆめ、きらり #1
気がつくと、みかこは川のほとりに立っていた。
広くもなく、狭くもなく、深そうであって、浅そうにも見えて、ただ静かに、そしてゆるやかに流れていくその川を見て、みかこはほうと息をこぼした。
空の光を反射して、揺れる水面がちらちら、てりてりと輝いている。
向こう岸にはうぐいす色の草むら。奥には深緑色の森が広がっていた。
それらは川をはさんだこちら側にもおんなじように存在していて、風が吹くたび、さらさら波打ち、ざわざわ揺れて、ちらちらてりてりした水の光と一緒くたになって、みかこが瞬きをするたびに表情を変えていく。
どうしてこんなところにいるんだろう、とか、ここはいったいどこなんだろう、とか、そんな疑問はひとつも浮かんでこなかった。
みかこはごくごく自然にそこに立ち、ごくごく自然に川を眺めているのである。そしてそれを、どこか遠くから見守っているもうひとりの自分があることも、とくに不思議には感じなかった。
ただ、傍観者の自分が、なんてきれいな夢だろう、と思っただけである。
そんなふうに、川のほとりにぼんやり佇んでいたみかこのもとに、ふたりのネコがあらわれた。
彼らは後ろ足で立ち、それを器用に動かして、肩を並べててくてく歩いてやってきた。
ひとりはシルクハットを頭に乗せ、片手にステッキを握り、まるで英国紳士のようなスマートな風貌だった。もうひとりは、土で汚れたオーバーオールにキャスケット帽をかぶった、太っちょのネコである。
対照的なふたりのネコは、みかこの前で足を止めた。
「こんにちは」
シルクハットのネコが、帽子を上げた。
「こんちは」
キャスケットのネコが、頭を下げた。
「こんにちは」
みかこも慌てておじぎをする。するとキャスケット帽のネコが一歩近づいて、みかこを見上げた。
「食いもの、持ってる?」
「兄さん」
シルクハットのネコが顔をしかめて、ステッキの先で彼の足元をちょんとつつく。
「失礼だろう、いきなりそれは」
「だっておれ、腹がへったんだ」
「だからと言って、……」
きょとんとするみかこを置いて、兄弟らしいふたりのネコは口げんかをはじめた。
彼らの背丈は低く、ちょうど、みかこの腰あたりにふたつの顔が並んでいる。しゃがんで、すこしの間ものめずらしそうに彼らを眺めたみかこは、ポケットを探ってみた。
そのとき初めて、自分が、普段ならぜったいに選ばない裾のひらひらしたワンピースを着ていることに気づいたのだけれど、みかこはやっぱりそれをすんなり受け入れて、両サイドについたポケットを片方ずつ確かめた。
どちらも、からっぽだった。
「ごめんね、私、なにも持っていないみたい」
「そうか」
キャスケットのネコはしょんぼりした。それがあんまり残念そうだったので、みかこも一緒になってしょんぼりした。
「お嬢さん、なにもそんな顔をすることはない。兄はいつもこうなんだ。気にしないでくれたまえ」
みかこが首をかしげると、シルクハットは、呆れ顔を兄ネコへ向けた。
「腹がへったとばかり言う。たとえへってなくたって、へったへったと言うんだから、まったく困ったものだ」
「それじゃあまるで、おれがうそつきみたいだ」
キャスケットが反論した。むっと両目を細めて、大きなお腹を両手でかかえる。
「おれ、本当に腹がへってるんだ。いまに腹と背中がくっつくぞ。どうするんだ、そうなったら」
「どうもこうも、兄さんの腹はちょっとやそっとじゃくっつきやしない」
キャスケットはちょっと黙ってお腹を見下ろした。むずかしい顔でぽんぽん腹鼓を打ったかと思うと、うん、とひとつうなずいた。
「たしかにそうだ。まだくっつきそうにない。うん、まだ平気だ」
納得してしまったキャスケットに、シルクハットはますます呆れたようだった。みかこは、そんなふたりのやり取りに、ついくすくす笑ってしまう。
するとシルクハットがこほんとひとつ咳ばらいをして、持っていたステッキをくるりと回した。「ところで」と調子を変えて、
「お嬢さん、お散歩ですかな」
みかこはまだちいさく笑いながら首をふった。
「ううん、川を見ていただけ」
「なんと。それはもったいない」
「うん、もったいないな」
ふたりのネコが顔を見合わせてうなずきあう。みかこは瞬いた。
「どうして。とってもきれいな川なのに」
「ふむ、確かにそうだが、しかし空をごらんよ。こんなに素晴らしい陽気の下、ただ立って川を眺めているだけなんて。やはりもったいない気がするよ」
「そうかしら」
「そうだとも」
「あんまりじっとしていると、根っこがはえるよ」
キャスケットが口をはさむ。え、とみかこが聞き返すと、彼は、
「知らないのか。足の裏から根っこがはえて、そのうち根っこそのものになっちまうんだ。動きたくても動けない、木になるよ」
と、草むらの奥に立ち並ぶ、青く茂った木々を指さした。
驚いたみかこは、まあ、と声をもらしたものの、それをよしと思う気持ちがこころのどこかからじわりとにじんで、すうとひろがっていくのを感じた。
あそこに根をはやす木々のように、対岸に連なるあの木々のように、この川のほとりに佇んで、日がな一日、ぽかぽか注がれる日差しのもとで川のせせらぎに耳を傾けていられたなら、どんなに幸せなことだろう。
誰になにを言われることもなく、重責や圧力とは無縁のこの世界で、いっぱいに広げた指に茂る葉っぱを風に揺らし、日光浴を楽しめたら。夜にはきっと、頭上にたくさんの星が瞬くに違いない。
毎日すこしずつ変わっていく夜空を見上げ、その変化を探しながらうとうとする。ゆっくりねむる。そのうちにやってくるやわらかな朝に大きなあくびをひとつすると、朝露のなみだがぱたぱた落ちる。
土が目覚め、なかまたちが目覚め、そうして彼らと、ゆったり流れていく一日に身をゆだねるのだ。
それは凪いだ海のように静かだけれど、とてもうつくしい人生であるようにみかこには感じられた。
みかこは立ち上がって、またぼうっと川を眺めた。
そうしていると、なんだか本当に、頭のてっぺんと足の裏がゆっくり一本につながって、それがだんだん土のなかに、頭の上に、伸びていくような気さえした。
「お嬢さん」
呼びかけられてはっとした。つながった一本が、糸のようにぷつんと切れる。
みかこの内側で起きたそれらは、たぶん、ほんの数秒のこと。シルクハットはさっきとなんら変わらない調子でまたくるりとステッキを回した。もう片方の手で、帽子のつばを持ち上げる。
「せっかくだ。散歩をしよう。私達が案内してあげるから」
「でも」
みかこは口をもごもごさせた。この景色から離れてしまうことが、なんだか惜しい。
シルクハットが歩きだした。キャスケットもそれに続く。みかこがまごついていると、
「歩かなければ出会えない景色というものも、ある」
と、シルクハットが振り向きざまにウインクをして、
「歩かなきゃ、食えない食いものだってある」
と、キャスケットがそれを真似た。ただ、キャスケットは弟ネコのようにうまくはいかず、顔をくしゃっとさせただけだったのだけれど。
みかこはもう一度、川を眺めた。広がる景色をしっかり瞳にやきつけてから、ふたたびてくてく歩きだした彼らの背中を追いかけた。
「どこに行くの」
そう尋ねてみると、シルクハットののんびりした声が返ってきた。
「さあ、どこに行こうか。この川沿いをずうっと行くのもいいし、森の中に入ってみるのもいい。あえて目的を決めずに気ままに歩きまわるのもまた、散歩の醍醐味と言える。もしお嬢さんが行きたいところがあるというのなら、そっちへ向かうがね」
「行きたいところ」
みかこはちょっと考えてみた。けれど、考えたところであの川のほとり以外をまるで知らないのだから、そうね、とつぶやくきりになってしまう。すると、キャスケットが振りかえった。
「森のどこかに、あまくてうまい果実がなってるって聞いたことがある。探しに行くかい」
「兄さんが行きたいだけだろう」
「うん」
うなずく兄ネコに、シルクハットが溜息をつく。
「すまないね」
みかこは、くすくす笑って首をふった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
