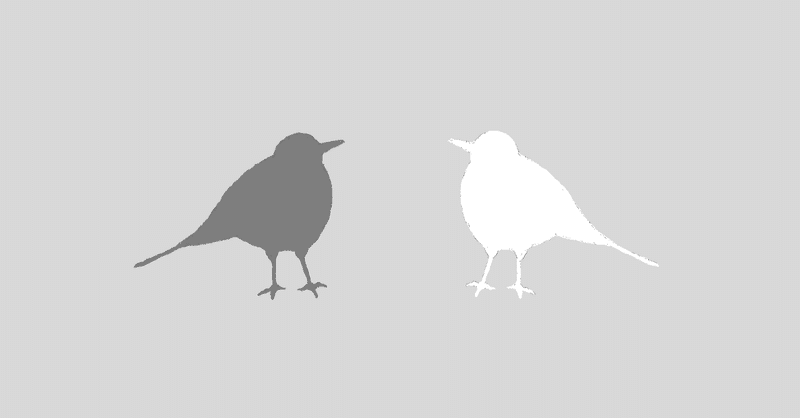
ゆめゆめ、きらり #7【最終話】
空は一向、暮れなかった。景色も一向、変わらなかった。
ずいぶん歩いたように思うけれど、いったいどのくらい進んでいるのか、みかこにはてんで見当もつかない。ただ、三か所も寄り道をしてしまったわけだから、かなり遅れているのだろうことは、みかこにも察しがついた。
「ごめんね。もっと早くつくはずだったのに」
みつまりをころころ転がしていた少女が、顔を上げた。首をふって微笑む。
「いいの。さみしいひとも、つまらないひとも、ほうっておけないもの。おなかのすいているひともね」
少女がキャスケットのまるい背中を眺めた。前を行くふたりのネコはまたまた兄弟げんかをしたらしく、怒り顔でそっぽを向きあっている。歩調もはやい。
みかこは、少女とくすくす笑いあったあと、
「いつも、おばあちゃんに会いにいくとき、どうしてるの」
と、聞いてみた。
「小鳥の背中に乗せてもらうの」
「今日は乗せてもらわなかったのね」
「そうなの。なんだか小鳥も忙しそうだったから、頼むに頼めなかったの」
「まあ。小鳥にも忙しいときがあるの」
「小鳥はいつも忙しそうよ。なにが忙しいのかわからないけれど」
そう言って、少女はまた笑った。
「ねえ。おばあちゃん、いる?」
今度は少女がたずねてきた。
「もちろん、いたわ」
「いたの。いまはいないの」
「うん、いまはいない」
「そうなの。さびしいね」
少女がかなしそうに言った。みかこも、
「うん。ときどき、とってもさびしくなる」
と微笑んで答えた。
「おうい」
いつのまにかずいぶん先まで進んでいたキャスケットが、みかこたちに手を振った。その隣で、シルクハットがステッキの先を浮かせている。
「あそこに蓮の花が咲いているんだが、違うかね」
少女が息をのんだ。
シルクハットの示したほうに、桃色のかたまりが見える。少女がいたところとおんなじに、岸にできた泉のなかに大ぶりな蓮の花がところせましと咲き誇っていた。
「あそこ。あそこだわ」
急いた少女が、みかこの肩からぴょんと飛び降りた。みかこは慌てて手をだしてちいさな体を受け止めると、彼女の代わりに、小走りで、群生する蓮の泉に向かった。途中で追い抜かした兄弟ネコも、みかこの後ろにくっついて、走った。
「おばあちゃん」
少女が声を上げた。
岸べりからすこし離れたところで、大きな蓮の花がそっと揺れた。花びらにかこまれ、花芯に手をついて立ち上がった、ちいさな老女。
彼女は、みかこの手のひらから身を乗りだしている少女を見るなり、とても驚いた顔した。したけれど、すぐにふわっと相好をくずした。少女とよく似た、微笑みだった。
「おかえり」
老女のそれを聞いたとき、なぜかみかこのなかで、なつかしさとさびしさが、いっせいにふくれあがった。
みかこは膝をついて、できるだけ腕をのばした。少女がぴょんと飛び降りる。蓮の花をひとつ、水面に浮かんだ葉っぱをひとつ渡って、老女のいる花びらのなかに駆け込んだ。老女の胸に、顔をうずめるようにしてひしと抱きつく。
「おやまあ。どうして泣いているの」
「うれしいの」
「そうかい、そうかい」
顔を上げた少女の目から、ほろほろとなみだがこぼれた。
「あのね、小鳥から聞いたの。おばあちゃんがさみしがってるって。でも小鳥は忙しかったの。でも、私、みつまりを届けたかったの。そしたらね、このひとたちがね、肩に乗せてくれたの。いろんなひとに会ったの」
堰をきったようにあふれだす少女の言葉はまるで要領を得ないのだけれど、老女はけっしてさえぎることなく、うん、うん、とうなずき、そうかいそうかい、と相槌を打って、幼い背中をやさしく撫でた。
みかこはほっと息をついて、そんなふたりを見守った。すると、ふと、老女と目が合う。彼女は、みかこたちをゆっくり見回してから、微笑みをたたえたまま、そっと頭を下げた。
みかこはそうだと思いだしてポケットをさぐり、赤い実をふたりに渡そうとした。けれど、みかこは大きく目を見ひらいたまま、動けなくなってしまった。泣きじゃくる少女とおだやかな老女の姿が、幼いころのみかこと祖母そのものに、なっていた。
葉っぱの一片から、赤い実が一粒すべり落ちた。若草に沈んで土の上をころころところがったそれが、蓮の花にうめつくされた桃色の水面に吸いこまれていった。
美佳子は、そこで目を覚ました。
今まで広がっていた色彩豊かな風景から一変して、ワンルームのせまい一室が、こじんまりと、視界の中に収まっている。
夢うつつ。
自分の部屋であるのにどこか違う場所にいるみたいな、ベッドに横になっているのにふわふわ浮遊しているみたいな、不可思議な違和感にまとわりつかれる。
目覚まし時計が、じりりとけたたましい音を立てた。無理やり現実に引き戻された美佳子は、腕を伸ばしてそれを止め、のそりと起き上がった。
あれが夢であったことが信じられないくらい、ひとつひとつの感覚が鮮明に残っていた。森のにおい、赤い実の味、住人たちとの会話や、それによって、静かにゆるやかに動いた、自分のこころ。
そしてこれまた不思議なことに、美佳子は、夢の中のみかことして、それを遠くで眺めているべつの存在として、さらに、住人たちひとりひとりとして、すべての方向からそれらを思い起こすことができたのである。
ベッドに腰かけたまま、夢の中でのできごとを追いかけていた美佳子は、少女と老女の再会まで来たところでカレンダーに目をやった。忘れないよう赤くめじるしをつけた、今日の日付。五月十五日。
美佳子はゆっくりとベッドから降りた。閉めきっていた分厚いカーテンを開けてみると、夢でみたような、一点のくもりもない澄んだ青空がひろがっていた。
祖母の命日は、毎年晴れる。
季節柄だと言ってしまえばそれまでだけれど、美佳子は、それを祖母の想いとして考えていた。くもり空が嫌いで、けれどしとしと雨はなんだか好きで、晴れた空を見上げるたびに、ああいい天気、と嬉しそうな顔をしていた祖母。だいすきだった、おばあちゃん。
美佳子は、窓を開けた。
初夏の、すこしだけしめったような、けれども休日の朝らしいさわやかで穏やかな空気が、美佳子の頬を撫で、部屋の中に流れこんでくる。
「ああいい天気」
美佳子は、大きな伸びをひとつして、澄み渡った空を見上げた。
【了】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
