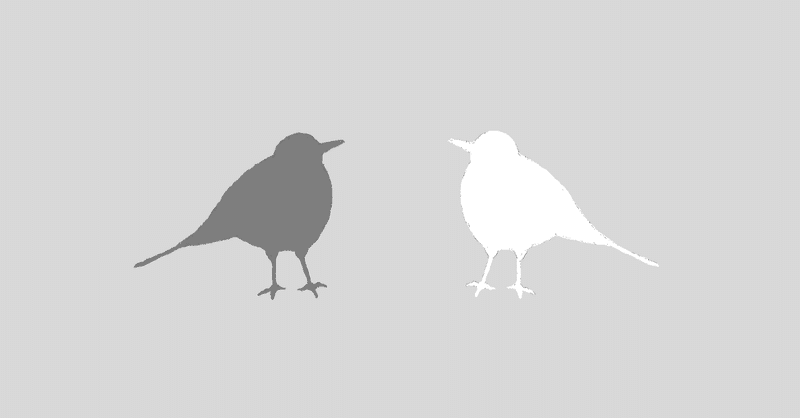
ゆめゆめ、きらり #2
川岸の草むらは、いつしかしめっぽい土に変わっていた。
それに気づいたときには、履いていたはずのペタンコ靴もすっかり消えてなくなって、みかこは、裸足のまま歩いていた。
焦げ茶色の土はひんやりふかふかしていて、まるでじゅうたんみたいに心地いい。踏みしめるたびに土が沈んで足跡がつく。みかこのものよりずいぶん小さなネコたちの足跡も、両隣にちょんちょんと残っていた。
たしかにこれは、歩かなければ出会えないもののひとつ。
みかこは顔をほころばせた。
土の感触を楽しみながら川沿いを進んでいると、ふたりのネコが、ふと足を止めた。みかこも立ち止まる。ネコたちは帽子の下からはみ出したそれぞれの耳をぴんと立てて、きょろきょろあたりを見回しはじめた。
すると、みかこの耳にも、風に乗ってちいさな音が聞こえてきた。それは、子どものすすり泣く声だった。
キャスケットが、前に向かってちょっと走り、岸べりを指さした。
「ここからだ」
みかこたちも彼に続いた。
川が岸べりにくいこんで、こじんまりした泉のようになっていた。大ぶりな蓮の花が、水面いっぱいに咲いている。平たい緑の葉っぱよりも花のほうがよほど多くて、まるで、花束をそっと浮かべたみたいにその一画を彩っていた。
キャスケットの言うとおり、泣き声はその泉から聞こえてくる。みかこたちは、そっと覗きこんだ。
泉のまんなかに浮かぶ、ひときわ大きな花の中に、ひとがいた。
薄い花びらにかこまれて、ぼこんと突き出たかたそうな黄色い花芯の上にうずくまっている、ちいさな少女。ぐすぐすと鼻を鳴らし、細い肩をふるわせている。
「どうしたの」
その姿があまりにもかなしそうだったので、みかこはたまらなくなって声をかけた。顔を上げた少女は、みかこたちを見るなり、またすぐにうつむいてしまった。ぐしぐし目をこすって泣き続ける。
キャスケットが言った。
「腹がへってるんだ、きっと。そうだ。あまくてうまい果実をとってきてやろう。すぐに元気になるよ」
シルクハットは、ううむ、とうなり声をひとつ落とす。
「それにしてはずいぶんかなしげじゃないか。きっと、こころを痛めているに違いない。つらいことでもあったんだろう、可哀想に」
キャスケットがまた言った。
「だから、あの果実がいいんじゃないか。うまいものを食えば、かなしさなんてふっとぶぞ。探しに行こう」
「ううむ」
みかこはそっと手を伸ばした。一片の花びらの先をつまんで、岸のほうに引き寄せる。少女を驚かせないように、少女が落ちないように、ゆっくり、やさしく。
水の上でゆらゆらと花が揺れ、少女が顔を上げた。蓮の花びらとおんなじ、しずくの乗った薄桃色の瞳が、みかこをじいっと見上げた。
「こんにちは」
みかこは微笑んだ。ふたりのネコも、「こんにちは」「こんちは」と、帽子を取ったり頭を下げたりしながらそれに続いた。
少女は、みかこたちを見つめたまま、目に溜まったしずくをほろほろこぼした。みかこはまた、たまらなくなった。
「どうして泣いているの」
少女がうつむく。
「おばあちゃんに会いに行きたいの」
ぽつんと声を落とした少女は、ぐすっと鼻を鳴らしてから静かに続けた。
「おばあちゃんがとってもさみしがってるって、小鳥から聞いたの。だから、おばあちゃんに会いにいきたいの。これを届けに行きたいの」
少女は、花芯の表面に埋まっていたまるいかたまりを取り上げた。それは、彼女の顔と同じくらいの大きさの、はちみつを丹念にかためて作ったビードロのまりのようなものだった。大切そうに胸に抱いて、また、ほろほろとなみだをこぼす。
「君のおばあさんは、どこにいるんだね」
シルクハットがそうたずねると、少女は川の下流を指さした。
「この川のずうっと向こう。とっても遠いの。私ひとりじゃ、歩いていけない。さみしがってるおばあちゃんに、なにもしてあげられない」
少女の声にいっそうかなしみが増した。
「どのくらい遠いのかしら」
みかこがそうつぶやくと、
「とっても」
と、少女もつぶやくようにして答えた。
それを聞いていたキャスケットが、はてと首をかしげる。
「そんなに長かったか、この川」
「この少女にとっては、そりゃ長いだろう。なんせこんなにちいさいんだから。ふむ、しかし」
シルクハットはそこで言葉を切って、少女に向けた目をやんわり細めた。
「私たちなら、決して歩いていけない距離ではない。『キリカブ』の先なら、近道も知っているよ」
少女がはっとして身を乗りだした。
「先。『キリカブ』の先」
口早に告げる少女に、みかこのこころもにわかにはやる。
「連れていってあげましょうか」
「ほんとう?」
少女の頬がぽっと赤らんで、濡れた瞳がきらきらと輝く。みかこはもちろん、ふたりのネコも快くうなずいた。
「ありがとう。私、すごくうれしい」
はちみつ色のまりを抱きしめた少女は、すっかりなみだを忘れたようにやわらかく微笑んだ。
みかこと少女と、ふたりのネコは、蓮の泉を離れ、川沿いをすこし進んでから、かくんと折れて森に入った。
これがシルクハットの言っていた近道で、彼によると、あの川は途中で大きくカーブをえがいているから、こうして森をつっきるのがいちばん早い――のだそうだ。ちょうど、『キリカブ』のところに出るらしい。
少女ははちみつ色のまりを胸に抱いて、みかこの左肩におとなしく座っていた。ときどき、みかこの横顔や、前を歩くふたりのネコの背中をじっと眺めたりしていたのだけれど、みかこたちの会話がふと途切れたときに、歩くたびに肩で揺れる彼女の横髪をひとたば握って、くいくいと引っぱった。
「ねえ。お花、すき?」
みかこはちょっと笑ってうなずいた。
「うん、すきよ」
「私もすき。よかった」
少女がほっと息をはきだした。すこししてから、彼女はまた、みかこの髪をくいくい引っぱる。
「ねえ」
「なあに」
「私ね、葉っぱのにおいもすきなの。濡れた葉っぱのにおいが、とってもすき」
「私もすきよ。とっても」
「よかった」
少女はまたほっと息をはきだして、嬉しそうな顔をした。みかこがふふと笑うと、少女も一緒にふふと笑った。
みかこは大きく深呼吸をしながら森を見渡した。
頭上で重なる緑の隙間から、筋になって差し込む春みたいな匂い。地面からのぼってくる土のしめっぽい匂い。それらが、葉と樹木の濃厚な匂いと混ざりあって、彼女の肺を満たしていく。
取りこまれてしまいそう、と、みかこは思った。
あの川のほとりで感じたものとはまた違う。風景のひとつになるのではなく、空気の一部にとけていく、そんな感覚だった。
さわさわ、さわさわ。風にささやく森の音を聞きながら、みかこたちはしばらく歩いた。歩けど歩けど景色は変わらず、一向に、森を抜けられそうな気がしない。
「いま、どのあたりかしら」
みかこがぽつとつぶやくと、シルクハットが振りかえった。
「ちょうど半分をすぎたあたりだな。あともう半分で『キリカブ』に出られるよ」
「まだ半分」
思わず声を上げたみかこに、シルクハットが笑いだす。
「まあ、長くないとは言ったがね、けっして短い川ではないんだ、あれは。これでもずいぶん近道なんだよ」
「そう」
みかこはそっと息をついた。その横顔をじっと見上げた少女が、
「すこし休んでいったら」
と、心配そうに言った。
キャスケットがぴたっと立ち止まる。
「そうだ、休憩だ。休憩しよう。おれはそろそろ疲れた。腹もへった」
言うなり、木の根元にどっかりと座りこんでしまった。
「ああ、兄さん」
「なんだ」
「服が汚れてしまう」
「もう汚れてる」
「そうだが、しかし」
「いいんだ。服ってのはそもそも、おれの代わりに汚れたりやぶけたりしてくれるものなんだから。かまうもんか」
「しかしだね」
「しかし、しかし。そんなことばかり言ってるから、おまえの頭はかたくなるんだ」
シルクハットが顔をしかめた。みかこは慌てて口をひらく。
「私も、すこし歩き疲れたな。休んでいきましょうよ」
兄ネコへの反論をのみこんだシルクハットは、顔をしかめながらも、ふむ、とひとつうなずいた。けれど、まわりは土だらけ。キャスケットみたいに座ろうものなら、服にくっきり、おしりのあとがつくのは目に見えている。
「どこか、ゆっくりできそうなところがあればいいんだけど」
みかこがきょろりとあたりを見回す。すると少女が、なにかを思いだしたように、あ、と声を上げた。
「あのね、私、小鳥から聞いたことがあるの。森の中には小屋があちこちに建っててね、小鳥たちはいつも、そこで翼を休めてるんだって」
「ほう」
シルクハットが瞳をまるくした。
「ひとは住んでるのかね」
「住んでたり、住んでなかったり」
「ふむ」
「どこにあるのかしら。近いかな。知ってる?」
みかこがたずねてみると、少女もシルクハットも首をかしげた。
「私、森に入ったのはじめてなの」
「私も、この辺は、この近道を行くばかりだからなあ。しかし途方に暮れていても仕方がない。探してみようか」
「見つからなかったらどうするんだ」
キャスケットが不満げな声をはさんだ。
「見つかるさ。小屋はいくつもあるっていうんだから」
シルクハットが肩をすくめて応じた。すると今度は、
「迷ったら」
と、また聞く。
「迷わないよ。水のかおりをたどればすむ」
キャスケットはちょっと黙ってから、少女を見た。
「きみ、急がなくていいの」
「いいの。私、おばあちゃんに会えたら、それでじゅうぶんだもの」
キャスケットはとうとう観念して、重たい腰をよいせと上げた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
