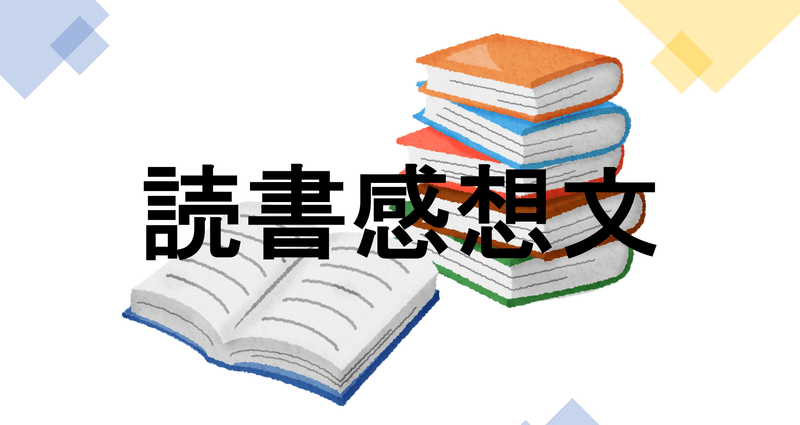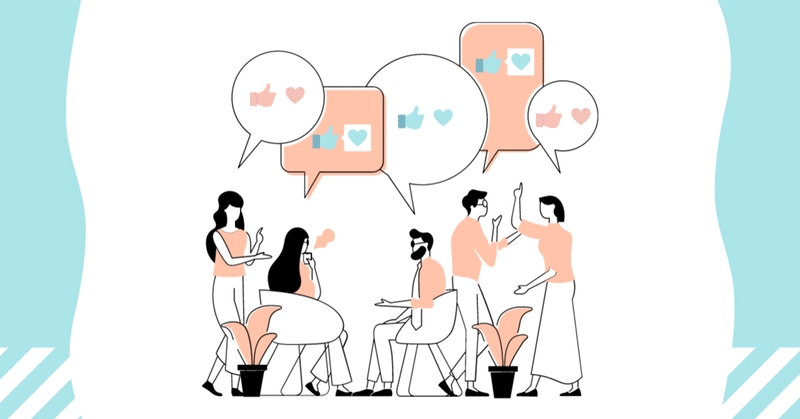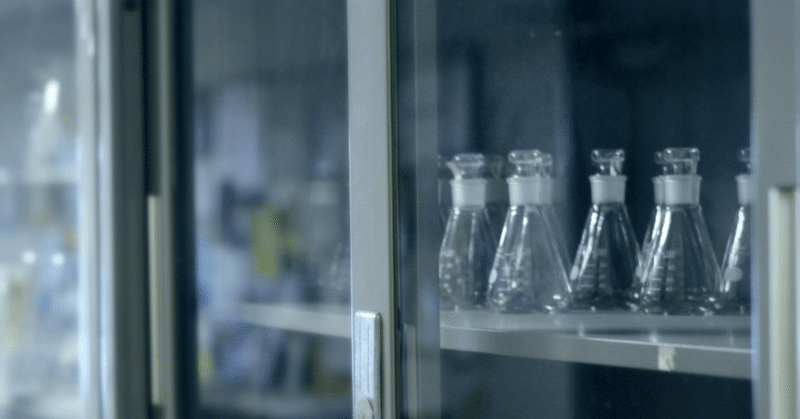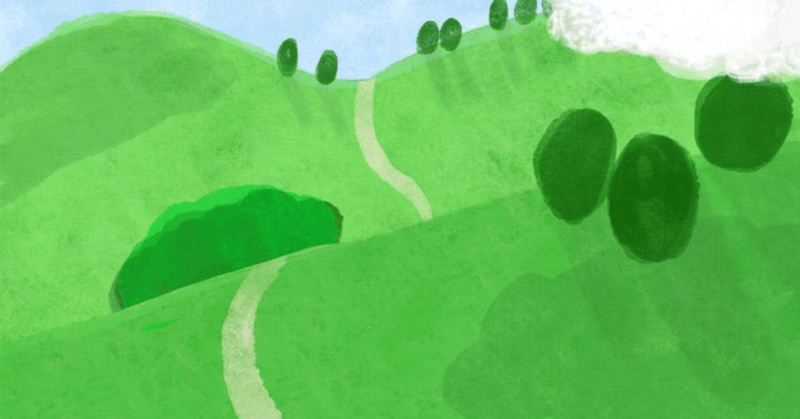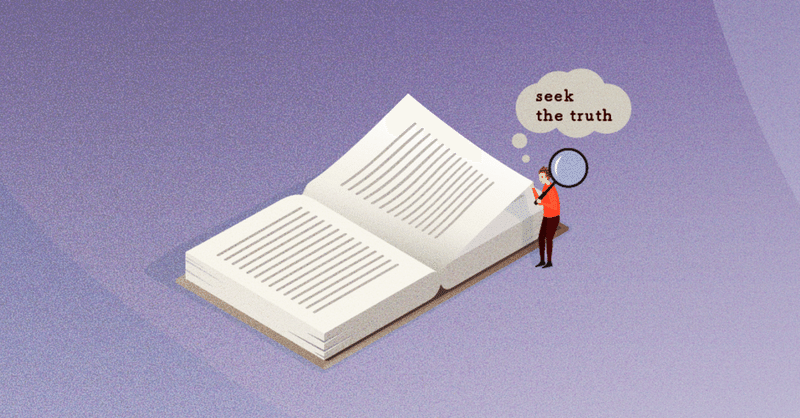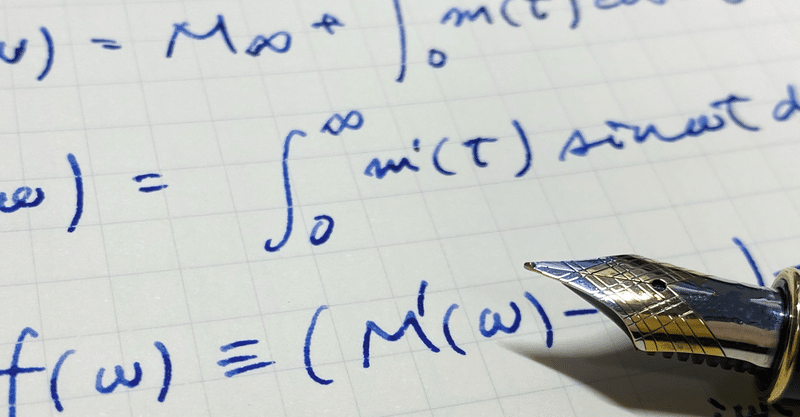#科学

『我々はなぜ我々だけなのか:アジアから消えた多様な「人類」たち』(川端裕人 著・海部陽介 監修 講談社 2017)読書感想文
「我々」とはホモ・サピエンスのこと。現存するホモ属は“我々だけ”。ではなぜ、“我々だけ”なのか。本書では、この問いに迫る人類学が描く「景色」を体感することができる。 舞台はアジアに点在する発掘現場。そこで発掘される謎の化石。監修者である海部氏率いる研究グループは、最先端の分析機器・手法を駆使し、謎に包まれた化石たちを分析している。 研究成果から描かれる人類史の「景色」とは。“我々だけ”でない時代はあったのか。ワクワク・ドキドキする研究成果を著者である川端氏の独特の記述と共