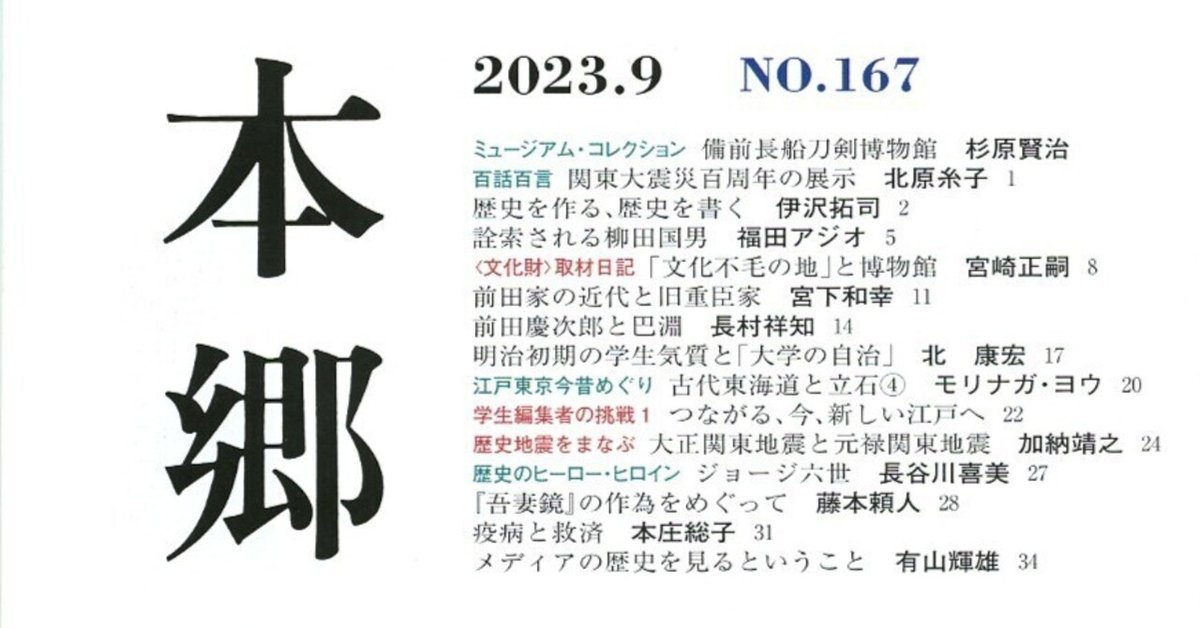
メディアの歴史を見るということ 有山輝雄
昨年刊行した『近代日本メディア史』全2巻の著者、有山輝雄先生は日本メディア史研究の第一人者で、いわばこの分野の草分け的な存在です。すっかりSNSから情報を得ることに慣れてしまっている私たちですが、「SNSはそれ以前のメディアを模倣して誕生していること」を忘れてはならないと思います。ご著書の刊行に因んでご寄稿いただいたエッセイをぜひご一読下さい。
30年ほど前に友人達と「メディア史」を名乗る研究会を立ちあげたときには、メディアという言葉は研究者の一部や広告業界で用いられていたが、一般的な用語ではなかった。むしろ、マスコミとかジャーナリズムといった言葉のほうがなじみのあるものだったろう。あえて「メディア史」という言葉を使ったのは、新しい研究への志向を示したかったからである。その後、若い研究者たちの個別的研究が積み重ねられ、また思いがけないことだが、この提案に共鳴したのか、メディア史を名乗るさまざまな研究が生まれてきた。「メディア史」という研究領域がそれなりに認知されてきているように感じる。
それはそれで結構なのだが、ただ現在の段階で厄介なのはメディアという言葉が社会できわめてありふれた言葉になっていることである。大学でもメディアという言葉を織り込んだ学部や学科の名称は珍しくないし、いつのまにかキャンパスから図書館は消えて情報メディア・センターとかいう看板に掛けかえられている。さまざまな会社や組織、あるいは商品の名前にもメディアという言葉が冠せられ、広告コピーなどでも盛んに使われている。
メディアという言葉がこれだけ大きく広まり、日常化したのは、現代の社会の急激な変化があることは明らかだ。いま、われわれの日常生活では、情報を発したり受けたりする新しい道具が急速に普及し、しかもそれら道具を使えば、はるかかなたの映像をありありと見ることができるし、何年もかけて大変な苦労をして集めなければならなかった資料を自宅にいたままでまたたく間に集めることもできる。かつてはとうてい考えられなかったことだ。われわれの視野は空間的にも時間的にも大きく広がった。しかもそこでは現実と想像とが区別できなくなっている。現実をもとに想像をふくらませるだけでなく、想像が現実を作っていく。
これらの道具やそれらの果たしている働きを何といったらよいのか戸惑っているところに、メディアという言葉は持ちだしてみると、何となく説明がつくような気がしてきたというところなのだろう。
メディアという言葉には固定的な翻訳語がない。媒体という言葉が一応翻訳語としてあるのだが、あまり一般化はしていない。せいぜい広告業界などが使うぐらいだろう。それも最近ではすたれてきているようだ。幕末から明治初期の学者達は外来語を翻訳することに大変な苦心を重ね、「社会」とか「哲学」とか現在では当たり前の言葉ができあがったことはよく知られている。それに比べて、いつまでたってもしっかりした翻訳語ができないというのは、現代の学者達の努力不足ということになろう。確かにそういう面もあるが、それだけではなく、苦労して翻訳語を作っても、その指示対象のほうがどんどん変化していって、たちどころに翻訳語が不適切ということになってしまうこともある。これでは翻訳語などないほうがかえって便利だということになる。

事態はあまりに流動的なのである。しかもこの言葉は音だけあって、意味が固定されていないから、意味を伸縮することもできて、さまざまな方面に応用することできる。今まではっきりつかまえられなかった現象もこの言葉によって説明できるように見える。これもメディアという言葉は多用される一つの要因であろう。
こうしたメディアの流行語化のなかで、研究を進めるのはかえって厄介で、メディアという言葉の意味を慎重に考えていかなければならない。この言葉を社会学、心理学などの観点から定義づけることも可能であろう。しかし、そこで忘れてはならないのは、メディアというのは歴史的概念であることである。現在多彩かつめまぐるしく変転しているメディアとそれが引き起こしている変動も、歴史的文脈のなかにある。現在の現象の歴史性を没却した論議はトートロジーに陥って、深い考察にはなっていかないであろう。
メディアを現代の最新技術の産物としてしか見ず、「歴史としての現在」を考えない言説が大手を振っている現状だからこそ、メディアを歴史のなかで改めてとらえ直していくメディア史が求められるはずである。「歴史の性質について超歴史的理論を想定するとか、社会のなかの人間が非歴史的な存在であると想定しないかぎり、社会科学が歴史を超越するとは想定できない」のである(ライト・ミルズ〈伊奈正人・中村好孝訳〉『社会学的想像力』2017年 ちくま学芸文庫 二四九ページ)。
ただ、メディアを歴史的存在として考えると一般的に言えても、既にかくかくたる実績を積みあげてきた政治史・経済史・思想史等のなかで独自の視角をもつことはなかなか難事である。いうまでもなく、メディアは言説・音声・画像・映像等を生産し、伝播する活動であるから、当然その内容の分析が必要である。だが、それと同時にその言説・画像等の表現を枠づけている形式の分析が必要である。そして、メディアの物理的特性と技術、諸活動を組織化する事業組織を明らかにしなければならない。無論、日常生活のなかでメディアを利用している人々とその利用の仕方を忘れてはならない。さらにそれらのメディアの活動を外側から条件づける政治権力の規制という大きな問題がある。これらが構成している構造を歴史内在的にとらえることができれば、メディア史は独自の視角と領域をもって成立することができるだろう。

しかしながら、前途は遼遠である。そこで起きがちなことは、既存の歴史研究の図式をそのままとりいれて、同じような図式でメディアの歴史を見てしまうことである。それではメディアの歴史を内在的に研究したことにならない。あくまでその構造を内在的に明らかにして、そこから見えてくる歴史を提示していかなければならないはずだ。
今回、そうした考えから、明治・大正・昭和戦前・戦後という時期区分をとらず、メディアの歴史に内在する論理をもとにして、1918(大正7)年で第1巻、第2巻を分けることとした。1918年は、白虹事件の起きた年である。これは大阪朝日新聞社で起きた事件であるが、新聞社全体の構造を基底的なところから変える事件であり、そこから形成されたメディアの構造とイデオロギーはその後に生まれたラジオ、テレビなどをも規定していったと考えたからである。無論、それと並ぶ大きな画期は1945年の敗戦である。大日本帝国憲法は「法律の範囲内に於て言論著作印行集会及結社の自由」を認めるだけであったが、日本国憲法は「一切の表現の自由」を保障している。また新しいさまざまなメディアの登場など戦後の状況は大きく変化しているように見える。しかしメディアの根本的構造は白虹事件以来の構造からまったく自由になったとは言いがたいのである。
いずれにせよ、今回の『近代日本メディア史』は一つの試みであり、一定の進展をみせてきたメディア史研究の次のステップのための踏み台になれば幸いである。
(ありやま てるお・メディア史研究者)
