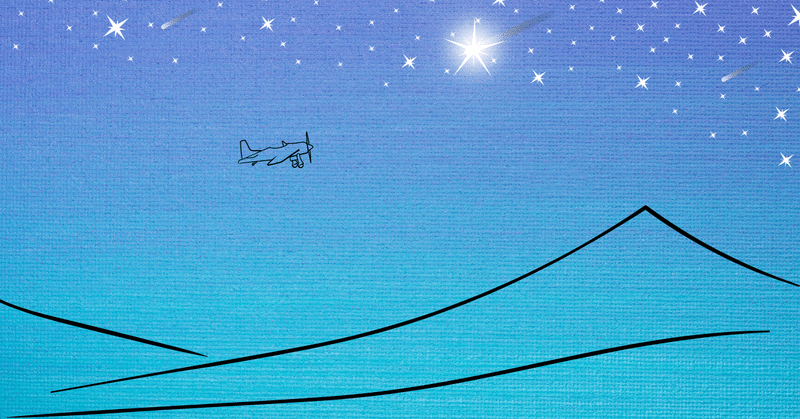
Saint-Ex
ぼっちゃん、ぼっちゃん。そう、声をかけたが返事はなかった。
音もなく倒れた少年の身体はあまりに軽く、その事実はあまりに残酷だった。
ぼくは声にならない声でむせび泣いた。
9年前のあの出来事を、未だに夢に見る。
本当だったとは、誰にも話したことはない。誰かに話せば、砂漠で遭難して白昼夢でも見たか、熱に浮かされて幻覚でも見たんだろうと言われるに決まっていた。米国にいて自由にものを言えなかったから子供向けの絵本にしたんでしょう。そう、大人は決めつける。そして自分の思い込みをひとにも思い込ませようとする。だんだん、そうだったかなという気になってくる。そして元のところにあった記憶が、知らぬうちに違う記憶になっている。
ぼくはちいさな王子さま――ぼっちゃんを忘れてしまうのが怖かった。このまま黙っていればいつか忘れてしまうかもしれない。それで絵と文章にして、書き残すことを思いついた。書いている間は、思い出しながら楽しいような気がしたし、まだこんなに覚えていることがあるんだと嬉しくなった。でも細かいところは、どんどん消えて行く。朝起きた時、絶対にこの夢を忘れないぞと誓っても、次第に靄がかかって曖昧になっていくのと似ている。必死に書き残そうとするのだけれど、よく覚えていると思った強烈な印象も、曖昧で細切れな断片になっていて元の形ではないような気がする。それとよく似ている。
夢だったのだろうか、あれは。
確かに存在したのに、どうしてこうもつかみどころがないのだろう。砂漠で子供と逢うなんて、ばかげているという大人の常識がぼくの記憶をじゃましてくる。会ったんだ。逢ったんだ。在ったんだ。確かに。
ぼっちゃんから聞いた話をひとつひとつ絵にしながら、確かだったことを確かめる。ぼっちゃんから聞いた言葉をなぞっていく。せわしなく思い込みに囚われた大人たち。威張ったり、数えたり、酒に溺れたり、実体のないことや無駄なことに時間といのちと情熱を浪費する大人たち。
ぼくは、そんな大人になりたくなかった。
戻った世界は、あの砂漠の静謐な世界とは全く違う場所だった。
ぼくは自分が変わってしまったことを悟った。ぼっちゃんと出会って、何かが変わってしまった。そもそも、前に当たり前にできていたことが、当たり前にできなくなってしまった。誰もがぼくから書くことを奪っていく。それを、周りの人は今が戦時だからだと言う。そうじゃない。あなたたちは忘れてしまっているだけなんだ。
ぼくは自分の国を愛している。
だから自分の国のために戦ってきた。それが最善だと信じていた。でもぼくは戦争がしたいから戦うんじゃない。
ぼくは飛びたかったし、飛んでいたかった。
世界が今どんなにひどいことになっているか、大人たちにわかっているのだろうか。自分が大切にしているものがほんとうは何か、わかっていない。
わかっているのはぼっちゃんだけだ。
ぼくはぼっちゃんから、それを教わったんだ。
そして友達のことを思った。今、辛い思いをしている友達を。
早くこの恐ろしいことを終わりにしなければ。
自由で美しいものを取り戻さなければ。
理解する人がいない場所に居続けるというのは、どんなに辛い、孤独なことだろう。ぼくは帰ってきたのに、まるであの砂漠より酷いところにいるような気がした。水も食糧もたっぷりある。でもそれは本当に必要な水とは違っていた。
ぼくに必要なのは、あの砂漠にある井戸の水だった。見つけにくいけど確かにある、ぼっちゃんの喉を潤した、こころによい、水。
この世界には、どこにもない。
ぼっちゃんの美しさは、たったひとつの大切なバラを心に秘めている美しさだった。あれより美しいものを、ぼくは他に知らない。
大切なものは目に見えない。
そして大切なものに気づくのは、たいてい、失った後だ。
あれからぼくはずっと、革紐のついたひつじの口輪の絵をポケットに入れている。ぼっちゃんに会ったら、渡すためだ。たったひとつの後悔は、あの子に羊が薔薇を食べないようにするための口輪に革紐を描いてあげなかったことだからだ。
そしてぼくは飛んで、飛んで飛び続けて、ぼっちゃんに会いに行こうと決めた。ぼっちゃんは言うだろうか。そんなに重い身体では、ぼくの星には到底来られないし、ぼくとバラと羊と活火山で星はいっぱいだよと。なによりぼくの気高いバラは、移り気なきみを嫌うよ、と。
空を、ぼくは見上げる。そこにはすずのような声で笑うぼっちゃんがいる。ぼっちゃんがぼくにプレゼントしてくれたのは、星ぜんぶだ。どの星にぼっちゃんがいるだろうなんて思わなくていいように、寂しくないように。そしてそれを、ぼくは、遠くにいる友達にもプレゼントしたかったんだ。
世界中どこにいても、誰の頭の上にも、星はかならずある。
ぼっちゃんがいるかもしれない星たちは、1日に四十回も夕日が見られる星たちは、人の世の穢れや苦しみから遠く離れて、凛として美しいバラを宿している。
ひとつひとつがぼっちゃんの大切な星なんだ。
大切な星は——ぼくにも、ぼくの友達にも、あなたにも、争いをしている最中の人々にもある。
誰もが、同じ星のことを指しているんだ。
まったく驚くべきことじゃないか。
ぼくの視界には今、メッサーシュミットが見える。
そしてぼくの頭上には、間違いないーー
あの子とバラの、星がある。
ふたたび、Ryéさんとの企画です。
『星の王子さま』で二次創作をしませんか?というお誘い。
以前『星の王子さま』の感想文を書きました。
フランス語の先生と『星の王子さま』でペアドクも。
もう「お誘いに乗らない」という選択肢はありません!笑
子供の頃より、大人になってからの方が、何度もページを開くようになった『星の王子さま』。
サン=テグジュペリのことを少しずつ知るにつけ、彼の最後の時について思いを馳せるようになりました。
どうしてそこまで飛ぶことに固執していたんだろう。
彼にとって戦争とはなんだったんだろう。
「星の王子さま」を思い出すたび、そんなことを考えていました。それで、Ryéさんにお話をいただいてすぐ「そのことを書こう」と思いました。
でも難しかったです。
それで、以前読んだときに最後のシーンが印象に残った『最終飛行』をまた読み返しました。実は私、佐藤賢一さんの本はスムーズに読める本と引っかかって読みにく本があって、これは「ひっかかるほう(しかもかなり)」だったのです。初回は、前半部はかなり飛ばし飛ばし読んでました。
今回はちゃんと読めましたが、やっぱりこの本のサン=テグジュペリは「ヤバい人」でした。愛すべき人物と感じるか、疎ましい奇人と感じるかは読者次第だと思います。笑
Ryéさん、今回も楽しいお誘い、ありがとうございます!!
Ryéさんの作品はこちらから✨↓
#Saint-Ex(サンテックス)はSaint-Exupéryの略でサン=テグジュペリの愛称
#「星の王子さま」とサン=テグジュペリへのオマージュです
#最後の飛行でサンテックスは何を思っていたのでしょう
#佐藤賢一の『最終飛行』でも、最後の場面で彼はちいさな王子さまを思い出していました
#1944年、44歳のとき偵察機に搭乗しコルシカ島に向かう途中消息を絶つ
#1998年、サン=テグジュペリのものと思われるブレスレットが発見される
#2000年、残骸機がサン=テグジュペリのものと確認
#2003年、正式な回収許可がおり戦死が確定
#2005年、日本の岩波書店の版権が切れ、パブリックドメインとなる。新しい翻訳が解禁(フランスでは愛国殉職者のため2044年まで著作権保護期間)。
#2008年、撃墜したドイツ機Bf109のパイロットがサン=テグジュペリの偵察機を撃墜したと証言
#参考はWikipediaと『最終飛行』佐藤賢一
#訳本は内藤濯訳
