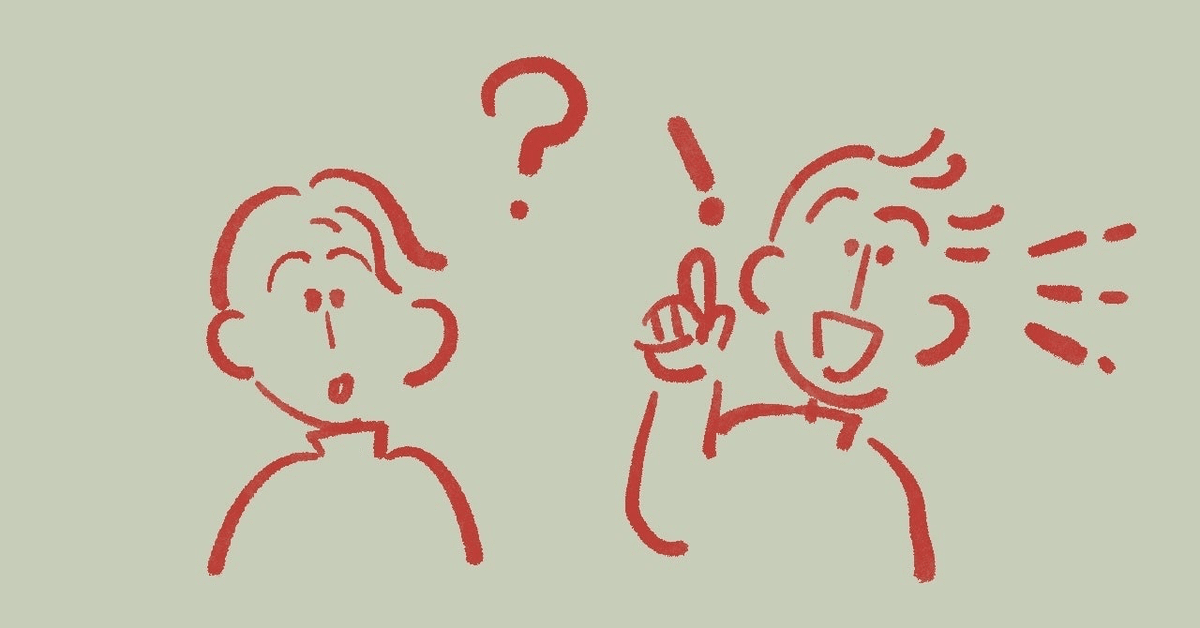
フットサルがサッカーをシンカさせる
こんにちは、こんばんわ。
現在フットサル日本代表が、AFCフットサルアジア杯クウェート2022に参加しておりますが、普段の日常よりフットサルという言葉がサッカー指導者にも届いているちょうどいい機会だと思い、フットサルのサッカーへの有用性について話そうと思いました。結論はもちろん、サッカーをシンカさせます。
僕自身、サッカーを8歳から始めて約20年にわたりフットボールに関わってきました。フットサルを初めてちゃんとプレーしたのは大学生の頃で、実際に自分がプレーをして構造を理解しようとし始めた時に「これは小さい頃からやっておくべきだった!」と心から思いました。なので、サッカー指導者はもちろん、選手としてプレーしている皆さんにもフットサルに触れることでサッカーをシンカさせていただきたく、今回まとめていくことにしました。根拠は大きく分けて3つ、掲示させていただきたいと思います。
①世界的なプレイヤーのルーツ
皆さんはどんな選手が好きですか?誰のファンですか?
僕は幼少期はロナウジーニョが好きでした。観客を魅了するテクニック、華麗なプレーや独創的なアイディア。指導者になり、当時のプレーを見直してみるとフットサルで習得ができる多くの個人戦術で構成されており、味方との繋がり・グループ戦術もフットサルでは言語化されているプレーが多く散りばめられているのだと気づきました。
皆さんの頭の中に思い浮かんだ選手はもしかしてスペイン人やブラジル人が多かったのではないでしょうか?
昔憧れだった選手、今現役で活躍している選手、実はその内訳を見てみるとブラジル人とスペイン人が多いことに気付かされます。下記資料はTwitterでの拾いものですが、CLで登録されている選手の国籍リストだそうです。
個人的に未だにフットボール大国一位はブラジル。
— ユウキ⚽️スカウト (@scoutyuki_) June 1, 2022
毎年のようにこのチャンピオンズリーグ国籍別プレー時間で1位もしくは2位に君臨しているから。
70人って代表3つ分ぐらいの選手でしょ。日本に置き換えたら異常じゃない?しかも欧州の国じゃないのよ。 pic.twitter.com/MRw6Q2hEnq
ではこのブラジルとスペインが育成年代に何をやっていたのかを理解することが、“優れた選手”への近道なのかもしれませんね。
答えは簡単、フットサルをサッカーと同様両方プレーしていたそうです。
ブラジルやスペインでは15歳のタイミングまで両方ともにプレーをし、日本でいう高校年代に上がるタイミングでフットサル選手かサッカー選手かの進路選択をするそうです。もちろん、これは日本とは違う文化・社会背景や環境要因も考慮にいれなければなりませんが、それが多くのプレイヤーが通る道であることは非常に大きな意味合いを持っていると考えます。
②サッカーを場面で切り取るとその多くが5×5の範疇に収まる
サッカーのグループ戦術がこの10年で大きく進化してきたと言われています。一昔前と比べて人々が多くの情報に触れることが可能になりましたし、グローバル化によってもたらされたものは大きいと多くの方々が言及されています。実際に僕自身もそれは感じていて、世界のトップリーグのプレーをいつでもどこでも見返すことは出来るようになりましたし、最新トレンドはインターネットを通じてわざわざ現地に行かなくても学ぶことが出来るようになりました。それによって現場レベルでも多くの議論が交わされるようになりましたし、試行錯誤の基準が大きく変わってきたように思います。『自分がこんな練習をしたかった』指導者界隈でよく言います。それほどまでに、以前と比べてサッカーが理論化され、トレーニングも同様に理論化されてきたんですね。
そしてその理論化されてきたものを“因数分解”していくと僕は5×5で行われるフットサルに凝縮され、またその凝縮され言語化されている原理原則がサッカーに反映できるものが多くあるということに気付かされました。
例えばカウンター局面でのボール保持者に対するレーンを意識したランニング、相手守備の同サイド圧縮によるスペースが限られた中でのスペーシング(スペースをつくる動き・ボールの動かし方)、守備組織のナンバリング(これは枝D理論で教わりました)、セットプレー時における考え方、局面の2×1の作り方・見つけ方等、挙げればキリがないですが多くのものがあります。
サッカーでは広大なピッチのなかで良くも悪くも曖昧でも解決出来ていたものが、戦術の高度化により曖昧のままでは解決・分析出来なくなってきた昨今、このスモールフィールドで得られるものの意味合いの大きさは日に日に増して行っているように感じます。
③細かいこだわりが勝負を分ける
前述のように、スモールフィールドで言語化されたものがサッカーにおいて大きな意味あいをもたらし始めています。
1×1での相手の背負い方、身体の角度。ボールを引き出す走るタイミング、相手との駆け引き、2人組の関係etc.
例えばですが、サッカーにおいて、相手の背後を攻略しようとしたときに、『裏!』と声をかけて走らせるとします。このときに想定されるのは下図のようなイメージになると思います。ここで言語化されたものを用いることで『パラ!(パラレラ)』『ゴー!』『ディアゴナール!』といった形で背後への狙い方がパスの出し手と受け手で共通認識となり、プレーの成功率があがることは明白です。

これは一例ですが、他にもビルドアップでのライン間の取り方・攻略ポイント等、スモールフィールドでの原理を理解しておけば、サッカーのフルピッチにおいても要所を掴んでいるので11×11でも応用を効かしていくことが出来ると思います。
フットサルはサッカーをシンカさせる
これまで見てきたように、つまりはフットサルはサッカーをシンカ(進化・深化・新化)させていく一助になります。ここまで読んでくださった皆様も『あのチームの戦術ってつまりはこういうことなのかな?』とか『あの選手ってやたらゴール奪うけど、こういうのが上手かったのかな?』とか新たな議論の対象がぼんやりと浮かんできたと思います。そのぼんやりを仲間同士で共有していくと新たな道が見えてくるのかもしれません。今回はライトに書きたかったのでここまでにしておきます。
それでは。
いただいたサポートはフットボール界の未来に繋げます😄
