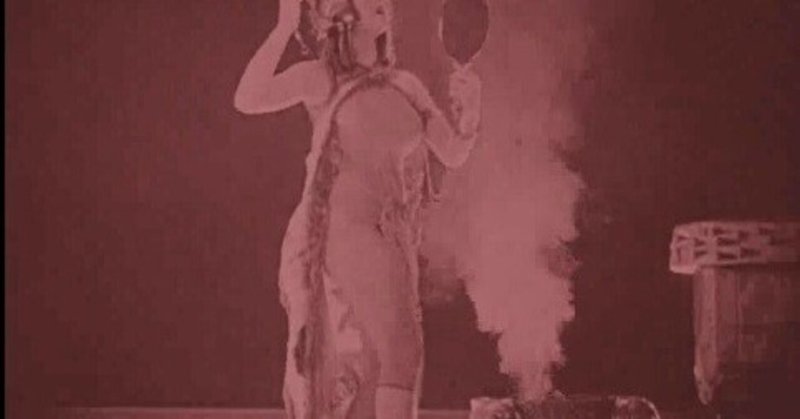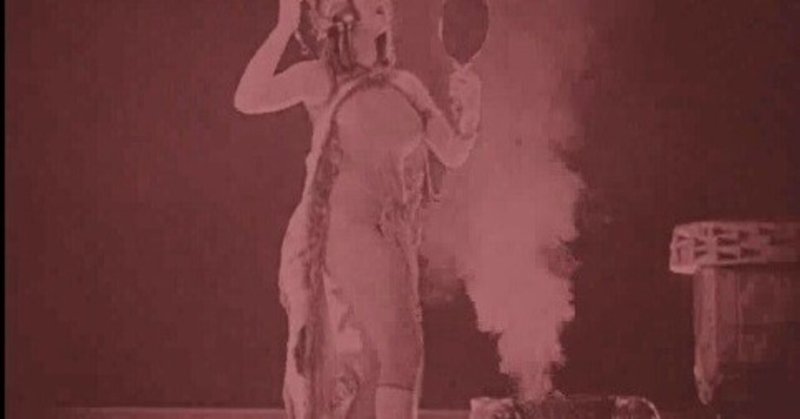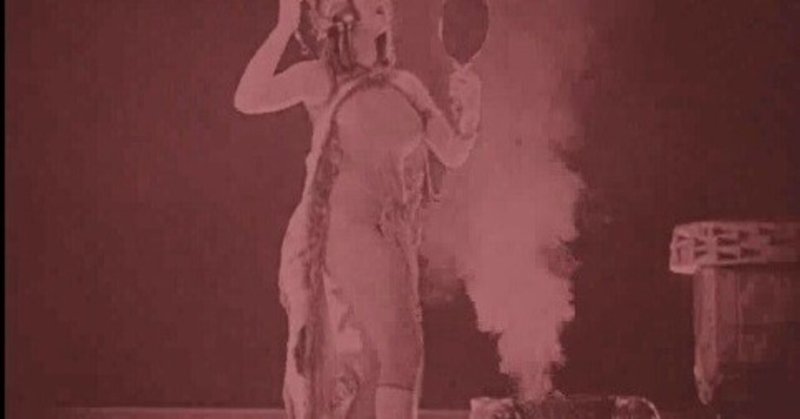- 運営しているクリエイター
#カール・マルクス
【とある本格派フェミニストの憂鬱11パス目】技術革新と認識革命②「1859年認識革命」仮説からの再出発。
前回の投稿を大胆に要約してみましょう。
統計学の入門書的記述の多くが「手持ちの標本データのみで統計表現を試みるのが記述統計、背後に大きな母集団を想定するのが推計統計」と説明している。
しかし実際には「背後に大きな母集団を想定する」という意味合いにおいては(20世紀に入ってから追加された)分散(Variance)$${σ^2}$$の概念が追加された時点で推計統計の世界に足を踏み入れているとも。
【とある本格派フェミニストの憂鬱8パス目】「自分の意思決定過程に割り込んでくる他者」としての外部性について
前回投稿でお伝えした「史上初の世界恐慌を契機にカール・マルクスとジョン・スチュワート・ミルとチャールス・ダーウィンが同時に指摘した事」というのは、ある意味…
経済学でいうところの「外部性」概念と深く関わってくるのです。
まさしく私の勝手な、とはいえそれなりに21世紀に入っても通用する部が厳選して抜き出されている様に見える要約「我々が自由意志や個性と信じているものは、社会的圧力によって型抜きされ
【とある本格派フェミニストの憂鬱7パス目】「必ず観察から入れ。それに立脚しない憶測は、ことごとく現実に裏切られることになる」
相変わらずここで触れたプロジェクトで手一杯なので、今回はさらに手短に。以前の投稿で触れられなかった内容の補足など。
この時代を生き延びた、すなわち当時の社会問題が「国王と教会の権威の絶対性」から「資本主義的活動が生む利益の正しい再分配方法」に推移するパラダイスシフトを見逃さず、正しく対応したカール・マルクスは、なす術もなく歴史の掃き溜め送りにされた他の革命家とはそもそも観察眼が違っていたのだと思