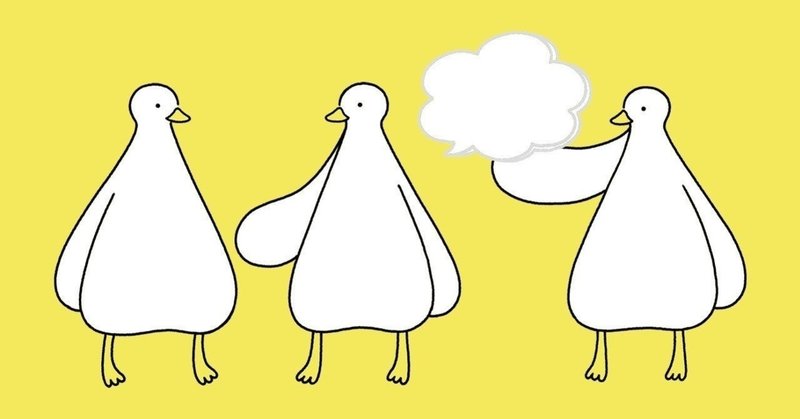
その言語にない概念の重要性〜「アイデンティティーの一掃」 内モンゴル抗議もむなしく進む中国語教育〜
「アイデンティティーの一掃」 内モンゴル抗議もむなしく進む中国語教育
こちら、物騒なタイトルだが、これは以下のヤフーニュースからの記事だ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3e1ec8c135f4782964a68afb407988a7a95191a5
今日はこの記事から、「その言語にない概念の重要性」について考えたい。
このニュースの内容に直接言及するわけではないが、なぜ自分たちが作ってきた言語を奪われることが問題なのだろうか?
もちろん「愛着がある」とか「新しい言語を覚えるのは大きな負担である」とか単純な理由もあるだろう。
さらに、
言語は文化を含むから、アイデンティティー自体が破壊される、というようなことも言われる。
これについて考えてみたい。
文化を含むとはどういうことか?
日本が近代化したときに、海外から「自由」「哲学」など多くの概念を輸入したが、それに当たる日本語の概念がなかったため新しく造語する必要があったことは有名な話。
逆に、現代においても日本の「過労死」「津波」などは、それにピッタリ当てはまる概念が英語圏になかったために、karoshi,tsunamiとなって使われている。
ここで、人間にとって言語は何かということを想定してみたい。
語というのは、別の語との関係でその価値が決まる。というのはソシュールのアイデアだ。価値というのは、ようはそれが何を意味するかがわかる、と思ってもらえばいい。
人間は、ある反復した経験をするとその対象をシンボル化する。ソシュールは、これをランガージュ(シンボル化能力)とし、文字や音声で固定される記号をシニフィアン、それで指示される意味や概念をシニフィエ、と呼んだ。
この用語でいうと、江戸時代には「自由」「哲学」というようなシニフィエはなかった。でも、それが入ってくることで、既存のシニフィエーシニフィアンのセットから、新しい語を生み出したのだ。
ある言語の全ての語は、ある言語が使われる地域での生活や人間関係のコミュニケーションなどから概念が生まれる。だから、歴史や文化そのものだと言われる。
そこで一つの疑問がある。
シニフィエーシニフィアンの組み合わせが多いほうがいいのだろうか?
多いにこしたほうがい、世界をより真実に近く捉えられる可能性は高い。
しかし、問題はある。
それは、ピンとこない語が増えることは問題だ。
日本に「自由」の概念が入ってきたように、それに対応するものがそもそもなかった場合、それを支える経験がないままシニフィアンだけが先行することになる。
よくわからないままに語が使われ、人を動かすようになると、人々の間で共通了解が起きずに事が進むわけだから、これは大きな誤解を生み争いを生む。
日本人は「幸福」を追求しようとするが、そもそもこれも西洋的な概念であり、社会という荒野を家族で生き抜くような文脈で意味がしっくりくるような概念だ。
語、というのは簡単に作れるものではない。時代の流れにより大多数の人々に理解されて、新しい語が生まれる。
一つの言語体系は基本的には、その文化と歴史に支えられた意味としてしっくりくる語しか持っていない。
その奇跡的なバランスで成り立っている言語体系を安易に切り崩すことがどれだけ人間の生の根本に影響があるかは、上述の説明で理解できるのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
