
なぜ教師になったのか?学生時代の気づきと衝撃の裏話
こんにちは。やしろです。
今回は、いつもと違った
角度から記事を書いていきます。
何でこの内容を
記事にしようと思ったかというと、
生徒からよく聞かれるのと
SNSでもたまに聞かれるからです!
あとは、
自分でも少し振り返って
みたい気持ちになったからです。
4つのパートに分けて書いていきます。
(1)両親の影響
校種は違いますが、
私の両親は、元教員なんです。
結構、親が教師で
教師になった人って
多いのではないでしょうか?
周りでも、よく耳にします。
ある論文では、
『職業選択に及ぼす親の職業的影響』について
成人の選択行動(実際に職に就いている)による職業継承性の存在を示すことができた。とくに、小・中学校教師及び建築設計士の子弟では高い継承率が見出され、本報告が専門的職業に焦点をあて、さらにその職に長年従事してきた親を対象としたことは有効であったと思われる。
とされています。
少なからず影響していることは
何となく分かるような気がします。
昔から、
良くも悪くも
学校の先生や教師の仕事を
身近に感じていました。
でも、
「意外!」
とよく言われるのが、
勉強に関して、あまり
関与してこないことです(笑)
これは個人差があると思いますが、
「勉強しなさい!」
と言われた記憶はありません。
高校生の時、
勉強をサボって、
テストで赤点を連発していた時も
特に何も言われませんでした。
大学受験の時もそうでした。
親が教師だからといって、
家でも勉強させるか
というと
そうではないんですよね。
これは意図的なのか、
忙しすぎて手が回らなかったのか
分かりませんが・・・
話が逸れました。
結局、
何が言いたいかというと、
親が教師であるということは、
無意識・無自覚に子どもの
職業観に影響を与えている"気"がする
ということです。
私もその一人だったということです。

(2)塾講師のアルバイト
高校を卒業してから、
友人の勧めもあり、
塾講師のアルバイトを始めました。
人前で話すことは
そこまで苦手ではなかったので、
「とりあえずやってみるか!」
くらいの感覚だったのを覚えています。
しかし、
初日から
塾講師の難しさを
実感するのでした。

何が難しかったというと、
思っていた以上に
アウトプットが難しい
ということです。
中学~高校、大学受験と
インプット型の勉強は
たくさんしてきましたが、
試験・受験という
アウトプット以外では、
そのような経験はなく、
それがいかに難しいか。
同時に、
塾講師や学校の先生が
当たり前のようにしている
授業(アウトプット)には
膨大な準備と知識量が
必要だと気づかされました。
このことは、
私が教師を目指す上で
とても重要な気づき
だったと思っています。

そこから、
アウトプットのための
インプットを積み上げました!
例えば、
「源頼朝が鎌倉幕府を開いた。」
という事象を理解するのに、
これまで通りのインプットなら、
このままでOKですが、
アウトプットのための
インプットなら、
「なぜ、鎌倉なのか?」
「源頼朝ってどんな人物なのか?」
「なぜ、源氏なのか?」
「源氏はどのように台頭したのか?」
こういった周辺知識が
必要とされます。
これらの周辺知識があることで
相手に分かりやすく
伝えることができます。
こういったインプットを
積み上げていくと、
これまでの学習がいかに
断片的で連続性のないもの
だったかを痛感しました。
塾講師のアルバイトを
始めたことで、
① アウトプットのためのインプット
② アウトプット
③ アウトプット改善のためのインプット
(→以下、②・③を繰り返す)
というPDCAサイクルに近いことが
自然とできるようになっていきました。
大学~院生までの7年間、
塾講師で培ったスキルは、
教師を目指す一番の理由に
なったといっても過言ではありません。

(3)社会科を選んだ理由
ここまで読んだ皆さんは、
そもそも
「何で社会科教師なの?」
って疑問に思いますよね。
実は、学生時代
一番好きな教科は、
英語だったんです!
英語の先生を目指そうと
思っていた時期もありました。
私が英語で一番好きだったのが
「文章が読める!楽しい!」
という場面でした。
つまり、
リーディングやライティングが好き!

しかし、
その頃から英語教育って
コミュニケーション重視
になってきていて、
スピーキングやリスニングに
重きがおかれるように
なっていると感じていました。
そんな中、
「好きだけど、授業できるか?」
って思ったんです。
なので、
その時点で英語は諦め、
二番目に好きだったのが
日本史だったので、
社会科を選んだわけです!
結構単純ですよね!

(4)"衝撃"を受けた教育実習
大学4年生の頃、
母校の中学校へ
教育実習へ行きました。
ここでの経験は
今でも忘れないです。
色々思うことは
ありましたが、
大きく分けて2つ、
衝撃的なことがありました。
一つ目は、何といってもコレ(笑)
・公立中学校のブラックな様相
幸いなことに、実習では
授業をたくさん持たせてもらえ、
貴重な経験を積むことができました。
社会科以外にも、
道徳、総合、学活も
それぞれ研究授業(?)
をやったほどです。
しかし、
毎日20~22時まで
学校に残って次の日の
授業準備をしていました。
研究授業の前日は、
23時まで居ましたが、
さすがに追い出され、
(指導教官にも申し訳なかった)
自宅で仮眠をとってから
朝4時までやっていました。
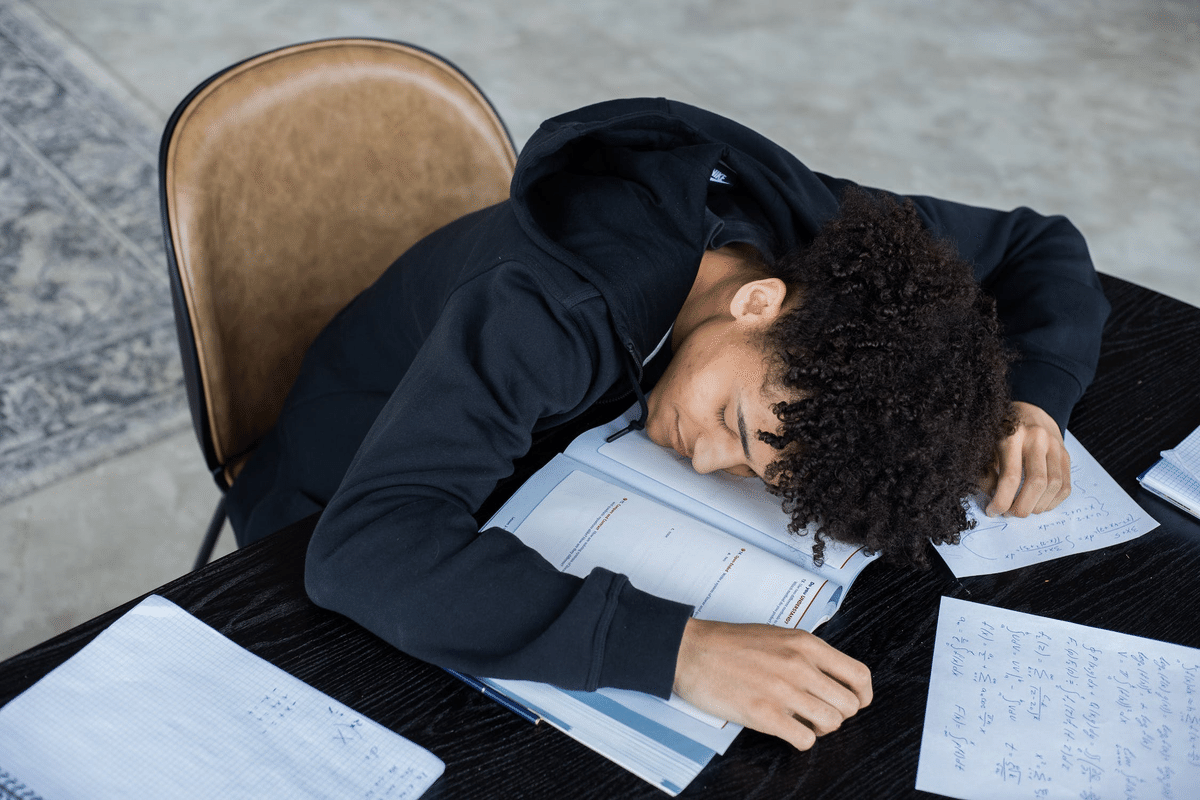
こんな日々を過ごしていたので、
「これ以外に、
担任の業務や部活動を
見ている世の中の中学教師って
スーパーマンすぎない!?」
と思っていました。
いや、本当にスーパーマン
だと思います。
しかし、
スーパーマンとはいえ「人間」。
疲れが溜まると
人間関係もピリピリ。
職員室も
ピリピリしていました。
「これが中学校かぁ~」
と黒い部分を初めて見たのでした。

・こんな授業がしてみたい!
とはいっても、
社会科の授業は観るのも
自分でやるのも楽しかったです!
指導教官の先生の授業は、
毎回パソコン室でした。
この時点で、
「自分が受けてきた社会科と違う!」
と衝撃を受けました。
当時はまだ、
教室にTVがある方が珍しかったので、
指導教官が
プロジェクターやパソコンを使いこなし
授業をする様子を見て、
「こんな授業をしてみたい!」
と思いました!
ICT教育への関心はこの時に
芽生えたような気がします。
さらに衝撃的だったのが、
「地理」の授業。
"地球を作る授業"でした。
「何でそんなことを
やる必要があるんだろう?」
と、最初は思っていました!

生徒には、
上記のような紙が配布され、
ハサミで切って、繋ぎ合わせて
地球を作っていました。
すると・・・
「あれ?教科書の地図と比べるとズレてる。」
一般的によく見る地図(メルカトル図法)
の方角や直線距離は、
実際とは異なるということに
生徒が気づいたんです!
また、高緯度ほど
面積のゆがみが出る。
ということにも気づき、
「地図は目的に応じて
使い分けることが大事」
ということが
非常に分かりやすく
体感的に理解できる
授業だったんです!
生徒がやっていたことは、
紙をハサミで切って、
繋ぎ合わせただけなのに・・・
衝撃を受けました!!
どうやって、
そのアイディアが浮かんだのか!
「自分もこんな授業をしてみたい!」
と強く実感した瞬間でした。
おわりに
ここまで、
長々と書いてきましたが、
これらのことが
私が教師になるきっかけ、
今の教師としての在り方の根幹を
築いていると思っています。
もちろん、
教師になってからの
出会いや経験、
時代の要請等によって
変化してきている部分もありますが、
基本的には、こんな感じです。
色々思うことはありつつも、
社会科教育に対する熱が
今の私の土台にはあります。
ここまでお読みいただき、
ありがとうございました。
次の記事もお楽しみに!
▼クリック友だち登録!

▼毎日、X(旧Twitter)でも発信中!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
