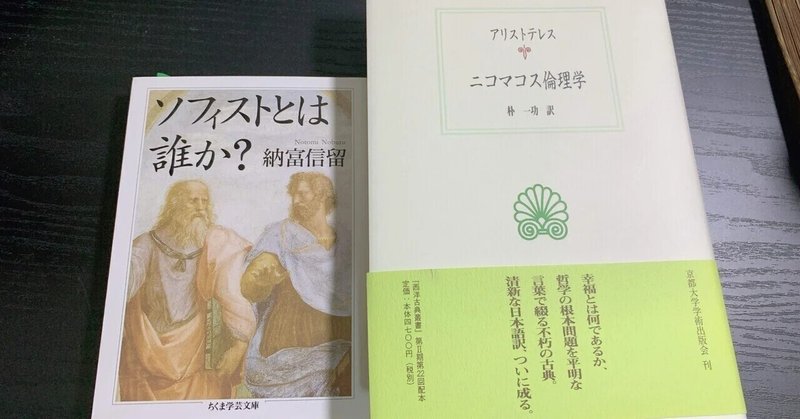
いかにして、それは“それ”になるのか。納富信留『ソフィストとは誰か?』をよむ(3)。
アリストテレスの『二コマコス倫理学』(朴一功訳、京都大学出版会)と納富信留『ソフィストとは誰か?』(ちくま学芸文庫)を交互に読んでいくという試み。今回は、納富先生の第1部第2章「誰がソフィストか」を読みます。
摘 読。
もともと、ソフィストという名称は「知者(ソフォス)」と同義であった。それが異なるニュアンスを持ち始めたのは、紀元前5世紀にプロタゴラスが自らこの名で呼ばれる専門職業人を標榜したことによる。そもそもソフィストの技術は古いものであった。かつては、詩の朗唱や神の言葉の解釈を通じて、あるいは体育教師や音楽家として人々を教化していたのが、人間の教育そのものを目標に掲げ、それに専門的に従事する職業人が誕生したとき、つまりプロタゴラスが詩や音楽といった「仮面」を脱ぎ捨てたとき、ソフィストが職業として自立した。これは、ギリシア社会にとって、大きな衝撃であったばかりでなく、人類の歴史にとって新たな1頁となった。
ギリシア社会においては、伝統的に、神々や英雄や人間のありようを唱う詩人たちが「知者」として尊敬されてきた。また、適切な判断と優れた弁舌で国と人民とを導く政治家も「知者」と呼ばれる。そして、自然や宇宙のあり方を探究する上流階層出身の思想家も「知者」と呼ばれていた。しかし、「ソフィスト」を名乗る新しい知識人は、そのような従来の社会的存在とは別に、職業として「知者」であることを宣言した。彼らの職業性は、人々から授業料をとって教育を与えるところにある。この点に、社会から、とりわけ伝統的で保守的な人々からの懐疑や批判の目が向けられた。他方で、このような新鮮な知的刺激と、直接的に社会に役立つ教育という謳い文句は、政治的野心を持つ若者たちの熱狂的な歓迎も受けた。一部の有力家系に独占されていたそれまでの政治や社会の体制から、能力と才覚によって誰もが政治権力の中枢に登りうるという開かれた民主政への変化が、ソフィストの職業と補完的であったことは、容易に想像される。
これを徹底的に批判したのがソクラテスであった。ソクラテスにとって、真の「知者」は神の他にはなく、神に比して人間の「知」などは無に等しいものであった。それゆえに、不知でありながら知を愛し求め続ける人間のあり方を「哲学者」と呼んだ。この考え方は、ホメロス以来の伝統的な見方を受け継ぐものでもあり、人間の血の伝達や進歩を高らかに謳うソフィストの対極にあった。ここから、ソフィストに対して「知者と現れているが、実際はそうではない者」という定義が与えられることになる。アリストテレスもまた、この考え方を継承する。
こうした考え方が広まったかのようにも考えられそうであるが、実際には必ずしもそうとも言えない。例えば、プラトンの同時代のライバル・イソクラテスの著作では「ソフィスト」は「知恵をもつ者」という一般的な定義でも用いられている。ただ、イソクラテスは、ソフィストという言葉が否定的な意味合いで用いられていることも自覚している。イソクラテスは、授業料をとって弟子たちに弁論術を教授したという点で紛れもなく「ソフィスト」であった。そのことを彼自身も自覚していた。同時に、イソクラテスは他のソフィストたちのいかがわしい教育法を厳しく批判した。彼にとって、真のソフィストとは哲学者であり、有益で尊敬に値する教育者だったのである。
このように、ソフィストという名称に対する評価は、否定的なものも肯定的なものも両方あった。むしろ、ローマ帝国期においても肯定から弁論術教授に任命されたヘロデス・アッティコスやフラウィオス・フィロストラトスなどのような人物もいたのである。
では、ソフィストという名称は古典期のギリシアで、いったい何を意味していたのだろうか。
そもそも、ソフィストと呼ばれる実体が存在したのか。前章でも明らかにされたように、プロタゴラスなどソフィストたちを厳しく批判するソクラテスその人が、当時のアテナイの人たちからソフィストと見なされていた。イソクラテスが他のソフィストたちを批判する際に、そのなかにプラトンが含まれていた可能性がある。
こう考えると、ソフィストという名称は相手を批判するために便宜的かつ恣意的に用いられていた可能性も想定される。実際、紀元前5世紀からアテナイに登場するシュコファンテスという名称(告訴常習者としてアテナイの民主的裁判制度を悪用して、人々から嫌悪された人々)も、そう呼ばれる職業人がいたのか、法廷などで相手方を貶めるために用いられたレッテルに過ぎないのか、論争になっている。シュコファンテスと呼ばれる人たちは紀元前404年に粛清された人たちが実際にいたが、それが紀元前4世紀に入ると単なるレッテルとしての機能が主となる。
ソフィストに関しても、同じように何らかの実態を伴う活動主体であるのか、単なるレッテルとして用いられているのかが判別でき、ある一群の知的専門家を「ソフィスト」とみなすことができ、その実態を特定する定義を与えることができれば、我々はソフィストを適正に捉えることが可能になる。
では、ソフィストとはどのような人々に付された名称か。ここでは、以下の点に整理できる。
(1)ソフィストたちは「学派」と呼びうる結びつきによる集団ではなく、一人ひとりが独立の自営業者であったために、互いに強烈なライバル意識を持っていた。
(2)ソフィストたちは「教義(doctrine)」と呼びうる思想を共有することもなかった。したがって、その内容は多岐にわたる(バラバラである)。
(3)ソフィストたちは、人々に授ける教育の見返りに授業料、つまり金銭を受け取る。これは、誰でも望むもの、そしてそれに見合う金銭を支払いうる富裕な人に、国籍や出身を問わずに教育を授ける。
この(3)に関しては、例外もあるため、必要条件ではあるが、十分条件とはならない可能性がある。とはいえ、多くのソフィストに該当するのも確かである。本章の第3節では、ソフィストと称された人々について、これらの点を基準にしながら、ソフィストという存在を浮き彫りにしようとしている。例えば、プロタゴラスはアテナイがかかわったイタリア南部の植民市トゥリオイ建国のために法律を起草したり、ギリシアをわたり歩いて金銭を取って人々に市民としての徳を教授すると公言していたり、言論の能力に優れると評判であったり、いわゆる典型的なソフィスト像を具現化していたし、エーゲ海のケオス島出身のプロディコスは言葉(名辞)の厳格な区別と使用にこだわった学者であったと同時に、『ヘラクレスの選択』なる書物の作者として倫理的な教訓を与えたり、『自然について』という著作もあったりと、多面的な活動を展開していた。博識で知られていたヒッピアスは、幾何学、天文学、音楽、詩、彫刻・絵画、歴史など多岐にわたる関心を持ち、外交活動や弁論の演示、教育活動などをおこなっていた。こういった人々が「ソフィスト」と呼ばれることに疑いはない。
ただ、ゴルギアスは祖国レオンティノイの外交使節を務めたのちに、諸国をめぐる「弁論術」の教育者となって巨万の富を築き、100歳を超える長寿を全うしたとされるが、自らを「弁論家」(レートール)と名乗り、「ソフィスト」と呼ばれることをきっぱりと拒否していた。あくまでも、ゴルギアス自身が教え授けるのは言論によって人を説得する術だけで、市民としての徳の教育など公言はしなかったという理由である。ただ、この弁論においては実質的に徳を教えることに至っており、その点でゴルギアスをソフィストとみなすことは自然である。
では、ソフィストと弁論家にどんな違いがあるのか。当時のアテナイにおいては、当事者が自ら告発や弁明の弁論を行う義務があり、検事や弁護士にあたる人々はいなかった。その際、一般市民のなかには、突然の必要に直面して、弁論作成の専門家に依頼し、金銭を支払ってあらかじめ弁論を代作してもらい、それを暗記して法廷に臨む者もいた。これが「言論代作人」(ロゴグラフォス)と呼ばれる人々である。ただ、この人々が教育に携わったわけではない。この点で、職業的に「教育」に携わる人々がソフィストと呼ばれる傾向があったことは窺われる。
ソフィストたちは、基本的に「徳」をめぐる教育を授けることを建前としていたが、実際に教授されたのは言論を扱う術=弁論術(レトリケー)であった。この活動によって、彼らはギリシアの人々のあいだで「知者」としての評判を勝ち取り、社会での地位を占めた。その点で、彼らはギリシア社会が要請した時代のニーズに応える、新しい職業知識人として一つのまとまりをなしていた。
この章で、ソフィストとは誰かという定義が確定しているわけではない。これについては、次章でのテーマとなる。
私 見。
あるなにものかに名前をつけるというのは、言語によって生きている人にとって欠かせない営みである。しかも、その名づけには、何がしかの“評価”が含まれることが少なくない。ソフィストなどは、その典型であろう。
実際、この章を読んでいると、現代においてイメージされるソフィストと、古代ギリシアや古代ローマにおけるソフィストの実態(の断片)には乖離もかなりある。たしかに、お金を取って市民としての徳を教授するという営みに対して、否定的な視線が当時においてもあったのは確かだろう。今においても、そういった営みに対して、似たような視線がないとは言えないようにも思う(徳など教えてはいないが、結果としてそこにつながりうることをしている自分にも、そういう自覚はある)。
その意味において、職業的教育者(=仕事として何かを他者に教える人)をソフィストと呼ぶこと自体、場合によってはそもそもの「知者」というニュートラルな意味しか持っていないケースもある。
ただ、あるソフィストがきわめて大きな影響力を持っていたりすると、それに対して批判的な視点を持つ者も当然出てくる。そのとき、「あいつはソフィストだから」という言い方が生まれる。「哲学者」の祖として位置づけられたソクラテスなどは、むしろ過激な(そう映る)ソフィストだったのかもしれない。「そうではないのだ!」と必死になって弁護し、そして「哲学者」として位置づけようと試み、それに成功したのがプラトン、そしてその流れを汲む者たちだったとみることもできる。そういう意味でも、「ソフィスト」か「哲学者」か、というような問いとそれに対する応答は、実はきわめて明瞭そうにみえて、流動的である。
そのような応答のなかで、悪名ばかりが残っていった一つの典型がソフィストといえるのかもしれない。
*****
最近、こういった名づけに対して、ときどき「あえて、名づけずにそのままにしておきたい」と感じることがある。もちろん、まったく名づけをせずに、「それ」について語ることは不可能である。しかし、名づけをすることによって漏れおちる部分はある。それはやむを得ないことでもある。
ただ、名づけに自覚的であること、その名づけを懐疑すること、その名づけによって見えなくなっている部分はないか問うこと、これらについてはつねに考えていたいと思う。
そこに、何か見落とされていた“新たな”発見/掘り出しがあるかもしれないので。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
