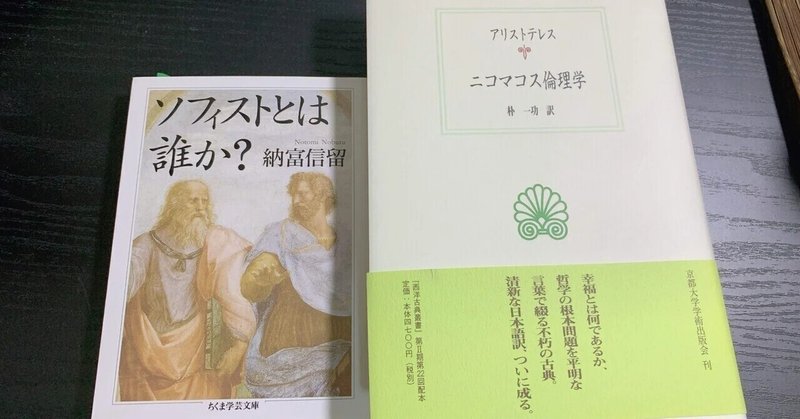
自然ならざるものとしての〈性格の徳〉、そしてまことに難しき中庸への道。アリストテレス『ニコマコス倫理学』をよむ(2)。
アリストテレスの『二コマコス倫理学』(朴一功訳、京都大学出版会)と納富信留『ソフィストとは誰か?』(ちくま学芸文庫)を交互に読んでいくという試みの第3回。
今回は、アリストテレス『ニコマコス倫理学』の第2巻。巻といっても、現代的な感覚でいえば“章”に近いです。
摘 読。
本章で主題となる〈性格の徳〉は、感覚のように自然に備わっているものではない。自然に備わっている限りのすべてのものは、先にまず当の能力がわれわれに与えられていて、後にそれをわれわれが現実化する。それに対して、徳の場合はまずその行為を現実化することによって身につける。これは建築や演奏の場合と同じである。人が家を建てることによって建築家に、竪琴を引くことによって竪琴奏者となるように、正しいことをおこなうことによって正しい人になり、節制あることをおこなうことによって節制ある人になり、勇気あることをおこなうことによって勇気ある人になる、そうアリストテレスは捉える。したがって、立法家たちは市民を習慣づけて善き人々にすることがその役割となり、国制の良し悪しはそれによって決まるとアリストテレスはいう。かくして、同じような活動の反復から、人間の性格の状態が生まれる。
そう考えると、「正しい道理」にもとづいて行為することが前提となる。この「正しい道理」については第6巻第13章で論じられる。ここでアリストテレスが留意している点は興味深い。
行為に関するどのような説明も、厳密に述べるべきではなく、ただその輪郭が示されればよい
つまり、個別の状況はそれぞれ異なるので、個別のことを論じようとしても厳密さを欠く。ここでめざすような一般的な論述は、個別の行為を助けるものであるが、この点についての留意が必要であるとする。
ここでアリストテレスは健康を類比的に議論に援用する。そして、過剰な運動も運動の不足も健康を損なうということに類比して、性格の諸状態においても不足も超過も、望ましくないことを指摘する。ここで出てくるのが〈中庸〉である。快楽にしても、そればかりに奔っても、またあらゆる快楽を避けても、どちらも徳のある状態にはならない。
徳とは、快楽と苦痛にかかわりながら、最善のことをおこないうるような魂の状態のことをさす。したがって、快楽や苦痛から離れているのではなく、快楽や苦痛に対して「正しい対応」ができるとき、その人を“善き人”と呼ぶわけである。
ただ、もちろんアリストテレスも、正しい行為を行う人、節制をおこなう人は、それぞれすでに正しい人、節制ある人なのではないかという反論を想定している。しかし、アリストテレスはこれを技術と区別する。技術によってつくり出されたものは、その作品自身のうちに善きありかたを持っており、技術作品は一定の性格を持つようにつくり出されさえすれば十分であるのに対して、徳にもとづいておこなわれる行為は、それが特定のありかたを持っているとしても、正しくおこなわれたり、節制あるしかたでおこなわれたことにはならず、行為者自身がある一定の状態で行為することもまた、まさに正しい行為や節制ある行為の条件である、というのがアリストテレスの主張である。したがって、アリストテレスは徳ある行為の条件として、
(1)行為者はなすべき行為を知っている
(2)その行為を選択し、しかもその行為そのもののためにそれを選択する
(3)行為者は確固としたゆるぎない状態で行為している
という3つが満たされなければならないとする。この条件を満たした行為を実際に反復的におこなうことで、その人は徳ある状態へと進むことが可能になる。
さて、このように徳のある行為について説明したうえで、アリストテレスは徳とは何かを定義しようとする。人間の魂には情念(パトス)/能力(デュナミス)/状態(ヘクシス)の3つがあるとしたうえで、情念を感情、能力を感受性と位置づけ、状態を「情念に対してわれわれによい態度をとらせたり、悪い態度をとらせたりするところのわれわれのありかた」と規定する。情念が湧き起っているとき「動かされている」のに対して、状態はある一定の「あり方をしている」。となると、状態は感受する能力とも異なる。
その点で、何らかの状況に直面して生じる情念、あるいはその状況を感受する能力、そしてそこから何らかの判断をして行為するその帰結として状態を捉えるというアリストテレスの考え方は、きわめて穏当であるといっていい。
では、徳があるとはどのような状態をいうのか。アリストテレスによれば、徳というのはすべて、それがそなわるところのものを善き状態にし、そのものに自分の機能をよくおこなうようにさせるところのものである。それが成り立つのは、両極端からそれぞれ等しく離れているという意味での「事柄における中間」とはちょっと異なる。特にここで論じられているのは〈性格の徳〉である。そうなると、単に「事柄における中間」という以上に、「われわれとの関係における中間」ということが重要になる。そのうえで、情念と行為における超過と不測は徳ある状態とは言えず、まさに中庸である状態こそが徳ある状態なのである。
したがって、徳とは「選択にかかわる性格の状態」であり、その本質はわれわれとの関係における「中庸」にあるということになる。この中庸状態こそが最善に当たる。その意味で、徳は「頂点」なのである。アリストテレスは、第7章において徳の個別具体的事例を紹介しているが、ここでは省略する。
ただ、その際にもあらゆる行為や情念に中庸がみられるわけではない。悪意や恥知らず、妬みといった情念や、姦通、盗み、殺人といった行為はそもそも低劣であって、そもそもからして誤っている。したがって、そういった低劣な行為や情念に「善い」状態はありえない。
さて、中間の状態は超過からも不足からも反対にある。ここのアリストテレスの論述はややこしいが、要は中間という状態がそれぞれの両極端にとっての反対を含んでいるがゆえに、両極端どうしの“反対”よりも、より反対的であるという指摘である。
そのようななかで、中庸の状態に至るのは容易ではない。円の中心を見出すのは、誰にでもできることではないからである。そうなると、中庸たるためには、まず反対のものから遠ざからなければならない。つまり、さまざまな悪のうち最小のものを取るようにすることが必要になる。同時に、流されやすい方向についても検討しておくことが欠かせない。快楽の場合、特にそうである。
そうはいっても、中間に命中することは難しい。とりわけ、個々の場面では、どうすれば具体的に中間に到達できるか規定することが難しいからである。その際、あるときには超過のほうへ、あるいは不足のほうへと傾く必要もある。そうすることで、中間がどこにあるのかを見出し、命中することができるからである。
私 見。
ひじょうに穏当なことをどうやって説明するのか、もちろん現代の視点からすれば物足りないところはあるとしても、アリストテレスの主張はひとまず首肯できるものといえる。
より重要なのは、個別具体的な状況によって、どのような状態が「善い」と言えるのか異なるとしている点であろう。どちらかといえば、プラトンが『国家』などでも哲人政治をめざしたのに対して、アリストテレスにはそういった点は見られない。ここでアリストテレスの『政治学』まで詳しく参照する余裕はないが、多様なありよう(例えば国制)のなかから、どこに中庸がありうるのかを探究しようとする姿勢は窺える。しかも、それを断定的に論じないのが、アリストテレスの中庸をめざす実践といえるのかもしれない。
この性格の徳の「性格」は“エティーケー”であり、習慣=エトスとを少し変化させたものだと、アリストテレス自身がこの巻の冒頭で言及している。エトスというと、倫理的な側面という以上に(これは、私がヴェーバーの影響を受けているからかもしれないが)風土/文化という側面をより色濃く持っているように感じられる。つまり、この章(もっというと、この本、さらにはアリストテレスの倫理学/政治学/経済学関連の言説)では、行為、さらにはふるまい(≒実践)の蓄積の帰結として、徳という状態が生じる、その際に「善い」方向へと導いていくことの重要性が示されているとみてもよさそうである。もちろん、「じゃあ、具体的にどう考えたらいいのか」という問いが生じたときには、アリストテレスなら「そりゃ、一つひとつの状況に応じて、“反対”から離れていくように考えなきゃ」という回答になりそうだが、倫理学/道徳哲学などの展開というのは、このアリストテレスの線上にあるといっても、そうおかしくはなさそうにも思う。
徳のある状態に近づくためには、もちろん形式論理的にも展開可能だが、対話などを通じて漸近的に“命中”を探索していくという方途もありそうだ。本章の最後に、「あるときには超過のほうへ、あるいは不足のほうへと傾く」ということを指摘しているのは、もちろん個人内部でのことを想定していようけれども、対話のなかで探っていくということもありえるのではないか。
しかし、それにしても中庸というのは、まことに難しい。
【追記】
晩酌もとうに終えて、さてぼちぼち今日を終えようかと思っていた矢先に、ふと思いついた。
本章のなかで、「事柄における中間」と「われわれとの関係における中間」とが登場する。これは上にも言及したとおり。これ、最近はやりのAIでの要約と、ここでの摘読要約との相違としても類推できるかもしれない。もちろん、AI要約とて単なる平均というわけでもないだろうし、AIに問いを投入した人間の問い方によってアウトプットも異なってこよう。ただ、それでもどちらかといえば、AIによる要約は「事柄における中間」としての性格を濃いめに有するとは言えるかもしれない(このあたりは、どんなデータベースをどんなアルゴリズムで処理しているのかによって決まってくるのだろう)。それに対して、“いびつ”である可能性が高い、というか“私”がどう読んだかという点が顕在化する人間要約は「われわれとの関係における」“中間”(実際に中間になっているかどうかはわからない。何ならなっていない可能性のほうが高い)であるともみることもできるかもしれない。
先日、勤め先の大学の3つのゼミの新メンバー向け合同ワークショップで将来においてAIを活用したサービスを提案するというお題もあった。そのなかでAIを駆使した裁判という提案もあって、実際にそういうのも出てきていると聞く。厖大な判例にもとづいて傾向を判断する際に、たしかにAIを活用できる可能性は大きいだろう。一方で、その判例が出てくるに至ったプロセスであったり、そこにかかわった諸当事者たちの背景や文脈までアルゴリズムは酌み上げるのだろうかという疑問も湧く。もちろん、将来においては可能になるのかもしれないが。
別に、私はAIを忌避していない。使えるものは使えばいいし、私もいずれ使うと思う。というか、ChatGPTはまだあんまり使ってないが、DeepLなどは大いにお世話になっている。ただ、それも“技術”の一つであるという認識ではある。さて、本章でアリストテレスは技術作品と、徳のある行為とを区別していた。このあたり、どう考えていくことができるだろうか。
アリストテレスの議論は、ある意味で大らかであるだけに、現代でも考える手がかりの一つになるところが恐ろしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
