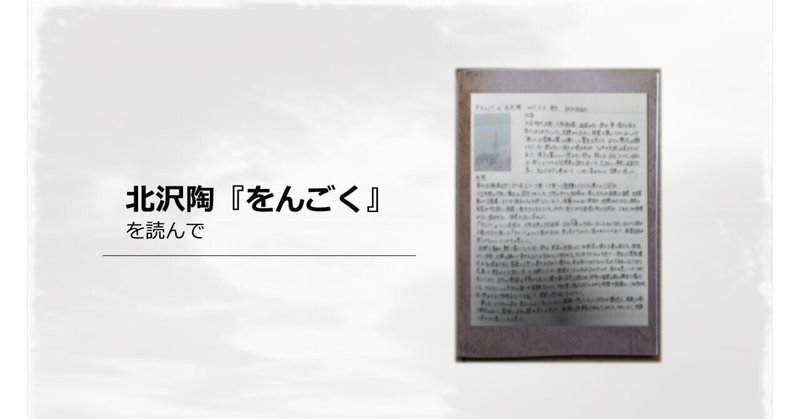
北沢陶『をんごく』を読んで
『をんごく』 北沢陶 2023.11.6 発行 KADOKAWA
内容
大正時代末期、大阪船場。画家の壮一郎は、妻・倭子の死を受け入れられずにいた。未練から巫女に降霊を頼んだがうまくいかず、「奥さんは普通の霊とは違う」と警告を受ける。巫女の懸念は現実となり、壮一郎のもとに倭子が現われるが、その声や気配は歪なものであった。
倭子の霊について探る壮一郎は、顔のない存在「エリマキ」と出会う。エリマキは死を自覚していない霊を喰って生きていると言い、倭子の霊を狙うが、大勢の“何か”に阻まれてしまう。壮一郎とエリマキは怪現象の謎を追ううち、忌まわしい事実に直面する。
家に、死んだはずの妻がいる。この世に留めるのは、未練か、呪いか。
第43回横溝正史ミステリ&ホラー大賞・〈大賞〉〈読者賞〉〈カクヨム賞〉の三冠作。
大正年間の大阪に舞台は設定されています。大阪の中でも船場は、商人文化が発達した結果、生活習慣から言葉遣いまでが、独自のものを使うようになりました。
町は暖簾で賑わい、独特の風習、また大正時代ということもあり、物語に風情と深みを与えています。作中で発せられる登場人物の台詞は、どれもこれも無理がなく、読みやすく、情景が目に浮かびます。
故郷を離れ、東京で暮らしていた壮一郎は、実家の世話により、幼馴染の倭子を妻に迎えます。結婚から一年後、夫婦の静かで幸せな日々は突如として破られます。1923年9月1日の午過ぎに発生した関東大震災がその理由です。
家屋の火災に巻き込まれた倭子は、命は取りとめたものの足が不自由になってしまいます。荒廃した東京から大阪に戻った夫婦でしたが、無理をしたのがよくなかったのか、倭子は患いつき、やがて死んでしまう。
この作品の骨格は冥界から戻ってくる霊を描く怪奇小説ですが、それと同時に推理小説の構造も帯びています。
大切な人との別れは誰しも経験すること。それを乗り越えるまでにかかる時間や経緯は人それぞれですが、壮一郎はかなり特殊なルートを辿って、現実に折り合いをつけていきます。
顔のないエリマキの姿は、見る人によってその人の心に根強く残っている人(例えば、親や恋人、家族)に見える設定はよかったです。
エリマキの顔が見えないという物語の謎要素があるのも良く、それによって、物語に深みが増していると思いました。最後にエリマキの本当の顔が見ることができて満足でした。
死者と生者が交錯する独特の世界を描き、不気味な雰囲気で読者を引き込む。死者の存在、呪いといったテーマに触れつつも、その描写が生み出す人間ドラマが心に染み入ります。
『をんごく』という表記は、以下のことを作者がインタビューで述べています。
ちなみにタイトルを『をんごく』という表記にしたのは、大阪出身の日本画家・木谷千種の作品にならったものです。おんごく遊びを覗く女性を描いた『をんごく』という絵があるのですが、弟の死をきっかけに描かれただけあって、風習自体は楽しげなのにどこかもの悲しい。この小説とも通じる世界なので、検索してみてください
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
