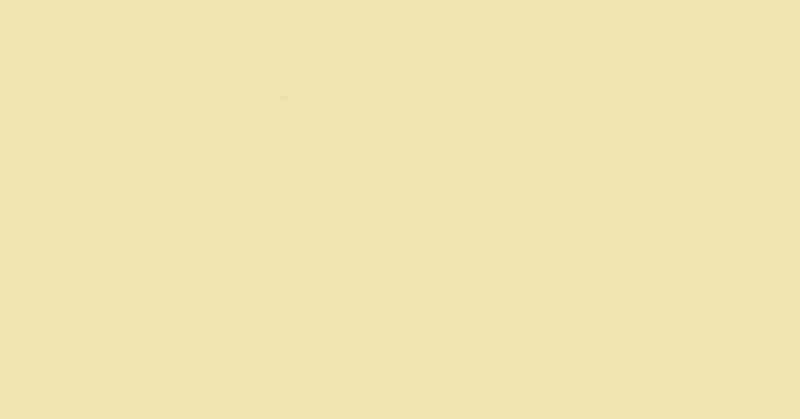
形骸な努力や形骸な救済について触れつつ、近代以降の文系者や世界の課題点を考察してみた話(サッカーの事例踏まえた、世界の変わらなさへの対策も付記)
2022-12-004
はじめに、例えば、嘘や演出であろうと、保護であろうと、
局面の疑似性剥いだ性質に即してない(場と不整合的である)という意味で、加工に過不足あるなら帰属操作的
(つまり、局面との一致不一致に鈍感な段階での擁護的振る舞いは搾取的側面を含んでしまう)、
過不足ないなら帰属修正的(内外境界の受容は前提で受容に値するしないの余地しかない事態意味する有限の与件性、より確からしいものが取って代わる運動性、
これらに帰属があるという意味で帰属に修正余地がない、受容に値する現象)と解する事にして、以下。
帰属操作が混入してるしてない(帰属修正が機能不全かどうか)を区別せずに文系知性や倫理を持ち出す事態は、
客観視できない理系者とフェア志向でない文系者の同列化(局面と着目無視との不一致を抽象次元とした時の個々具体扱い)をもって積極的な正当化を防げる
(できるできないは小学生でも実存に関わる重大な問題でしょうが、
存在と引き換えの内在事情外在事情にしか応じない有り様に自由を見る事で、
欲望のベクトル含めた有限性形態に関する個別性に対し、ひいては、理解限界や死を含めた有限性一般、より抽象的には、与件である内外境界に対し、受容に値するだけの内実の確からしさを持たせる、
という問題へと話を捉え直す、それにより対実存での暴走という振り回され状態を抑える事は、
表裏問題だろう、親や先生などの管理者ポジション含め他者の不完全さを認めつつ、許容する不完全さしない不完全さを分けて後者の影響抑える、という対世界にも拡張すべき処理と共に、
小学生でも小学生なりに可能であって、
その自由観を実存的と見た時の認識的な自由、認識的な振り回されなさ、認識的な帰属操作拒否である上の合致は、
通用領域と確からしさとの相関という認識の前提を、対象の固有性について見る事意味する、存在と引き換えな部分を取り出す処理の前提なので、
少なくとも、その合致への志向が、できないという事態に振り回される事なく、対内在でも対外在でも引き受けるに値するものだけ引き受けてる生の前提になってくる)
ように思うので、文系事象に対して内実不問を含んでる現象解釈(確からしい内実の反映かどうかと関係なく表層形、
成功失敗なり硬軟なり理想との遠近なりを肯定否定するセンス)が世界標準である
(その種の現象解釈はそれを許してる限り、帰属修正な感じがするだけで帰属操作を多分に含んでる雰囲気哲学に留まるだろうに、そこからの脱却の意味での哲学再構築を果たすでもなく、
局面が要請してない個別性捨象の形で内実不問を含んでる不当合理を抱えたままのカント系譜、内実不問な個別性保障である過剰特殊なままのニーチェ系譜が見られる以上そう言える)直接的原因、
また、機能不全な代物をそうでないかのように扱わせると搾取なのに、帰属操作に鈍感なせいで、
世界の有り様について奪い合いを所与と捉えてない人まで奪い合いに参加してる形になってる直接的原因は、
教育におけるその同列化の不在と思われます。
例えば、偶々何らかの優位性を持ってる人がその非対等性を肥大化させてしまってる
(非対等性肥大が現象解釈に反映される、自己を優先すべき局面もすべきでない局面もあるだけなので局面の性質把握の問題なのに尊厳の話にすり替え先の意味での有限の与件性とも向き合わない、
といった帰属操作を、局面の固有性把握の精度向上含め、局面と着目無視の合致、
自身の内容を確からしくすると仮説検証の構造から類推されるそれをもって抑えにいくのを怠ってる)のと大して変わらない話として、
受けた10のダメージを100のダメージとして周りに扱わせる搾取もあると捉えるべきだし、
そもそも、フェア志向でない(帰属操作の混入を問題視してない、あるいは、環境とそこに置かれたものとの間の責任帰属に厳密でないまま功罪を捉える事に疑問がない)時点で、
文系事象に関し、確からしさ差として取り出す差異が恣意の対象であり、通用領域の広狭と確からしさとの相関という認識の前提が形骸化してる事態を意味してるのであって、
その人の感情なり、文系事象に関して選抜した解釈なりは搾取の側面(批判系は少なくとも冤罪の側面)を持ってる、
厳密には、何をもって最善かの追究に関するやむを得ない内外事情以外での不断な、かつ、形骸でない努力を欠くのに、できるだけの事をしてきた感を醸すだけで搾取が生じてるわけなので、
理系空間並みの帰属操作混入抑制を持たない文系空間の現状
(特に、文系域が帰属操作の混入に鈍感なままでも知的上層や教える側になれてしまう再生産サイクルが回ってる直接的原因である、先の同列化不在の環境下)においては、
自身が帰属操作の有無に敏感であろうとしていなければ、救済に参加してるつもりで搾取に参加してる形になってしまいます。
例えば、実存の内実不問肯定をはじめ、受容に値する状態まで持っていってない段階の生の正当化
(行動原理と状況把握に対する、より確からしいものが取って代わる運動性へのいらぬ阻害を持つ生は、疑似問題に囚われてる状態なのにその正当化)を強いるとか、
できるだけの事をしてるしてないを区別せずに引いたこれ以上無理という境界線の受容を強いるとか、努力を内実不問で根拠にするとかも、
負わせるに値しないものを負わせてる形です。
ABはできるがCはできない、本番では思い出せなかった等々が、通用してる具体化条件の広狭の話である事から分かるように、実力は対象に関して持ってる抽象具体関係構造なので、
形骸でない努力とは、抽象化具体化の不十分さ解消であり、
また、有限能力の事情であらゆる対象について高い実力を持てない為に生じる、対象ごとのその解消具合の差異に関して、
代替不可能な内外事情にしか応じない主体像をもって具体化したもの(存在と引き換えな要素にしか応じない対内在対外在をもって受容に値する状態にまで持ていったもの)が、
その主体にとっての、できるだけの事に相当してると思われます。
そして、その主体像は抽象化具体化の不十分さ解消の一具体形ですから、この主体像と不十分さ解消との間には、不十分さ解消の問題がメタ的にあって、
受容に値する生(実存)なり、有限性形態(できるできないや欲望強弱の形)なりの正当化条件になってる、
したがって、その不十分さ解消が結果的にでも内容である時に、自他の救済は形骸でない、と想像されます。
ここで、対象理解も知的実力の反映と見るとして、主体の個別性なり、文系的概念なりに対する理解についても同様の事が言えるので、
同種の他との共通要素の捨象を用いた抽象化具体化の不十分さが解消されるほど深くなるし、
同じ対象に関して生じる個人間だったり人生上での深さ差異や角度(観点)差異は、上で言う主体像の反映である時に受容に値する(浅い理解故の冤罪的非難すら許容に値する)事になります。
論点がズレてるという局面の性質理解の失敗は、具体化精度確保の不十分さであり、実力不足を意味しますし、
論点が維持されると都合が悪いので論点をずらしにいく、という振る舞いは、
結果的に具体化精度の不十分さを解消させるのでないなら、形骸な努力や形骸な救済に他ならず、
また、形骸物をそうでないかのように扱わせる搾取でもあるので、奪い合い状態へと世界を誘導してるも同然であるわけです。
そして、不当合理と過剰特殊の二択に縛られた地平(論点ずらし戦略含む硬軟操作を、不当合理への対策として本筋かのように捉えるなど)に代表される、
近代(近代科学や、内実不問な主観の始点化といった、分離の成功体験がパラダイム化してる状況)の外に、
たとえどれだけ実態露呈に見えても、新しいものに見えても、一歩も出てない現象解釈は、
個別性が根拠になる局面での、同種の他との共通要素捨象にさらされてる程度と確からしさとの相関
(例えば、場で割り振り原理になってるものがさらされているいない、つまり、場の固有性が疑似でないかどうかをもって、
場に置かれてるものがその原理の下に受ける整合に対し確からしさ差を見る観点)を、取り出せない局面性質理解失敗ですから、
近代以降の文系者や世界の課題点は、
受容に値するとは言えない局面性質失敗が、上の相関の取り出し失敗の形で現れる、という点にあるとの現象解釈が言えるはずです。
実際、その課題点を克服できれば、
Aを論理展開してBを得るという現象にイコール性だけでなく、具体化条件差異への視点の内包、
つまり、Aを抽象次元とする、あるいは、AとBを個々具体とする抽象具体の関係構造に関する、抽象化具体化の不十分さ解消の論点化を含めた論理観が可能になるでしょうし
(個別性が根拠になる局面では同種の他との共通要素捨象を、ならない局面では差異要素捨象を用いたその解消によって、
通用領域の広狭と確からしさとの相関という認識の前提踏まえた、限定前後の確からしさ保存の達成試みへの捉え直しであるその論理観は、
限定を内実不問的に解釈するせいで、不当合理的切り捨てと同一視し、その切り捨ての表層形反転でしかない類、言わば、分離に対する分離という結局は近代な反応を通しにいくパターンも否定できてる形であり、
また、検証結果のフィードバックによる仮説の確からしさ向上を機能させるのに必要な具体化抽象化の精度確保を、
例えば、言葉の意味合いやニュアンスの時代に合わせた単なる変遷における論点にも見る、
抽象化具体化の交互反復に内実の確からしさを求める観点とも重なる事情で、
内容が確定しない境界線問題にかこつけた内実不問な曖昧さ推奨や、
内実の確からしさの下での表層形開放とは関係ない単なる両極保有志向含め、限定を取り除く事に固執し、既存の不十分さへの否定である新規まで取り除く開かれ観押し付けも、否定できてる形なので、
先の二択への矮小化から、文系論理を解放するものと見なせます)、
文系知性と倫理の表裏性から、
奪う奪われる現象一般へと遡らずに特定の戦争だけを問題視する(泣き寝入り込みの平和のような、確からしい受容条件の不随を欠いた寛容推奨の有害性に対応できない)、
表層形のみで肯定否定する次元に生きながら特定の表層形断罪を非難する(世界の有り様を特権の奪い合いへと矮小化してる形)、
疑似化による内在外在の固有性埋没を許してる、当然、現象に固有性が反映されない類の平等(内在軽視外在不問)や自由(内在不問外在軽視)をもって尊厳を語るなど、
そうした無数に見られる、倫理の実力不足(抽象化具体化の不十分さ)な振る舞いに対する低減化も期待できる
(自己の被限定事態に対し受容条件を設ける事は、その受容条件が確からしいほど、理解限界などの限定作用としての自己と、対象なり世界なりとの和解の形に近づく)と考えます。
注、
現時点でまだ終わってない大会での結果から、日本の代表チームについて、運次第では強豪国にも勝てるレベルにまで実力格差を縮小できたと見なされているようですが、
一方で、10年前のパターンを繰り返した形(下で言う傾向について、修正指示がなかった前回と、指示が直接的に引き起こした今回とでニュアンスに違いはあるものの、
運要素の強い決戦方式に相手にとって嬉しい展開のまま突入した構図は同じ)である為、
勝負ごとに向いてない傾向がその専門家にすら持続的に持たれてる、との理解なり疑念なりも必要でないかと思います。
(そもそも、自身に関する像を、帰属関係に修正余地がない方向へと持ってくのに自力では限界があるので、外からの指摘を生かすべく、
つまり、外に開きつつも改悪フィードバックとならないよう、情報への帰属操作の混入に敏感であるべく、
肯定的側面と否定的側面をひっくるめた対象情報を、局面に合わせて切り出す、
これについての例の解消による抽象次元具体化次元双方での帰属修正の話があるだけ、との毀誉褒貶に対する捉え直しも必要。)
相手が困る方向性を失敗厭わず繰り返し、相手の都合を突き崩すのではなく(運の良さを都合の良い展開と捉えるなら、この突き崩し方向でない振る舞いは勝負事において自身の運を相手に差し出すようなものだろうに)、
その方向性をむしろ自ら封じて、相手の喜ぶ状況をつくり、ひいては、相手の都合に取り込まれる(相手にとってのラッキー存在を自分達の中に自ら生み出しさえする)というその傾向
(専門家が自身の専門分野でこれを見せる以上、専門知識の有無とは直接的な関係にはないわけで、
恐らく、文系事象一般への現象解釈能力の問題であって、勝負事を負う立場の人は、
対象に関する抽象具体関係構造の像における抽象化具体化の不十分さに鈍感な人や言動に親しむのは、たとえ学者のような肩書を掲げていようとも避けるべきでしょう、
また、アンフェアな人達や彼らが構築した世界と自身との関係を勝負事として見た場合に必要になってくるのは、フェア志向欠如に対し、
選抜精度にも主体と場の責任分別にも難がある事を意味する、
場合によっては、改悪フィードバックを防ぐ内容の割り引かれ受容による質の向上を、割り引かれ忌避によって放棄した井の中の蛙的な純度追求意味する、それに対し、
対文系での実力不足として扱い続ける事でないかと疑えるのでないかと思います)
も場との不整合(場に合わせた上で味方と繋がるなり敵との関係構築する、あるいは、自身と繋がるなり他者との関係構築する、
この形でないという意味で人に直接合わせてしまっていたら、場の性質の深掘りによって可能になる、
引き受けるに値するしないの分別精度向上、ひいては、本質的でないものに振り回される事態阻止も期待できない)と解せば、
通用してない具体化条件を意味するわけで、
この不整合の解消について、偶然的に起きる運の奇跡性の度合いを下げ、起きやすさを上げにいく、
つまり、運の領域を無闇に大きくしない(内外境界を受容に値する確からしいものにする)為に、通用させるべき具体化条件として自覚すべき対象と捉える、
という話はそのまま、強豪国の顔触れが変わらないという意味での低変化性への揺さぶりにも繋がってるはずです。
拡張すると、実力を対象に関して持ってる抽象具体関係構造として捉え、具体形パターン網羅への志向を機能させる事が、
もっと言えば、対実存や対世界の内容を、同種の他との共通要素捨象を用いた抽象化具体化の不十分さ解消とする事が、
世界の変わらなさに関して、それが安易なものであった場合に、受容に値するだけの確からしい内実の反映としての変化不変化へと持ってく為の条件である
(もちろん、理想現実関係もその内容となるので、世界の理想化なり、具体化精度と無関係な手段の肯定なりを言ってるのではない)、
そう期待できるのでないかと思います。
ご支援の程よろしくお願い致します。
