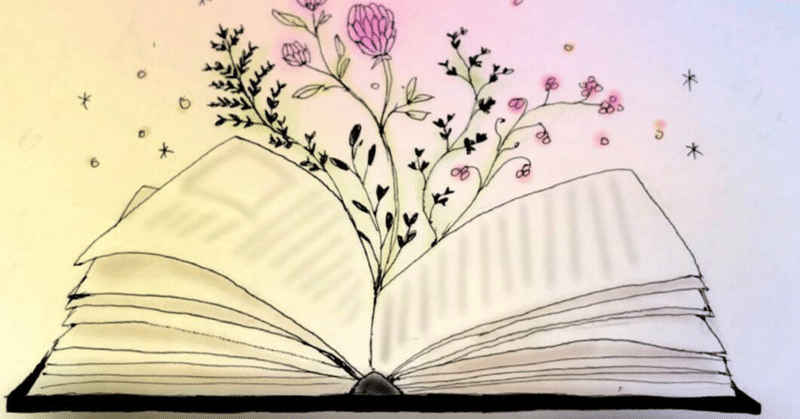
読書について
おはようございます 渡辺です。サッカー負けちゃいましたね。今週もよろしくお願いいたします!
週末、「読書について」- 小林秀雄 を読みました。
なんで、この本を読もうと思ったのか忘れてしまったのですが、きっと誰かがおススメしてたんだと思います。小林秀雄さんはどなたでしょうか?と思う方も多いかもしれませんが、wikipediaによると、
小林 秀雄(こばやし ひでお、1902年〈明治35年〉4月11日[注釈 1] - 1983年〈昭和58年〉3月1日)は、日本の文芸評論家、編集者、作家、美術・古美術収集鑑定家。
だそうです。という訳で、この本自体は、2013年初版ですが、収録作品は昭和七年から昭和四十八年にかけて発表されたエッセイを編集したものになっています。
この本の解説によると、
どれもとても平明で分かりやすい文章ばかりですから、楽しんでお読みください。
とありましたが、言いまわしや難しい漢字などあって、僕にとっては決して ”読み易い” ものではありませんでした。昨日の天気の良さと相まって、何度となくよみながら、うとうとしてしまいましたが、それほど厚い本でもないので、(解説含め187頁)読み終えることが出来ました。
という訳で、今週はこの本から「読書」に関する内容をピックアップしつつ色々と考えてみようかと思います。
それでは、今週末には12月突入ですね。そうなると、2022年もあと僅か。
残り1か月あまり頑張っていきましょう!
文は人なり
おはようございます 渡辺です。なにやら、週間予報によると、12月に入る木曜日から気温が下がるみたいですね。みなさま、服装などお気を付けくださいませ。
さて、「読書について」を読み解いていこうと思います。
著者は、読書の楽しみの源泉は「文は人なり」という言葉を用いて表しています。そして、この言葉を理解するには、全集を読んでみるのが良いと。そうすることにより、作家の性格とか、個性が奥の方にぼんやりと見えてくるような感覚を著者は、以下のように書いています。
文は眼の前にあり、人は奥の方にいる
とはいえ、僕は村上春樹や伊坂幸太郎(まさか、マリアビートルがブラピ主演の映画になるとは!)が大好きで、著書やエッセイなど結構読み込んではいるものの、まだまだその域には達することは出来ていません。
著者の創作する作品としての文章を楽しむことは出来ても、性格や個性というものは、分からないです。
確かに、エッセイとか読むと著者の性格や思想が何となく分かったような気になるのですが、それはまだアウトプットとしての ”エッセイ” の域を出ておらず、その奥の方にあるものまでは到達で出来ていないような気もちになります。
とは言え、こんな僕みたいに書物から人が現れるのが待ちきれない人に、著者は以下のような文でこのセクションを締めくくっています。
人間が現れるまで待っていたら、その人間は諸君に言うであろう。君は君自身でい給へ、と。一流の思想家のぎりぎりの思想というものは、それ以外の忠告を絶対にしてはいない。諸君に何んの不足があると言うのか。
如何でしょうか?「読書について」考える機会になれば幸いです。
それでは、本日もよろしくお願いいたします!
読むことに関する助言
おはようございます 渡辺です。今朝は心なしか気温が高いですね。電車の中が暑いです。。さて、「読書について」引き続き読み解いていこうと思います。今日は、「作家志願者への助言」のセクションで作家志願者への「読むことに関する助言」を紹介します。
1.つねに第一流作品のみを読め
質屋の主人が小僧の鑑賞眼教育に、先ず一流品ばかりを毎日見せると言います。確かにいいものばかり見慣れていると悪いものがすぐ分かるというのは納得の理論ではありながら、本 というもので考えた場合、次の2に繋がるのですが、難解なものや重厚長大なものが多い気もします。
そうなると、中々読み進めることが出来ないです。時間が十分にあれば、それを毎日少しづつ読み解いていくというのも良いかと思いますが、忙しい現代人にとっては、分かり易く書かれたもの、手に取りやすいものから始めて、気が向いた時に一流作品を読むのでも良いのかなとも思います。
2.一流作品は例外なく難解なものと知れ
これはそもそも作品自体が難しいというものと、分かった気になってもそれはまだまだある段階まで理解したに過ぎないということを指しています。再読する度に何かが見つかる筈だと。
3.一流作品の影響を恐れるな
影響を受けたとか受けないとかではなく、”文句なしにガアンとやられることだ。心を掻き廻されて手も足も出なくなることだ。”
とのことだそうです。このような文章を書くこともできないような正に声もでないようないわゆるショックを受けることを恐れるなということかと
4.若し或る名作家を択んだら彼の全集を読め
これは、正に昨日の内容になりますね。
5.小説を小説と思って読むな
作家志願者へ向けた文章ということで、純粋に小説を楽しめということだと思います。巧い拙いとか何派だ何主義だとかではなく、なまじ文学を志しているがゆえに、少し斜めからモノを見るような態度を改めよという事ではないかと。
如何でしょうか?「読書について」考える機会になれば幸いです。
それでは、今日で11月もお終いですね。今月もありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします!
読書の楽しみ
おはようございます 渡辺です。今朝は一段と気温が下がりましたね。朝の散歩がいつも通りの服装だと寒かったです。
さて、「読書について」引き続き読み解いていこうと思います。今日は、「読書の楽しみ」のセクションです。このエッセイは、昭和四十八年ということで、亡くなる10年前、71歳頃の作品になります。
若い頃は、濫読していた著者ですが、その頃になると以前読んだものを読み返す事が多くなり、そうすることで改めて読書の楽しみをはっきりと自覚するようになったそうです。
また以下のようにも書かれています。
私は、依然として、書物を自分流にしか読まないが、その自分流に読むということが、相手の意外な返答を期待して、書物に話しかける、という気味合のものになったのである。
結局のところは、本なんて自分の好きなように読めばよくて、自分が好きなように読むことによって、本との対話がなされ、相手への関心を深めていくということなのかもしれませんね。
知らんけど。
という訳で、今日から12月突入です。年の瀬で何かと慌ただしい月ではありますが、みなさま体調など崩しませぬようご自愛くださいませ。
いつまでたっても容易にはならない
おはようございます 渡辺です。今朝はモクモクとした空が広がっています。寒いと言えば寒いような、12月の割には暖かいようなそんな気分です。
さて、「読書について」最終日。良薬は口に苦し。初日に書いたように、決して”読み易い”ものでは無かったですが、たまにはこういう本を一生懸命に読んでみて、なんとかかんとか解釈してみるのも良いですね。
また「国語という大河」のセクションの中でこんなエピソードも語られていました。
あるとき、娘が、国語の試験問題を見せて、何だかちっともわからない文章だという。読んでみると、なるほど悪文である。こんなもの、意味がどうもこうもあるもんか、わかりませんと書いておけばいいのだ、と答えたら、娘は笑い出した。だってこの問題は、お父さんの本からとったんだって先生がおっしゃった、といった。
なんとも言えないエピソードでこの本の中で一番面白かったです。
著者自身も、
自分で作る文章ほど、自分の自由にならぬものはない
書くことは、いつまでたっても容易にはならない
と書かれています。
このように後世に名を残すような文筆家の人でも、日々苦悩と闘いながらも文章を書き続けているんだなと思うと、いわんや毎朝僕の駄文を読んでいただいている皆々様におかれましては、本当に感謝の言葉しかございません。
そもそも、仕事をしているとこんなことばかりだし、日々自分の能力と今のポジションのギャップに打ちのめされそうにもなりますが、そんな時はアメリカのプロデューサーのアイラ・グラスのこの言葉思い出して何とかしのいでいます。
センスがあるからこそ、自分のつくっているものがそんなに良くないとわかって落ち込むんだ。 — アイラ・グラス
Your taste is good enough that you can tell that what you’re making is kind of a disappointment to you. — Ira Glass
というわけで、泣き言のような形で終わってしまいましたが、今週もあと1日。本日もよろしくお願いいたします!
(2022.11.28-12.02)
サポート頂きました分は、他の方へのサポートに使わせて頂きたいと思います。サポートの輪が拡がっていくとよいですね。
