
芥川賞受賞作「サンショウウオの四十九日」と「バリ山行」
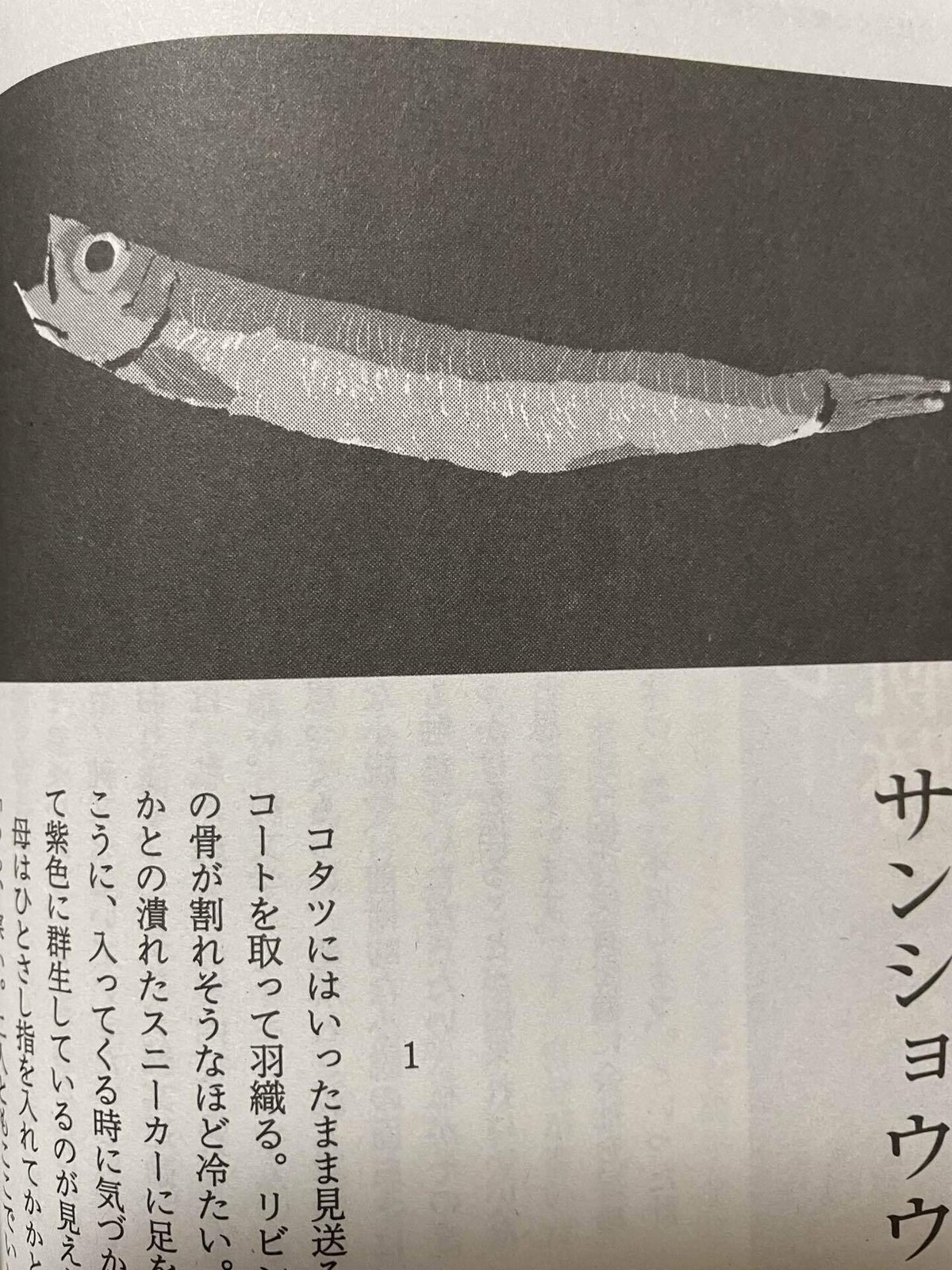
わたしはこの小説を読んで、純文学という器がなんでも包摂してしまう奥行きのある大きな構造を持っていることを知り驚嘆しました。
なんとこの小説に登場する父親は、赤ちゃんであった兄の体内にシシャモのように存在していた胎児が手術によって産み出された胎児内胎児なのです。
さらにその父親の娘である主人公の姉妹、杏と瞬の身体は右側が瞬であり、左側が杏でそれが合体して一体になっているが一人でないという結合双生児なのです。ベトちゃん、ドクちゃんのように腹がくっいていても、上半身は別々ではなく、結合双生児なのです。
でも、結合双生児の瞬と杏は、独立した人格を持っていて、意識も思考も別々なのです。
こうした奇抜なことを考えだした朝比奈秋さんという作家の構想力はすごいと思います。
ただ、結合双生児でも、人格も意識も別々で、一体である身体ですらお互いが使い分けている人物を描くことはそう簡単ではないでしょう。
作者は、「二人が同じ人を好きになったことは今まで一度もない。性行為も共有の膣を使うのだから、どちらかがレイプされることになるので永遠にできない」とか、働いているパン工場ではパンの仕分けを合体した身体で人の二倍やるのだが、給料は一人分しかもらえないなど、苦心のエピソードを披露していきます。
しかしながら、二人の苦悩や葛藤が深刻に描かれるわけでもなく、それは救いにもなる半面、「私のなかに瞬が生まれて、瞬の中に私が生まれる。それがどういうことなのか考えるたびに頭の中でサンショウウオが育っていった。私が黒サンショウウオで瞬が白サンショウウオ。くるくるまわれば一つになる、二人で一つの陰陽魚」とマジックリアリズムとも言えない、やや抽象的な思念が描かれていき、話は一向に深まらないきらいがあるのです。
欲を言えば、当初の構想が素晴らしかっただけに、全体をもっと深めてほしかったと少し残念に思われました。
その後、日経新聞の読書欄で文芸評論家の三宅香帆さんがこの小説は「はたして、自分と他人との境界はどこにあるのか?……本作の面白さは、小説の語り手である杏と瞬の視点が、入れ替わりつつ混在しているところにある。つまり、この小説を読んでいると、いまの語り手は誰なのかがふわりと曖昧になるのだ。小説を読んでいる読者は、語りの揺れに翻弄されているうちに、杏と瞬ははたして別人だと言えるのだろうか?身体を共有していたら、それは同じ人間なのでは?という問いを考えざるを得なくなる。つまり本作が描き出す不思議な意識や思考の揺れこそが、意識をつくるのは、脳なのか?臓器なのか?自他の境界はどこにあるのか?という問いを提示するような構造となっているのだ。……サンショウウオとは二元論で分けられない、互いに影響し合う存在を意味する。現実には二元論ではっきりと分けられないことが多々存在する、たとえば自分の意識ですら揺れ動くものではないか?という問いかけが、小説を通して私たちに強く響く」と書いています。三宅香帆さんに脱帽です。

これに対してもう一つの芥川賞受賞作「バリ山行」は、小気味よいリズムで書かれた、わかりやすい小説です。
主人公の波多はリフォーム工事会社に途中入社してなかなか馴染めないなかで六甲山への山行に誘われます。すると、変わり者で一匹狼の妻鹿さんという男が偶然に山行に参加してきて、妻鹿さんから通常の登山道でない道を行くバリエーション、バリルートというものがあり、妻鹿さんは毎週末ひとりで山に分け入ってバリ山行をしていることを知ります。
主人公の波多はバリ山行に興味を持ちますが、妻鹿さんと仲がよかった常務が退職すると、リフォーム工事会社は小口の元請工事から撤退して、大手の下請だけするという営業方針に大きく転換、それが裏目に出て、業績は一挙に悪化、会社の存続が危ぶまれるなかで誰がリストラの対象になるか噂は飛び交い、そんななか、波多は妻鹿さんとバリ山行に行きます。
バリ山行は藪のなかを手鋸で藪をなぎはらいながら進んだり、谷底に転げ落ちそうな、落葉に埋もれた急斜面を恐る恐る渡って行ったり、岩場で滑落して死にそうになったりして、波多は散々な目に合います。しかし、妻鹿さんは、何ごともなかったように黙々とバリ山行を続けます。そうしたなかで波多は、リストラで一番危ないのは妻鹿さんですよ、とついしゃべってしまいます。それでも、妻鹿さんはそんな噂話に頓着せずに、バリ山行で遭遇している、いま、死ぬかもしれない、この目の前の危機こそ本物だと言い、自分は自分のやることをやるだけだ、と言って、多くを語ろうとしません。
詳しくは書きませんが、妻鹿さんは会社を辞めてしまいます。それが何故なのかは分かりませんが、ごちゃごちゃ考えずに行動する、そんな人物として妻鹿さんは描かれていて、好感が持てます。そんな妻鹿さんにバリ山行は、もっともふさわしい舞台であり、いまも妻鹿さんはバリ山行を続けているのではないか、という形でこの小説は終わっています。
○©錦光山和雄 All Rights Reserved
#芥川賞 #サンショウウオの四十九日 #朝比奈秋 #バリ山行
#松永K三蔵 #文藝春秋 #六甲山 #結合双生児 #山ガール
#日経新聞 #読書欄 #文芸評論家 #三宅香帆
過分なサポートをいただきまして心より御礼もうしあげます。
